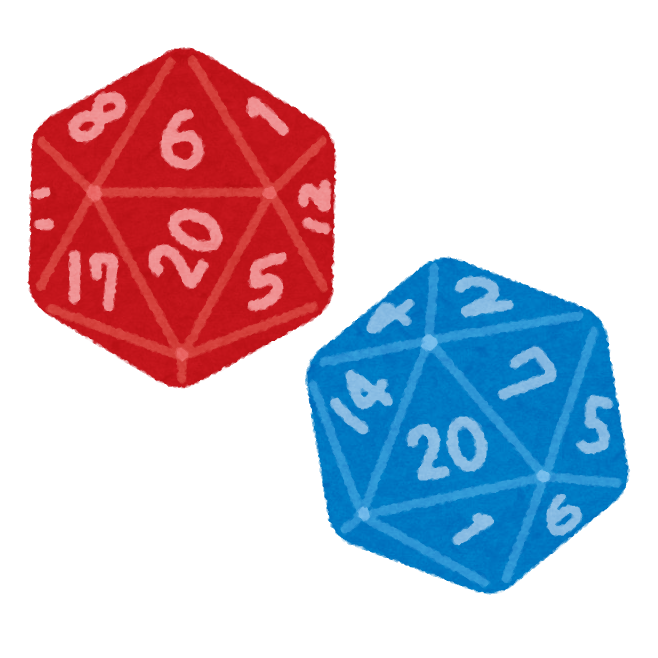有効な膵がん検診は存在しない
日本人の部位別のがん死亡数の上位は、肺がん、大腸がん、胃がん、膵がんが占める。男女計では膵がんは第4位であると思っていたが、さきほど確認したところ、2023年の統計では胃がんを抜いて第3位になっていた。肺がん、大腸がん、胃がんは、がん死亡率を減らす相応のエビデンスがある有効ながん検診が存在する。しかし、■こんな検診ビジネスに騙されてはいけない…内科医直伝「エビデンスに基づいた効果的な"がん検診"の受け方」 あらゆる検診には利益だけでなく害もある | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン)でも書いたように、現時点で、有効な膵がん検診は存在しない。存在しないのは仕方がないので、一般的ながんリスクを下げる生活習慣をできる範囲内で心がけ、あとは症状が出ない限り膵がんの心配なんてせずに過ごすことをおすすめする。
尿中マイクロRNAを用いた膵がん検査の性能とその限界
とはいえ、人間の心理はそのように単純に割り切れるものではない。検診の害と限界を承知の上でなら、受けてみるのは個人の自由だ。プレジデントオンラインの記事で言及したCraif社は、尿中のマイクロRNAを利用して膵がんを早期発見できるとする検査『マイシグナル』を提供している。値段は7万円弱。膵がん以外に肺がんや卵巣がんなどの7種類のがんのリスクもわかるとされているが、線虫がん検査(N-NOSE)のように「全身のどこかにがんがあるかもしれない」というものではなく、個別のがんについてリスク判定される。なので、陽性という結果が出たからといって全身の検査をする羽目にはならない。膵がんで高リスクと判定されれば、腹部超音波検査、腹部造影CT、MRCP(MR胆管膵管撮影)、超音波内視鏡ぐらいで済むだろう。
論文も読んでみた。
学習のためのトレーニングセットで膵臓がん患者99人を、検証のためのテストデータセットでは54人を対象とした。膵がん検出の感度は、トレーニングセットで93.9%、テストデータセットで77.8%、特異度はトレーニングセットで91.7%、テストデータセットで95.7%だった。ステージ I/IIAに限れば、感度はそれぞれ97.0%と77.8%だった*1。詳しくは各自、論文を参照してほしい。
以下は私の考察。腫瘍マーカー(CA19-9)より高性能であるのは確かであろう。ただ、膵がん検診として有効かどうかは別問題である。膵がん死亡率の減少につながるかどうかは検証されていない。加えて、本研究はがん患者集団と健常者集団の2つの集団から感度・特異度が算出されており、検診を受けるような集団に対する感度・特異度は不明である(■「線虫がん検査」の感度・特異度は過大評価されているを参照)。とくにテストデータセットにおけるステージ I/IIA症例は9例と少なく、本研究だけでは「早期すい臓がんでも優れた検出性能が確認された」とは言えない。膵がんと診断されていない検診対象者を用いた感度・特異度の評価といった今後の研究の発展に期待したいところだが、商品として高額で販売されている以上、企業にとって都合の悪い結果が出かねない研究を避ける強いインセンティブが働くことを懸念する。
上部消化管内視鏡時に採取した十二指腸液を利用した膵がん検査
『マイシグナル』以外にも、膵がんの早期発見が可能と称する検査はたくさんある。つい先日も、九州大学病院が「世界初の検査法」を開発したというニュースがあった。
■「膵臓がん」胃カメラ検査で早期発見へ…九州大学が世界初の検査法、カテーテルで採取した十二指腸液で判定:地域ニュース : 読売新聞
上部消化管内視鏡(いわゆる胃カメラ)は、胃がん検診として行われているので、そのついでに採取した十二指腸液を用いた検査であるようだ。「初期段階を含む膵臓がん患者約8割の十二指腸液内で、[膵臓がんの細胞が作るたんぱく質の]一定以上の濃度が確認できた」とあるので、感度は80%台ということであろうが、特異度については不明である。他の報道も参照したが、これ以上の詳しいことはわからない。現時点では九州大学からのプレスリリースは見つけられなかった。がん患者集団と健常者集団の2つの集団を対象とした感度85%、特異度77%とする論文はあったが、2017年発表のものである*2。何をもって世界初とするのかもよくわからない。十二指腸液を用いて膵がんを早期発見できるとする報告は他にもある*3。まあ、研究は大いに進めてもらいたいが、問題は「新年度から福岡赤十字病院(福岡市)で導入される」という点。がん死亡率減少どころか、検診を受けるような集団に対する感度・特異度すらわかっていないのに、安易に臨床応用すべきではない。
「尾道方式」による膵がん検診の検証は進んでいない
他に膵がんの早期発見を目指す検査方法として、有名どころは、いわゆる「尾道方式」がある。リスク因子や腹部超音波検査で膵がんのハイリスク者を絞り込んで超音波内視鏡につなげるという方法は、合理的できちんと検証すれば膵がん死亡率の減少を示せる可能性はあると個人的には考える。しかし、残念なことにいまだに検証はなされていない。2023年から横浜市において、尾道方式を取り入れた「YCU横浜早期膵癌診断プロジェクト」が「前向きコホート研究としても」行っているとのことで*4、ようやく検証が開始されたかと思いきや、主要アウトカム評価項目が「膵癌患者の5年生存率」だそうで、思わず「なんでやねん」と声が出た*5。あのな、5年生存率を指標にしても、がん検診の有効性は検証できんのやで。
医療者の間すら、生存率改善が検診の有効性の指標となるという誤解があることがわかる。ちなみに、医師国家試験にも出題されている。■医師国家試験を解いてみよう。「がん検診の有効性を示す根拠はどれ?」を参照。YCU横浜早期膵癌診断プロジェクトにかかわった医師たちは、この問題を正答できないであろう。
*1:『マイシグナル』のサイトや本田圭佑氏のポストにある「ステージI/IIAの感度・特異度は92.9%」は、Youden Indexに基づいて感度と特異度のバランスが最も良いカットオフ値を設定した場合のもの
*2:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28984789/
*3:たとえば https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39902566/
*4:■「尾道方式」でアプローチ! 病診連携と超音波内視鏡を駆使して膵がん早期発見をめざす横浜 | がんサポート 株式会社QLife
*5: https://center6.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000055544