左利きの猫と右利きの犬

実家の家でよくわからない葉を食べているカタツムリを見つけた。きれいな色をした貝の部分を持って指の上に乗せるともぞもぞと体を動かして貝の中に入ってしまうと、地面に落ちた。犬がすばやくそれを銜えて走っていった。カタツムリを食べないように母が犬を追いかけた。母が転ばないように猫が母を追いかけた。それは実家で見られた食物連鎖だった。
朝日新聞日曜版beのによると殆どのカタツムリは右巻きらしい。右巻きの種で極稀に左向きが生まれることがあるが、逆向きのカタツムリでは交尾ができなくなる。そのために左巻きのカタツムリが生まれてもその個体で終わってしまう。が、そこをものすごい執念で本来右向きの種から、左巻きの可能性のある個を見つけて15年間左向きのカタツムリを作り続けている。という、そんな喉かな日曜版の記事を読んで、この人の仕事は神に挑戦するかのような仕事だと感動した。
 先週みた映画の「ゼア・ウィル・ビー・ブラッド」には椅子から立てなくなるくらい感動した。と、その感動加減というのはカタツムリの記事と同義だ。ここでは小洒落たポール・トーマス・アンダーソンという味わいは一切無く、美しい最新の古典映画を見させられた。ラストのボーリング場対決が圧巻で、わたしはこれはドストエフスキーだよね。と呟くけど、そんな言葉はどこにも書いてない。だからこんな世界の片隅で「ポール・トーマス・アンダーソンは現代のドストエフスキーだ」って鼻をほじりくながら書いてみるよ。ドストエフスキー辺りから、人の罪と神の存在についての闘いがよく描かれるけど、たいていは神が打ち負かされることになる。しかしこれだけ頻繁に闘いに呼ばれてしまう神様というのもさぞ忙しかろうけど。それは結局のところ、現実では神だけが勝ち続けているからなのでだろう。ひとり勝ちってのは、このことだろう。
先週みた映画の「ゼア・ウィル・ビー・ブラッド」には椅子から立てなくなるくらい感動した。と、その感動加減というのはカタツムリの記事と同義だ。ここでは小洒落たポール・トーマス・アンダーソンという味わいは一切無く、美しい最新の古典映画を見させられた。ラストのボーリング場対決が圧巻で、わたしはこれはドストエフスキーだよね。と呟くけど、そんな言葉はどこにも書いてない。だからこんな世界の片隅で「ポール・トーマス・アンダーソンは現代のドストエフスキーだ」って鼻をほじりくながら書いてみるよ。ドストエフスキー辺りから、人の罪と神の存在についての闘いがよく描かれるけど、たいていは神が打ち負かされることになる。しかしこれだけ頻繁に闘いに呼ばれてしまう神様というのもさぞ忙しかろうけど。それは結局のところ、現実では神だけが勝ち続けているからなのでだろう。ひとり勝ちってのは、このことだろう。
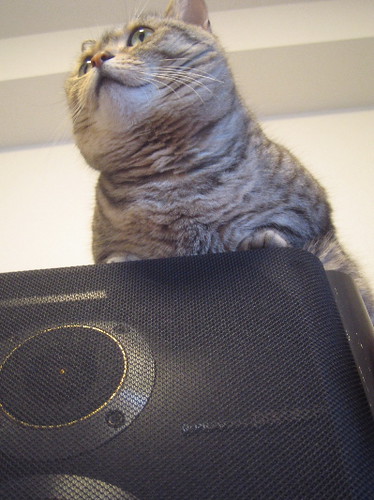 今週も実家で料理をする。筍ご飯と筑前煮を大量に作る。料理の間、アダム・ジョンソン「トラウマ・プレート」、エイミー・ベンダーの「わがままなやつら」を読む。エイミー・ベンダーは奇妙な設定という味わいがなくなって、奇妙な切なさが増した。死や生や性が観たことが無いくせに可愛くさえ感じるようなクロワッサンやカタツムリの貝のようなねじれ加減で書かれている。欲望について語り合い、最後に自分の欲望の部屋に閉じ込められる男の物語「マザー・ファッカー」は箸を持ちながら何度も読み返すが、そういうわけで、わたしにはカタツムリな感触がする。
今週も実家で料理をする。筍ご飯と筑前煮を大量に作る。料理の間、アダム・ジョンソン「トラウマ・プレート」、エイミー・ベンダーの「わがままなやつら」を読む。エイミー・ベンダーは奇妙な設定という味わいがなくなって、奇妙な切なさが増した。死や生や性が観たことが無いくせに可愛くさえ感じるようなクロワッサンやカタツムリの貝のようなねじれ加減で書かれている。欲望について語り合い、最後に自分の欲望の部屋に閉じ込められる男の物語「マザー・ファッカー」は箸を持ちながら何度も読み返すが、そういうわけで、わたしにはカタツムリな感触がする。
昨年あたりから両親とは「もうすぐ死ぬから」という言葉が日常的になってしまい、全く誰にとっても切羽詰まり感がない。映画「最高の人生のみつけかた」で死んで行く前にすることをリストにするところでは、いっしょに考えてしまう。リストのひとつ「知らない人に親切にする」を実行する場面だけはよかったけど。それ以外はとてもつまらない映画だった。わたしの家の♀犬と猫と親の最後のリストには「外泊をしたい」というのがあるらしいので、面倒なのでいっしょに叶えてしまいたい。が、そんなことをしたら、「リトル・ミス・サンシャイン」のような珍道中になって誰かが死んでしまう気がする。そうそう。リトル・ミス・サンシャインで、わたしは、ポール・ダノの表情にやられました。「ゼア・ウィル・ビー・ブラッド」でも、ポール・ダノの小心者を気取る顔にやられまくり唾を飲み込みまくりだった。



わたしが好きなMark Kozelekが今週ライブをやるけど行くのかという連絡をもらう。が、好きだといったことだけでなく、Mark Kozelekの名前すら忘れていた。ひどい。もう一度聴き直すが、簡単に好きになる。Sun Kil Moonも好きになりなおす。好きだった頃のことをいまひとつ思い出せないところをお許しください。
映画「つぐない」は、メロドラマとしては、とてもよくできていた。しかし、と小説「贖罪」のことを思う。現代の英文学で古典として残るのは、カズオ・イシグロとイアン・マキューアンだとよく書かれている。そんなものかしらね。とカズオ・イシグロ「わたしを離さないで」やイアン・マキューアン「贖罪」のやりすぎ感を思うのだけど。それらをやりすぎだなんてことは、どこにも書かれていない。わたしが「せっかく」贖罪を読み直したので、ちょっとそれはやりすぎだべえ感を書いてみる。



「すべての小説愛好家は読まなければならない」豊崎由美。とか。映画は、とても立派に物語を映像にしていたけど、この小説自体が小説の構造と物語について書かれているところまでは省かれている。グレート・ギャツビーの冒頭の言葉と近い言葉を13歳の少女が語る「他人も自分と同じくリアルであるという単純な事実を理解しそこねるからこそ人間の不幸は生まれるのだ。それらが同等の価値を持っていることを示せるのは物語だけなのだ」なんで13歳の少女がこんな言葉を。というのは気にしない。平たく言うと、他人のことをリアルに考えましょうよというこことで。そして、それを教えられるのは物語だけだという。と、少女が小説家を目指すことから、全篇にいたって小説の物語とは何であるのかが語られる。そしてそれは、上の少女の言葉と殆ど同じ言葉をイアン・マキューアンが9.11の事件に対して語っている言葉と同じで、文学や物語が世界を救う。と彼は語る。その彼の倫理観で美しく描かれた、第一部が少女が目撃した姉と恋人と少女が犯した過ち。第二部がまた美しく残酷な戦場。第三部が主人公が再会した姉とその恋人。それらはまさしく、作者の語る世界を救う物語となっていたのかもしれない。しかし、最後のエピローグで、作家になって死を迎える前に少女の時に実現しなかった舞台を再現するという泣きのあとに、今まで読んできた物語を大崩ししてしまうのだ。何と言うか夢落ちや妄想落ちではないが、小説落ち?それが小説の構造として新しいとか主題がより迫真となる。なんてことより、そんな派手なことをしなくても。とわたしは怖じ気づいてしまったのだ。そして、主人公やイアン・マキューアンや世界の小説家達が信じるらしい、物語だけが世界を救うという理想が、少し遠く感じてしまったのだ。また、「神が贖罪することがありえないのと同様、小説家にも贖罪はありえない」というまとめに至っては逆に小さな小説家の人生の物語になってしまったように感じてしまったのだ。
いつも読んだことが無い少女漫画を選ぶ参考にさせていただいている id:ichinicsさんへのお礼ついでに、岩本ナオのどこがそんなに良いのかを考えて読み返すが、どこが気に入ったのかが、わからなくなる。
いちばん好きなのが、たぶん最初の作品集でたぶん一番絵が上手くない「スケルトン イン ザ クローゼット」なのだけど。カットがどうこうではなくて、リアルな少女を感じたから?でもそれは、数多ある少女漫画なの中でどうして特別なのかというと。バランスが狂っているところを含めた作者のリアルさに勝手に少女漫画を感じてほっとすることができたからなのか。いや、もう好きになるのに理由は無いわ。じゃあ、なんだ今日こんなにだらだら書いたこともみんな意味が無いんだと納得。
わたしが誰かを好きになる理由がなくてもそれをわたしは信じるくせに。誰かがわたしを好きになる理由が無いとそれをわたしは信じないくせに。そのくせ誰かがわたしを好きでなかったことへの想像力がわたしには全く欠けていた。
わたしが大量に作った筑前煮と筍ご飯をタッパに入れて持たされる。少しも嬉しくないが嬉しいふりをする。母の日であったことを思い出し、母の日の花は朝顔が咲いたら持ってくるとでまかせを言ってみるが、それで本当に喜んでいたかどうかはもちろんわからない。