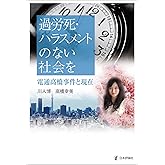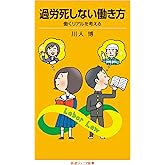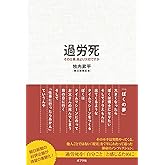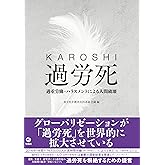事例が多く読み進めていくうちに
なんども涙が出てきます。追い込
まれていて「私に責任があります」
と書いてしまう人々。
叙述の基本として、具体的なことを
書くという原則がありそうです。
説明が丁寧でもあるので、非常にわ
かりやすいです。
原因をさぐるためには制度にも目を
くばりつつ責任ある組織、政府・自
治体・労働組合のあり方にも目を向
けて行こうと思いました。

無料のKindleアプリをダウンロードして、スマートフォン、タブレット、またはコンピューターで今すぐKindle本を読むことができます。Kindleデバイスは必要ありません。
ウェブ版Kindleなら、お使いのブラウザですぐにお読みいただけます。
携帯電話のカメラを使用する - 以下のコードをスキャンし、Kindleアプリをダウンロードしてください。

過労自殺 第二版 (岩波新書) 新書 – 2014/7/19
川人 博
(著)
このページの読み込み中に問題が発生しました。もう一度試してください。
2014年、過労死等防止法成立。近年、二、三〇代の青年や女性たちの間にも、仕事による過労・ストレスが原因と思われる自殺が拡大している。なぜ悲しい犠牲が減らないのか。初版の内容を基調にしつつ、最近の事例や労災補償の有り様の変化、歴史の検証などを新たに盛り込み、法制定後に求められる防止策と善後策を具体的に示す。
- 本の長さ272ページ
- 言語日本語
- 出版社岩波書店
- 発売日2014/7/19
- 寸法11.5 x 1.2 x 17.5 cm
- ISBN-104004314941
- ISBN-13978-4004314943
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
ページ: 1 / 1 最初に戻るページ: 1 / 1
商品の説明
著者について
川人 博 (かわひと ひろし)
1949年大阪府泉佐野市生まれ.東京大学経済学部を卒業.
78年東京弁護士会に弁護士登録.
88年から「過労死110番」の活動に参加し,現在,過労死弁護団全国連絡会議幹事長.
著書─『過労死社会と日本』(花伝社)
『過労死と企業の責任』(社会思想社)
『過労自殺』(初版,岩波新書)
共著─『就活前に読む 会社の現実とワークルール』
『過労死・過労自殺労災認定マニュアル──Q&Aでわかる補償と予防』(いずれも旬報社)他多数
1949年大阪府泉佐野市生まれ.東京大学経済学部を卒業.
78年東京弁護士会に弁護士登録.
88年から「過労死110番」の活動に参加し,現在,過労死弁護団全国連絡会議幹事長.
著書─『過労死社会と日本』(花伝社)
『過労死と企業の責任』(社会思想社)
『過労自殺』(初版,岩波新書)
共著─『就活前に読む 会社の現実とワークルール』
『過労死・過労自殺労災認定マニュアル──Q&Aでわかる補償と予防』(いずれも旬報社)他多数
登録情報
- 出版社 : 岩波書店; 第二版 (2014/7/19)
- 発売日 : 2014/7/19
- 言語 : 日本語
- 新書 : 272ページ
- ISBN-10 : 4004314941
- ISBN-13 : 978-4004314943
- 寸法 : 11.5 x 1.2 x 17.5 cm
- Amazon 売れ筋ランキング: - 573,678位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- カスタマーレビュー:
著者について
著者をフォローして、新作のアップデートや改善されたおすすめを入手してください。

著者の本をもっと見つけたり、似たような著者を調べたり、おすすめの本を読んだりできます。
カスタマーレビュー
星5つ中4.2つ
5つのうち4.2つ
25グローバルレーティング
評価はどのように計算されますか?
全体的な星の評価と星ごとの割合の内訳を計算するために、単純な平均は使用されません。その代わり、レビューの日時がどれだけ新しいかや、レビューアーがAmazonで商品を購入したかどうかなどが考慮されます。また、レビューを分析して信頼性が検証されます。
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中にエラーが発生しました。ページを再読み込みしてください。
- 2021年10月10日に日本でレビュー済みAmazonで購入過労自殺しないでこの弁護士さんたちが助けてくれます。過労死100当番、連絡してみてください。
- 2014年7月26日に日本でレビュー済み企業が時短に取り組み始めたところから、バブルの崩壊から時短の議論が冷えていって、女性の残業時間規制や深夜労働禁止の規定が撤廃されたこと、
裁量労働制の対象職種の拡大、派遣対象業種の拡大と非正規社員の草増加、リーマンショック後の派遣切り...と労働環境の変化をふりかえってくれます。
職場がメランコリー親和型化した几帳面さや他者配慮性を備えたことによって、うつになりやすい人が増えているのではないかという視点を引用してくれて
いるところは、最近のCSRの取り組みの流れからも分かるような気がします。
過労自殺をなくすためには、「失敗が許容される職場」,「義理を欠いてもよい職場」,「失業してもやっていける社会」が必要であると説いてくれます。
理想ではありますが、これもわかります。
冒頭、過労自殺についていろいろな職種の多くの事例を挙げてくれているのもいいです。
紙数の関係やこの本の趣旨からは極端な事例しか挙げられないのかもしれませんが、別な機会にグレーな事例を挙げていただきながらその考え方を
教えていただけると、さらに理解が進むようにも思います。
- 2014年8月24日に日本でレビュー済みAmazonで購入以前 著者の講演を聞き大変誠実な人柄に感銘を受けた。
この本は第2版で初版の時も話題になったようだ。初版は読んでいないのでそれとの比較等はできないが、大変参考になった。
著者が遭遇したであろう実例が記されておりこれも参考になる。次章から過労死の背景や会社社会の実態の記述が丁寧になされている。
最終章で過労死をなくすために 著者はいくつか提言している。
高校生や大学生に企業社会の実態を教えておくことの重要性を強調している。
日本の企業で働き始めるのは、初めて自動車の路上運転をするのとよく似ていると言っている。あらかじめ 違法駐車が氾濫している状況をたとえている。あらかじめ違法状態があることを認識してそれにどう対処するかを考えておかないとパニックになるだろうと指摘している。
これはいいえて妙である。
また 高校生の生活で、受験勉強もそうだが、ほとんど休日なしの過剰なクラブ活動にも批判は向かう。
著者の本で 「金正日と日本の知識人」という本も素晴らしい。この種の本を出すのはいわゆる人権派弁護士という目で見られる傾向があるが、 「金正日と日本の知識人」の中で 拉致問題にむきあっている。また 拉致問題に冷淡な知識人たちを実名で告発している。
理非曲直をただす智者の姿勢に感銘を受ける。
- 2017年3月4日に日本でレビュー済みAmazonで購入過労自殺がなぜ起き、どのように対処するべきか具体論が載った良書。
- 2019年12月20日に日本でレビュー済み私自身が、東大の川人ゼミこと「法と社会と人権ゼミ」に、右も左もわからない大学1年生の時に、誰かから誘われて面白そうだから入ってみたという経緯でした。その結果、川人先生に人生を救っていただいたと思います。
過労死、過労自殺の膨大な事例と、川人先生の「過労死110番」の取り組みについて直接お伺いするうちに、企業社会のヘドロのような汚さがすっかり嫌になってしまいました。東大を出たのにまったく企業への就職活動をせず、リクルートスーツじたいも買わないという人生の選択をしました。
そのことについて、周囲からもったいないだのなんだのと散々言われましたが、「20代を自分のことに使いたい。10代は受験勉強に費やされ、いつテストがあって何をしなければならないと他人に決められてしまい、給料がもらえない仕事のような10代を過ごしてしまった。自分で選択して、自分でアルバイトでもなんでもお金を稼いで、自分の行きたい時に自分の行きたいところに行く20代を過ごす」と決めて、その通り実現して、28歳からママになって、ずっとお金は無いままですが40代まで死なずに楽しく過ごしてこられました。
この本の事例に出てくる方々と自分を比べた時に「なんと、自分は自分勝手で、この事例の方々は正反対に真面目で滅私奉公して、自分以上に会社や他人のことを考えているのだろうか」と驚かされました。
昔話や民話と違って、真面目で他人のために尽くすほど幸せになって、自分のことを自分勝手に考えるほど不幸になるという結末にはならず、正反対であるということが、現代の皮肉なのか?と考えさせられてしまいました。
自分の健康を守り、命を守り、理不尽な要求をしてくる人・会社の言う事を聞かない、ということは、自分勝手ではなく、川人先生がこれでもかと授業で強調されていた通り「当然の権利、皆が知っていなければならない自分自身の人権なのだ」という事だと思います。
まだまだ、自分に人権があるということをわかっていない人たち、子供達、若者たちがたくさんいるというお寒い状況なのだと思います。
これ以上、誰も過労自殺などという、理不尽な悲しい亡くなり方をしてほしくありません。
もっとたくさんの方に川人先生の本を読んでほしいと思います。
- 2016年10月19日に日本でレビュー済み常識を外れたこと言ったらだめだよね。人を意味もなく傷つけるのはだめだよね。おじさんになっても気がつかないのは本当にだめだよね。だめなおじさんだらけ。」(2015年11月3日 2:36)
10月7日に大手広告代理店一年目社員の過労自殺に関連するニュースを聞きましたが、このニュースをどう考えれば良いのか私には分かりませんでした。その後、過労自殺してしまった女性の遺族代理人を務められた方が本書の著者であるということを知ったため、考えるためのヒントを得たいと思い本書を購入して一読してみました。第1章からとても悲惨な事例が次から次へと出て来たので途中で気が滅入ってしまいましたが、本書は過労自殺を考える上でとても参考になると思いました。ご一読をお薦め致します。
なお、私は本書第1章にあげられている全10事例のうち、51歳の方の事例以外がすべて45歳未満のものであったこともあって、「とくに深刻なのは、二〇-三〇代の青年労働者の過労自殺である」(本書「はじめに」ii頁)ことを改めて認識致しました(ちなみに、51歳の方の事例は他とは背景が少し異なる様に思えました。ただし、この事例は部下に脅迫されたという、普通では考えられないものであったため、非常に痛ましいという意味では他の事例と同じでした)。そして、それらの事例において、過労自殺してしまった「青年労働者」に対する周囲の評価がどの様なものであったのかということについて、とても気になるようになりました。というのは、「ウソツキ」(30頁)、「硫酸で顔を洗ってこい」(53頁)、「もういいです」(88頁)など、本書に登場する周囲の人々の言葉はとても辛辣だったからです。過労自殺は長時間労働だけが原因である訳ではなく、周囲の人達による厳しい態度も原因であり、その厳しい態度はその人に対する評価がベースになっているのではないかと思えたのでした。そして、その「周囲の評価」がどの様なものであったのかが気になるようになったのでした。
上述の通り、私が本書を読もうと思ったのは、大手広告代理店における過労自殺のニュースについて考えるためのヒントを得たいと思ったからでしたが、実際に本書を読んでみて「周囲の評価」が思いの外重要であると感じました。そのため、この痛ましい出来事を、過労自殺してしまったこの女性に対する「周囲の評価」を意識しながら考えこんでしまいましたが、それをここに記してしまいます。
この一年目の女性は周囲の人達にどう評価されていたのでしょうか。女性がツイッターに書かれた言葉である「君の残業時間の20時間は会社にとって無駄」や、「女子力がない」を拝見する限り、この女性が「仕事ができない」と周囲に評価されていた可能性が、もしかしたらあるのではないかと思います。なぜなら、もし職場で一目置かれている優秀な若手にそんなことを言ったとしたら、言った人が逆に周囲に非難されるからです。「あいつに何てことを言うんだ。あいつが辞めたらお前のせいだ」と。そして、小さなことかもしれませんが、この一つの可能性を見落してしまうと、現実を見間違えかねないとも思います。
もし、「仕事ができない」と評価されてしまっていたとしたら、その人は職場で排除される傾向にあると言えます。つまり、職場の人々は「育成」の真逆方向へ突き進む傾向にあると言えます。例えば、「仕事ができない」と周囲に評価されている部下を持った上司は、往々にして被害者意識を持つものですが、被害者意識を持ちつつも無意識的にその部下を利用しようともします。つまり、何か問題が発生しそうになったら、その部下に責任があったといえる様に持っていくという形で。そして、実際に問題が発生したら、その部下に責任ありと声高に主張します。建前上は部下の失敗は上司の責任ですが、実際にはその上司の上司がどう判断するのかによるので、主張が通れば上司は責任を回避できたりもします。他にも、例えば、面倒臭くかつ難易度が高いけれどもさほど重要では無い様な仕事は「仕事ができない」と評価されている社員に与えられます。ある種のゴミ箱のようになるのです。それで案の定、それらの仕事が頓挫すると過度に非難されることになります。この様に追い詰めていくことで、職場の人々は自身の鬱憤を晴らしながらも、最終的には円満退社まで持って行こうとします。一方で、「仕事ができない」と評価された人がそんな状況で仕事をしていくと、例えば、仕事をする上で過剰に相手の考えを斟酌してしまうなど、独特な癖が付いたりしてしまい、更に仕事ができなくなってしまったりもします。もちろん、そんな中、親切に接してくれる人が現れることもありますが、その親切な人も上司や顧客になったりすると、一転してパワハラや大クレームをしてくるものです。それが分かるだけに、誰に対しても心を開くことはできなくなっていきます。
もちろん、こんな状況から抜け出すための方法として、一旦会社を辞めて他社で仕事に再挑戦するという選択肢も考えられます。しかし、周囲に「仕事ができない」と評価されたら、それを察知して、自分は「仕事ができない」と思うのが普通であり、そのように自他供に「仕事ができない」と認めている状態で退職してしまっては、転職後に「仕事ができる」人になれるという根拠を見つけることは、とてもできません。というか、そもそも転職できる自信を持てません。だから、転職をしないで今の職場に留まるという現実的な選択をする様になります。そして、極度に孤独な状況下、うまくいかなくてもめげずに仕事に取り組んでいこうとするのです。ただひたすら「仕事ができる」人になることを目指して。
ちなみに、仮に、過労自殺してしまった一年目の女性が、自分は「仕事ができない」と思っていたとしたなら、グローバルビジネス学会という学会に所属されている、ある60代の男性教授が、偶然ではあるものの同じ10月7日に書かれた 「月当たり残業時間が100時間を越えたくらいで過労死するのは情けない。会社の業務をこなすというより、自分が請け負った仕事をプロとして完遂するという強い意識があれば、残業時間など関係ない。自分で起業した人は、それこそ寝袋を会社に持ち込んで、仕事に打ち込んだ時期があるはず。更にプロ意識があれば、上司を説得してでも良い成果を出せるように人的資源を獲得すべく最大の努力をすべき。それでも駄目なら、その会社が組織として機能していないので、転職を考えるべき。また、転職できるプロであるべき長期的に自分への投資を続けるべき。」 という文章は、単なる、参考にならないアドバイスとなってしまうことが分かります。なぜなら、それは、自分は「仕事ができる」と思っている人向けのアドバイスだからです。「仕事ができる」人になろうと格闘している、「仕事ができない」と思っている人にとって、このようなアドバイスは参考になりません。さらに言うと、自分は「仕事ができない」と思っている人は、このようなアドバイスを受けても、受け流すことしかできません。なぜなら、そのアドバイスがなぜ参考にならないのかを説明することは、いかに自分が「仕事ができない」かを説明することでもあり、過酷な作業になるからです。
また、先生は、その後の謝罪文の一部に「とてもつらい長時間労働を乗り切らないと、会社が危なくなる自分の過去の経験」とも書かれていた様です。この部分だけを拝見する限り、先生はご自身が「仕事ができる」人であると考えられている様に見えます。一方で、自分は「仕事ができない」と考えている人にとっては「とてもつらい長時間労働を乗り切らないと、会社が危なくなる」事態は発生し得ません。なぜなら、「仕事ができない」自分が、傾きそうな会社を救う事態などありえないからです。「仕事ができない」と思っている人が感じていることは、そんな大袈裟なものではなく実にシンプルで、自分が辞めて他の人が入社した方がよっぽど会社のためになるのではないかということです。この「仕事ができる」と思っている人と「仕事ができない」と思っている人との間の意識の違いは、実は大きなものです。
しかし、仮に、過労自殺してしまったこの女性が「仕事ができない」と周囲に評価されており、そのために自分でもそう思っていたとしても、この女性が本当に「仕事ができない」人であったとは、私には全く思えません。単に「仕事が出来る」と評価されるための基準が極端に高かっただけだと思うまでです。背景に、今の雇用制度では、質・量ともにとてつもない高みを要求されるため要求を満たせない「仕事ができないことになっている若手」と、社内で役割がほとんど無いにも関わらず高給取りの「仕事をしていることになっている中高年」が随時生み出されているということがあります。このことは、終身雇用と年功賃金が残ったまま事業拡大が減速し、どこでも現場担当者は不足し偉い管理者は余っているために、自然に起こることです。
そして、私が一連の報道に触れてつくづく感じるのは、仕事をしていると思っている大学の先生が、実は、仕事をしていることになっているだけの、仕事をしていない(もしかしたら「仕事ができない」)大学の先生であるのかもしれず、一方で、自殺してしまった女性が、仮に「仕事ができない」と自他供に認める女性であったとしても、それは単に「仕事ができない」とされていただけで、本当は「仕事ができる」女性であったのかもしれないということです。
このようなことを考えつつ、この女性がツイッターに記した「がんばれると思ってたのに予想外に早くつぶれてしまって自己嫌悪だな」とか「生きているために働いているのか、働くために生きているのか分からなくなって」という言葉を拝見するにつけ、言いようの無い悲しみにとらわれます。
もちろん、過労自殺してしまった女性が周囲に優秀な「仕事ができる」若手と評価されていた可能性も大いにあります。しかし、万が一「仕事ができない」と評価されていた女性であったとしても、この出来事は、自己責任などでは片づけられない、今の社会を反映した痛ましい出来事であることに変わりは無いのだと思います。
本書を読んで、思わず以上のことを考えてしまいました。私は特定の一つのニュースについて考えるためのヒントを得るために本書を読んだので、私の本書へのアプローチはあまり一般的なものではなかったものと思います。しかし、本書は過労自殺を考える上で、非常に参考になると思いました。ご一読をお薦め致します。
なお、蛇足ながら一言申し添えます。大きな票田である団塊世代の正社員の雇用を何とかして守る、という必要がなくなった今、「解雇には厳しく、過労には緩い」という従来の日本の雇用制度が急速に変化していく可能性があります。そうなったら、「仕事ができないことになっていた若手」と「仕事をしていることになっていた中高年」が、ともにドライに評価されていくことになるでしょう。その時、「仕事ができないことになっていた若手」は、いくらか余裕を持つことになるのかもしれませんが、「仕事をしていることになっていた中高年」は大丈夫なんでしょうか。仕事をしていることになっていた団塊世代のようには逃げ切れないことになります。そんなことも合わせて考えてしまいました。
- 2014年12月26日に日本でレビュー済み状況に同情しますし、いわれのない理不尽への怒りややりきれなさ、遺族の憤りにも共感はできます。
が、ハラスメントなく、労基を厳格に守り、残業もなく、体調が悪い時は配慮し、義理や周囲の迷惑は考えず、新人は丁寧に指導研修し、ベテランになれない異動は命じず、役職が上がっても責任は重くならず、突発案件発生時の余剰人員も確保し、ノルマもなくetc.…「そんな職場や仕事どこにあるんだ」仮にあったとして会社も本人も経済的に成り立つのか、と思った事も否めません。