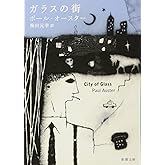無料のKindleアプリをダウンロードして、スマートフォン、タブレット、またはコンピューターで今すぐKindle本を読むことができます。Kindleデバイスは必要ありません。
ウェブ版Kindleなら、お使いのブラウザですぐにお読みいただけます。
携帯電話のカメラを使用する - 以下のコードをスキャンし、Kindleアプリをダウンロードしてください。

ガラスの街 単行本 – 2009/10/31
- 本の長さ223ページ
- 言語日本語
- 出版社新潮社
- 発売日2009/10/31
- ISBN-104105217135
- ISBN-13978-4105217136
この著者の人気タイトル
ページ 1 以下のうち 1 最初から観るページ 1 以下のうち 1
登録情報
- 出版社 : 新潮社 (2009/10/31)
- 発売日 : 2009/10/31
- 言語 : 日本語
- 単行本 : 223ページ
- ISBN-10 : 4105217135
- ISBN-13 : 978-4105217136
- Amazon 売れ筋ランキング: - 449,368位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- - 117,700位文学・評論 (本)
- カスタマーレビュー:
著者について
著者をフォローして、新作のアップデートや改善されたおすすめを入手してください。

著者の本をもっと発見したり、よく似た著者を見つけたり、著者のブログを読んだりしましょう
イメージ付きのレビュー
4 星
読むにつれて錯綜しアイデンティティーの揺さぶりをかける類を見ない物語
ニューヨークに住むダニエル・クインは、かつては探偵小説で腕を鳴らした名作家。しかし現在はというと、世間をあっといわせるような作品を書こうといった野望もなく、匿名で細々とミステリーを執筆しながらの生活をする状況です。そんなクインのもとにある日、彼に助けを求める電話がかかってきました。電話の内容は「探偵のポール・オースター氏に事件を解決してほしい」というもの。しかし、ポール・オースターという人物にさっぱり心当たりのないクイン。間違い電話と考え、その場では電話を切ってしまいます。ところが、助けを求める電話はその後も日を置いてかかってくるため、やむなくクインはポール・オースターなる探偵のふりをして電話の主に会うことにしたのでした。指定の場所でクインを待っていたのは、ヴァージニアと名乗る女性。彼女は依頼人のピーター・スティルマンの妻だと言います。依頼人のスティルマンはというと、幼少期に外の世界から隔絶され、長年の間暗い部屋に閉じ込められて過ごした過去を持つ人物ということでした。そんなスティルマンを暗闇から救い出したのは、彼の父親であるスティルマン氏。しかし現在、スティルマン氏は精神に異常をきたしており病院に収容されているとのこと。闇の中で長年過ごし他者との交流もままならなかったスティルマンの話は要領を得ないため、クインは代わりに妻のヴァージニアから依頼を受けることになります。ヴァージニアの依頼とは、間もなく退院する父親から夫を守って欲しいというものでした。「そもそものはじまりは間違い電話だった」という書き出しから始まる本書は、いかにもミステリー仕立てという感じで、レイモンド・チャンドラーのようなハードボイルドな探偵小説の雰囲気を漂わせています。しかしそれも最初のうちだけで、探偵小説やミステリーの趣からは徐々に離れ始めます。というのも、ミステリー作家であるクインが、自分のペンネームの「ウィリアム・ウィルソン」と、小説に登場する探偵「マックス・ワーク」について思弁し、やたらと2人の人物を引き合いに出すことが増えてきて、雲行きがだんだん怪しくなってくるからです。クインにとってのウィリアム・ウィルソンはあくまで小説を出す時に名を借りる抽象的な人物であり、これに対しあくまで小説の登場人物に過ぎない探偵のワークが、なぜか実体を持っているかのように生き生きと存在感を増してくるわけです。ウィルソンがまるで人形遣いで、クイン自身は人形、そしてワークは次第にこの物語に目的をかのような生気に満ちた役回りを与えられるのです。小説が進むにつれ、クインとウィルソンそしてワークという3人の人物によって、次第に錯綜し始める物語。このことから私は、自分自身や他者との継続的に変化し続ける対話のプロセスによって個人のアイデンティティは定義されるという、ミシェル・フーコー的なものを感じました。加えて、スティルマンに迫る父親が宗教学の権威の元大学教授というのも本書のディテールにまた彩りを加えます。スティルマン教授は自身の著書『楽園と塔』の中で、第二のエデンの園を来るべき新世界のビジョンとして描き、バベルの塔の崩壊の原因となった人々の言語の混乱を堕落したアダムと重ね合わせて論じます。そして、真の言語の復活により世界は新たな楽園として再臨すると綴り、息子への仕打ちは、エデンの園で人間が堕落する前の神の言語を発見するための実験であったという事が示唆され始めるのですが。旧約聖書の引用からのビジョンを多分に含む本書は、象徴に富んでおり、ディック作品にみられるアイデンティティーの揺さぶりとも相まって、今までに味わったことのない不思議な雰囲気をもつ一冊と言えます。故にミステリや探偵小説を期待するとかなり面食らうことになり、決して読みやすい内容とは言えません。しかし、読んでいくうちにどんどん錯綜していくテーマだとか、主人公のアイデンティティが喪失していく(ネタバレになっちゃうのでこれ以上は書けない)展開を期待する人にとってはまたとない一冊になると思います。
フィードバックをお寄せいただきありがとうございます
申し訳ありませんが、エラーが発生しました
申し訳ありませんが、レビューを読み込めませんでした
-
トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中に問題が発生しました。後でもう一度試してください。
2024年5月23日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
この作品はどこの出版社も最初は一顧だにしなかったらしいが出版社というのは売れる売れないという頭ありきだからそれもわかる。探偵小説のようだが本質は全く違って村上春樹の作品に近い実に現代的な奥の深い小説で仏教観に近いものさえ感じる。読後の後味は「朗読者」や「オン ザ ロード」に似たやるせない気持ちが残る。二つとも映画になったから案外この作品も映画化したら面白いかもしれないが文中のことばの深淵さと情景描写の美しさは秀逸である。探偵小説ならばこれら作中のことばのなかに真相への隠されたイースターエッグがあるのだがこの作品にはおそらくないだろう。でも読み返したくなる作品で読むたびに新しいすばらしい気づきがあるはずだ。
2020年10月11日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
既成を打破しようという試行とその成果の萌芽が見られるが、大好きな素晴らしい「ブルックリン・フォーリーズ」を読んだ後なので、あまり好きになれなかった。
2021年4月9日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
自分の輪郭を浮き上がらせるのは他者で、また他者の輪郭を浮き上がらせるのは自分である。
世界は人の数だけあって、世界の数だけの自分がいる。迷路のような街や、そこに溢れかえる人々はまるでそんなことを象徴するかのよう。
駅に降り立った、まったく対照的な身なりをした二人の同じ人物が、それぞれ右と左の反対方向へ歩き出す場面は、なんとなくパラレルワールドを連想させられました。
この作品をミステリー小説として捉えるなら、物語のストーリーを追い、謎を解こうとすることには何の意味もないように思います。
なぜなら、本当のミステリーは、読み終えた読者の心のみを起点にして動き出すからです。
世界は人の数だけあって、世界の数だけの自分がいる。迷路のような街や、そこに溢れかえる人々はまるでそんなことを象徴するかのよう。
駅に降り立った、まったく対照的な身なりをした二人の同じ人物が、それぞれ右と左の反対方向へ歩き出す場面は、なんとなくパラレルワールドを連想させられました。
この作品をミステリー小説として捉えるなら、物語のストーリーを追い、謎を解こうとすることには何の意味もないように思います。
なぜなら、本当のミステリーは、読み終えた読者の心のみを起点にして動き出すからです。
2024年5月14日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
1981年、レーガンは福音主義右派と選挙協力協定を結び、大統領選にやっと勝利した。その頃から欧米文学報道関係の人々が、米本土へのムスリム過激派の攻撃と、いつまたどこで核兵器が使われるかについて議論を始めた。本作はその議論から生まれた最初の記念碑的作品である。最初の予想は9.11貿易センタービルの爆破で現実のものとなった。二つ目の予想も的中するかもしれない。
たとえば、この作品は東京に人民解放軍のGHQが設置され、東京都庁舎に毛沢東の肖像がライトアップされるSF程の衝撃を、かれらに与えた。タイトルのガラスは鏡との複意味。
たとえば、この作品は東京に人民解放軍のGHQが設置され、東京都庁舎に毛沢東の肖像がライトアップされるSF程の衝撃を、かれらに与えた。タイトルのガラスは鏡との複意味。
2022年8月15日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
以下、感想と考察です。
●語り手の構造
この物語の構成は
クイン、オースター、オースターの友人である私という三人から構成される。
これはクインの作品
ワーク、ウィルソン、クインという三位一体の構造と相似をなしていると言える。
すなわち、ワーク=クイン、ウィルソン=オースター、クイン=私という対応関係が成り立つ
クインの作品において筆者であるウィルソンはクイン自身であることから、この相似関係に当てはめるとオースター=私であることが予想がつく。
つまり、あえてオースターという登場人物を出すことで、ドン・キホーテのように物語に信憑性を持たせているのではなかろうか。
●言語について
楽園を追放された人々は用いる言語の名前とそれが表すものが呼応しなくなった
いま私達が使っている楽園から追放された言語はソシュールの恣意的な言語を指していると思われる
物語ではソシュールの恣意的な言語の対義語としてピーターJr.が習得させられた無垢な言語が登場する。
両者の違いとして恣意的な言葉とはそれ自身に根拠がないことから別の記号、言葉に置き換え可能である特徴を持ち、一方で無垢な言語とは対象自身を直接指し示すものであるため交換不可能であるという特徴を持つ。
そのため恣意的な言葉で生きる私達の周りは交換可能な言葉で溢れるため無秩序に混沌としているとスティルマン父は考える
このことはオースターの小説の特徴に見られる登場人物が交換可能ということにも現れている
彼の作品では見られるもの、見るもの、他者と自己との区別とその境界が曖昧になる。それによって登場人物は混沌を極め、ついには入れ替わり、交換可能な状態となってしまう。このことはソシュールの言う恣意的な言語で描かれる物語である以上、登場人物に物語上は常に交換可能であるという彼の文学的見地の表れなのではないだろうか
●偶然と運命
そもそものはじまりは間違い電話だった
この偶発的な出来事から物語が始まる
しかし、この間違いが実は必然性、即ち運命によって引き起こされたことをクインは最後に理解する。
このことは、突き詰めると運命=偶然は交換可能でありそれを捉えた人物により恣意的に語られる言葉であることを示唆しているのではないだろうか
●本書に残る謎
以上のことから筆者は恣意的に語ることができないリアルを描こうとする。実際にフィクションではあるものの、物語中で筆者は事実だけを紡いで物語を構成するよう努力する。
だからこそ、客観的立場をとれる第三者という遠回しなやり方で物語を語るという形式がとられているのではないだろうか
なぜスティルマン氏は自殺したのか
なぜスティルマン氏はセントラル駅で分裂したのか
なぜ小切手は不渡りだったのか
スティルマン夫妻はどこへいったのか
クインはどうなったのか
それらは事実のみが述べられており、意味や理由は描かれていない。きっとそれこそがこの小説がとるべき態度なのだろう。
●語り手の構造
この物語の構成は
クイン、オースター、オースターの友人である私という三人から構成される。
これはクインの作品
ワーク、ウィルソン、クインという三位一体の構造と相似をなしていると言える。
すなわち、ワーク=クイン、ウィルソン=オースター、クイン=私という対応関係が成り立つ
クインの作品において筆者であるウィルソンはクイン自身であることから、この相似関係に当てはめるとオースター=私であることが予想がつく。
つまり、あえてオースターという登場人物を出すことで、ドン・キホーテのように物語に信憑性を持たせているのではなかろうか。
●言語について
楽園を追放された人々は用いる言語の名前とそれが表すものが呼応しなくなった
いま私達が使っている楽園から追放された言語はソシュールの恣意的な言語を指していると思われる
物語ではソシュールの恣意的な言語の対義語としてピーターJr.が習得させられた無垢な言語が登場する。
両者の違いとして恣意的な言葉とはそれ自身に根拠がないことから別の記号、言葉に置き換え可能である特徴を持ち、一方で無垢な言語とは対象自身を直接指し示すものであるため交換不可能であるという特徴を持つ。
そのため恣意的な言葉で生きる私達の周りは交換可能な言葉で溢れるため無秩序に混沌としているとスティルマン父は考える
このことはオースターの小説の特徴に見られる登場人物が交換可能ということにも現れている
彼の作品では見られるもの、見るもの、他者と自己との区別とその境界が曖昧になる。それによって登場人物は混沌を極め、ついには入れ替わり、交換可能な状態となってしまう。このことはソシュールの言う恣意的な言語で描かれる物語である以上、登場人物に物語上は常に交換可能であるという彼の文学的見地の表れなのではないだろうか
●偶然と運命
そもそものはじまりは間違い電話だった
この偶発的な出来事から物語が始まる
しかし、この間違いが実は必然性、即ち運命によって引き起こされたことをクインは最後に理解する。
このことは、突き詰めると運命=偶然は交換可能でありそれを捉えた人物により恣意的に語られる言葉であることを示唆しているのではないだろうか
●本書に残る謎
以上のことから筆者は恣意的に語ることができないリアルを描こうとする。実際にフィクションではあるものの、物語中で筆者は事実だけを紡いで物語を構成するよう努力する。
だからこそ、客観的立場をとれる第三者という遠回しなやり方で物語を語るという形式がとられているのではないだろうか
なぜスティルマン氏は自殺したのか
なぜスティルマン氏はセントラル駅で分裂したのか
なぜ小切手は不渡りだったのか
スティルマン夫妻はどこへいったのか
クインはどうなったのか
それらは事実のみが述べられており、意味や理由は描かれていない。きっとそれこそがこの小説がとるべき態度なのだろう。
2017年8月19日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
やっぱりトシなのかなぁ。病院での付き添い中ときて長編はムリなのかも
中断ばかりしていたせいか、内容がさっぱり、柴田元幸氏の訳はとても
読みやすいのにピンとこなくて、オースターの良さがわかりませんでした。
いつになるかわからないけど、もう一度ゆっくり読んでのレビューにしたいと
今はおもいます。あいすみませんです。
中断ばかりしていたせいか、内容がさっぱり、柴田元幸氏の訳はとても
読みやすいのにピンとこなくて、オースターの良さがわかりませんでした。
いつになるかわからないけど、もう一度ゆっくり読んでのレビューにしたいと
今はおもいます。あいすみませんです。
2023年10月10日に日本でレビュー済み

ニューヨークに住むダニエル・クインは、かつては探偵小説で腕を鳴らした名作家。しかし現在はというと、世間をあっといわせるような作品を書こうといった野望もなく、匿名で細々とミステリーを執筆しながらの生活をする状況です。そんなクインのもとにある日、彼に助けを求める電話がかかってきました。電話の内容は「探偵のポール・オースター氏に事件を解決してほしい」というもの。
しかし、ポール・オースターという人物にさっぱり心当たりのないクイン。間違い電話と考え、その場では電話を切ってしまいます。ところが、助けを求める電話はその後も日を置いてかかってくるため、やむなくクインはポール・オースターなる探偵のふりをして電話の主に会うことにしたのでした。
指定の場所でクインを待っていたのは、ヴァージニアと名乗る女性。彼女は依頼人のピーター・スティルマンの妻だと言います。依頼人のスティルマンはというと、幼少期に外の世界から隔絶され、長年の間暗い部屋に閉じ込められて過ごした過去を持つ人物ということでした。そんなスティルマンを暗闇から救い出したのは、彼の父親であるスティルマン氏。しかし現在、スティルマン氏は精神に異常をきたしており病院に収容されているとのこと。闇の中で長年過ごし他者との交流もままならなかったスティルマンの話は要領を得ないため、クインは代わりに妻のヴァージニアから依頼を受けることになります。ヴァージニアの依頼とは、間もなく退院する父親から夫を守って欲しいというものでした。
「そもそものはじまりは間違い電話だった」という書き出しから始まる本書は、いかにもミステリー仕立てという感じで、レイモンド・チャンドラーのようなハードボイルドな探偵小説の雰囲気を漂わせています。しかしそれも最初のうちだけで、探偵小説やミステリーの趣からは徐々に離れ始めます。というのも、ミステリー作家であるクインが、自分のペンネームの「ウィリアム・ウィルソン」と、小説に登場する探偵「マックス・ワーク」について思弁し、やたらと2人の人物を引き合いに出すことが増えてきて、雲行きがだんだん怪しくなってくるからです。クインにとってのウィリアム・ウィルソンはあくまで小説を出す時に名を借りる抽象的な人物であり、これに対しあくまで小説の登場人物に過ぎない探偵のワークが、なぜか実体を持っているかのように生き生きと存在感を増してくるわけです。ウィルソンがまるで人形遣いで、クイン自身は人形、そしてワークは次第にこの物語に目的をかのような生気に満ちた役回りを与えられるのです。
小説が進むにつれ、クインとウィルソンそしてワークという3人の人物によって、次第に錯綜し始める物語。このことから私は、自分自身や他者との継続的に変化し続ける対話のプロセスによって個人のアイデンティティは定義されるという、ミシェル・フーコー的なものを感じました。加えて、スティルマンに迫る父親が宗教学の権威の元大学教授というのも本書のディテールにまた彩りを加えます。スティルマン教授は自身の著書『楽園と塔』の中で、第二のエデンの園を来るべき新世界のビジョンとして描き、バベルの塔の崩壊の原因となった人々の言語の混乱を堕落したアダムと重ね合わせて論じます。そして、真の言語の復活により世界は新たな楽園として再臨すると綴り、息子への仕打ちは、エデンの園で人間が堕落する前の神の言語を発見するための実験であったという事が示唆され始めるのですが。
旧約聖書の引用からのビジョンを多分に含む本書は、象徴に富んでおり、ディック作品にみられるアイデンティティーの揺さぶりとも相まって、今までに味わったことのない不思議な雰囲気をもつ一冊と言えます。故にミステリや探偵小説を期待するとかなり面食らうことになり、決して読みやすい内容とは言えません。しかし、読んでいくうちにどんどん錯綜していくテーマだとか、主人公のアイデンティティが喪失していく(ネタバレになっちゃうのでこれ以上は書けない)展開を期待する人にとってはまたとない一冊になると思います。
しかし、ポール・オースターという人物にさっぱり心当たりのないクイン。間違い電話と考え、その場では電話を切ってしまいます。ところが、助けを求める電話はその後も日を置いてかかってくるため、やむなくクインはポール・オースターなる探偵のふりをして電話の主に会うことにしたのでした。
指定の場所でクインを待っていたのは、ヴァージニアと名乗る女性。彼女は依頼人のピーター・スティルマンの妻だと言います。依頼人のスティルマンはというと、幼少期に外の世界から隔絶され、長年の間暗い部屋に閉じ込められて過ごした過去を持つ人物ということでした。そんなスティルマンを暗闇から救い出したのは、彼の父親であるスティルマン氏。しかし現在、スティルマン氏は精神に異常をきたしており病院に収容されているとのこと。闇の中で長年過ごし他者との交流もままならなかったスティルマンの話は要領を得ないため、クインは代わりに妻のヴァージニアから依頼を受けることになります。ヴァージニアの依頼とは、間もなく退院する父親から夫を守って欲しいというものでした。
「そもそものはじまりは間違い電話だった」という書き出しから始まる本書は、いかにもミステリー仕立てという感じで、レイモンド・チャンドラーのようなハードボイルドな探偵小説の雰囲気を漂わせています。しかしそれも最初のうちだけで、探偵小説やミステリーの趣からは徐々に離れ始めます。というのも、ミステリー作家であるクインが、自分のペンネームの「ウィリアム・ウィルソン」と、小説に登場する探偵「マックス・ワーク」について思弁し、やたらと2人の人物を引き合いに出すことが増えてきて、雲行きがだんだん怪しくなってくるからです。クインにとってのウィリアム・ウィルソンはあくまで小説を出す時に名を借りる抽象的な人物であり、これに対しあくまで小説の登場人物に過ぎない探偵のワークが、なぜか実体を持っているかのように生き生きと存在感を増してくるわけです。ウィルソンがまるで人形遣いで、クイン自身は人形、そしてワークは次第にこの物語に目的をかのような生気に満ちた役回りを与えられるのです。
小説が進むにつれ、クインとウィルソンそしてワークという3人の人物によって、次第に錯綜し始める物語。このことから私は、自分自身や他者との継続的に変化し続ける対話のプロセスによって個人のアイデンティティは定義されるという、ミシェル・フーコー的なものを感じました。加えて、スティルマンに迫る父親が宗教学の権威の元大学教授というのも本書のディテールにまた彩りを加えます。スティルマン教授は自身の著書『楽園と塔』の中で、第二のエデンの園を来るべき新世界のビジョンとして描き、バベルの塔の崩壊の原因となった人々の言語の混乱を堕落したアダムと重ね合わせて論じます。そして、真の言語の復活により世界は新たな楽園として再臨すると綴り、息子への仕打ちは、エデンの園で人間が堕落する前の神の言語を発見するための実験であったという事が示唆され始めるのですが。
旧約聖書の引用からのビジョンを多分に含む本書は、象徴に富んでおり、ディック作品にみられるアイデンティティーの揺さぶりとも相まって、今までに味わったことのない不思議な雰囲気をもつ一冊と言えます。故にミステリや探偵小説を期待するとかなり面食らうことになり、決して読みやすい内容とは言えません。しかし、読んでいくうちにどんどん錯綜していくテーマだとか、主人公のアイデンティティが喪失していく(ネタバレになっちゃうのでこれ以上は書けない)展開を期待する人にとってはまたとない一冊になると思います。
ニューヨークに住むダニエル・クインは、かつては探偵小説で腕を鳴らした名作家。しかし現在はというと、世間をあっといわせるような作品を書こうといった野望もなく、匿名で細々とミステリーを執筆しながらの生活をする状況です。そんなクインのもとにある日、彼に助けを求める電話がかかってきました。電話の内容は「探偵のポール・オースター氏に事件を解決してほしい」というもの。
しかし、ポール・オースターという人物にさっぱり心当たりのないクイン。間違い電話と考え、その場では電話を切ってしまいます。ところが、助けを求める電話はその後も日を置いてかかってくるため、やむなくクインはポール・オースターなる探偵のふりをして電話の主に会うことにしたのでした。
指定の場所でクインを待っていたのは、ヴァージニアと名乗る女性。彼女は依頼人のピーター・スティルマンの妻だと言います。依頼人のスティルマンはというと、幼少期に外の世界から隔絶され、長年の間暗い部屋に閉じ込められて過ごした過去を持つ人物ということでした。そんなスティルマンを暗闇から救い出したのは、彼の父親であるスティルマン氏。しかし現在、スティルマン氏は精神に異常をきたしており病院に収容されているとのこと。闇の中で長年過ごし他者との交流もままならなかったスティルマンの話は要領を得ないため、クインは代わりに妻のヴァージニアから依頼を受けることになります。ヴァージニアの依頼とは、間もなく退院する父親から夫を守って欲しいというものでした。
「そもそものはじまりは間違い電話だった」という書き出しから始まる本書は、いかにもミステリー仕立てという感じで、レイモンド・チャンドラーのようなハードボイルドな探偵小説の雰囲気を漂わせています。しかしそれも最初のうちだけで、探偵小説やミステリーの趣からは徐々に離れ始めます。というのも、ミステリー作家であるクインが、自分のペンネームの「ウィリアム・ウィルソン」と、小説に登場する探偵「マックス・ワーク」について思弁し、やたらと2人の人物を引き合いに出すことが増えてきて、雲行きがだんだん怪しくなってくるからです。クインにとってのウィリアム・ウィルソンはあくまで小説を出す時に名を借りる抽象的な人物であり、これに対しあくまで小説の登場人物に過ぎない探偵のワークが、なぜか実体を持っているかのように生き生きと存在感を増してくるわけです。ウィルソンがまるで人形遣いで、クイン自身は人形、そしてワークは次第にこの物語に目的をかのような生気に満ちた役回りを与えられるのです。
小説が進むにつれ、クインとウィルソンそしてワークという3人の人物によって、次第に錯綜し始める物語。このことから私は、自分自身や他者との継続的に変化し続ける対話のプロセスによって個人のアイデンティティは定義されるという、ミシェル・フーコー的なものを感じました。加えて、スティルマンに迫る父親が宗教学の権威の元大学教授というのも本書のディテールにまた彩りを加えます。スティルマン教授は自身の著書『楽園と塔』の中で、第二のエデンの園を来るべき新世界のビジョンとして描き、バベルの塔の崩壊の原因となった人々の言語の混乱を堕落したアダムと重ね合わせて論じます。そして、真の言語の復活により世界は新たな楽園として再臨すると綴り、息子への仕打ちは、エデンの園で人間が堕落する前の神の言語を発見するための実験であったという事が示唆され始めるのですが。
旧約聖書の引用からのビジョンを多分に含む本書は、象徴に富んでおり、ディック作品にみられるアイデンティティーの揺さぶりとも相まって、今までに味わったことのない不思議な雰囲気をもつ一冊と言えます。故にミステリや探偵小説を期待するとかなり面食らうことになり、決して読みやすい内容とは言えません。しかし、読んでいくうちにどんどん錯綜していくテーマだとか、主人公のアイデンティティが喪失していく(ネタバレになっちゃうのでこれ以上は書けない)展開を期待する人にとってはまたとない一冊になると思います。
しかし、ポール・オースターという人物にさっぱり心当たりのないクイン。間違い電話と考え、その場では電話を切ってしまいます。ところが、助けを求める電話はその後も日を置いてかかってくるため、やむなくクインはポール・オースターなる探偵のふりをして電話の主に会うことにしたのでした。
指定の場所でクインを待っていたのは、ヴァージニアと名乗る女性。彼女は依頼人のピーター・スティルマンの妻だと言います。依頼人のスティルマンはというと、幼少期に外の世界から隔絶され、長年の間暗い部屋に閉じ込められて過ごした過去を持つ人物ということでした。そんなスティルマンを暗闇から救い出したのは、彼の父親であるスティルマン氏。しかし現在、スティルマン氏は精神に異常をきたしており病院に収容されているとのこと。闇の中で長年過ごし他者との交流もままならなかったスティルマンの話は要領を得ないため、クインは代わりに妻のヴァージニアから依頼を受けることになります。ヴァージニアの依頼とは、間もなく退院する父親から夫を守って欲しいというものでした。
「そもそものはじまりは間違い電話だった」という書き出しから始まる本書は、いかにもミステリー仕立てという感じで、レイモンド・チャンドラーのようなハードボイルドな探偵小説の雰囲気を漂わせています。しかしそれも最初のうちだけで、探偵小説やミステリーの趣からは徐々に離れ始めます。というのも、ミステリー作家であるクインが、自分のペンネームの「ウィリアム・ウィルソン」と、小説に登場する探偵「マックス・ワーク」について思弁し、やたらと2人の人物を引き合いに出すことが増えてきて、雲行きがだんだん怪しくなってくるからです。クインにとってのウィリアム・ウィルソンはあくまで小説を出す時に名を借りる抽象的な人物であり、これに対しあくまで小説の登場人物に過ぎない探偵のワークが、なぜか実体を持っているかのように生き生きと存在感を増してくるわけです。ウィルソンがまるで人形遣いで、クイン自身は人形、そしてワークは次第にこの物語に目的をかのような生気に満ちた役回りを与えられるのです。
小説が進むにつれ、クインとウィルソンそしてワークという3人の人物によって、次第に錯綜し始める物語。このことから私は、自分自身や他者との継続的に変化し続ける対話のプロセスによって個人のアイデンティティは定義されるという、ミシェル・フーコー的なものを感じました。加えて、スティルマンに迫る父親が宗教学の権威の元大学教授というのも本書のディテールにまた彩りを加えます。スティルマン教授は自身の著書『楽園と塔』の中で、第二のエデンの園を来るべき新世界のビジョンとして描き、バベルの塔の崩壊の原因となった人々の言語の混乱を堕落したアダムと重ね合わせて論じます。そして、真の言語の復活により世界は新たな楽園として再臨すると綴り、息子への仕打ちは、エデンの園で人間が堕落する前の神の言語を発見するための実験であったという事が示唆され始めるのですが。
旧約聖書の引用からのビジョンを多分に含む本書は、象徴に富んでおり、ディック作品にみられるアイデンティティーの揺さぶりとも相まって、今までに味わったことのない不思議な雰囲気をもつ一冊と言えます。故にミステリや探偵小説を期待するとかなり面食らうことになり、決して読みやすい内容とは言えません。しかし、読んでいくうちにどんどん錯綜していくテーマだとか、主人公のアイデンティティが喪失していく(ネタバレになっちゃうのでこれ以上は書けない)展開を期待する人にとってはまたとない一冊になると思います。
このレビューの画像