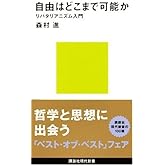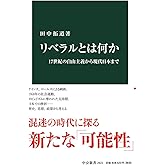つい、値段と商品説明にて衝動買いをしてしまいましたが、非常に良い物を送って戴き感謝しております。有難うございました。
この注文でお急ぎ便、お届け日時指定便を無料体験
Amazonプライム無料体験について
Amazonプライム無料体験について
プライム無料体験をお試しいただけます
プライム無料体験で、この注文から無料配送特典をご利用いただけます。
| 非会員 | プライム会員 | |
|---|---|---|
| 通常配送 | ¥460 - ¥500* | 無料 |
| お急ぎ便 | ¥510 - ¥550 | |
| お届け日時指定便 | ¥510 - ¥650 |
*Amazon.co.jp発送商品の注文額 ¥3,500以上は非会員も無料
無料体験はいつでもキャンセルできます。30日のプライム無料体験をぜひお試しください。
新品:
¥880¥880 税込
発送元: Amazon.co.jp 販売者: Amazon.co.jp
新品:
¥880¥880 税込
発送元: Amazon.co.jp
販売者: Amazon.co.jp
中古品 - 非常に良い
¥731¥731 税込
無料配送 4月13日-15日にお届け
発送元: 買取王子 本店 販売者: 買取王子 本店
中古品 - 非常に良い
¥731¥731 税込
無料配送 4月13日-15日にお届け
発送元: 買取王子 本店
販売者: 買取王子 本店

無料のKindleアプリをダウンロードして、スマートフォン、タブレット、またはコンピューターで今すぐKindle本を読むことができます。Kindleデバイスは必要ありません。
ウェブ版Kindleなら、お使いのブラウザですぐにお読みいただけます。
携帯電話のカメラを使用する - 以下のコードをスキャンし、Kindleアプリをダウンロードしてください。

リバタリアニズム-アメリカを揺るがす自由至上主義 (中公新書) 新書 – 2019/1/18
渡辺 靖
(著)
このページの読み込み中に問題が発生しました。もう一度試してください。
{"desktop_buybox_group_1":[{"displayPrice":"¥880","priceAmount":880.00,"currencySymbol":"¥","integerValue":"880","decimalSeparator":null,"fractionalValue":null,"symbolPosition":"left","hasSpace":false,"showFractionalPartIfEmpty":true,"offerListingId":"mBVNr3Dp6Y9u2YnkbirPLwexU2Ozd9xd9RUDB4gFurWnaTfEW%2FlhRDRle9dmI5DmsEcSTo2M4pOqgcuae0mmr%2B3hB%2FzzJ1ayIZtfvcY7pSqi%2FOFgJeOvklm6Y07FX6RDyN9e3fDiO%2FI%3D","locale":"ja-JP","buyingOptionType":"NEW","aapiBuyingOptionIndex":0}, {"displayPrice":"¥731","priceAmount":731.00,"currencySymbol":"¥","integerValue":"731","decimalSeparator":null,"fractionalValue":null,"symbolPosition":"left","hasSpace":false,"showFractionalPartIfEmpty":true,"offerListingId":"mBVNr3Dp6Y9u2YnkbirPLwexU2Ozd9xdzY1jhqw2WlTx6JYbyfs%2B1tg06IEZg77MCKvJVu9qtjEmwugY6LM9wwTil9Jk0k4Qj%2FUkw0dW5y5%2BMSFwyIWrCpgE8te%2FmSfk9cr%2BAciYRG65RKdKSA%2BCpukYLysfm%2BGIxmW6M0BRiWiFsQWOiOJTJQ%3D%3D","locale":"ja-JP","buyingOptionType":"USED","aapiBuyingOptionIndex":1}]}
購入オプションとあわせ買い
アメリカ社会、とりわけ若い世代に広がりつつあるリバタリアニズム(自由至上主義)。公権力を極限まで排除し、自由の極大化をめざす立場だ。リベラルのように人工妊娠中絶、同性婚に賛成し、死刑や軍備増強に反対するが、保守のように社会保障費の増額や銃規制に反対するなど、従来の左右対立の枠組みではとらえきれない。著者はトランプ政権誕生後のアメリカ各地を訪れ、実情を報告。未来を支配する思想がここにある。
- 本の長さ213ページ
- 言語日本語
- 出版社中央公論新社
- 発売日2019/1/18
- 寸法11.2 x 1 x 17.4 cm
- ISBN-104121025229
- ISBN-13978-4121025227
よく一緒に購入されている商品

対象商品: リバタリアニズム-アメリカを揺るがす自由至上主義 (中公新書)
¥880¥880
最短で4月11日 金曜日のお届け予定です
在庫あり。
¥990¥990
最短で4月11日 金曜日のお届け予定です
在庫あり。
¥946¥946
最短で4月11日 金曜日のお届け予定です
残り11点(入荷予定あり)
総額: $00$00
当社の価格を見るには、これら商品をカートに追加してください。
ポイントの合計:
pt
もう一度お試しください
追加されました
一緒に購入する商品を選択してください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
ページ: 1 / 1 最初に戻るページ: 1 / 1
商品の説明
著者について
渡辺靖
慶應義塾大学SFC教授。1967年(昭和42年)、札幌市に生まれる。97年ハーバード大学大学院博士課程修了(Ph.D.)。オクスフォード大学シニア・アソシエート、ケンブリッジ大学フェローなどを経て、99年より慶應義塾大学SFC助教授、2005年より現職。専攻、アメリカ研究、文化政策論。2004年度日本学士院学術奨励賞受賞。著書に『アフター・アメリカ』(サントリー学芸賞・アメリカ学会清水博賞受賞)、『アメリカン・コミュニティ』『アメリカン・センター』『アメリカン・デモクラシーの逆説』『文化と外交』『アメリカのジレンマ』『沈まぬアメリカ』『〈文化〉を捉え直す』など。
慶應義塾大学SFC教授。1967年(昭和42年)、札幌市に生まれる。97年ハーバード大学大学院博士課程修了(Ph.D.)。オクスフォード大学シニア・アソシエート、ケンブリッジ大学フェローなどを経て、99年より慶應義塾大学SFC助教授、2005年より現職。専攻、アメリカ研究、文化政策論。2004年度日本学士院学術奨励賞受賞。著書に『アフター・アメリカ』(サントリー学芸賞・アメリカ学会清水博賞受賞)、『アメリカン・コミュニティ』『アメリカン・センター』『アメリカン・デモクラシーの逆説』『文化と外交』『アメリカのジレンマ』『沈まぬアメリカ』『〈文化〉を捉え直す』など。
登録情報
- 出版社 : 中央公論新社 (2019/1/18)
- 発売日 : 2019/1/18
- 言語 : 日本語
- 新書 : 213ページ
- ISBN-10 : 4121025229
- ISBN-13 : 978-4121025227
- 寸法 : 11.2 x 1 x 17.4 cm
- Amazon 売れ筋ランキング: - 100,379位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- - 451位中公新書
- - 13,367位社会・政治 (本)
- - 24,466位ノンフィクション (本)
- カスタマーレビュー:
著者について
著者をフォローして、新作のアップデートや改善されたおすすめを入手してください。

著者の本をもっと見つけたり、似たような著者を調べたり、おすすめの本を読んだりできます。
カスタマーレビュー
星5つ中4.1つ
5つのうち4.1つ
104グローバルレーティング
評価はどのように計算されますか?
全体的な星の評価と星ごとの割合の内訳を計算するために、単純な平均は使用されません。その代わり、レビューの日時がどれだけ新しいかや、レビューアーがAmazonで商品を購入したかどうかなどが考慮されます。また、レビューを分析して信頼性が検証されます。
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中にエラーが発生しました。ページを再読み込みしてください。
- 2024年11月6日に日本でレビュー済み海外で学ばないかぎり、著者のような知識や視点は得られないであろうと強く思った。ロシア革命を経験したアイン・ランドは、革命がどのようなものか身をもって知りえたはずだが、亡命直後は、それを表現できず、その後、資本主義を知るようになったことで社会主義と対比、比較できるようになり資本主義の道徳的優越性を説けるようになったのだと思う。画一的な集合的価値しか知らなければ、分かっていても表現はできない。
共同体主義という集合的価値で覆われた日本には対比する視点が希薄、対立よりも立ち寄らば大樹の陰、集合的価値のなかで、どのようにうまくやるかに知恵を割くのが古来からのやり方だと思う。
「人々は、命じられたとおりにしている限り、結構自分は自由だと思うものだよ。本当に自由が試されるのは、みんなと違うことをしようとするときだ。そのときは苦労するだろうが、色んなことを学べるものさ」。
経験しても対比する視点がなければ、なかなかそれを表現するのは難しい。日本のテレビでは「デモクラシー・ギャング」(派閥)劇場が毎日のように流れている。「デモクラシー・ギャングから身を守る唯一つの方法はもっと仲間の多いほかのギャング団に入ることね」。そこからはこんな倫理観しか形成されないであろう。
そんなギャングそこかしこにはびこり、多数決の原理に訴えた個人の意思に背く財産や身体への強制的介入が日常的に起きているのがこの国の現状ではないか。これは今に始まったことではなく、古来より統治システムとして組み込まれてきたと思う(ライシャワーの著書、日本の歴史がそのようなことを示唆している)。個人の意思に背く財産や身体への強制的介入を「暴力」として認識して、明確に否定できる論理的視点を「デモクラシー・ギャング」(派閥)劇場を見て育った者が持てるだろうか。命じられたとおりにしている限り、自由だと思い、暴力に加担してもそんな意識を持つこともないのではかろうか(闇バイト)。また、統治システムとして命じられた通り動かすような体制(集団知)があるとも考えられる。
身分制社会を否定して成立したアメリカは建国思想そのものが自由主義。親と子が大統領になるなど現実と理想とは隔たりがあるが、そこで教育を受けたものであれば、その過程で必ず建国思想の影響を受けているはずである。高い教育を受けた者はことさらだろう。その自由主義という枠のなかでの左右に分かれた保守、リベラルを理解するには、対立する権威主義、共同体主義を知らなければならないはずだ。おそらく自由主義という枠内にとどまっているかぎり、そのような対立なのか理解できないはずだ。日本で教育を受けていれば権威主義、共同体主義は教えられる必要はないだろう。
実体験しなければアメリカで建国思想、自由主義がどのように息づいているのかはなかなかわからない。また、経済的、社会的、教育的分断が生活レベルでどのようなものか、実体験として知らなければ分からないだろう。現在行われている大統領選に関する国内の報道は反トランプ寄り、日本語で発信している在日アメリカ人はいわゆるアメリカのエリート層で反トランプのような気がする(エリート層以外の者が日本で日本語で発信することはあまり考えられない)。受け取る側は、権威主義/自由主義、エリート/グラスルートなど対立するどちらかの視点が欠けていることを認識する必要があろう。
- 2020年11月24日に日本でレビュー済み著者の「白人ナショナリズム」を読んでこれも読まなきゃと思っていた。というのは、この「リバタリアニズム」というのも、どうも日本人にはわかりにくい考え方だからだ。僕も体系的にこの考え方をフォローしたことなない。せいぜい、ayn randの伝記「Ayn Rand and the World She Made」をだいぶ前に読んだくらいだ。アマゾンにreviewを書いたことがあるので興味のある方はそちらを参照していただきたい。
基本的なアプローチは著者の前著と同じだ。リバタリアニズムの政党や様々な団体(その中にはcato instituteも含まれている)やworkshopを実際に訪れ、代表者にインタビューを行う。「リバタリアニズム」への批判はひとまず横において、日本人にはわかりにくいこの思想潮流の多彩にわたる特徴を丁寧に明らかにしていく。この記述論ともいうべき丁寧な解説のおかげで、この複雑な思潮の様々な側面を理解することが出来る。
政策論としては様々なvariationが存在するのだろうが、つまるところは、リバタリアニズムは保守派なるものではなく、「変化の先にある社会の在り方」という観点からは、根源的なラジカルなのだ。なぜこのような根源的なラジカリズムがアメリカでは生まれてくるのか、それはアメリカをどうとらえるか、特にアメリカ建国神話の理解が必要なのだろう。
- 2022年5月27日に日本でレビュー済みAmazonで購入ビットコインスタンダードや世紀の大博打 仮想 通貨に賭けた怪人たち
を読み、リバタリアンとは何かが気になり本書を読んだ。
本書ではリバタリアンの活動、定義、著名人の色んな例を確認する事ができた。
ネットの記事を見ているとリバタリアンの定義については色々あり、
twitterなどをみると、無政府主義などの表層的な印象をもって議論されることも少なくない。
この本を読んで自分の中でリバタリアニズムとは
個人を最大限尊重する事を前提とし、既存のルールや規制を評価、再考する姿勢だと認識した。
リベラルと保守などとの比較はノーランチャートがわかりやすいと感じた。
- 2019年2月15日に日本でレビュー済みAmazonで購入自由市場、最小国家そして社会的寛容を尊重する思想・運動としてのリバタリアニズム。
アメリカ研究の第一人者である渡辺靖氏による当該新書を読んで、左派・右派とも接点をもつ、まさに<多彩な顔>をもつリバタリアニズムの思想の広さと深さに驚かされた。サバティカルを活用しての精力的な実地調査は見事で、有識者へのインタビューや研究所スタッフとのインタラクションなど、現地の生の声を伝えている。これが本書のもつ大きな魅力だろう。
そしリバタリアニズムやリバタリアンの将来の趨勢が、ことにアメリカの政治や経済をどう動かしていくのか(ミレニアル世代中心か)、その展望も語られている。日本ではリバタリアニズムを捉える「ノーラン・チャート」のなかの象限が意識されることが少ないという氏の見解も印象的だ。リバタリアニズムを通じて日本社会をうらなう認識営為も今後はより重要になるだろう。
第3章「リバタリアニズムの思想的系譜と論争」はもっとも学術的で興味深い章だっただけに、もう少し分量を増やしての解説をしても良かったのではないか。本書ではやや薄い印象を受けた。政治哲学や社会思想の分野に限らず、あきらかに(政治)経済学の根幹にも関わってくるテーマでもあるからだ。ミーゼスやハイエクらオーストリア学派、フリードマンのシカゴ学派、ミーゼスの学説を急進化するロスバードら(ミーゼス派とハイエク派という区分もある)。そしてロールズ、ノージック、サンデルらの社会哲学。彼らの学説の距離(共通性と差異性)についても深く知りたい内容。
むろん本書はあくまで「記述論ないしは運動論としてのリバタリアニズム」の現状報告に焦点化されているので、思想的系譜や現時点での論争を新書水準(の分量)でまとめきるのは難しいだろう。その点で「☆1つ」減らしたが、それでも氏の博識ぶりは圧巻。貴重な一書の誕生とみた。
- 2021年8月1日に日本でレビュー済みAmazonで購入日本ではあまりメジャーではない「リバタリアン」の思想とその米国での動きについてまとめられている。
思想自体は経済・社会的な自由を志向するというもので、詳しくは本書を読んでいただきたい。
私が本書を読んだ背景は、自粛警察やマスク強制といった動きに「強烈な嫌悪感」を持ったことに由来する。
マスクの必要性は当然理解しているが、それを強制されたり、自分の「スペース」に不用意に立ち入られる
ことに、嫌悪感というよりも恐怖を感じるのだ。
これ以外にも、同性婚や夫婦同姓のような当事者にメリットがあり、それ以外に関係が薄い政策が、
高齢者や保守派の反対によって頓挫する、飲食業にのみ高額な補助金を出し、それ以外を無視したあまりに
大雑把な政策が継続する、といった事態への「呆れ」を感じる機会も多い。
(本書より:日本の話は耳が痛い。「規制大国」「最も成功した社会主義国」「アベノミクスの本質は
ケインズ主義」「道徳教育まで政府主導」「公文書改竄」……。私が出会った多くのリバタリアンから
揶揄された。)
この思想は著者が指摘するように「経済的には弱者切り捨てのイデオロギーであり、外交・安全保障的には
現実離れしたユートピア思想に他ならない」ものである一方で、特に権威主義を感じる日本においては、
一部取り入れるに値する思想だと考えるし、実際全員が極端な自由主義者というわけではない。
コロナ禍において、「俺のことは放っておいてくれ!」と叫びたくなる衝動が高まっている私は
少なくともそう思うのであった。
- 2021年4月18日に日本でレビュー済みリバタリアニズム(自由至上主義)とは何か。アメリカの活動家達を訪ね歩く。
リバタリアニズムは経済優先というわけでもない。トランプの様なものとも違う。
リバタリアニズムは国家や政治からなるべく自由に。でもそれは自然に任せた弱肉強食の世界とも違う。細かい部分は色んな考えがあって違うが、決して無慈悲な冷たい社会を理想としてるのではないことは感じられた。
アメリカでも少数派なリバタリアニズム。だが、その思想から学べることは少なくないのではないか。
- 2019年1月20日に日本でレビュー済みAmazonで購入著者の学問的背景には文化人類学があり、そのため本書は主としてアメリカそして中国や香港を取材したルポルタージュの体裁をとっている。一口に個人の自由を最大限に尊重するリバタリアンと言っても、その細部の主張は大変に異なっていて、さらに具体的な政策課題や社会問題に対する立ち位置となるとまさに千差万別であるという印象を受ける。それはこの個人の自由という概念の幅が広すぎるし、さらには当然ながら他人の自由をも最大限尊重するという前提がある以上、リバタリアンの多様性は当然であるという感がある。そのため、リバタリアンの存在意義は、社会に対するアンチテーゼの表現や思考実験を極限まで推し進めるとどうなるか、という問題提起にとどまるという気がする。事実、本書では空想的なリバタリアン共和国の建設を目指す例がいくつか紹介されていて、例えば洋上を漂う無主の国をハイテクにより建設することを目指す、とかだ。また、リバタリアンの限界として、以下のような場合があると思う。個人はその性質上自由を行使したくてもできないように生まれつく人たちがいるのは事実で(例えば重い遺伝病を抱えて生まれてきた人)、そのような人たちには政府や徴税による所得の再分配はどうしても必要だ。ちなみにリバタリアンは、政府による徴税を合法的に行われる個人財産の収奪と考える。また、自分の自由と同様に他人の自由を尊重して生きる生き方は、全ての人間に可能だろうか?言い換えれば倫理的に高い人間同士の間でしか成立しないのではなかろうか。リバタリアンの国にサイコパスが侵入したらやり放題にやられてしまう気がする。以上のような感想を評者は抱いたにも関わらず、本書は日本でも最近リバタリアンという考え方や生き方が紹介されてきて、その実情を知って見たいという方には最適の好著であると思う。