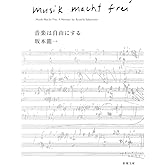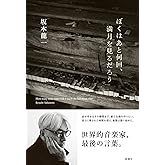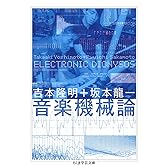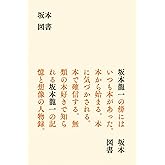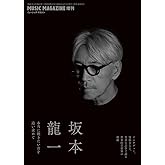高校生時代から、20年以上に渡って、ずうっと愛聴している身としては、坂本龍一を歴史的対象として固定しようとする身振りそのものを、拒絶したいような気にもなる。
坂本龍一は、生きている。
彼は、常に、現在形で、何度も、わたしたちの前に、姿と、音とを、立ち現すことだろう。
しかし、わたしたちが、坂本龍一の録音を聞いて、枯れ枝のような指といった身体のディティールを捉えた録画を見て、彼がそこに居ると感じ、その腕の重みを聞こえに乗せ、耳で受け止める時、彼は、実際にそこにいるのだろうか。人は言う。彼は、もう、いない。いや。
彼は、今、そこに、いる。
そう大森荘蔵なら、答えるだろう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
坂本龍一
いま、音を作るほうも、聴くほうも、二つのスピーカーを、音源として使います。ステレオ・サウンドっていうのが、一般的ですね。あれは人間がそうあるべく作ったものですから、当然といえば当然ですが、ある音を同時に両方の音源から出しますと、その音は真ん中で鳴っているように聴こえるわけですね。真ん中に音があるように認識される、それ錯覚なんでしょうか。
大森荘蔵
私は錯覚とは思いません。『新視覚新論』の中では、光や視覚について考えてみなしたが、ステレオの音が二つのスピーカーの真ん中から聴こえてくるという現象は、光でいうと虚像に当たると思うんです。光学的な虚像と言われるものです。ところで私は光学的な虚像というのは、じつは虚像ではないと思うので、この音の場合も、私は虚像ではないと思います。一般的に心理学者が錯覚と言っているものはどれも錯覚ではない。つまりイリュージョンではないと思っております。心理学者もこの頃、大体賛成してくれています。
坂本龍一
イリュージョンというふうに言ったんじゃおかしいというわけですね。こういう仮定はいかがでしょうか。たとえば、自然の中、森があって……狩人が狩りにいきます。オオカミが二匹別々の場所にいたとします。ごく少ない確率ですけれども、狩人が二匹のオオカミから等距離の位置に来た時に、二匹のオオカミが同じ声色で同時に啼いたとします。この狩人にとってオオカミは、実在の二匹のオオカミのちょうど真ん中に一匹だけいます。それを避けるためにどっちかにきます。すると食べられてしまう。もっとも、ぼくがこういう関係図を頭に描くこと自体、いわば神のような視点から描き、語ってしまっているから困るんですけれども……。
大森荘蔵
それ、いい言葉ですね。神さまというのは、いちばん上から俯瞰して見ていますからね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
かくして、坂本龍一に出会い続けるわたしたちにとって、彼は、今、そこに、いる、ということになる。
(坂本龍一じしんは、たぶん、違う考えだと思う。音は音源のある場所から聞こえてほしい、という趣旨の発言を、ワタリウム美術館でのasync設置音楽展開催時に行われたインタビューに行っている)
しかし、今、そこ、とは、なんだろうか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
写真のピンボケと〈今現在〉
大森荘蔵
音っていうものの一つの特徴は生まれたとたんに死ぬことである。ところがこれが音だけの特徴かというとそうでもないように思うんです。たとえばこの紅茶の受皿ですね。いまそれから出た光は私のところへ到達して、いまこの瞬間にこれ見えてますね。しかもこの姿は、もう次の瞬間にはないわけですね。たまたまこの受皿は、次の瞬間もその様子を変えないだけです。ところがネオンサインみたいにしょっちゅう変わるものを見ていると非常に音的であって、生まれたとたんに死んでいきます。だから刹那に死ぬのはかならずしも音だけじゃないと思うんです。しかし〈今現在〉は幅がゼロの点時刻ではありません。もし時間を線と考え、その線上の一点でその線を切ったのが〈今現在〉だと考えるならば、それはヨーカンの切断面にはヨーカンがないように、〈今現在〉は何もない虚空のようなものになりましょう。点時刻とは空を切った空振り時刻なのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今、というのは、わたしたちが生きている時間その物であるはずなのに。
こんなにも、捉え難い。
(と書きながら、20年ぐらい実感していなかったデリダ的な「差延」にようやく突き当たったような感触が、ある)
ともあれ。
坂本龍一の、一種の転換点が、どの辺りにあったのか、あるいは、なかったのか、それ自体が問題になるだろうが、この本を読むと、彼の、モノとオトと知覚と時間をめぐる思考の根幹は、80年代から、変わっていないのかもしれない、と思わされる。
そういう思いは、吉本隆明との対談である『音楽機械論』を読むと、一層、強まる。
ぜひ、合わせて、お読みいただけますと。

無料のKindleアプリをダウンロードして、スマートフォン、タブレット、またはコンピューターで今すぐKindle本を読むことができます。Kindleデバイスは必要ありません。
ウェブ版Kindleなら、お使いのブラウザですぐにお読みいただけます。
携帯電話のカメラを使用する - 以下のコードをスキャンし、Kindleアプリをダウンロードしてください。

音を視る・時を聴く: 哲学講義 (LECTURE BOOKS) 単行本 – 1982/10/1
このページの読み込み中に問題が発生しました。もう一度試してください。
ダブルポイント 詳細
- 本の長さ237ページ
- 言語日本語
- 出版社朝日出版社
- 発売日1982/10/1
- ISBN-104255820198
- ISBN-13978-4255820194
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
ページ: 1 / 1 最初に戻るページ: 1 / 1
登録情報
- 出版社 : 朝日出版社 (1982/10/1)
- 発売日 : 1982/10/1
- 言語 : 日本語
- 単行本 : 237ページ
- ISBN-10 : 4255820198
- ISBN-13 : 978-4255820194
- Amazon 売れ筋ランキング: - 510,908位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- - 2,399位哲学・思想 (本)
- カスタマーレビュー:
著者について
著者をフォローして、新作のアップデートや改善されたおすすめを入手してください。

著者の本をもっと見つけたり、似たような著者を調べたり、おすすめの本を読んだりできます。

著者の本をもっと見つけたり、似たような著者を調べたり、おすすめの本を読んだりできます。
カスタマーレビュー
星5つ中4.5つ
5つのうち4.5つ
29グローバルレーティング
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星5つ59%37%4%0%0%59%
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星4つ59%37%4%0%0%37%
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星3つ59%37%4%0%0%4%
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星2つ59%37%4%0%0%0%
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星1つ59%37%4%0%0%0%
評価はどのように計算されますか?
全体的な星の評価と星ごとの割合の内訳を計算するために、単純な平均は使用されません。その代わり、レビューの日時がどれだけ新しいかや、レビューアーがAmazonで商品を購入したかどうかなどが考慮されます。また、レビューを分析して信頼性が検証されます。
イメージ付きのレビュー
星5つ中5つ
坂本龍一は音楽家にならなければ硬派の出版社の編集者になっていた知性
坂本龍一はとても頭が良い 名門高校 都立新宿高校 お父さんは著名な文学編集者 坂本龍一本人は出版社「本本堂」を設立 東大教養学部科学哲学科の大森荘蔵教授を相手にちゃんと対話している 坂本龍一は当時30歳 単なる音楽家ではない 青土社や岩波書店の哲学担当編集者になるレベルの専門的理解をしている
フィードバックをお寄せいただきありがとうございます
申し訳ありませんが、エラーが発生しました
申し訳ありませんが、レビューを読み込めませんでした
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中にエラーが発生しました。ページを再読み込みしてください。
- 2023年5月12日に日本でレビュー済みAmazonで購入
- 2012年12月22日に日本でレビュー済み哲学者の大森と、音楽家の坂本龍一による、華麗な協奏曲。
坂本は、自分の音楽家としての経験を踏まえ、大森に哲学的な質問をする。
大森は、坂本の音楽に関する話を受けて、自分の哲学理論と絡めながら、話を展開する。
実に刺激的で、面白い本だ。
- 2022年7月9日に日本でレビュー済み第1講 見ることと聴くこと
第2講 〈今〉とはどういう時間か
第3講 イメージは頭蓋骨の中にあるか
第4講 風景を透かし視る
第5講 未来が立ち現われる
第6講 〈私〉はいない
用語解説
おわりに
のうちわけです。ついに、大森教授にはお会いしませんでした。好奇心のゆくえをつきとめないでおいた数少ない相手です。
- 2022年12月5日に日本でレビュー済み坂本龍一はとても頭が良い
名門高校 都立新宿高校
お父さんは著名な文学編集者
坂本龍一本人は出版社「本本堂」を設立
東大教養学部科学哲学科の大森荘蔵教授を相手にちゃんと対話している
坂本龍一は当時30歳
単なる音楽家ではない
青土社や岩波書店の哲学担当編集者になるレベルの専門的理解をしている
 坂本龍一はとても頭が良い
坂本龍一はとても頭が良い
名門高校 都立新宿高校
お父さんは著名な文学編集者
坂本龍一本人は出版社「本本堂」を設立
東大教養学部科学哲学科の大森荘蔵教授を相手にちゃんと対話している
坂本龍一は当時30歳
単なる音楽家ではない
青土社や岩波書店の哲学担当編集者になるレベルの専門的理解をしている
このレビューの画像
- 2005年11月20日に日本でレビュー済み今読むとかなり面白い。つまり、脳のシステムに関する研究も進んでいなく、「共感覚」という現象もまだ取り沙汰されてなかった時代に出された本だけれども、哲学と音楽という立場からすでに、そういったテーマを先取っていたんですね。
私事で恐縮ですが、友だちから、中沢新一&細野晴臣によるちくま文庫の『観光―日本霊地巡礼』とともにプレゼントされて読みました。YMOの両ブレーン(ごめんなさい、幸宏さん、あくまでロジックという意味です)のキャラの違いが浮かび上がって興味深かった。でも、『観光』と対になるのは、村上龍&坂本龍一の『EV.Cafe』かと思っていたけど、本質的には、この『哲学講義』なんだろうな、と改めて実感しました。っていつの時代の話でしょうか?
- 2010年10月17日に日本でレビュー済み坂本龍一といういい聞き手を得て「時間と存在」にはなかった無脳論の具体的組み立てが詳細に語られていて驚き、享受し、腑に落ちた。
以下、列挙する。
.現在信仰あるいは知覚信仰のため意識により知覚されるもの以外は存在しないことになっている。過去・現在・未来も強く信じられていて両者は結びついている。
そこに、「イメージ」という言葉(物理学が排除した形容詞の全てを背負う)が要請されるのであろう。
しかし、これは我・意識・心とダイレクトに結びつく倒錯した世界像である。
存在は、頭の中にあるのではない。空間の中に実物がある。そして、時間的には現在もあり、過去もあり、未来もあるということである。ただし、現在以外は「知覚様式」で知覚不可能な「立ち現われ」である。
現在只今(過去と未来を含んだある時間の拡がり・厚み)において、四次元の「立ち現われ」が常時現われている。
正法眼蔵「有時」の巻の存在、時間についての個所はそういうことを言っているのだと受け取った。
.視覚について脳生理学は因果関係で説明するが、それと逆方向でわれわれは見透している。(透視関係)
遠い星はものすごい距離を透視して見ている。意識は不要である。透かして「ただ、見えている」。「立ち現われ」る。
聴覚についても、意識は不要である。「鳴り現われ」る。
われわれは、「現在只今」の中で時間の厚みを見、そして聴いている。
.感動というものは、タブローに張り付いている。「立ち現われ」る。のであって頭の中にあるのではない。感情は決して内心のものではないし私を含む世界のある相貌と私の肉体の状態全体をいう。
記憶についても、想いだすのは実物でなければいけない。「思い出し様式」で「立ち現われ」る。
未来も、「見込み様式」で「立ち現われ」る。
.<私>はいない。身の回りに様々なものが「立ち現われ」ている。この状況のすべてが生きているということそのものである。
この中に主客を入れ込む必要はない。包括的な全体、それでピリオド。それで十分。踏み込まない。けっして私は消えたわけではないのだから。
仏教思想は、一段踏み込む。主客対立が鮮やかに出すぎるために悟りの世界に入ろうとする。
西洋哲学は、主客対立を剥き出しにする。
以上。
鐘消えて 花の香は撞く 夕べかな 芭蕉
- 2009年10月22日に日本でレビュー済み大森氏は、哲学をやるというのは一種の病気であり、緑野に枯れ草を食らうことにたとえる。考えなくても済むこと、むしろ考えることが日常生活に支障さえきたすに関わらず、考えずにおれないという病にとりつかれた人が哲学者なのである。しかし、誰の中にも哲学者の素質は1,2%あるという。この本を読んで少しでも面白いと感じるものがあったなら、自分の中の1,2%の哲学者が目覚めたということだろうか。
本書にもいわゆる専門用語はいくつか登場する。特に坂本氏の発言にある音、音楽に関する用語は私にはまったく理解できず、したがってそれに絡む対話部分は読み飛ばすしかなかったが、それ以外についてはおおむね平易な日常語で語られる。術語や学史的用語が出てきても脇役的な位置づけである。
メインは、本書の大半を占める大森氏が日常語で哲学するくだりである。〈今〉〈知覚〉〈イメージ〉〈意志〉〈私〉といったテーマで、氏が語る内容は既成観念をことごとくはずす捉え方を提示する。それは慣れ親しんだ考え方または感じ方とは異なるから、わかりにくいし、私もわかったと言える自信はないが、それでも「へえ、なるほど、すごい」と思える瞬間がある。「表現によって立ち現れてくる事態」、しかも全く予想もしなかった事態に向き合うのである。それが専門語ではなく、日常普段の言葉で行われる。
哲学した結果を読むのではなく、哲学のライブに立ち会う感覚をもって読み進んでいける。〈今〉というのが点や断面ではなく、幅のある〈今頃〉という言葉に置き換えられる。喩えをもって説明が重ねられる。しかし次には喩えが不適切だとされ、他の説明が続く。しかしそれも十分ではないとされ、別の表現が試みられる。〈今〉という事態の端的な表現を求めて模索するその過程を通して、読者は哲学者とともに〈今〉なるものへ接近していく。正解にたどり着けないとしても、このスリリングな体験を共有した読者は、従来と異なる相の〈今〉が見えてくるはずである。