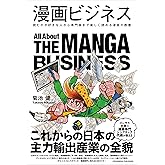米国のアメコミ流通について書かれた貴重な本
掛け率40%買い切りのダイレクトセールス、出版社はほぼ3社という特殊な米国アメコミ流通の世界で
80年代のコレクターズバブルで5千店舗あったものが90年代半ばに半減
日本のマンガ市場とは比較にならないほど衰退していたコミック市場はその5年後に日本マンガが市場の3割以上を占めるまでになる。その契機を切り開いたのがポケモンである。(Vizは98年を境に売上11億から翌年130億と10倍に!)
Vizmediaがいかに2000年前後にポケモン景気の後押しを受けて日本マンガを輸出していったかの歴史はエンタメ業界の人間は必見の事例といえる

無料のKindleアプリをダウンロードして、スマートフォン、タブレット、またはコンピューターで今すぐKindle本を読むことができます。Kindleデバイスは必要ありません。
ウェブ版Kindleなら、お使いのブラウザですぐにお読みいただけます。
携帯電話のカメラを使用する - 以下のコードをスキャンし、Kindleアプリをダウンロードしてください。

萌えるアメリカ 米国人はいかにしてMANGAを読むようになったか 単行本 – 2006/8/14
堀淵 清治
(著)
このページの読み込み中に問題が発生しました。もう一度試してください。
米国でマンガ出版社ビズ(現在は小学館・集英社の共同出資)を立ち上げ、少年ジャンプやポケモンなどの米国版を成功させた著者が、いかに日本マンガを英訳し、販路を拡大したのかを、ドキュメンタリー形式で紹介。 ここ数年、日本のアニメやゲームなどのポップカルチャーは世界的に認知度が高まりマンガの翻訳本も人気を集める。もともと米国のマンガは、マニアックなファンたちのものだった。そこへビズはカムイ伝やナウシカなどの日本マンガを英訳して持ち込み、マニアたちの人気を集めながら徐々に成長。その後、ポケモンブームなどの波に乗り、現在の市場規模は1億ドル超で、ビズはトップ5に入る。 コンテンツ輸出は日本にとって極めて大きなビジネスチャンスだが、多くの日本企業はそのチャンスを生かしきれてはおらず、一部メディアによる日本文化ブームの報道は実態よりも少し誇張されている。 そうしたなかで、本書に描かれた事例は、単なる成功物語としてではなく、学ぶべき価値あるケーススタディとなっている。
- 本の長さ272ページ
- 言語日本語
- 出版社日経BP
- 発売日2006/8/14
- ISBN-104822245284
- ISBN-13978-4822245283
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
ページ: 1 / 1 最初に戻るページ: 1 / 1
登録情報
- 出版社 : 日経BP (2006/8/14)
- 発売日 : 2006/8/14
- 言語 : 日本語
- 単行本 : 272ページ
- ISBN-10 : 4822245284
- ISBN-13 : 978-4822245283
- Amazon 売れ筋ランキング: - 327,810位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- - 381位コミック・アニメ研究
- - 5,843位社会学概論
- - 163,340位コミック
- カスタマーレビュー:
著者について
著者をフォローして、新作のアップデートや改善されたおすすめを入手してください。

著者の本をもっと見つけたり、似たような著者を調べたり、おすすめの本を読んだりできます。
カスタマーレビュー
星5つ中4.5つ
5つのうち4.5つ
8グローバルレーティング
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星5つ68%12%20%0%0%68%
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星4つ68%12%20%0%0%12%
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星3つ68%12%20%0%0%20%
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星2つ68%12%20%0%0%0%
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星1つ68%12%20%0%0%0%
評価はどのように計算されますか?
全体的な星の評価と星ごとの割合の内訳を計算するために、単純な平均は使用されません。その代わり、レビューの日時がどれだけ新しいかや、レビューアーがAmazonで商品を購入したかどうかなどが考慮されます。また、レビューを分析して信頼性が検証されます。
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中にエラーが発生しました。ページを再読み込みしてください。
- 2020年9月12日に日本でレビュー済みAmazonで購入
- 2006年11月24日に日本でレビュー済みAmazonで購入『萌えるアメリカ』という俗っぽいタイトルなのが勿体無い。本書は現在北米で
日本のマンガやアニメなどのコンテンツを扱い急成長を遂げているビズメディア社
の生みの親である堀淵氏の自伝である。本書のプロローグにも記されている通り、
日本のマンガが北米のコミックス市場へどのようにして登場し、発展したかという
ことについて、出版社側の人間の実体験を綴る現在唯一の本であり、希少な情報が
詰まっている。
一応、起業からのビジネスを記したビジネス書として読むことはできるが、自伝
的要素との兼ね合いを考えたためかそれに関する分量は少ない。しかし、文の構成
を作者以外が加わって行っているため、アメリカのコミック市場、ライセンスの形
態など必要な情報は最低限含まれている。
また、作者はビズメディアの創業者であり、アメリカにおけるマンガ市場の形
成、動向をその視点から語っているということには注意が必要である。作者の成功
体験、失敗体験の作者自身による分析は偏りが生じているかもしれない。ビズメ
ディアは日本のマンガを北米に輸出することがメインとしている。それを受け、ア
メリカのマンガ市場は発展していくわけだが、現在ではその市場の中から独自のマ
ンガを作り出そうとする動きがある。アメリカ産のマンガの誕生である。しかし、
本書ではそれについては言及していない。
アメリカにおいてのマンガ市場に興味を持つ方なら是非読んでおきたい一冊。堀
淵氏の半生を追いつつ、市場の形成、発展の歴史を知ることができる。
- 2006年9月20日に日本でレビュー済みAmazonで購入本書の内容を一言で言うと、著者の回顧録半分、アメリカのコミック事情半分というところで、ビジネス書と思って読むとやや物足りなさを感じるかも知れない。著者もプロローグの中で、『この本はいわゆるビジネス書というより、あくまで僕自身の体験を中心に綴った手記に近いものだ。』(11ページ)、と書いているので、購入する方は注意が必用ではないだろうか。
私はそんな事情を知らず、仕事の参考になるかと思って読んでみたが、やや期待はずれであった。なぜかと言うと、新しいビジネスを立ち上げて成功を収める過程では、我々の体験し得ないような困難な場面に遭遇し、多くの難しい決断を下してきていると思うが、そのあたりが描ききれていないからである。非常に新鮮ですばらしい素材でありながら、料理の仕方が適切でなく、素材のすばらしさが十分に伝わらなかったと言うことか。
または、全体に淡々と書かれており、文章も読みやすいため、さらっと読み終わって、あまり鮮明な印象が残らないと言えば良いのかもしれない。
さらに、アメリカのコミック事情を全く知らない読者を意識したのか、背景やプレイヤーに関する説明にも多くページを割いており、やや本書の趣旨に沿わないのではないかと感じる部分もあった。
例えば、175ページにナショナルディストリビューター(雑誌の卸売業者)の名前がカタカナで羅列してあるが、本書に必要な記述だとは考え難い、また仮に、読者が何らかの興味を持ったとしても、カタカナ名しかわからないのでは調べようもなく、不要なくだりと言えるのではないだろうか。
そうは言っても、著者の体験はとても貴重なもので、本をアメリカ式に左開きにするため、原稿を反転させて印刷した事や、性描写に関する日米の受け取り方の違いなど、興味深く読めた箇所も多くあった。
また、一言でコミックと言っても、日米で全く異なる進化を遂げていることを初めて知ったし、その昔、我々がハリウッド映画やテレビドラマを見てアメリカの豊かさを知ったように、コミックは海外に日本を紹介するメディアとなり得ることも何となく理解できたような気がする。
- 2006年11月12日に日本でレビュー済み本書は著者の堀淵さんの自伝であり、小学館・集英社の米国マーケットへの果敢な挑戦伝です。
内容を正しく示すタイトルは「私および小学館はいかに米国でMANGAビジネスを立ち上げたか」だと思います。
本書では、米国のMANGAファンは販売戦略上の顧客ターゲットとして語られているのみで、
個別のファンの嗜好、心理の変遷等までは、踏み込んではいません。
従って米国人MANGAファンの貌(かお)は見えてこない部分はありました。
あくまでマクロな視点からの米国人ファン論にとどまっています。
「米国人はいかにMANGAを読むようになったか」というタイトルは、
むしろ現在発売中の「オタク インUSA」のサブタイトルにふさわしと思います。
じゃあ、本書はつまらないかと言えば、全然そんなことはありません。
時代の捉え方、ビジネス上の成功・失敗等、すごく面白いのです。
米国のコミック業界事情に始まり、黎明期のMANGAに関わった人たち、流通事情、翻訳の困難さなどを、堀淵さんが当事者として語っています。
その苦闘と最後の勝利は、まるで少年ジャンプのストーリーのような成功譚です。
本書で特に印象に残ったのは、
初期のMANGAビジネスに関心をもった人々は、
堀淵さんも含め、カウンターカルチャーの影響下にあった人たちだったとこと。
要するにヒッピーだったということと、MANGAビジネスを救ったのは高橋留美子だったという著者の感慨です。
絶対に受け入れられないと言われた地点から、米国出版市場における唯一の急成長分野に至る、現在までの、MANGAの貴重な記録だと思います。
- 2006年9月22日に日本でレビュー済みこの手の本を、ビジネス書であるか自伝であるかを正すというのは
あまり意味のないことだと思う。用は、著者がなぜいまこういう本を
書いたのか、ということのほうが重要だと思う。
個人的には、最近読んだなかでも飽きずに面白く読めた一冊だ。
自伝としても、文化論としても、ビジネス書としても、
なかなかよくまとまっていると思うし、マンガビジネスや
アメリカの出版界に興味のあるひとにとっては
資料的な価値もかなり高いのではないだろうか。
起業のノウハウだとか、そのへんの苦労だとかを書いた本は、
世の中に腐るほど出ているのだし、そういうものが読みたい人は
そちらへいけばいいと思う。
しかし、かつて海外に住んでいたことのある身としては、
海外に出て見てはじめて自分が日本人であるということを
強く意識した覚えがある。
著者のように、日本の素晴らしさや美しさを思い返すだけでなく
その弱さや欠点も見えてくる。でも、そういう想いをすべて
含めて、日本人として生まれてよかった、と感じたのを憶えている。
この本を読んで、海外から日本に向けて応援メッセージを送るような
著者の気持ちが、手を取るようにわかる気持ちがした。
とくに興味深かったのは、アメリカにいるマンガアニメ好きの
若い人たちのなかに、「日本人になりたい」という願望を持って
いる人が現れているという話だ。フランス人に憧れてフランス語
をならい、パリ旅行なんぞへ出かける若い日本人女性がよく
いるように、マンガアニメを通じて、日本文化に憧れて日本語を
学び、日本へ遊びに来る外国人たちがもっと増えるといいと思った。
- 2007年1月11日に日本でレビュー済みタイトル名から、“アメリカのマンガの現在”をオタク的に分析した書物だと思ったが、予想が外れた。二十年前、彼の地に、日本のマンガをはじめて本格的に持ち込んだ当事者による回顧録である。で、予想は外れたんだけど、予想外に面白かった。ある種の成功物語なんだけど、こういう古いタイプの読み物こそ、今、新鮮なんじゃないかと。やっぱどんな文化もビジネスも、人であり、人の歴史であり、人と人の交わりであり、っていう。この本を読んで「北米へは、マンガよりもアニメのほうが二十年以上早く上陸していた」「二十年前には『マンガ』の市場規模はほぼゼロだった」「現在、アメリカで売られている雑誌のうち、87パーセントが定期購読」「国民の四人に一人は、自分の名前程度しか読み書きができない」といった様々な事実を知ったのだけど、もっとも興味深かったのは、著者や著者の仲間らが、70年代のニューエイジ・ムーブメントの影響下にあった若者たちだったということだ。ヒッピー文化、ニューエイジ文化、カウンターカルチャーの水脈が、日本を飛び出した若者たちによって、こんなところにつながっていたのかって言う驚き。そして、一旦は日本を捨てたはずの著者が、彼の地で日本由来のマンガをビジネスとすることで、「日本の魅力とは、この国のおおらかさや曖昧さから生まれる美しい柔軟性」と、みごとに本質を突いているであろう(もしくは、今の日本人が見失ってしまった)日本観を持つに至ったことにも、なにか、とっても感激してしまうし、勇気付けられる。彼の地に渡ったからこそ日本が好きになったり、日本が好きだからこそ海外に出て日本を伝える、ってことに対して、ものすごく可能性を感じてしまうのだ。
- 2007年3月8日に日本でレビュー済みてっきりアメリカのオタクの話かと思いきや、
日本のマンガをアメリカで売ったビジネスマンの
サクセスストーリーなのであった。
ともすれば現地のコミケのような
「絵になる」報道しか日本ではされない中、
アメリカへの日本マンガ文化普及の一端が
(アネクドータルなものであるとしても)
その歴史とともに伺えて大変興味深かった。
著者は現在サンフランシスコで日本映画・
アニメ専門の映画館を企画中と書かれている。
私もそうであるが、外国にいればいるほど
日本人であるというアイデンティティを
強く意識する日本人は多い。
マンガをスタートとして、本書が軽く
日本論にまで踏み込んでいる流れは
読んでいてとても共感できる。