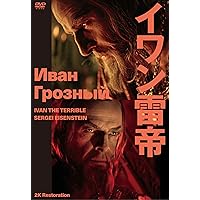『戦艦ポチョムキン』が有名なセルゲイ・エイゼンシュテインのよる、いわゆるイワン雷帝(イヴァン4世)の内面、外面の闘争を1部・2部構成3時間で描く。ひとことでいうとパワーとその対立の物語であるが、当方、史実に暗く、ごく表面的な知識しかない。監督が緻密な理論・繊細な計算を用いながらも、反面、いや、それだからこその巨岩のような、あるいは禿山の山脈を睥睨するような壮大さ、力強さとむき出しの生々しさに満ちている。第1級の「映像タペストリ」となっているように思われる。
前述『ポチョムキン』は観ておらず「モンタージュ理論」なるものも実はあまりわかっていない・・。それでも巨大なセット・美術(これが実に「らしい」威厳と美しさに満ちている)や広大な土地のロケにみられる構図の大胆さと繊細さ。あまり動かぬフレームの中で被写体が動くというスタイルを採っているが、その絶妙な被写体の配置・動きに引き込まれる。「画力」は抜きんでたものであり、私はなにより「画」を楽しみ、かつ、驚かされた。観ていて「ああ、映画だ」・・と思う。
少し歴史的背景もあった方がよいと思われるので付け焼刃ながら補足しておきたい。適切でない点あると思うが、詳しい方には何卒ご容赦いただきたい。15世紀、モスクワ大公国はイヴァン3世の治世に地域の諸公国を併合し、おおむねロシアの統一を完成した。自らをローマ帝国の後継者とギリシャ正教の守護者を任じ、ツァーリ(皇帝)を名乗った(大公として載冠)。彼の政策は孫のイヴァン4世に受け継がれた。1547年にツァーリとなる(ツァーリとしての載冠式から本作は始まる)。ロシア・ツァーリ国(モスクワ・ロシア国等とも)を名乗り(ただこのあたりの名称については複雑で理解しきれていない・・)この名称は1721年にピョートル1世(ツァーリではなくインペラートル)がロシア帝国(帝政ロシア)の建国を宣言するまで用いられていた。
彼は専制・恐怖政治を強化したため、「雷帝」Ivan the Terribleと恐れられた。世襲、私利私欲に走る貴族との軋轢、対立はひどかったという(注1, 2)。
それとともにロシア正教会(キリスト教正教会の一派)とも激しく衝突した。雷帝は過去の恨みと孤独を抱え込み、精神的に不安定であり、貴族や外敵に乗っ取られるという、雷帝本人が感じた「恐怖」の物語、孤独、復讐の物語でもある点が興味深い。実は「歴史に沿いながら、時にはほとんど史実を無視したプロットの中で構築されている」という(注3。221頁)。
以下、★まで内容に触れています。
第1部は即位した若きイヴァン4世と妻の生活、治世改革が叫ばれ、貴族・正教会を弱体化し、強大ロシアへの野望が語られる。そして息子を皇帝の座につかせようとする、雷帝の伯母エフロシニヤの画策が描かれる。この伯母の顔、やることなすことが狡猾でコワイ。妻は伯母に毒殺される。妻の葬儀場面は見事。ここでは楽式でいう対位法、フーガで表現されているという(注3。216頁)。嘆き、自信を無くす雷帝と、弔いに読まれるダヴィデ王の詩編の吟誦のフーガ。そして怒りを爆発させる(「ローマは2度滅びた。第三のローマ、モスクワは不滅だ。第四のローマはありえぬ」・・)。燃え盛る松明。親衛隊結成の端緒となるシーンである。そしてモスクワを去った雷帝へ民衆がモスクワへの帰還を請願する。ここでの超近景と超遠景の鳥肌立つような同居にハッとさせられる。
第2部は帰還した雷帝と、貴族・正教会との暗闘。重要なのは雷帝の少年時代の描写である。幼いイヴァンの前で毒殺され(父はすでに他界)、形ばかりの大公即位。摂関政治が敷かれるのだが、貴族は領土や財産を食いつぶすばかり。子どもの戯言と一笑にふされ為すすべもない。しかしこの時の体験が、イヴァンに鮮烈に貴族憎しという憎悪と、強烈な孤独を味わった。母を侮辱されたとき、「この男を捕らえよ!」と叫び、衛兵が幼いイヴァンに従ってその貴族をあやめるシーンがある。ある本では、イヴァンが権力をはじめて意識し、行使の恍惚に目覚めるシーンだという(注3。212頁)。
雷帝の孤独と暴走、対立は進み、貴族を処刑。葬儀シーンも構図の厳しさと相まって見事。対立は決定的となり、やがて雷帝暗殺計画が始まる。
ラスト近くでパートカラーが用いられる(画面の一部ではなくシーン)。鮮烈な赤が支配する画面が後を予感させるのか。ここは現実の作品内の色とは思われず、空間や人物内面の温度か何かを表しているのだろうか。そして決定的な一言で映画は終わる。★
ところで本作は3部作として構想されていたが第3部が創られることはなかった(一部は撮影されていたという)。このあたり時の政権の怒りに第2部が触れたかららしい(ジダーノフ批判)。余計だが本作とソ連との関係に少しだけ触れる。本作の提案は、第二次大戦に突入することで直面した危機を16世紀のイヴァン雷帝が克服したように、スターリンの指導によって克服されることを予言するためのものであった。雷帝の物語をスターリンの讃仰に一致させることがエイゼンシュテインの仕事だったようである(注3。209頁)。第1部は賞賛されたが、第2部は上映を禁止され、人々が観ることができたのはスターリン没後の1958年。親衛隊の描写がまるでKKKのようであり、イヴァンの真実を描かず、反歴史的であるとされたらしい(注3。219頁)。しかし一方でエイゼンシュテインの体調が思わしくなかったともいわれる。エイゼンシュテインがどのような姿勢で、当局に配慮しながら撮ったのか否かは定かではなく、一概にプロパガンダ作ともいえない。
この恐怖物語はエイゼンシュテインの少年期の人格形成の一部であり、イヴァンの物語の暴虐ぶりで味わった恐怖感をポーの世界と結びつけ、少年の深層に棲息する快楽(エクスタシー)を目覚めさせたに違いないと言われる(注3。210頁)。またエイゼンシュテインの両親はまだ彼が幼いこと離婚し、孤独と不安であった。両親に捨てられた彼が革命の混乱に巻きこまれたものの、『戦艦ポチョムキン』によって映画という権威を身につけ自らの地位を獲得したときの恍惚が、(映画の)イヴァンの性格に投影されているとのことである(注3。212頁)。ここは第2部冒頭のシーンと重なる。この政治がらみ、エイゼンシュテインとイヴァン4世の重複・類似する点は注3の文献『エイゼンシュテイン』第9章に詳しい。
イコン画というのだろうか、建物内のあらゆるところに描かれた宗教画が崇高かつおどろおどろしい背景となり、醜悪で妄執的な欲の渦巻く世界を取り巻いている様は一種、異様な雰囲気を醸し出している。この壁画にも何か比喩がありそうだ。ロシア正教会はツァーリに冠を授けて式を行い、強力に当時の支配層の貴族と利害を共にしていたように描かれる。雷帝から権力と利権をとりあげられて無視されて激しい憎悪を抱き、府教は雷帝を亡き者にしようとさえする。それには同じ穴のムジナである貴族の伯母さえも驚くほどであった。このあたり史実か否かはわからないが、ロシアの治世に深く関与し、権力の争いの裏側が垣間見える。イコン画や儀式の様子もオカルトの域に達しそうな人々の醜さと相まって、宗教(とその儀式)も作品の底部に暗く流れているように思われる。
俳優陣では雷帝を演じたニコライ・チャルカーソフが見事。他はちょっと見分けがつきにくいが、みな目つきが尋常ではない。伯母エフロシニアを演じるセラフィマ・ビルマンが圧巻の顔芸。息子への倒錯した執着・母性の表現も見物。顔のクローズアップがここぞというところで多用され、他のレビュアーさまが触れておられるように歌舞伎の見栄やメイクを取り入れたような表情のつくり、構図を優先したような様式的な所作、決めポーズが採り入れられている。一方でセリフも比較的多く舞台劇のような一面もあり、セリフ、顔、所作が一体となり登場人物の内面を語る。とりわけ眼の表情が強烈だ。つまり演劇的な芝居、サイレント映画のような表現様式、極めて映画的な大胆な寄りと引き、奇跡的な構図、意識的な影の使用法のすべてがめまいを覚えるような力で迫ってくる。
音楽はロシアの作曲家、セルゲイ・プロコフィエフを起用。あまりクラシックに明るくないが、名はきいたことがあり、本作の音楽は素晴らしい。前作『アレクサンドル・ネフスキー』でもプロコフィエフと組み、「音楽とモンタアジュ映像の同時性によって『ネフスキイ』は音楽映画との親縁性を強めている」(注3。206頁)らしいので、本作再見時には音楽と編集のリズムにも注意して観たい。
エイゼンシュテインといえば映画の教科書的な、基礎知識として構えて観勝ちだが、本作にそんなセットアップは不要。政治的側面はとりあえず置いておいて、荒々しく赤裸々な人間たちのドラマに飲まれ、画に陶然となるのが正解かと思われる。パワーゲームと信念、裏切りとパトスの一大パノラマ。あの「モンタージュ理論の・・」というとっつきにくさを払い、お勉強映画と思わず戦時下の70年前につくられた異形が跋扈するこの作品に接して欲しいと思う。第3部がなくてもこれで1つの作品として充分観ることができる。
画質は可もなく不可もなく。ただ全体的にノイズ、傷等がみられ、チラチラするところがあるが、パートカラー部分を除いて滲みはあまりなく、あの耐えられないフレームのガタツキはほとんどない。画質重視の方には不満足かもしれないが、個人的には許容範囲。ただ当然綺麗、というか公開当時の状態に近いことは望ましい。そのような邦盤をぜひ廉価で発売して欲しい。撮影が素晴らしいだけにもったいないし、パートカラー部分はどのような発色だったのだろう。ロシア語のみ。字幕ON,OFF不可。あまりに簡単なスタッフ・キャスト解説(ディスク内特典)。紙特典なし。片面2層。DOLBY DIGITAL.某サイトでは、第1部 1時間39分 / 第2部 1時間50分とされているが商品裏面ではトータル184分。
イワン雷帝 ИВАН ГРОЗНЫЙ Ivan the Terrible 製作第1部44年、第2部45年、公開第1部1946年、第2部1958年
注1『改訂版 詳説世界史研究』木下康彦他(2008、山川出版社)、
注2Wiki(イヴァン4世、ロシア・ツァーリ国)、
注3『エイゼンシュテイン』篠田正浩(1983、岩波書店)を参考にしました。注3書籍は有益です。
関連キーワード ロシア、ソ連、ツァーリ、暴君、貴族、ロシア正教会、農奴、イコン画、パートカラー
関連作 『アレクサンドル・ネフスキー』『戦艦ポチョムキン』
イワン雷帝 [DVD]
| フォーマット | ドルビー |
| コントリビュータ | ニコライ・チェルカーソフ, セルゲイ・エイゼンシュテイン |
| 言語 | ロシア語 |
| 稼働時間 | 3 時間 4 分 |
この商品を見た後にお客様が購入した商品
ページ: 1 / 1 最初に戻るページ: 1 / 1
商品の説明
レビュー
監督・脚本: セルゲイ・エイゼンシュテイン 撮影: エドゥアルド・ティッセ/アンドレイ・モスクヴィン 音楽: セルゲイ・プロコフィエフ 出演: ニコライ・チェルカーソフ/セラフィマ・ビルマン/リュドミラ・ツェリコフスカヤ
-- 内容(「CDジャーナル」データベースより)
登録情報
- アスペクト比 : 1.33:1
- 言語 : ロシア語
- 梱包サイズ : 18.03 x 13.76 x 1.48 cm; 83.16 g
- EAN : 4933672230382
- 監督 : セルゲイ・エイゼンシュテイン
- メディア形式 : ドルビー
- 時間 : 3 時間 4 分
- 発売日 : 2006/2/24
- 出演 : ニコライ・チェルカーソフ
- 字幕: : 日本語
- 言語 : ロシア語 (Mono)
- 販売元 : アイ・ヴィ・シー
- ASIN : B000E0VTBA
- ディスク枚数 : 1
- Amazon 売れ筋ランキング: - 226,133位DVD (DVDの売れ筋ランキングを見る)
- カスタマーレビュー:
カスタマーレビュー
星5つ中3.7つ
5つのうち3.7つ
全体的な星の数と星別のパーセンテージの内訳を計算するにあたり、単純平均は使用されていません。当システムでは、レビューがどの程度新しいか、レビュー担当者がAmazonで購入したかどうかなど、特定の要素をより重視しています。 詳細はこちら
41グローバルレーティング
虚偽のレビューは一切容認しません
私たちの目標は、すべてのレビューを信頼性の高い、有益なものにすることです。だからこそ、私たちはテクノロジーと人間の調査員の両方を活用して、お客様が偽のレビューを見る前にブロックしています。 詳細はこちら
コミュニティガイドラインに違反するAmazonアカウントはブロックされます。また、レビューを購入した出品者をブロックし、そのようなレビューを投稿した当事者に対して法的措置を取ります。 報告方法について学ぶ
イメージ付きのレビュー
5 星
色眼鏡でみないで
『戦艦ポチョムキン』が有名なセルゲイ・エイゼンシュテインのよる、いわゆるイワン雷帝(イヴァン4世)の内面、外面の闘争を1部・2部構成3時間で描く。ひとことでいうとパワーとその対立の物語であるが、当方、史実に暗く、ごく表面的な知識しかない。監督が緻密な理論・繊細な計算を用いながらも、反面、いや、それだからこその巨岩のような、あるいは禿山の山脈を睥睨するような壮大さ、力強さとむき出しの生々しさに満ちている。第1級の「映像タペストリ」となっているように思われる。前述『ポチョムキン』は観ておらず「モンタージュ理論」なるものも実はあまりわかっていない・・。それでも巨大なセット・美術(これが実に「らしい」威厳と美しさに満ちている)や広大な土地のロケにみられる構図の大胆さと繊細さ。あまり動かぬフレームの中で被写体が動くというスタイルを採っているが、その絶妙な被写体の配置・動きに引き込まれる。「画力」は抜きんでたものであり、私はなにより「画」を楽しみ、かつ、驚かされた。観ていて「ああ、映画だ」・・と思う。少し歴史的背景もあった方がよいと思われるので付け焼刃ながら補足しておきたい。適切でない点あると思うが、詳しい方には何卒ご容赦いただきたい。15世紀、モスクワ大公国はイヴァン3世の治世に地域の諸公国を併合し、おおむねロシアの統一を完成した。自らをローマ帝国の後継者とギリシャ正教の守護者を任じ、ツァーリ(皇帝)を名乗った(大公として載冠)。彼の政策は孫のイヴァン4世に受け継がれた。1547年にツァーリとなる(ツァーリとしての載冠式から本作は始まる)。ロシア・ツァーリ国(モスクワ・ロシア国等とも)を名乗り(ただこのあたりの名称については複雑で理解しきれていない・・)この名称は1721年にピョートル1世(ツァーリではなくインペラートル)がロシア帝国(帝政ロシア)の建国を宣言するまで用いられていた。彼は専制・恐怖政治を強化したため、「雷帝」Ivan the Terribleと恐れられた。世襲、私利私欲に走る貴族との軋轢、対立はひどかったという(注1, 2)。それとともにロシア正教会(キリスト教正教会の一派)とも激しく衝突した。雷帝は過去の恨みと孤独を抱え込み、精神的に不安定であり、貴族や外敵に乗っ取られるという、雷帝本人が感じた「恐怖」の物語、孤独、復讐の物語でもある点が興味深い。実は「歴史に沿いながら、時にはほとんど史実を無視したプロットの中で構築されている」という(注3。221頁)。以下、★まで内容に触れています。第1部は即位した若きイヴァン4世と妻の生活、治世改革が叫ばれ、貴族・正教会を弱体化し、強大ロシアへの野望が語られる。そして息子を皇帝の座につかせようとする、雷帝の伯母エフロシニヤの画策が描かれる。この伯母の顔、やることなすことが狡猾でコワイ。妻は伯母に毒殺される。妻の葬儀場面は見事。ここでは楽式でいう対位法、フーガで表現されているという(注3。216頁)。嘆き、自信を無くす雷帝と、弔いに読まれるダヴィデ王の詩編の吟誦のフーガ。そして怒りを爆発させる(「ローマは2度滅びた。第三のローマ、モスクワは不滅だ。第四のローマはありえぬ」・・)。燃え盛る松明。親衛隊結成の端緒となるシーンである。そしてモスクワを去った雷帝へ民衆がモスクワへの帰還を請願する。ここでの超近景と超遠景の鳥肌立つような同居にハッとさせられる。第2部は帰還した雷帝と、貴族・正教会との暗闘。重要なのは雷帝の少年時代の描写である。幼いイヴァンの前で毒殺され(父はすでに他界)、形ばかりの大公即位。摂関政治が敷かれるのだが、貴族は領土や財産を食いつぶすばかり。子どもの戯言と一笑にふされ為すすべもない。しかしこの時の体験が、イヴァンに鮮烈に貴族憎しという憎悪と、強烈な孤独を味わった。母を侮辱されたとき、「この男を捕らえよ!」と叫び、衛兵が幼いイヴァンに従ってその貴族をあやめるシーンがある。ある本では、イヴァンが権力をはじめて意識し、行使の恍惚に目覚めるシーンだという(注3。212頁)。雷帝の孤独と暴走、対立は進み、貴族を処刑。葬儀シーンも構図の厳しさと相まって見事。対立は決定的となり、やがて雷帝暗殺計画が始まる。ラスト近くでパートカラーが用いられる(画面の一部ではなくシーン)。鮮烈な赤が支配する画面が後を予感させるのか。ここは現実の作品内の色とは思われず、空間や人物内面の温度か何かを表しているのだろうか。そして決定的な一言で映画は終わる。★ところで本作は3部作として構想されていたが第3部が創られることはなかった(一部は撮影されていたという)。このあたり時の政権の怒りに第2部が触れたかららしい(ジダーノフ批判)。余計だが本作とソ連との関係に少しだけ触れる。本作の提案は、第二次大戦に突入することで直面した危機を16世紀のイヴァン雷帝が克服したように、スターリンの指導によって克服されることを予言するためのものであった。雷帝の物語をスターリンの讃仰に一致させることがエイゼンシュテインの仕事だったようである(注3。209頁)。第1部は賞賛されたが、第2部は上映を禁止され、人々が観ることができたのはスターリン没後の1958年。親衛隊の描写がまるでKKKのようであり、イヴァンの真実を描かず、反歴史的であるとされたらしい(注3。219頁)。しかし一方でエイゼンシュテインの体調が思わしくなかったともいわれる。エイゼンシュテインがどのような姿勢で、当局に配慮しながら撮ったのか否かは定かではなく、一概にプロパガンダ作ともいえない。この恐怖物語はエイゼンシュテインの少年期の人格形成の一部であり、イヴァンの物語の暴虐ぶりで味わった恐怖感をポーの世界と結びつけ、少年の深層に棲息する快楽(エクスタシー)を目覚めさせたに違いないと言われる(注3。210頁)。またエイゼンシュテインの両親はまだ彼が幼いこと離婚し、孤独と不安であった。両親に捨てられた彼が革命の混乱に巻きこまれたものの、『戦艦ポチョムキン』によって映画という権威を身につけ自らの地位を獲得したときの恍惚が、(映画の)イヴァンの性格に投影されているとのことである(注3。212頁)。ここは第2部冒頭のシーンと重なる。この政治がらみ、エイゼンシュテインとイヴァン4世の重複・類似する点は注3の文献『エイゼンシュテイン』第9章に詳しい。イコン画というのだろうか、建物内のあらゆるところに描かれた宗教画が崇高かつおどろおどろしい背景となり、醜悪で妄執的な欲の渦巻く世界を取り巻いている様は一種、異様な雰囲気を醸し出している。この壁画にも何か比喩がありそうだ。ロシア正教会はツァーリに冠を授けて式を行い、強力に当時の支配層の貴族と利害を共にしていたように描かれる。雷帝から権力と利権をとりあげられて無視されて激しい憎悪を抱き、府教は雷帝を亡き者にしようとさえする。それには同じ穴のムジナである貴族の伯母さえも驚くほどであった。このあたり史実か否かはわからないが、ロシアの治世に深く関与し、権力の争いの裏側が垣間見える。イコン画や儀式の様子もオカルトの域に達しそうな人々の醜さと相まって、宗教(とその儀式)も作品の底部に暗く流れているように思われる。俳優陣では雷帝を演じたニコライ・チャルカーソフが見事。他はちょっと見分けがつきにくいが、みな目つきが尋常ではない。伯母エフロシニアを演じるセラフィマ・ビルマンが圧巻の顔芸。息子への倒錯した執着・母性の表現も見物。顔のクローズアップがここぞというところで多用され、他のレビュアーさまが触れておられるように歌舞伎の見栄やメイクを取り入れたような表情のつくり、構図を優先したような様式的な所作、決めポーズが採り入れられている。一方でセリフも比較的多く舞台劇のような一面もあり、セリフ、顔、所作が一体となり登場人物の内面を語る。とりわけ眼の表情が強烈だ。つまり演劇的な芝居、サイレント映画のような表現様式、極めて映画的な大胆な寄りと引き、奇跡的な構図、意識的な影の使用法のすべてがめまいを覚えるような力で迫ってくる。音楽はロシアの作曲家、セルゲイ・プロコフィエフを起用。あまりクラシックに明るくないが、名はきいたことがあり、本作の音楽は素晴らしい。前作『アレクサンドル・ネフスキー』でもプロコフィエフと組み、「音楽とモンタアジュ映像の同時性によって『ネフスキイ』は音楽映画との親縁性を強めている」(注3。206頁)らしいので、本作再見時には音楽と編集のリズムにも注意して観たい。エイゼンシュテインといえば映画の教科書的な、基礎知識として構えて観勝ちだが、本作にそんなセットアップは不要。政治的側面はとりあえず置いておいて、荒々しく赤裸々な人間たちのドラマに飲まれ、画に陶然となるのが正解かと思われる。パワーゲームと信念、裏切りとパトスの一大パノラマ。あの「モンタージュ理論の・・」というとっつきにくさを払い、お勉強映画と思わず戦時下の70年前につくられた異形が跋扈するこの作品に接して欲しいと思う。第3部がなくてもこれで1つの作品として充分観ることができる。画質は可もなく不可もなく。ただ全体的にノイズ、傷等がみられ、チラチラするところがあるが、パートカラー部分を除いて滲みはあまりなく、あの耐えられないフレームのガタツキはほとんどない。画質重視の方には不満足かもしれないが、個人的には許容範囲。ただ当然綺麗、というか公開当時の状態に近いことは望ましい。そのような邦盤をぜひ廉価で発売して欲しい。撮影が素晴らしいだけにもったいないし、パートカラー部分はどのような発色だったのだろう。ロシア語のみ。字幕ON,OFF不可。あまりに簡単なスタッフ・キャスト解説(ディスク内特典)。紙特典なし。片面2層。DOLBY DIGITAL.某サイトでは、第1部 1時間39分 / 第2部 1時間50分とされているが商品裏面ではトータル184分。イワン雷帝 ИВАН ГРОЗНЫЙ Ivan the Terrible 製作第1部44年、第2部45年、公開第1部1946年、第2部1958年注1『改訂版 詳説世界史研究』木下康彦他(2008、山川出版社)、注2Wiki(イヴァン4世、ロシア・ツァーリ国)、注3『エイゼンシュテイン』篠田正浩(1983、岩波書店)を参考にしました。注3書籍は有益です。関連キーワード ロシア、ソ連、ツァーリ、暴君、貴族、ロシア正教会、農奴、イコン画、パートカラー関連作 『アレクサンドル・ネフスキー』『戦艦ポチョムキン』
フィードバックをお寄せいただきありがとうございます
申し訳ありませんが、エラーが発生しました
申し訳ありませんが、レビューを読み込めませんでした
-
トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中に問題が発生しました。後でもう一度試してください。
2015年5月19日に日本でレビュー済み

Amazonで購入
『戦艦ポチョムキン』が有名なセルゲイ・エイゼンシュテインのよる、いわゆるイワン雷帝(イヴァン4世)の内面、外面の闘争を1部・2部構成3時間で描く。ひとことでいうとパワーとその対立の物語であるが、当方、史実に暗く、ごく表面的な知識しかない。監督が緻密な理論・繊細な計算を用いながらも、反面、いや、それだからこその巨岩のような、あるいは禿山の山脈を睥睨するような壮大さ、力強さとむき出しの生々しさに満ちている。第1級の「映像タペストリ」となっているように思われる。
前述『ポチョムキン』は観ておらず「モンタージュ理論」なるものも実はあまりわかっていない・・。それでも巨大なセット・美術(これが実に「らしい」威厳と美しさに満ちている)や広大な土地のロケにみられる構図の大胆さと繊細さ。あまり動かぬフレームの中で被写体が動くというスタイルを採っているが、その絶妙な被写体の配置・動きに引き込まれる。「画力」は抜きんでたものであり、私はなにより「画」を楽しみ、かつ、驚かされた。観ていて「ああ、映画だ」・・と思う。
少し歴史的背景もあった方がよいと思われるので付け焼刃ながら補足しておきたい。適切でない点あると思うが、詳しい方には何卒ご容赦いただきたい。15世紀、モスクワ大公国はイヴァン3世の治世に地域の諸公国を併合し、おおむねロシアの統一を完成した。自らをローマ帝国の後継者とギリシャ正教の守護者を任じ、ツァーリ(皇帝)を名乗った(大公として載冠)。彼の政策は孫のイヴァン4世に受け継がれた。1547年にツァーリとなる(ツァーリとしての載冠式から本作は始まる)。ロシア・ツァーリ国(モスクワ・ロシア国等とも)を名乗り(ただこのあたりの名称については複雑で理解しきれていない・・)この名称は1721年にピョートル1世(ツァーリではなくインペラートル)がロシア帝国(帝政ロシア)の建国を宣言するまで用いられていた。
彼は専制・恐怖政治を強化したため、「雷帝」Ivan the Terribleと恐れられた。世襲、私利私欲に走る貴族との軋轢、対立はひどかったという(注1, 2)。
それとともにロシア正教会(キリスト教正教会の一派)とも激しく衝突した。雷帝は過去の恨みと孤独を抱え込み、精神的に不安定であり、貴族や外敵に乗っ取られるという、雷帝本人が感じた「恐怖」の物語、孤独、復讐の物語でもある点が興味深い。実は「歴史に沿いながら、時にはほとんど史実を無視したプロットの中で構築されている」という(注3。221頁)。
以下、★まで内容に触れています。
第1部は即位した若きイヴァン4世と妻の生活、治世改革が叫ばれ、貴族・正教会を弱体化し、強大ロシアへの野望が語られる。そして息子を皇帝の座につかせようとする、雷帝の伯母エフロシニヤの画策が描かれる。この伯母の顔、やることなすことが狡猾でコワイ。妻は伯母に毒殺される。妻の葬儀場面は見事。ここでは楽式でいう対位法、フーガで表現されているという(注3。216頁)。嘆き、自信を無くす雷帝と、弔いに読まれるダヴィデ王の詩編の吟誦のフーガ。そして怒りを爆発させる(「ローマは2度滅びた。第三のローマ、モスクワは不滅だ。第四のローマはありえぬ」・・)。燃え盛る松明。親衛隊結成の端緒となるシーンである。そしてモスクワを去った雷帝へ民衆がモスクワへの帰還を請願する。ここでの超近景と超遠景の鳥肌立つような同居にハッとさせられる。
第2部は帰還した雷帝と、貴族・正教会との暗闘。重要なのは雷帝の少年時代の描写である。幼いイヴァンの前で毒殺され(父はすでに他界)、形ばかりの大公即位。摂関政治が敷かれるのだが、貴族は領土や財産を食いつぶすばかり。子どもの戯言と一笑にふされ為すすべもない。しかしこの時の体験が、イヴァンに鮮烈に貴族憎しという憎悪と、強烈な孤独を味わった。母を侮辱されたとき、「この男を捕らえよ!」と叫び、衛兵が幼いイヴァンに従ってその貴族をあやめるシーンがある。ある本では、イヴァンが権力をはじめて意識し、行使の恍惚に目覚めるシーンだという(注3。212頁)。
雷帝の孤独と暴走、対立は進み、貴族を処刑。葬儀シーンも構図の厳しさと相まって見事。対立は決定的となり、やがて雷帝暗殺計画が始まる。
ラスト近くでパートカラーが用いられる(画面の一部ではなくシーン)。鮮烈な赤が支配する画面が後を予感させるのか。ここは現実の作品内の色とは思われず、空間や人物内面の温度か何かを表しているのだろうか。そして決定的な一言で映画は終わる。★
ところで本作は3部作として構想されていたが第3部が創られることはなかった(一部は撮影されていたという)。このあたり時の政権の怒りに第2部が触れたかららしい(ジダーノフ批判)。余計だが本作とソ連との関係に少しだけ触れる。本作の提案は、第二次大戦に突入することで直面した危機を16世紀のイヴァン雷帝が克服したように、スターリンの指導によって克服されることを予言するためのものであった。雷帝の物語をスターリンの讃仰に一致させることがエイゼンシュテインの仕事だったようである(注3。209頁)。第1部は賞賛されたが、第2部は上映を禁止され、人々が観ることができたのはスターリン没後の1958年。親衛隊の描写がまるでKKKのようであり、イヴァンの真実を描かず、反歴史的であるとされたらしい(注3。219頁)。しかし一方でエイゼンシュテインの体調が思わしくなかったともいわれる。エイゼンシュテインがどのような姿勢で、当局に配慮しながら撮ったのか否かは定かではなく、一概にプロパガンダ作ともいえない。
この恐怖物語はエイゼンシュテインの少年期の人格形成の一部であり、イヴァンの物語の暴虐ぶりで味わった恐怖感をポーの世界と結びつけ、少年の深層に棲息する快楽(エクスタシー)を目覚めさせたに違いないと言われる(注3。210頁)。またエイゼンシュテインの両親はまだ彼が幼いこと離婚し、孤独と不安であった。両親に捨てられた彼が革命の混乱に巻きこまれたものの、『戦艦ポチョムキン』によって映画という権威を身につけ自らの地位を獲得したときの恍惚が、(映画の)イヴァンの性格に投影されているとのことである(注3。212頁)。ここは第2部冒頭のシーンと重なる。この政治がらみ、エイゼンシュテインとイヴァン4世の重複・類似する点は注3の文献『エイゼンシュテイン』第9章に詳しい。
イコン画というのだろうか、建物内のあらゆるところに描かれた宗教画が崇高かつおどろおどろしい背景となり、醜悪で妄執的な欲の渦巻く世界を取り巻いている様は一種、異様な雰囲気を醸し出している。この壁画にも何か比喩がありそうだ。ロシア正教会はツァーリに冠を授けて式を行い、強力に当時の支配層の貴族と利害を共にしていたように描かれる。雷帝から権力と利権をとりあげられて無視されて激しい憎悪を抱き、府教は雷帝を亡き者にしようとさえする。それには同じ穴のムジナである貴族の伯母さえも驚くほどであった。このあたり史実か否かはわからないが、ロシアの治世に深く関与し、権力の争いの裏側が垣間見える。イコン画や儀式の様子もオカルトの域に達しそうな人々の醜さと相まって、宗教(とその儀式)も作品の底部に暗く流れているように思われる。
俳優陣では雷帝を演じたニコライ・チャルカーソフが見事。他はちょっと見分けがつきにくいが、みな目つきが尋常ではない。伯母エフロシニアを演じるセラフィマ・ビルマンが圧巻の顔芸。息子への倒錯した執着・母性の表現も見物。顔のクローズアップがここぞというところで多用され、他のレビュアーさまが触れておられるように歌舞伎の見栄やメイクを取り入れたような表情のつくり、構図を優先したような様式的な所作、決めポーズが採り入れられている。一方でセリフも比較的多く舞台劇のような一面もあり、セリフ、顔、所作が一体となり登場人物の内面を語る。とりわけ眼の表情が強烈だ。つまり演劇的な芝居、サイレント映画のような表現様式、極めて映画的な大胆な寄りと引き、奇跡的な構図、意識的な影の使用法のすべてがめまいを覚えるような力で迫ってくる。
音楽はロシアの作曲家、セルゲイ・プロコフィエフを起用。あまりクラシックに明るくないが、名はきいたことがあり、本作の音楽は素晴らしい。前作『アレクサンドル・ネフスキー』でもプロコフィエフと組み、「音楽とモンタアジュ映像の同時性によって『ネフスキイ』は音楽映画との親縁性を強めている」(注3。206頁)らしいので、本作再見時には音楽と編集のリズムにも注意して観たい。
エイゼンシュテインといえば映画の教科書的な、基礎知識として構えて観勝ちだが、本作にそんなセットアップは不要。政治的側面はとりあえず置いておいて、荒々しく赤裸々な人間たちのドラマに飲まれ、画に陶然となるのが正解かと思われる。パワーゲームと信念、裏切りとパトスの一大パノラマ。あの「モンタージュ理論の・・」というとっつきにくさを払い、お勉強映画と思わず戦時下の70年前につくられた異形が跋扈するこの作品に接して欲しいと思う。第3部がなくてもこれで1つの作品として充分観ることができる。
画質は可もなく不可もなく。ただ全体的にノイズ、傷等がみられ、チラチラするところがあるが、パートカラー部分を除いて滲みはあまりなく、あの耐えられないフレームのガタツキはほとんどない。画質重視の方には不満足かもしれないが、個人的には許容範囲。ただ当然綺麗、というか公開当時の状態に近いことは望ましい。そのような邦盤をぜひ廉価で発売して欲しい。撮影が素晴らしいだけにもったいないし、パートカラー部分はどのような発色だったのだろう。ロシア語のみ。字幕ON,OFF不可。あまりに簡単なスタッフ・キャスト解説(ディスク内特典)。紙特典なし。片面2層。DOLBY DIGITAL.某サイトでは、第1部 1時間39分 / 第2部 1時間50分とされているが商品裏面ではトータル184分。
イワン雷帝 ИВАН ГРОЗНЫЙ Ivan the Terrible 製作第1部44年、第2部45年、公開第1部1946年、第2部1958年
注1『改訂版 詳説世界史研究』木下康彦他(2008、山川出版社)、
注2Wiki(イヴァン4世、ロシア・ツァーリ国)、
注3『エイゼンシュテイン』篠田正浩(1983、岩波書店)を参考にしました。注3書籍は有益です。
関連キーワード ロシア、ソ連、ツァーリ、暴君、貴族、ロシア正教会、農奴、イコン画、パートカラー
関連作 『アレクサンドル・ネフスキー』『戦艦ポチョムキン』
前述『ポチョムキン』は観ておらず「モンタージュ理論」なるものも実はあまりわかっていない・・。それでも巨大なセット・美術(これが実に「らしい」威厳と美しさに満ちている)や広大な土地のロケにみられる構図の大胆さと繊細さ。あまり動かぬフレームの中で被写体が動くというスタイルを採っているが、その絶妙な被写体の配置・動きに引き込まれる。「画力」は抜きんでたものであり、私はなにより「画」を楽しみ、かつ、驚かされた。観ていて「ああ、映画だ」・・と思う。
少し歴史的背景もあった方がよいと思われるので付け焼刃ながら補足しておきたい。適切でない点あると思うが、詳しい方には何卒ご容赦いただきたい。15世紀、モスクワ大公国はイヴァン3世の治世に地域の諸公国を併合し、おおむねロシアの統一を完成した。自らをローマ帝国の後継者とギリシャ正教の守護者を任じ、ツァーリ(皇帝)を名乗った(大公として載冠)。彼の政策は孫のイヴァン4世に受け継がれた。1547年にツァーリとなる(ツァーリとしての載冠式から本作は始まる)。ロシア・ツァーリ国(モスクワ・ロシア国等とも)を名乗り(ただこのあたりの名称については複雑で理解しきれていない・・)この名称は1721年にピョートル1世(ツァーリではなくインペラートル)がロシア帝国(帝政ロシア)の建国を宣言するまで用いられていた。
彼は専制・恐怖政治を強化したため、「雷帝」Ivan the Terribleと恐れられた。世襲、私利私欲に走る貴族との軋轢、対立はひどかったという(注1, 2)。
それとともにロシア正教会(キリスト教正教会の一派)とも激しく衝突した。雷帝は過去の恨みと孤独を抱え込み、精神的に不安定であり、貴族や外敵に乗っ取られるという、雷帝本人が感じた「恐怖」の物語、孤独、復讐の物語でもある点が興味深い。実は「歴史に沿いながら、時にはほとんど史実を無視したプロットの中で構築されている」という(注3。221頁)。
以下、★まで内容に触れています。
第1部は即位した若きイヴァン4世と妻の生活、治世改革が叫ばれ、貴族・正教会を弱体化し、強大ロシアへの野望が語られる。そして息子を皇帝の座につかせようとする、雷帝の伯母エフロシニヤの画策が描かれる。この伯母の顔、やることなすことが狡猾でコワイ。妻は伯母に毒殺される。妻の葬儀場面は見事。ここでは楽式でいう対位法、フーガで表現されているという(注3。216頁)。嘆き、自信を無くす雷帝と、弔いに読まれるダヴィデ王の詩編の吟誦のフーガ。そして怒りを爆発させる(「ローマは2度滅びた。第三のローマ、モスクワは不滅だ。第四のローマはありえぬ」・・)。燃え盛る松明。親衛隊結成の端緒となるシーンである。そしてモスクワを去った雷帝へ民衆がモスクワへの帰還を請願する。ここでの超近景と超遠景の鳥肌立つような同居にハッとさせられる。
第2部は帰還した雷帝と、貴族・正教会との暗闘。重要なのは雷帝の少年時代の描写である。幼いイヴァンの前で毒殺され(父はすでに他界)、形ばかりの大公即位。摂関政治が敷かれるのだが、貴族は領土や財産を食いつぶすばかり。子どもの戯言と一笑にふされ為すすべもない。しかしこの時の体験が、イヴァンに鮮烈に貴族憎しという憎悪と、強烈な孤独を味わった。母を侮辱されたとき、「この男を捕らえよ!」と叫び、衛兵が幼いイヴァンに従ってその貴族をあやめるシーンがある。ある本では、イヴァンが権力をはじめて意識し、行使の恍惚に目覚めるシーンだという(注3。212頁)。
雷帝の孤独と暴走、対立は進み、貴族を処刑。葬儀シーンも構図の厳しさと相まって見事。対立は決定的となり、やがて雷帝暗殺計画が始まる。
ラスト近くでパートカラーが用いられる(画面の一部ではなくシーン)。鮮烈な赤が支配する画面が後を予感させるのか。ここは現実の作品内の色とは思われず、空間や人物内面の温度か何かを表しているのだろうか。そして決定的な一言で映画は終わる。★
ところで本作は3部作として構想されていたが第3部が創られることはなかった(一部は撮影されていたという)。このあたり時の政権の怒りに第2部が触れたかららしい(ジダーノフ批判)。余計だが本作とソ連との関係に少しだけ触れる。本作の提案は、第二次大戦に突入することで直面した危機を16世紀のイヴァン雷帝が克服したように、スターリンの指導によって克服されることを予言するためのものであった。雷帝の物語をスターリンの讃仰に一致させることがエイゼンシュテインの仕事だったようである(注3。209頁)。第1部は賞賛されたが、第2部は上映を禁止され、人々が観ることができたのはスターリン没後の1958年。親衛隊の描写がまるでKKKのようであり、イヴァンの真実を描かず、反歴史的であるとされたらしい(注3。219頁)。しかし一方でエイゼンシュテインの体調が思わしくなかったともいわれる。エイゼンシュテインがどのような姿勢で、当局に配慮しながら撮ったのか否かは定かではなく、一概にプロパガンダ作ともいえない。
この恐怖物語はエイゼンシュテインの少年期の人格形成の一部であり、イヴァンの物語の暴虐ぶりで味わった恐怖感をポーの世界と結びつけ、少年の深層に棲息する快楽(エクスタシー)を目覚めさせたに違いないと言われる(注3。210頁)。またエイゼンシュテインの両親はまだ彼が幼いこと離婚し、孤独と不安であった。両親に捨てられた彼が革命の混乱に巻きこまれたものの、『戦艦ポチョムキン』によって映画という権威を身につけ自らの地位を獲得したときの恍惚が、(映画の)イヴァンの性格に投影されているとのことである(注3。212頁)。ここは第2部冒頭のシーンと重なる。この政治がらみ、エイゼンシュテインとイヴァン4世の重複・類似する点は注3の文献『エイゼンシュテイン』第9章に詳しい。
イコン画というのだろうか、建物内のあらゆるところに描かれた宗教画が崇高かつおどろおどろしい背景となり、醜悪で妄執的な欲の渦巻く世界を取り巻いている様は一種、異様な雰囲気を醸し出している。この壁画にも何か比喩がありそうだ。ロシア正教会はツァーリに冠を授けて式を行い、強力に当時の支配層の貴族と利害を共にしていたように描かれる。雷帝から権力と利権をとりあげられて無視されて激しい憎悪を抱き、府教は雷帝を亡き者にしようとさえする。それには同じ穴のムジナである貴族の伯母さえも驚くほどであった。このあたり史実か否かはわからないが、ロシアの治世に深く関与し、権力の争いの裏側が垣間見える。イコン画や儀式の様子もオカルトの域に達しそうな人々の醜さと相まって、宗教(とその儀式)も作品の底部に暗く流れているように思われる。
俳優陣では雷帝を演じたニコライ・チャルカーソフが見事。他はちょっと見分けがつきにくいが、みな目つきが尋常ではない。伯母エフロシニアを演じるセラフィマ・ビルマンが圧巻の顔芸。息子への倒錯した執着・母性の表現も見物。顔のクローズアップがここぞというところで多用され、他のレビュアーさまが触れておられるように歌舞伎の見栄やメイクを取り入れたような表情のつくり、構図を優先したような様式的な所作、決めポーズが採り入れられている。一方でセリフも比較的多く舞台劇のような一面もあり、セリフ、顔、所作が一体となり登場人物の内面を語る。とりわけ眼の表情が強烈だ。つまり演劇的な芝居、サイレント映画のような表現様式、極めて映画的な大胆な寄りと引き、奇跡的な構図、意識的な影の使用法のすべてがめまいを覚えるような力で迫ってくる。
音楽はロシアの作曲家、セルゲイ・プロコフィエフを起用。あまりクラシックに明るくないが、名はきいたことがあり、本作の音楽は素晴らしい。前作『アレクサンドル・ネフスキー』でもプロコフィエフと組み、「音楽とモンタアジュ映像の同時性によって『ネフスキイ』は音楽映画との親縁性を強めている」(注3。206頁)らしいので、本作再見時には音楽と編集のリズムにも注意して観たい。
エイゼンシュテインといえば映画の教科書的な、基礎知識として構えて観勝ちだが、本作にそんなセットアップは不要。政治的側面はとりあえず置いておいて、荒々しく赤裸々な人間たちのドラマに飲まれ、画に陶然となるのが正解かと思われる。パワーゲームと信念、裏切りとパトスの一大パノラマ。あの「モンタージュ理論の・・」というとっつきにくさを払い、お勉強映画と思わず戦時下の70年前につくられた異形が跋扈するこの作品に接して欲しいと思う。第3部がなくてもこれで1つの作品として充分観ることができる。
画質は可もなく不可もなく。ただ全体的にノイズ、傷等がみられ、チラチラするところがあるが、パートカラー部分を除いて滲みはあまりなく、あの耐えられないフレームのガタツキはほとんどない。画質重視の方には不満足かもしれないが、個人的には許容範囲。ただ当然綺麗、というか公開当時の状態に近いことは望ましい。そのような邦盤をぜひ廉価で発売して欲しい。撮影が素晴らしいだけにもったいないし、パートカラー部分はどのような発色だったのだろう。ロシア語のみ。字幕ON,OFF不可。あまりに簡単なスタッフ・キャスト解説(ディスク内特典)。紙特典なし。片面2層。DOLBY DIGITAL.某サイトでは、第1部 1時間39分 / 第2部 1時間50分とされているが商品裏面ではトータル184分。
イワン雷帝 ИВАН ГРОЗНЫЙ Ivan the Terrible 製作第1部44年、第2部45年、公開第1部1946年、第2部1958年
注1『改訂版 詳説世界史研究』木下康彦他(2008、山川出版社)、
注2Wiki(イヴァン4世、ロシア・ツァーリ国)、
注3『エイゼンシュテイン』篠田正浩(1983、岩波書店)を参考にしました。注3書籍は有益です。
関連キーワード ロシア、ソ連、ツァーリ、暴君、貴族、ロシア正教会、農奴、イコン画、パートカラー
関連作 『アレクサンドル・ネフスキー』『戦艦ポチョムキン』
このレビューの画像












2023年6月1日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
イワン雷帝は、残酷な人というイメージがあったのですが、そういうシーンはほとんどなくて、イワン雷帝の真の姿に迫ってないのではと思いました。もいい会みてみます。
2014年8月10日に日本でレビュー済み
「チャップリン自伝・下巻 栄光の日々」で、チャップリンも会ったエイゼンシュタイン監督の本作品「イワン雷帝」について、「およそ歴史映画というものの最高作といってよかった。詩人の精神で歴史を扱っているのだ」と書かれていたので観た。
全編3時間と長い。基調はモノクロで、途中と最後はカラー。細部まで明確に映っているモノクロは美しく、また白と黒の対比を効果的に使っている。
イワン皇帝の長く伸びたひげの横顔の影を大きく壁に映したり、長身イワン皇帝の背景に、アレクサンドロフからモスクワへ戻るよう陳情に訪れた民衆の蟻のように連なりカーブを描く隊列等、構図が面白い。
音楽はあのプロコフィエフ。冒頭の戴冠式での男性バリトン独唱は声明(しょうみょう)のように感じた。チャイコフスキーの1812年や、最後の方はベルリオーズの幻想交響曲のテーマに似たフレーズもあった。
権力闘争を描いている。ラストシーンでイワン雷帝がこう語る。
「皇帝には常に細心の配慮が求められる。忠臣には恩愛と柔和さで、逆臣には残酷と怒りで。この素質なき者は皇帝たり得ない。今やモスクワでは、ロシア統一の敵はついに打倒された。鎖は解かれた。今後、我々はロシアの主権を侵そうと外部から企てる者に対し、反撃の正義の剣を断固ふるうであろう。ロシアへの侮辱は許さむ。」
16世紀にイワン雷帝によって統一された独裁国家ロシア。トップの考えは共産主義革命のソ連を経た今も全く変わらないことに驚いた。現在のウクライナ情勢に対するロシアのスタンスも同じ。プーチン大統領、あるいはロシアの歴代党首は本作品を何度も観て台詞をまねび己を鼓舞し、意気高揚してきたのではなかろうか。クリミアで、プーチン大統領は「侮蔑的態度はゆるすべきではない」と演説した。イワン雷帝の言そのものではないか。
一党独裁制の単細胞より、政権交代もある議会制民主主義の多細胞の方が自由と平等、人権は間違いなく確保される。国際法上、法律的に独立している日本は、政治的あるいは軍事的には米国の属国であることに変わりないが、集団的自衛権なるものを米国から求めれて現在、国内紛糾している。
それにしても、政権が選挙で信を問われるシステムは、完璧ではないにしても一党独裁制より進んでいることは間違いない。一党独裁制は時代遅れ、もう流行らないのだ。
全編3時間と長い。基調はモノクロで、途中と最後はカラー。細部まで明確に映っているモノクロは美しく、また白と黒の対比を効果的に使っている。
イワン皇帝の長く伸びたひげの横顔の影を大きく壁に映したり、長身イワン皇帝の背景に、アレクサンドロフからモスクワへ戻るよう陳情に訪れた民衆の蟻のように連なりカーブを描く隊列等、構図が面白い。
音楽はあのプロコフィエフ。冒頭の戴冠式での男性バリトン独唱は声明(しょうみょう)のように感じた。チャイコフスキーの1812年や、最後の方はベルリオーズの幻想交響曲のテーマに似たフレーズもあった。
権力闘争を描いている。ラストシーンでイワン雷帝がこう語る。
「皇帝には常に細心の配慮が求められる。忠臣には恩愛と柔和さで、逆臣には残酷と怒りで。この素質なき者は皇帝たり得ない。今やモスクワでは、ロシア統一の敵はついに打倒された。鎖は解かれた。今後、我々はロシアの主権を侵そうと外部から企てる者に対し、反撃の正義の剣を断固ふるうであろう。ロシアへの侮辱は許さむ。」
16世紀にイワン雷帝によって統一された独裁国家ロシア。トップの考えは共産主義革命のソ連を経た今も全く変わらないことに驚いた。現在のウクライナ情勢に対するロシアのスタンスも同じ。プーチン大統領、あるいはロシアの歴代党首は本作品を何度も観て台詞をまねび己を鼓舞し、意気高揚してきたのではなかろうか。クリミアで、プーチン大統領は「侮蔑的態度はゆるすべきではない」と演説した。イワン雷帝の言そのものではないか。
一党独裁制の単細胞より、政権交代もある議会制民主主義の多細胞の方が自由と平等、人権は間違いなく確保される。国際法上、法律的に独立している日本は、政治的あるいは軍事的には米国の属国であることに変わりないが、集団的自衛権なるものを米国から求めれて現在、国内紛糾している。
それにしても、政権が選挙で信を問われるシステムは、完璧ではないにしても一党独裁制より進んでいることは間違いない。一党独裁制は時代遅れ、もう流行らないのだ。
2015年2月4日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
エイゼンシュタインのイワン雷帝は今ではおどろおどろしいホラー映画の主人公のように見える。この映画の巨匠の他の二作「戦艦ポチョムキン」と「アレクサンデル・ネフスキー」とは異なり、これは、極度に影付けを強調した様式を人物の描写の手法に多用している。その結果、作品が観者に与える映像は、大きく歪められ、それがこの作品の好悪の分かれ道となる。批評子は、どうも長く見ていられない。やはり過ぎたるは及ばざるが如しである。また、音楽は、「アレクサンデル・ネフスキー」と同様に、セルゲイ・プロコフィエフが担当している。
2019年8月4日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
1944年のセルゲイ・エイゼンシュテイン監督の映画。二部構成であるが、内容は連続しており、一部だけを見ても中途半端な印象が残ると思われる。本来は第三部も作られるはずだったが、スターリンにより二部が上映禁止となったため、第三部は作られなかった。それゆえ、第二部まででは“イワン雷帝”ことイヴァン4世の晩年は知ることができないが、二部を見終わった印象は、皇帝が親族や貴族を抑え専制を完成させていく様子が描かれているので完結はしている。二部合わせると3時間ほどであるが、長さを感じさせない出来で、映像も美しく、人物の影をたくみに使った撮影は印象的。二部で饗宴のシーンがカラーになるあたりも見事。
第1部は戴冠式の様子であるが歴史映像をみているような重厚さ。カザン・ハン国との戦争は大砲を使ったシーンなどあり。第2部は叔母を中心とするイワンの暗殺のたくらみが中心。史実と異なる内容が多いが、イワンの性格やとりまきの人物、歴史的背景、当時の貴族、協会、皇帝の関係などは理解できる。
スターリンが監督とイワンを演じたチェルカーソフをクレムリンに呼んで会見した内容については「ソビエトとロシア(森本良男著)p54-57」に書かれているが、スターリンはオプリーチニナ(親衛隊)をKKKのように描いているとか、イワンを決断力のない、ハムレットのような人物として描いていると非難している。なおイワンの行った大粛清がスターリンのそれを思わせるため、第2部は上映禁止になったとされていることが多いが、本作を見た印象では、粛清のシーンはわずかで(しかも殺害が正当であったような印象を与える)、映画の大半はイワンに好意的・同情的で、敵対する貴族・教会は史実を曲げて(想像して)悪役に描かれている。スターリンは、イワンを賛美し自らを擬するところがあった。映画のイワンが神に祈ったり自省するようなところが気に入らなかったのかもしれないが、上映禁止にするほどのシーンはなかった印象なのでスターリンはそれほど神経質になっていたことのあらわれとは解釈できる。
主要な登場人物は、皇帝の妻アナスタシア、親友のアンドレイ・クルプスキー公(アナスタシアに好意を寄せるという設定になっている)、叔母のエフロシニア(黒いベールをかぶっているせいか女性であるのに、男性のように見える)、その子ウラジーミル公、ロシア正教会モスクワ府主教マカリー(イワンの敵対者として描かれる)、府主教フィリップ2世(イワンのかつての親友として描かれ、イワンを生神女就寝大聖堂で非難するシーンはあるが後に殺されるのは描かれていない)、イワンが低い身分から採用したらアレクセイ・バスマーノフとその子フョードル・バスマーノフ。
第1部は戴冠式の様子であるが歴史映像をみているような重厚さ。カザン・ハン国との戦争は大砲を使ったシーンなどあり。第2部は叔母を中心とするイワンの暗殺のたくらみが中心。史実と異なる内容が多いが、イワンの性格やとりまきの人物、歴史的背景、当時の貴族、協会、皇帝の関係などは理解できる。
スターリンが監督とイワンを演じたチェルカーソフをクレムリンに呼んで会見した内容については「ソビエトとロシア(森本良男著)p54-57」に書かれているが、スターリンはオプリーチニナ(親衛隊)をKKKのように描いているとか、イワンを決断力のない、ハムレットのような人物として描いていると非難している。なおイワンの行った大粛清がスターリンのそれを思わせるため、第2部は上映禁止になったとされていることが多いが、本作を見た印象では、粛清のシーンはわずかで(しかも殺害が正当であったような印象を与える)、映画の大半はイワンに好意的・同情的で、敵対する貴族・教会は史実を曲げて(想像して)悪役に描かれている。スターリンは、イワンを賛美し自らを擬するところがあった。映画のイワンが神に祈ったり自省するようなところが気に入らなかったのかもしれないが、上映禁止にするほどのシーンはなかった印象なのでスターリンはそれほど神経質になっていたことのあらわれとは解釈できる。
主要な登場人物は、皇帝の妻アナスタシア、親友のアンドレイ・クルプスキー公(アナスタシアに好意を寄せるという設定になっている)、叔母のエフロシニア(黒いベールをかぶっているせいか女性であるのに、男性のように見える)、その子ウラジーミル公、ロシア正教会モスクワ府主教マカリー(イワンの敵対者として描かれる)、府主教フィリップ2世(イワンのかつての親友として描かれ、イワンを生神女就寝大聖堂で非難するシーンはあるが後に殺されるのは描かれていない)、イワンが低い身分から採用したらアレクセイ・バスマーノフとその子フョードル・バスマーノフ。
2020年9月25日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
問題なく購入、再生できました。
2011年2月15日に日本でレビュー済み
これも映画史の一本。今に劣らぬ、迫力ある映画作りである。


![イワン雷帝 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51NUZJbB9nL.__AC_SX300_SY300_QL70_ML2_.jpg)

![戦艦ポチョムキン【淀川長治解説映像付き】 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/71fSvWBnZML._AC_UL200_SR200,200_.jpg)

![アレクサンドル・ネフスキー [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61z0lLN87hL._AC_UL200_SR200,200_.jpg)