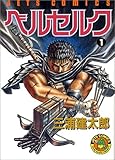[]『BREAK/THROUGH』ふたたび。
『BREAK/THROUGH』もいっしょに通販するわけで、『BREAK/THROUGH』の紹介記事を貼りなおしておきます。通販購入希望の方は以下のフォームからよろしく。委託しようかなあという気もあるのですが、まだ先の話になると思うので、通販がいちばん確実かと。
http://my.formman.com/form/pc/cWm1Ro0AGDHLfpfn/
■目次■
前記
序章「あなたならエヴァンゲリオンに乗りますか?」
第一部「血 life」
第一章「少年の夢――『プラネテス』が見る風景」
第二章「世界が空気に溶けるまで――『ほしのこえ』から『けいおん!』へ」
第三章「阿良々木暦の可能性殺し――『猫物語(白)』とハーレムブレイカー」
コラム1
第二部「夜 survival」
第四章「『日本沈没』か『東のエデン』か」
第五章「論理と論理の陷穽――山本弘のSF世界」
第六章「蛇と王冠――『十二国記』から『コードギアス』まで」
第七章「欺瞞の帝国――『グイン・サーガ』小論」
コラム2
第三部「花 human」
第八章「『SLAM DUNK』は遠く」
第九章「それでもぼくたちはらくえんをめざす」
第十章「花の勲章――『SWAN SONG』を解読する」
終章「たとえあなたがエヴァに乗らなくても」
第十一章「暗黒の世界へようこそ」
■各章内容解説■
『BREAK/THROUGH』は序章と終章を含めて全十二章から構成されています。さらに、そこにゲスト寄稿者によるコラムと対談が付け加わります。このうち、序章と終章の内容は「秘密」です。ちょっと一般の批評本ではありえないことになっているとだけいっておきましょう(ま、たいしたことではありませんが……)。
以下、各章及の内容を解説していきます。
●「序章 あなたならエヴァンゲリオンに乗りますか?」
秘密。
●「第一章 少年の夢――『プラネテス』が見た風景」
少年の夢――男の価値――人間らしさ――どのような言葉でいいあらわしてもいいが、それは、人間が持ちえる最も純粋なモチベーションのことである。痛々しいような想いの純粋さこそが夢を輝かせる。
『修羅の門』の陸奥九十九、『バガボンド』の宮本武蔵、『プラネテス』のロックスミスといった人物を通して、「少年の夢」を追いかける男たちの姿を綴った章です。少年の夢とは、この世で最も純粋なスピリットのこと。多くのひとが成長とともに失うその究極のモチベーションの秘密とは何か? 考察しています。
●「第二章 世界が空気に溶けるまで――『ほしのこえ』から『けいおん!』へ」
それは終末の光景だ。世界の終わり。人類のたそがれ。天まで届けと建てられた塔はことごとく崩れ落ち、とわとも思える繁栄を誇った都市はあっけなく灰燼と化した。幾万幾億ともしれぬ光の十字架が大地に墓標のように突き刺さり、半ば砕けた少女の顔が死んだ瞳で世界を見つめている。あとは血のように赤い赤い海がどこまでもただ広がるばかり――そんな風景。
第二章は「セカイ系」及び「空気系」について語った章。「セカイ系」そのものは定義できないが、「セカイ系のようなもの」は多数存在していることを実証しながら、「空気系」に話を繋げていきます。「空気系」の代表作、『らき☆すた』や『けいおん!』のおもしろさとはどこにあるのか? いま、教室で繰り広げられる「キャラ戦争」とは? おそらく全編で最も評論らしい章です。
●「第三章 阿良々木暦の可能性殺し――『猫物語(白)』とハーレムブレイカー」
しかし、西尾維新は『猫物語(白)』できちんと「死亡宣告」を行った。この意味は大きい。阿良々木暦は一見、典型的なハーレムメーカーである。しかし、西尾は可能性を「保留」し続けることなくはっきりと「殺す」ことによって、ハーレム構造を打破した。いわば阿良々木は「可能性殺し(ポッシビリティ・キラー)」である。
第三章では西尾維新の傑作『猫物語(白)』を取り上げ、この作品の主人公阿良々木暦を「可能性殺し(ポッシビリティ・キラー)」であると捉えたうえで、「物語を綴るとはそもそもどういうことなのか?」を検証していきます。「生きた可能性」、「死んだ可能性」、そして「生きているように見える可能性」とは? ご一読ください。
- 作者: 西尾維新,VOFAN
- 出版社/メーカー: 講談社
- 発売日: 2010/10/27
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- 購入: 19人 クリック: 420回
- この商品を含むブログ (153件) を見る
日本という国はたしかに一時期、東の楽園であった。しかし、その楽園はいま、沈もうとしている。いまこそまさに救世主の出番だ。だが、その救世主はまさにその救おうとしている人びとによってひたすらになぶられる存在なのではないか、「映画界の王様」である神山監督はそう考えたのかもしれない。
第四章ではゼロ年代を代表する傑作漫画『日本沈没』及び傑作アニメ『東のエデン』を取り上げ、「日本」という沈みゆく大国の自画像を描き出そうとしています。ぼくがそこに見いだした絶望、そしてほのかな希望。ある意味で後半の章への伏線ともいえる一章となっています。
●「第五章 論理と論理の陷穽――山本弘のSF世界」
そう、山本の作品――特に最近の作品を特徴付けるものは人間と人間性に対する絶望、あるいはすくなくとも失望である。『神は沈黙せず』以降、山本のほとんどすべての作品で人間がいかに愚かしいかということがくどいほどに強調されている。山本の思想を名づけるなら、性善説でも性悪説でもなく、性愚説ということになりそうだ。
SF作家山本弘の作品世界を批判的に検討した一章です。主に取り上げるのは『神は沈黙せず』及び『アイの物語』。「論理」に至上の価値を置き、その具現であるマシンを理想の存在と見る山本弘の思想に疑問を呈し、「人間らしさ」の価値を考えています。理性と論理に還元できない「人間らしさ」の価値、その意味とは? 本書全体のテーマ「人間らしさとは何か?」を語るうえで重要な意味を持つ章です。
●「第六章 蛇と王冠――『十二国記』から『コードギアス』まで」
血のように紅い落日が辺りを染め上げる夕べ、遊び疲れた子どもたちがそれぞれの家へ帰ってゆく。しかし、グリフィスに帰るべき家はない。かれは遥かに遠い玩具を手にするそのときまでひたすら遊び続けるしかない。
第一章「少年の夢」を受けて、「王」たちについて語った章です。『十二国記』、『アルスラーン戦記』、『マヴァール年代記』、『国盗り物語』、『ファイブスター物語』、『ベルセルク』など、多数の作品に登場する「王」を見ながら、「王の条件」とは何か、と考えていきます。ここらへんからテンションはさらにヒートアップしていくことになります。
王都炎上・王子二人 ―アルスラーン戦記(1)(2) (カッパ・ノベルス)
- 作者: 田中芳樹,丹野忍
- 出版社/メーカー: 光文社
- 発売日: 2003/02/21
- メディア: 新書
- 購入: 4人 クリック: 48回
- この商品を含むブログ (31件) を見る
ファイブスター物語 (1) (ニュータイプ100%コミックス)
- 作者: 永野護
- 出版社/メーカー: 角川書店
- 発売日: 1998/09
- メディア: コミック
- 購入: 5人 クリック: 50回
- この商品を含むブログ (80件) を見る
●「第七章 欺瞞の帝国――『グイン・サーガ』小論」
さあ、語ろう、世にも陰鬱な話を。これは中原のさる大国の王位戴冠を巡る物語、誰にも愛されなかった少女と、万能でありながら無能極まりない彼女の夫君の物語に他ならぬ。
栗本薫の大長編ファンタジー小説『グイン・サーガ』に登場する悲劇の少女シルヴィアを取り上げ、「国家に圧殺される個」、「正論がひとを追い詰めていくプロセス」を論じた一章です。上に取り上げた冒頭の文章を読んでもわかると思いますが、ここまで来ると文体がもはや批評のものとも評論のものともいいがたい何かに切り替わっています。そのよしあしはともかく、気に入っている章です。
●「第八章 『SLAM DUNK』は遠く」
勝利以外の価値観もありえる。むしろ、それこそがスポーツの価値ではないのか。わたしは何も「頑張れば結果は問題ではない」といいたいのではない。たしかに結果は問題である。湘北高校の五人がどこまでも結果にこだわり続けたように。しかし、ある結果を目指して精進した末、いつのまにかその領域を追い越してしまう、そういうことはありえるのではないだろうか。
井上雄彦のスポーツ漫画『SLAM DUNK』と『リアル』を比較しながら、ひとにとって「勝利」とは何か、「成功」とは何を意味するのか、その点を考えた章です。タイトル「『SLAM DUNK』は遠く」からわかる通り、あの名台詞「あきらめたらそこで試合終了だよ」の「その先」を描いた『リアル』に注目して考察しています。ここからいよいよ本書はクライマックスに入っていきます。
SLAM DUNK 完全版 1 (ジャンプ・コミックスデラックス)
- 作者: 井上雄彦
- 出版社/メーカー: 集英社
- 発売日: 2001/03/19
- メディア: コミック
- 購入: 2人 クリック: 37回
- この商品を含むブログ (107件) を見る
●「第九章 それでもぼくたちはらくえんをめざす」
『らくえん』はたしかに努力の物語ではあり、ある種、成長の物語ではあるけれども、決して勝利の物語ではない。ここにはサクセスはないのだ。しかし、だからこそ、この物語は「結果」の呪縛から解放されている。「勝利」の重苦しさとは無縁である。
わが最愛のエロゲ『らくえん』を皮切りに、乙一、絲山秋子、滝本竜彦といった作家たちによる「ダメ人間小説」を見ていく章です。この章の読みどころは「ダメの可能性」を切り開いていくところ。「ダメ」には未だ未知の可能性がのこされていると無謀にも主張し、ダメ人間の採るべき生き方を探っていきます。そしてそれが第十章への接続となるのです。
●「第十章 花の勲章――『SWAN SONG』を解読する」
そう、ひととは風になびくかよわいひと茎の葦に過ぎぬ。吹きすさぶ風にそよぐ葦の何と頼りないことだろう。しかし時にゆれ、時に撓みながら、いまなお折れることなく葦は立ちつづけている。わたしはそのことを誇らしく思うのだ。
実質的な最終章であり、それまでのすべての「伏線」が集合して最大の盛り上がりを見せる章です。間違いなく本編のなかで最もテンションの高い章であり、そして最も感動的な章であります(自分で感動的というのもどうかと思いますが)。ここまで来るとほとんど評論の体裁をかなぐり捨てており、限りなく小説的/物語的なクライマックスといえます。いままでぼくが書いたなかで最高の文章です。この章を嫌う方は、ぼくのほかの文章も嫌うでしょう。
●「終章 たとえあなたがエヴァに乗らなくても」
秘密。
●「第十一章 暗黒の世界へようこそ」
おまけ。
■一問一答■
Q1 批評されている作品にかんするネタバレはありますか?
A1 『SWAN SONG』、『グイン・サーガ』、『猫物語(白)』の三作品にかんしては全面的にネタバレした章が存在します。ほかの作品には大きなネタバレはありません。ただし、『DEATH NOTE』や『SLAM DUNK』など、その展開が周知のものとなっていると思われるメジャーな作品にかんしては遠慮なくネタバレしている箇所があります。それはこのブログと同じです。
Q2 批評されている作品を知らなくても楽しめますか?
A2 主要な作品はすべてその場で紹介しているので、問題なく楽しめると思われます。ただし、小説/漫画/映画など、何らかの「物語」にかんして全く興味がない方には関係ない内容ではあるでしょう。まあ、そんなひとはこのブログを読んでいないでしょうが。「物語」を好まれる方なら、知識がなくても楽しめるはずだと思っています。
その他、知りたいことがありましたら、メールフォームからメールしてください。お答えいたします。
■サンプル■
本編第六章をサンプルとして公開します。
冠の話をしよう。ただひとつの冠の話を。それは黄金で出来ており、偉大な魔力を帯びている。否、どこぞの老いぼれた魔術師の作ではない。そのような下らぬ手品ではない。その冠に魔法を与えているのは、ただ人々の期待と忠誠のみ。それは王冠と呼ばれる冠なのだ。それを被るものは王と名指され、一国を統べる。
それでは、いまからわたしが知る幾人かの王について語ろう。それは限りなき信頼と重責を背負った帝王たちの物語、そしてかれを信じ、かれに仕えた者たちの物語である。どのような国であれ、一国に王はただ一人、至尊の玉座に坐すものは特別の人物でなければならぬ。故に王と王の物語を語ることは、特別な人間とは何か、それを語ることでもあろう。
このあとの第七章では国家に潰された一人の少女の悲劇を語ることになるが、本章に登場する人物たちはある意味で彼女と対照をなす。かれらは、自ら国家の重みを背負うことを選び、王土に暮らす万民のために生きている。かれらこそは気高き義務の奴隷、見しらぬ誰かのために生きる者である。
しかし――おお、忘れてはならない、王冠にはいつも一匹の蛇が巻き付いている。〈孤独〉という名の毒蛇。あるいは〈猜疑心〉と呼ばれることもある。この蛇の毒言に耳を貸したとき、王は暴君、狂王と呼ばれることになる。この章では幾人かの暴君のことも語ることになるであろう。王道を往く王、覇道を歩んだ王、さまざまな王が登場するが、あなたはだれが最も支配者にふさわしいとお考えだろうか。読み終えるまでにあなたなりの回答を出していただければ嬉しい。
さて――どこから語り始めたものか。そう、小野不由美『十二国記』がふさわしいだろう。『十二国記』はまさに王の物語である。小野は、田中芳樹『銀河英雄伝説』の解説で『十二国記』が『銀英伝』の主題を発展させた作品であることを示唆しているのだが、それはよくわかる。
ひとは死ぬ、王ですら、稀代の英君ですらも。そこで多くの王朝は血統主義を採るわけだが、それはいわば次善の策である。もし建国者が不死であれば後継者など必要ない。『十二国記』の世界では、この白痴の夢が現実となっている。王に選ばれたものが不老不死となるこの世界では、真に英邁な君主が立てば、理論上、その政権は永遠に続くのである。それでは、その世界ではいくつも理想政権が実現しているのだろうか。否。ひとは百年の齢ですら老い疲れる。いかに麗質に恵まれた王といえども、数百年の時のあいだには衰える。したがって、大半の王朝が百年の時を閲することなく倒れていくのだ。『十二国記』の世界では五百年の時を経た王朝はわずかに二つという設定である。
主人公陽子はこの世界で景麒と呼ばれる麒麟に選ばれ、景国の王となり、単なる高校生から一人前の帝王へと成長していく。この陽子の成長のプロセスが『十二国記』の読みどころだ。しかし、ここで気にかかるのが、先代景王の存在である。陽子の前には当然、いったん国を亡ぼした王が存在するのだが、作中では予王と呼ばれるこの人物が、わたしは妙に気にかかる。それはおそらく、第七章で語るケイロニア王妃シルヴィアが気にかかるのと同じ理由だろう。予王とは国家に圧殺された人物なのではないか、と思えるのである。
彼女はあるとき景麒に選ばれて王位に就くのだが、どうしても平凡な女性としての幸福をあきらめきれない。己が一天万乗の天子であることを理解できない。彼女はあらゆる手段を用いて平凡な日常に拘泥し、王としての責務を放棄する。そして予王はさいごには景麒に恋着し、かれの心を得るため国中から女性という女性を追い出して国を亡ぼす。畢竟、彼女は王冠に巣くった毒蛇の囁きに耳を貸してしまったということだろうか。予王はほとんど物語には登場していないのだが、その愚かさは景麒の口からくり返し語られる。
亡国の責を一身に背負っているかのような予王であるが、しかし、すべてが彼女の責任とはやはりいえまい。彼女は悪意でもって国を亡ぼしたわけではない。ただ、与えられた責務から逃避しつづけただけである。それこそが罪だ、ということはおそらく正しい。正しいのだが、しかし、その正しさにどれだけの意味があるだろう。王として選定された以上、私人としての幸福を投げ打ってでも公務に先進するべきだ、とはたしかにいえる。だが、その「べき」という言葉にわたしは意義を見いだせない。
ところで、『十二国記』においてわたしが最も好きな台詞は、実は陽子や予王のものではなく、かれらが収める景国の隣国の君主、延王のひと言である。シリーズ第三章『東の海神、西の滄海』において未だ即位から間もない延王尚隆は、ある部下に対し任務を与える。思わぬ厚遇に歓喜するその部下に対し、かれはこう続ける。
「礼は言わぬほうがいい。仮に州侯が叛旗を翻せば、まず間違いなく牧伯の身は危うい。州侯城へ行ってくれと言うは、万が一、事があったときには命を捨ててくれと言うに等しい。――だが、俺には手駒が少ない。死なせるにはあまりに惜しいが、お前の他に行ってもらう者がいない」
この台詞が好きでならない。あまりに惜しいが、お前しかいない。仕えるべき王からこの言葉をもらったなら、そのひと言のために死んでもかまわない、と本心からそう思う。というより、そのひと言でひとを死地に向かわせることができるのが真の王というものなのではないか。カリスマといえばいかにも軽いが、ひとがかれのため歓喜して死んでいく、それが王なのだと考える。
わたしがこの場面で連想したのは、司馬遼太郎『国盗り物語』である。『国盗り物語』のなかで、一世の傑物斎藤道三が、遂に亡び去り死んでゆくそのとき、長年仕えてきた部下に向かい、「お前は死ね」と命じる場面がある。お前は統治者ではなくじぶんの一配下なのだから、義を守って義のために死ね、といっているのだが、この言葉を耳にしたその部下は、喜び勇んで死んでいく。
この場面も好きだ。一見、道三は無情なことをいっているようだが、そうではない。じぶんといっしょに死ね、という命令は、受け取る側にとって無上の喜びとなりえることを承知の上でいっている。そういえば、永野護『ファイブスター物語』でも、それまで泥いくさに不平不満を漏らしていた兵士たちが、すべてが皇帝天照帝救出のための作戦だと聞いた途端に士気を取り戻し、己の命を捨てて奮戦するという場面があった。
さて、それでは、小野が影響を受けたという田中芳樹は王をどのように描いているのだろうか。田中の作品には幾人もの帝王が登場するが、最も印象的なのは二人、『銀英伝』のラインハルトと、『アルスラーン戦記』のアルスラーンだろう。
ラインハルトは貧乏貴族の身の上から立身し、新銀河帝国を建国して全宇宙を統べるにいたる英雄である。破格の野心と比類なき天才をあわせ持つかれはある意味で理想の王そのもの。人間に考えられるあらゆる能力を最高の値で与えられているといってもいい。しかし、ここではパルス国の王太子アルスラーンのほうに注目してみたい。
幼少から天才を発揮するラインハルトに対し、アルスラーンは一見ごく平凡な少年である。しかし、十四歳にして国難に遭い、その真価を発揮することになる。かれは亡国の際、ダリューン、ナルサス、ギーヴ、ファランギースといった人々に支えられて東方国境に逃れると、そこで一軍を形成し、遂に侵略軍を撃退するのだ。これは、アルスラーンの指揮が際立って優れていたから「ではない」。かれはラインハルトのような政戦両略の天才ではない。ごく無力な一少年に過ぎないのであり、個人としての力量は乏しい。国土回復戦争において力を発揮したのはダリューンを初めとするかれの部下たちであった。
しかし、それでもなお、侵略軍撃退の大功はアルスラーンのものである。なぜなら、アルスラーンなしには、パルスの軍が一つにまとまることはなかったからだ。アルスラーンは複数の、それぞれ異なる価値観を持つ人々を一つに統合する星なのだ。アルスラーンがいて初めて生まれも故郷も母国、母語すらも異なる人々が一つにまとまる。かれはある種のシンボルである。そしてシンボルであることを厭わないことがアルスラーンの才能なのだ。
そんなアルスラーンと好対照をなしているのがヒルメス王子である。かれはパルス王国の正当な王を自認し、策略を用いて王位を目指すのだが、さいごにはアルスラーンを前に敗北する。それでは、ヒルメスは無能なのか。そうではない。むしろ、かれもまた十分に優れた素質の持ち主といえる。しかし、アルスラーンと比較するとき、かれですらやはり見劣りする。
一個人としての能力を問うなら、ヒルメスはさまざまな面でアルスラーンを遥かに凌駕する。剣士としての腕前、大将軍としての采配、あるいは大人の男としての魅力。しかし、それは必ずしも王たるものに求められる資質ではない。君主に求められるもの、それはやはり、多様な個性を許容する度量なのである。アルスラーンを見ていると、王のために家臣がいるのではなく家臣のために王が必要なのだ、とわかる。
アルスラーンの能力とは、家臣の一人ひとりに、その個性に応じた「役割」を与えていくことだ。たとえば、皮肉で犀利な頭脳を持ち、亡国の瀬戸際にあってなお立ち上がろうとしないナルサスを、アルスラーンは「宮廷画家」という地位で勧誘する。ナルサスは趣味で絵を描くじぶんに対し、宰相でも副王でもなく、宮廷画家の地位を与えることにしたアルスラーンに清新なものを感じ、かれの配下となるのである。
なるほど、ナルサスはたしかに天才だ。しかし、かれのその天稟は、アルスラーンが適切な地位を与えて初めて輝きだす。アルスラーンがいて、ナルサスがいる。その順番こそ正しく、決してナルサスがいて初めてアルスラーンがいるわけではないのである。
アルスラーンの資質がいかに稀有なものか、それを物語るエピソードは枚挙にいとまがないが、ここでそれを列挙することはしない。考えてみるべきなのは、アルスラーンがなぜこうも人心を得ることができるのか、ということである。士は己を知る者のために死す、という金言がすべてを表しているかもしれない。ひとは、結局、じぶんを発見してもらいたいものなのだ。じぶんの資質を見出してほしいものなのである。アルスラーンは的確にそのひとの最高の才能を見極め、人事する。それがかれの最大の美質だろう。「ひとに必要とされていると感じさせる」能力、それがアルスラーンを不世出の大君主にしている。それに比べれば、ヒルメスの剣術も指揮能力も、はるかにありふれたものに過ぎない。
一方、田中のもうひとつの異世界歴史小説『マヴァール年代記』では、カルマーンとヴェンツェルという二人の若者がマヴァール帝国の帝冠を巡り死闘を繰り広げる。カルマーンは帝王の血筋に生まれながら父を弑逆し、そのために人格を歪めるのだが、より興味深いのは大貴族の身の上から帝位を狙うヴェンツェルのほうだろう。ヴェンツェルは帝国第二の大貴族の身の上で、その権勢は諸王の上に立つ。しかし、かれはそのすべてをチップにしてさらなる高みを目指すのである。
なぜそうまでしか帝冠を望むのか。単なる権勢欲のためではない。一代の梟雄として世界に覇を唱えんとする野心、という説明すらおそらく正確ではない。ヴェンツェルは、ただ純粋に王様になってみたいだけなのだ。痛々しいほど純粋な「少年の夢」がこの若者を駆り立てている。その夢はどこまでも汚れなく美しい。しかし、かれが見た夢のために広大なマヴァール帝国は崩壊し、かずしれぬ人々が地獄へ落ちていく。
その系統でいうと、『コードギアス』のルルーシュが思い出されるところだろう。「反逆のルルーシュ」というサブタイトルからもわかる通り、ルルーシュは物語全体の九割において単なる反逆者である。かれがブリタニア帝国の帝位に就くのは物語終盤のことだ。呪われた聖戦の果てに遂に父であるブリタニア皇帝を撃破したかれは、〈Cの世界〉と呼ばれる集合無意識の世界で真理を悟り、ブリタニアの帝冠を被ることを決意する。
むろん、この国の冠にも毒蛇は巻き付いている。ルルーシュは最愛の妹ナナリーを敵にまわすことになってしまうのである。そもそも、ルルーシュが反逆者ゼロとして蜂起したのはこの盲目の妹のためであった。しかし、運命の何たる皮肉か、ルルーシュはその実の妹とたたかわなければならぬ宿命を帯びていたのだ。かれは苦悩しつつも、なお、たたかいをやめようとはしない。やがてルルーシュはいかなる豪傑をも従える〈ギアス〉の絶対遵守の力をナナリーに向ける。世界をその手にするために。
そしてかれは遂に世界統一に成功する。世界中の人々がかれを独裁者と罵るが、その言葉はルルーシュには届かない。いまや、世界がかれの手中にある。血まみれのハッピーエンド。否、物語はここで終わらない。世界の敵と化したかれのまえに英雄ゼロが姿を現す。そう、すべてはルルーシュの策略だったのだ。世界のあらゆる憎悪と怨恨を己一身に集め、ゼロとなった盟友スザクによって討たれる。そのことによってすべての憎悪怨恨を散華させる。そこまでルルーシュは計算していたのだ。そしてスザクの剣はかれの胸を貫き、事ここに至ってようやく真相を悟ったナナリーは、かれの手を握りながら血まみれの独裁者へ向け叫ぶ。愛しています、と。かくして世界に平和の時代が訪れる。あらゆる憎悪はルルーシュが持ち去った。あとには協調と相互理解だけがのこされた。
しかし、はたしてルルーシュの策略は正しかったのだろうか。己を犠牲にし、世界すべてを騙したそのやり方はたしかにあまりにかれらしい。そしてまた世界の王にふさわしい生き様であり死に様であったといえるかもしれない。しかし、これでは大衆は相変わらず愚劣なままではないか。何一つ真実を知ることなく、恩人を悪漢と思い込んだままのかれらに成長があるだろうか。このままでは、いずれまた同じことがくり返されるだけなのではないか。ルルーシュは正しく王であった。世界のすべてを華奢な双肩に背負っていた。だが、そもそもただ一人世界を背負うことは正しいのか? 考えさせられる問題である。
少年漫画に目を向ければ大高忍『マギ』でも、王がひとつのテーマとなっている。しかし、『マギ』の場合、少々王冠が軽く見えることは否めない。アルスラーンが、ヴェンツェルが、ルルーシュが、あれほどまでの犠牲を払って手に入れようと望んだこの玩具が、それほどの価値を持っているように見えてこないのだ。むろん、すべての王冠が同じ重さを持っているわけではないであろう。あるいはメッキの王冠もあるかもしれぬ。しかし、メッキの王冠を巡る物語など、誰が見たいだろう。『マギ』の今後の展開に期待はしているが、物語がこのまま進んでいくようであれば、いささかの失望は禁じえない。
一方、メッキではない本物の王冠の重さを思い知らせる物語もある。たとえば、永野護『ファイブスター物語』のように。この物語では無数の王が登場するが、なかでも最も重い責任を背負っているのは、ジョーカー太陽星団最大の大国フィルモア帝国を統べるエラニユース・ダイ・グ・フィルモアだろう。ダイ・グは先帝からフィルモア帝国を譲り受けた直後、〈マジェスティック・スタンド〉と呼ばれる大戦争に参戦する。
初め、かれがこの大戦に参入した理由は、単なる領土欲に過ぎぬように見える。しかし実はより深い思惑が存在する。かれはこの〈魔導大戦〉の戦火を果てしなく拡大させ、その最中にその戦地へフィルモア帝国全体を移すつもりだったのだ。フィルモア帝国が存在する惑星カラミティは、既に星としての寿命が近づいており、いつ崩壊するかわからぬ状況にある。もしこのままカラミティ星が崩壊したならば、何十億という人々が死に、あるいは流民と化すであろう。この危機をまえに、ダイ・グはフィルモア皇帝として決断したのだ。どこまでも戦火を広げ、果てしない大戦争によってフィルモア国民を救済することを。それこそがダイ・グが皇帝として背負わねばならぬ責務なのだ。
むろん赦されることではない。かれのこの決断のために、何億という人々が地獄を見るだろう。老人や幼子までも含めた無数の命が散り果ててゆくことだろう。決して赦されることではない。もとよりダイ・グは赦されることなど求めてはおらぬ。かれは己が背負う罪の重さをしっている。それでもなお、かれに他の選択肢はないのだ。ダイ・グを未熟な帝王と呼ぶべきだろうか。しかし、ほかにどんな方策があるというのか。
ダイ・グが直面する状況は、『魔法先生ネギま!』でネギが出逢う試練と似ている。『ネギま!』でも魔法世界崩壊という問題が浮上している。しかし、『ネギま!』と異なり、ダイ・グには危機回避策は存在しない。『ファイブスター物語』の場合、カラミティ星が崩壊してしまうことがあらかじめ年表によって決まっているからである。
巨大な破滅をまえに、ダイ・グはどれほどのことができるだろうか。かれが何百年と長引かせようとした大戦はじっさいには数十年で集結を見るはずである。おそらく、ダイ・グの計画は失敗に終わることだろう。待ち受けるものは、さらなる悲劇以外の何物でもないのかもしれない。王冠の蛇はダイ・グを破滅へ導こうとしているのかもしれない。しかし、物語を眺める我々は、悪の皇帝と呼ばれる運命にすすり泣きながら、なお重い決断を下すダイ・グに共感せずにはいられない。『ネギま!』が英雄の物語であるとすれば、『ファイブスター物語』はあくまでも王の物語を描いているといえる。そしてわたしにはやはりダイ・グは真の王であるように思える。
ここまで語ってきて、ひとつ見えてきたことがある。野心のために王位を目指すものと運命的に王位に就いてしまうものという対比である。ルルーシュやヴェンツェルは前者、陽子やアルスラーン、それにダイ・グは後者であろう。前者を覇王、後者を聖王とでも呼べばわかりやすいかもしれない。
覇王と聖王、いずれが王位にふさわしいか。それは一概にいえることではないが、このような視点から物語を見ると見えてくるものがある。覇王の物語は一歩一歩、野望の階を登っていくところに魅力があり、聖王の物語は一気に王に「選ばれる」ところに魅力があるということだ。同じ王の物語といっても、両者はある意味、対照的である。
その意味では、『ベルセルク』のグリフィスは覇王にあたるであろう。グリフィスもまた、平凡な一庶民から王位を目指す孤高の男である。その野望は壮麗をきわめるが、しかしかれもまた乱世の梟雄というにはあたらない。かれが黄金の王冠を望むのは、少年の日決意した夢をそのままに望みつづけているに過ぎぬ。それはかずしれぬ少年が見る夢であろうが、その大半は過酷な現実をまえに夢を折る。しかし、グリフィスはどこまでも愚直にその夢を追いかけつづける。その意味でかれの心は未だ少年のままであり、だからこそかれは不可能を可能にできるのである。
とはいえ、ただ華麗と呼ぶにはかれの夢はあまりに血まみれだ。その玩具の王冠のため、かれはひたすら血と泥に塗れてゆく。グリフィスは己の夢のために〈鷹の団〉なる精鋭騎士団を築くが、その〈鷹の団〉はかれの仲間ではない。そのような対等の存在ではありえない。〈鷹の団〉とはかれの夢のために利用されるべき道具に過ぎぬ。しかし、無数の若者が自ら利用されようとそこに集まってくる。なぜか。かれらもまた夢を見ているからである。グリフィスが玉座への階を上るその日、その光景をこの目で見るという夢を。
一人ひとりの力ではとうてい見ることを許されぬ夢を、束ね、より力強くまとめるもの、それこそが王だとするなら、グリフィスにはまさに王者の風格がある。そしてたたかえばたたかうほどに、グリフィスを信じ集まるもの、戦場に骸を晒すものも増える。そのものいわぬ骸のためかれにできることは、何としても王冠をその手に掴むこと。そう、それぞれより小さな夢を抱いていたはずの若者たちがかれの壮麗な夢のために死したこと、それを悔やむことは許されぬ。ひとたび悔やめば己の夢と、そして己を信じた人々を裏切ることになる。そもそも、かれの起こした夢のかがり火は、ひとの夢を食らって成長していくものでしかありえないのだ。
しかし、あるときグリフィスは、盟友ガッツを喪失したことに耐えきれず、己の夢を破綻させる。王冠まであとわずかに数歩というところで、夢の階段から滑落するのだ。ただ一度の、しかし絶対的な失敗。英雄グリフィス卿の物語は、ここに終わったかに見えた。ところが、〈宿命〉の指先はなおもグリフィスを見放さない。すべてを失ったグリフィスは、ありえないことにかれの元に戻ってきた〈覇王の卵〉なる魔具を用い、魔王フェムトへと転生する。そのための生贄は生きのこった〈鷹の団〉全員の命。かれはかれを信じ、かれの夢を共に見たはずのかけがえのない同胞たちの命を魔物に食わせ、そして超越者へと生まれ変わる。
〈蝕〉。
グリフィスは〈鷹の団〉を裏切ったのだろうか。そうではあるまい。〈鷹の団〉の人々の目から見てそう見えるとしても、グリフィスから見ればそれは裏切りではない。かれは単に神聖な誓約を果たしたに過ぎぬ。いかなる犠牲を払ってでも王冠を掴むこと。それがかれの誓い。グリフィスにとって王冠とは下らぬ玩具に過ぎぬと先に書いた。しかし、その玩具こそがかれにとって唯一無二の価値なのだ。
血のように紅い落日が辺りを染め上げる夕べ、遊び疲れた子どもたちがそれぞれの家へ帰ってゆく。しかし、グリフィスに帰るべき家はない。かれは遥かに遠い玩具を手にするそのときまでひたすら遊び続けるしかない。やがて恐怖の夜が訪れる。それでも少年は玩具の王冠を探しつづけ、そしてその暗やみのなかで、かれはあらゆるものを振り捨てていくことだろう。誓約を結んだ若者たちはもちろん、ひとたびは友と呼んだ男すらも。それが、それこそが覇王の往くべき道なのだ。
覇王の道は常に紅く血に塗れている。その夢があざやかであればあるほど、壮麗をきわめればきわめるほど、その影で失われるものは大きい。そう考えると、王冠の意味するものはあまりに重い。いずれ、グリフィスはかつて求めたミッドランド国の王冠をその手に掴むことだろう。渇望の福王なる超次元の霊的存在と成り果てたいまなお、狂おしい夢のかがり火はかれの心を焼いているのだから。かれの統べる国は真の千年帝国となるかもしれぬ。そこに失われた夢はさらなる壮麗さで復活を遂げるのだ。しかし、その王冠はそのために捨てたものに見合うだろうか。かれの戴く王冠にもまた〈孤独〉なる蛇は巻き付いている。いまのグリフィスにとってどれほどの意味も持たぬとしても。〈千年帝国の鷹〉グリフィス王の物語はいままさに始まろうとしているところだ。はたして、その結末がいかなるところに落ち着くのか、遂に玩具の王冠を手にしてしまったグリフィスに、その先の夢は存在しうるのか、『ベルセルク』の今後は気にかかる。
さて――幾人かの王を語ってきたが、あなたのお好みの人物は登場しただろうか。メルニボネ帝国最後の皇帝エルリックや、『グイン・サーガ』の中原三国の王たち、あるいは『ロードス島戦記』の光の王ファーンと暗黒皇帝ベルド、『ヴィンランド・サガ』のクヌート王、『まおゆう』の魔王、『指輪物語』や『ナルニア』や無数の名作の王たちなどなど、他にも取り上げたい王は無数にあるが、比較的最近の作品に限って語ってみた。
賢王、愚王、英主、暴君、物語には枚挙にいとまのない王たちが登場するが、やはり王という言葉にはある種の蠱惑がある。そこには単なる最高権力者を超えた妖しい響きがあると思う。おそらくはそのために多くの英雄が王冠を目指し、乱世を巻き起こしたのであろう。そのなかには、よく孤高を保ち、王者の孤独を守りぬいたものもあれば、王冠に巣くう蛇の毒言に惑わされたものもあるだろうが、いずれにしろ、王は他の何者にも似ていない。
さいごに、王を描いた異色作として、『東のエデン』を挙げておこう。この作品について詳しくは先の第四章でも語ったが、ここでもかるくふれておきたい。
『東のエデン』の主人公滝沢明はジュイスと呼ばれる人工知能に「この国の王様にしてほしい」と願う。結局、かれは王にはなれないのだが、ある意味でかれもまた王への階を登った人物の一人といえなくもない。それでは、滝沢はグリフィスやヴェンツェルのように少年めいた野心から「王様」を目指したのだろうか。そうではない。かれは現代日本において、王という身分が見合わないことを知っていた。なぜならば、王となるものは大衆の生贄として生きなければならないからである。あまりにその報酬に不釣合いな身分。
しかし、いまや時代は王を必要としている。困難な時代をまえに、我々にはリーダーが必要なのだ。それは、独裁者の登場を待つ心理に過ぎないだろうか。アドルフ・ヒトラーの登場を促した、その心理が我々にも働いているのだろうか。しかし、いま、独裁者の登場を心配する必要は薄いのではないだろうか。なぜなら、人々が王を崇めるよりも蹴落とすことにより魅力を感じる時代なのだから。
不世出の王が黄金の冠を戴くとき、そこに罵声が浴びせられる。それが現代。しかし、それでもなお王冠と蛇の物語は描かれつづけるのである。




![けいおん! 1 (初回限定生産) [Blu-ray] けいおん! 1 (初回限定生産) [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51qvzEo9FYL._SL160_.jpg)
![らき☆すた 1 限定版 [DVD] らき☆すた 1 限定版 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41W2TY8iNsL._SL160_.jpg)


![東のエデン 第1巻 (初回限定生産版) [Blu-ray] 東のエデン 第1巻 (初回限定生産版) [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51sxmWsywlL._SL160_.jpg)