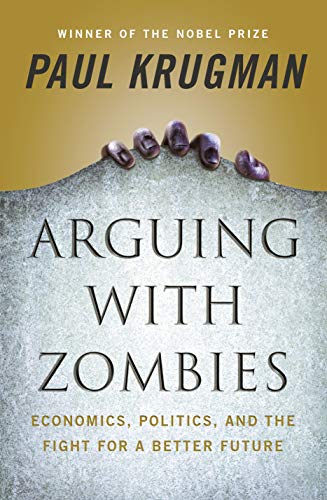数学セミナーの2025年3月号ではフィッシャーが特集されている.私は数学徒ではないし,もちろん数学セミナーを毎号購読しているわけではないが,フィッシャー特集と聞いて入手してみた.
フィッシャーは統計学において傑出した業績を上げているが,進化生物学にとっても重要な学者だ.まずダーウィンの自然淘汰とメンデルの遺伝法則を統合*1した「進化の現代的総合」の数理的基礎を作った3人組み(フィッシャー,ホールデン,ライト)の1人として有名であり,個別の議論としては一般的な頻度依存淘汰理論をはるかに先駆けて性比が1:1になることを頻度依存淘汰の数理モデルを用いて説明したこと,これも性淘汰が進化生物学に一般的に受け入れられるよりはるかに先駆けて,メスの選り好み型性淘汰のランナウェイモデルを提唱したことが思い浮かぶ.そしていろいろ学んでいくとフィッシャーの「自然淘汰の遺伝学的理論」が難攻不落の要塞のようにどーんとそびえ立っているようだということがわかってくるということになる.
さらに私にとってフィッシャーは(私の知的ヒーローである)ハミルトンが深く尊敬していた学者という意味でも軽々しく扱えない人物だ.ハミルトンのフィッシャーに寄せる思いは2000年に出版されたフィッシャーの「自然淘汰の遺伝学的理論」完全版の裏表紙に書かれた推薦文によく示されている.
数理生物学者フィッシャーが拓いた地平 辻和希
冒頭は行動生態学者辻和希による総説.
まずフィッシャーが扱った分野が広範にわたっていることが紹介され,特に数理化がマクロ生物学周りで始まったことについて集団思考(population thinking)が重要だったことが指摘される(特に個体群を認識するためには抽象化が必要だった).そこから本特集の全体像が紹介されている.
そして(本紙の依頼内容を当初「性比研究の統計学を使った実証を解説してほしい」というものと誤解して準備していたので,せっかく書いた原稿のうち本特集各寄稿と重ならない部分を残しておきたいということで)フィッシャーによる性比のデータ解析の解説がある.
- フィッシャーは多くの生物の性比が1:1であるのは頻度依存的な自然淘汰が働いた結果だと考え,理論的な枠組みを提示した.この理論が予測するのは母集団(population)の状態であり,統計学はサンプルから母集団の状態を探る方法論ということになる.
ここから実際の生物の性比を調べて検定を行う過程が説明される.具体例が面白い.
- 1:1性比から逸脱しているように見える生物としてオオガラゴがある.クラークはこれを局所資源競争から説明しようとした.
- 論文発表時点(1978)の世界の博物館の標本記録では,オスメスの標本数は16個体,10個体だった.クラークが得た野外で誕生して性別判定できたデータはオスメス13個体,4個体だった.クラークは帰無仮説を1:1性比(確率1:1で二項分布するモデル)とおき検定した.帰無仮説のもと17個体中でメスが4個体以下になる確率は0.02452,(オスが4個体以下になる場合も合わせた)両側検定でp値は0.04904となった.これによりクラークは帰無仮説を棄却し,局所資源競争により性比が偏っていると主張した.(このあと区間推定についても解説がある)
オオガラゴの局所資源競争の話は面白い.なおここではこの検定がフィッシャー流なのか,ネイマン-ピアソン流なのか明示していないが,帰無仮説のみを両側検定しているのでフィッシャー流の有意検定ということになるだろう.フィッシャー特集なのだから,このあたりも解説していれば面白かっただろう.
フィッシャー方程式 大槻久
まずフィッシャー方程式(フィッシャー - KPP方程式)が提示される.ただし tは時刻 xは位置 u(t,x)は個体群密度 r, Kは内的自然増加率と環境収容力,Dは拡散係数を表す.
∂∂tu(t,x)=ru(1−uK)+D∂2∂x2u(t,x)
そしてこの方程式は内的増加と環境収容を扱ったロジスティック方程式と移動分散を示す拡散方程式を統合したものであることが解説されている.
ロジスティック方程式
ddtu(t)=ru(t)(1−u(t)K)
拡散方程式
∂∂tu(t,x)=D∂2∂x2u(t,x)
このような統合の結果,対象が増殖しながら拡散していく状態が表現されることになる.ここでそもそもフィッシャーがこの方程式を導出したのは,個体群密度ではなく遺伝子が頻度を上げながら空間的に拡散していく様子を捉えたかったためであることが解説されている.
またこの方程式の性質として,環境収容力がありながら増殖すると分布の形状が変化せずに等速で広がっていく等速進行波解が現れることが説明されている*2.さらに等速進行波解の進行速度の下限,境界条件がある場合などの様々な拡張が可能であり,現在でもこの方程式の価値が色あせていないことなどが解説されている.
フィッシャーのランナウェイと配偶者選択の進化 巌佐庸
巌佐庸によるランナウェイ淘汰の解説.
性淘汰の学説史,性差の存在,メスの選り好み型性淘汰をどう説明するかという問題があることがまず前振り的に解説され,そこからフィッシャーの議論が説明される.巌佐はフィッシャーの議論は興味深かったが,当時多くの生物学者はそれに納得せず,これを説得力を持って示したのはランデによる数理モデルであると指摘し,それを解説する.
ランデのモデルはオスの装飾形質をx,メスの選り好み形質をy,遺伝相加分散をG,2つの性質の遺伝共分散をB,適応度をWとする,xについての淘汰勾配βは以下の形で表すことが出来る
β=∂∂xlogW(x)
ここでx, yの同時進化は以下の形で表される
(ΔˉxΔˉy)=12(GxBBGy)⋅(βxβy)
xを作るためのコストc(生存率がe^-2cx)などのいくつかの仮定をおき,これを解いていくと,と2つの形質の集団平均値は次の形に従う.
Δˉx=12Gx(aˉy−2cˉx)
Δˉy=12B(aˉy−2cˉx)
これはオスの装飾形質xはメスの好みにより大きくなり,コストによって抑えられ,以下の線で止まる.これがフィッシャーの議論のランデ的表現ということになる.
aˉy=2cˉx
巌佐は,これについて,フィッシャーの議論では息子が高い交尾成功率を持つことで母親の選好遺伝子が広がり配偶者選択が強まるということになるが,量的遺伝学的には直接淘汰を受けないyがオスのxとの間の遺伝相関によって間接的な淘汰を受けて増大していくものとして表現されると解説している.
ここからはフィッシャー以後の理論の進展が解説されている.
- 以上の議論ではメスの選好にコストがかからないことが仮定されていた.仮に選択にわずかでもコストがかかるとすると,まず両形質が大きくなる方向に進化しても,その後均衡解線上を原点に向かって進み,xは生存率最大の点(つまり装飾がなくなる点)まで縮小し,yはゼロ(メスの選好なし)が平衡となる(つまり装飾は進化しない).
- さらにランダムな突然変異が生ずるとして,その突然変異がオスの装飾が壊れる方向に偏っているとすると上記平衡点の手前で停止する(つまりごく小さな性淘汰形質は残りうる)
- また突然変異に偏りがない場合も,オスの装飾コストに非線形性がある場合などの特殊な状況では,装飾が消滅せずに振動したり,カオス系の挙動が生まれる可能性がある.
なお巌佐はフィッシャーのランナウェイモデルだけでなく,ハンディキャップモデルについても簡単に触れている.オスの元気の良さvを組み込んだx, y, vの3変数の量的遺伝学モデル(巌佐,ポミヤンコフスキー 1991)によれば,メスの好む性質(装飾)がxだけでなくvにも依存する場合にメスの配偶者選択性が進化する,そしてオスがvを反映させた装飾を作る理由を調べるとvの大きさがコスト負担力と相関する場合にそうなる(ポミヤンコフスキー,巌佐 1993)と説明している.
巌佐の説明はフィッシャーモデルについては見事なものだが,ハンディキャップモデルの説明には不満がある.巌佐が前段で説明しているのは自身とポミヤンコフスキーによる1991年の量的遺伝モデルの結論で,これはオスの装飾形質sが,xとvの両方に依存して定まるという条件で装飾が進化することが示されている.そしてこのモデルではメスの選好性がxにのみ依存する場合には装飾が進化しないことが示唆される.
この結論は,装飾を決める遺伝子が元気の良さを決める遺伝子と独立の場合{多くの場合そうであろう),装飾が騙しが不可能なインデックス的性質を持つか,メスの選好性が(直接観測できないはずの)vにも依存している(観測できるというのはある意味装飾形質がインデックスになっているという状況)必要があるように解釈されやすい(装飾の進化にはx,vの連鎖不平衡やインデックスを必要とするように解釈されやすい).しかし仮に騙しが有利になるなら,(連鎖不平衡でもインデックスでもない)元気の良さと独立に装飾を大きくする遺伝子がすぐに広まるだろう.だから真の問題はオスが正直になる方が進化的に有利なことを示すことにある(そもそもハンディキャップは正直な信号の進化の問題).だから,1991年のモデルでは問題を説明しきれていない.
そして1993年に(この論文については私は不勉強で理解不足だが),それだけではなく,オスが(騙しを行わず)装飾をvに依存して示す理由を説明したということになる.
だが,1990年の時点でアラン・グラフェンは遺伝子xがvの条件依存的に装飾の大きさx(v)を決め,メスがx(v)を観察して配偶者選択する数理モデルを発表している.そしてこのモデルでオスの正直な信号としての装飾とメスの装飾への選好が進化するのは,オスにとってメスに好まれることによる適応度上昇分と装飾にコストがかかることによる適応度減少分の比がオスの質が高いほど大きい場合であると示されている.つまり質の高いオスの方が広告効果/コストが高ければ(質が高いほどコスト負担力があれば),オスにとっても正直な広告を行う方が有利になり,正直な装飾形質が進化できるということになる.
そして多くの行動生態学者がハンディキャップモデルを受け入れたのは,そもそも正直な信号がなぜ進化するのかを見事に説明したグラフェンのモデルが1990年の時点で提示されたためだ.だから本稿においてもグラフェンモデルにも言及するのがフェアな態度ではないかと思う.
なぜか日本の数理生物学者は選り好み型性淘汰のハンディキャップモデルを説明する時にグラフェンモデルを無視する(本寄稿はその典型だが,粕谷・工藤編「交尾行動の新しい理解」,山内著「進化生態学入門」などもそうだ).これは全く理解に苦しむ態度だし,本当に残念だ.
フィッシャーの進化遺伝学 入谷亮介
フィッシャーの業績のうち,総合説確立において重要であった量的遺伝形質の進化遺伝学における平均効果の理論と繁殖価の理論を解説するもの.
<フィッシャーの平均効果>
アリルAの「平均効果」は「あるアリルAを持つ個体の形質値の集団平均値からの逸脱度」を表すもので,「集団中から無作為抽出された個体のアリルの1つ(Aである場合も含む)をAに置き換えた場合の個体の形質値の平均変化量」であること,ここから置換効果,適応度,平均過剰(注目アリルの適応度への増減効果)を示し,離散時間におけるアリル頻度の動態方程式を導出する.(q(t)は時刻tにおけるアリル頻度,EW|1は集団平均適応度,EW|1は少なくとも1つアリルA1を持つ個体の平均適応度)これは適応進化の普遍的表現であり,プライス方程式,レプリケータ方程式,適応動態理論,学習理論など幅広いモデルに出現する表式だと解説されている.
q1(t+1)−q1(t)=q1(t)(EW|1−Ew)
さらに以下のことが解説される.
- フィッシャーは遺伝子型,形質値を説明変数,適応度の応答変数とする線形回忌モデルによって,相加性と非相加性を分離した.
- さらに因果分析理論の基礎も築いた.アリルの置き換えによる適応度の置換効果は,反事実的にアリルを置き換えた処理(介入)の適応度の平均変化量(潜在結果)と考えることができ,適切な仮定のもとでの因果推論理論の平均因果効果と一致する.
- このような平均効果の因果推論への拡張は包括適応度理論にも意義深い洞察を与える.包括適応度理論は血縁度という個体間の類似指標を用いた回帰式で表されるので,それは因果ではない(相関に過ぎない)という批判を受けてきた.しかし包括適応度理論を集団などの複数の階層に適用し,平均効果を集団の平均形質値の平均変化量に対して拡張するとハミルトン則も因果関係として解釈できる.
<フィッシャーの繁殖価理論>
集団内に何らかのクラス構造(環境条件,年齢,など)があり,クラス間で適応度に差がある場合について適応動態を記述が可能かという問題を解決するのが繁殖価理論になる.
(フィッシャーは離散・連続の年齢クラスを検討しているが)ここでは離散クラスの場合について解説がある.生物の生活環の各ステージを個別クラスとすると,クラス集合(たとえば(卵,幼体,成体))と有向グラフ(たとえば(卵→幼体,幼体→成体,成体→卵))を考えることができ,クラスごとの個体数ベクトルが時間1単位でどう移り変わるかを示す次世代行列を求めることができる.そしてここから人口学の基本定理式が導かれることを示し,個体繁殖価,集団の平均効果,平均過剰がどう表されるかについて解説されている.
最後に現代から見たフィッシャーについてコメントされている.
- フィッシャーによる進化・遺伝・統計科学の厳密で有機的な体系化,その科学者としての全体像はもっと評価されてよいと思う.
- フィッシャーによる進化遺伝学の諸概念は,フィッシャーの優生学への傾倒と深く関連しているが,しかし得られた理論自体はあくまで生物の適応進化に対する概念だ.現在フィッシャーはその優生学思想から,賞や建物から名前が消されつつある.しかし優生学という「負」の遺産は,科学を受け継いだ科学者が責任を持って返済を続けていくべきで,単に覆い隠すのはその責任の放棄に思われる.
- フィッシャーはもう一つ「喫煙と肺ガンの因果関係」に対して真っ向から反論したことでも知られる.当時は相関のみが示されていて因果については明らかではなかったからだ.ただしフィッシャーには2つの利益相反があったこと(タバコ業界のキャンペーンに加担していた広告会社から小額の賃金対価を得ていたこと,フィッシャー自身愛煙家だったこと)も事実だ.
- 本稿執筆のためにフィッシャーについての様々な文献や動画に目を通した.それを通じてフィッシャーのような幅広い科学活動を目指したいという気持ちは強まるばかりであった.
フィッシャーの輝かしい業績だけでなく晩節を汚したとされる優生学への傾倒や喫煙と肺ガンの因果関係の否定まで扱ったうえで,その業績をたたえる寄稿であり,著者の思いがよく伝わってくる.
実はハミルトンも自伝のエッセイにおいて,マイルドな優生学的主張*3や喫煙の健康への悪影響への懐疑*4を表明していたりする.おそらくフィッシャーへの傾倒が影響しているのだろう.そして,科学者の価値観的政治的発言については,まず発言の正確な中身と発言当時の状況をよく踏まえるべきこと*5,仮にその上で問題があっても科学者の業績とその価値観については分離して評価すべきであろうとあらためて思う次第だ.
フィッシャーの原理と性比の進化 安倍淳
本稿のテーマはフィッシャーによる1:1性比の進化の議論.
現代における性比の進化の説明は,親による性比の調節行動の進化として進化ゲーム理論が適用される分野になるが,フィッシャーは進化ゲーム理論確立前に同様な議論を行っていたことを指摘してから,フィッシャーの議論が詳しく解説される(フィッシャーの用いた数理的な説明は補足にまとめられている).そしてこれは進化が集団全体や種の利益でなく個体利益最大化に向かって進むことが含意されていること,ここで1:1とされるのは子孫個体数ではなく,親の投資量であること,フィッシャー性比は配偶システムや出生後の死亡率により影響を受けないことが解説される.
続いてフィッシャー性比が成り立たない場合(フィッシャーの議論の仮定が満たされない場合)についての解説がある.フィッシャーの議論は集団中の個体は分散し,血縁個体同士が遭遇しないことが前提になっていること,そうでない場合として局所配偶競争や局所資源競争があることが解説される.また性転換する生物についての考え方も簡単に触れられている.
フィッシャーの自然選択の基本定理とその一般化 足立景亮
フィッシャーの自然淘汰の基本定理を導出してみせ,そこから基本定理とフィッシャー情報量との関係,基本定理の一般化,変化速度の速度限界不等式の導出,フィッシャーの基本定理は速度限界不等式の特殊な場合(自然淘汰のみを考慮した場合)であること,限界不等式を用いた分析の具体例などが解説されている.
この寄稿のテーマはなかなか興味深いものだが,本稿は本特集の中でもとりわけ数理的に難解なものになっており,私としては最初の定理の導出のところからついていけなかった.自らの不精進を恥じる次第だ.
以上が本特集の内容になる.数理生物学に興味のある人にはとても刺激的な特集だと思う.
補足 フィッシャーの自然淘汰の基本定理について
足立稿を理解できなかったこともあり,私なりにちょっと調べたことも覚え書きしておこう.
- まずこの基本定理はフィッシャーの「自然淘汰の遺伝学的理論」に記述があるが,そこでは数式は示されておらず,以下のような記述になっている.
- The rate of increase in fitness of any organism at any time is equal to its genetic variance in fitness at that time."
- ある生物(それがいかなる生物であっても)のある時点(それがいかなる時点であっても)の適応度の増加率はその時点の適応度の遺伝分散に等しい
- いかにもフィッシャーらしい簡潔で難解な言い回しだ.この記述は「だったら生物の適応度は常に上昇し続けることになるではないか,無意味だ」と当時の集団遺伝学者たちに誤解され,あまり真剣に取り上げられなかったらしい.
- 足立稿による数式は以下の通り(適応度をs,その平均をバー,標準偏差をΔsで表示)
ddtˉs=(Δs)2
- 足立稿の導出は難解で私の手には負えないが,これはプライス方程式から導出することができる(これはプライスによる1970年の論文で示されたもので,フィッシャーが以上の文言で本当は何を意味していたかが説明されている.ここではフランクによる解説をもとにする)
プライスの論文
https://www.zoology.ubc.ca/let/pdfs/Price_1972_FisherMadeClear.pdf
- プライス方程式は以下の通り(適応度がw,何らかの表現形質がz,平均がバー,重みづけ平均がE( ),分散がVar( ),共分散がCov( )で示される).*6
¯wΔ¯z=Cov(w,z)+E(wΔz)
- ここで何らかの形質zに適応度wそのものを代入すると以下の式になる
¯wΔ¯w=Var(w)+E(wΔw)
- すると適応度の変化(自然淘汰の速度)は¯wΔ¯wで示され,それは,適応度の分散とE(wΔw)で決まることになる.ここでE(wΔw)は環境によって生じた適応度の変化だと解釈することができ,遺伝要因にかかる自然淘汰の進化速度は適応度の分散で決まることになる.
- なおここで適応度が安定する平衡状態を考えると(フィッシャーはこれを念頭に置いていた),平衡条件はVar(w)=E(wΔw)=0となる.
- しかしこの時点での適応度分散は表現型としての適応度分散であり,フィッシャーのいう「遺伝分散」ではない.
- ここで適応度の遺伝要因をgとおき,プライス方程式に代入すると以下の式が得られる(βは偏回帰計数)
¯wΔ¯g=Cov(w,g)+E(wΔg)=βwgVar(g)+E(wΔg)
- 適応度wは遺伝要因gと残差δに分けることができ,δは適応度と回帰しないのでβwgは1となる.またVar(g)は適応度の遺伝分散となる.
- フィッシャーは各変数の平均効果の合計が一定の場合の適応度変化に興味を持っていた.gの平均効果の合計を一定にすればE(wΔg)=0となる.
- これにより
¯wΔ¯g=Cov(w,g)+E(wΔg)=βwgVar(g)+E(wΔg)=Var(g)
- 残る変化は適応度の遺伝分散Var(g)のみになる.ここで適応度の偏変化をΔfˉwとおくと以下の式が得られる*7.これがフィッシャーの基本定理の意味となる.
Δfˉw=Cov(w,g)/ˉw=Var(g)/ˉw
フランクの解説本
補足2 「自然淘汰の遺伝学的理論」
フィッシャーの代表的著書.後半は優生学がテーマになっているので,近時あまり取り上げられることはないが,非常に深い内容の書物であるようだ.これは2000年に出された完全版.
これはハミルトンによる裏表紙にある推薦文になる.
本書は,私が学生の時に,ケンブリッジ生活の残りすべてと同じ重さを持つ本だった.そして読めば読むほど自分の学問的水準の低さを教えてくれる本だった.ほとんどの章は1章を読むのに数週間を必要とし,中には数ヶ月必要なものもあった.例えばフィッシャーの「博愛」についての文章は当時読んでいたカフカの本よりも私を落ち込ませるものだったし,「文明」についての理論は私を熱狂させた.いくつかのトピックについては「恐怖」としか表現できないものであったし,今の私にとってもそうだ.それは私のそれまでの考えを深く変えるものだった.フィッシャーのアイデアと理論は,その後の分子的な発見によってもほとんど修正を受けず,広がり続ける道の基礎になり続けていて,その上でダーウィニズムは人の思想への侵入を続けている.
本書は,私の考えでは,進化理論にとってダーウィンの「種の起源」(と「由来」による補完)の次に重要であり,今世紀最高の本の1つである.そしてこの完全版の出版は意義ある出来事だ.フィッシャー後期の1958年のドーバー版による改変はむしろ理解に混乱をもたらしているところがあり,この完全版によっていくつかの謎は解決されるだろう.
1958年と異なり,今では自然淘汰は私達の知性的人生の一部となり,すべての生物学のコースに含まれるトピックになっている.とはいえ,私が人生を卒業するときまでに,私は本書に含まれる真実をすべて理解できるだろうか,そして優をもらえるだろうか? たぶんできないだろう.確かに私達のうちの幾人かはいくつかの点でフィッシャーを超えた,しかしながら多くの点でこの明晰で大胆な男は,なお私達のはるか先にいるのだ.
W. D. Hamilton