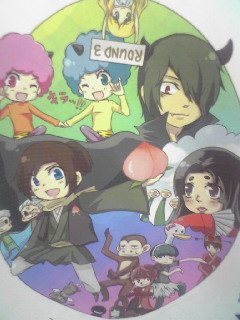
勤務先の学校で毎年恒例の文化祭、ようやく終わりました。
生徒が主体になって準備をする行事ですが、そこはそれ、私たち教師も陰になり日向になり支えるわけで……いや、疲れました。
うちの学校の文化祭は各クラスとも中国語の芝居を上演するのが伝統で、私が担任をしているクラスはコメディと「お涙頂戴モノ」の二本立てでした。昨年までの担任は、かつて中国の山村工作隊みたいな“単位”で演劇指導をしていたこともあるとか……という、いわばその道のプロみたいな方でしたから、毎年素晴らしい舞台作りを指導されていました。だもんで、後任の私は多少プレッシャーもあったのですが、まあ無事に終わってよかったです。
日本語を学んでいる中国人留学生は、日本語劇を上演していました。写真はそのポスター。留学生が描いたんだそうです。「いまふう」のアニメちっくなイラストですけど、上手ですよねえ。
ひと昔前までは、日本人学生のほうが得意だったんですよね、こういうタイプの絵は。「日本人はみんな絵が上手いねえ。子供の頃からマンガやアニメに親しんできてるからかな」と中国人講師に言われたものです。いまではもう彼我の差がなくなっていますね。
一方で、グーグルの図像検索あたりを使って、適当にいろいろな絵や写真を組み合わせて「ちょちょい」とポスターを作ってしまう生徒もいます。そういう技術に長けているのも「いまふう」です。
サイドウェイズ
本当に久方ぶりに映画館で映画を見ました。実はうちから五分ほどの所にシネコンがあるのです。が、行ったのは今日が初めて。
この映画は大好きな『サイドウェイ』の日本リメイク版。はっきり言ってかなり心配だったのですが、やっぱり立場上見ておかないと(ナニサマですか、と細君に一蹴されました)……と出かけました。
http://movies.foxjapan.com/sideways_jpn/
(ネタバレがあります)
う〜ん、やっぱりこうなってしまいましたか。名作の誉れ高いオリジナルに比べると、その「だしがら」ぶりには目も当てられません。
様々なエピソード、例えば試飲のカウンターでスピッティングボウル(試飲したワインを吐き出す桶)をがぶ飲みしようとするとか、「お遊び」の結果鼻に怪我したことをカムフラージュしようと車を樹にぶつけるとか……がどれも不発でした。置き忘れた財布を取りに戻った「遊び相手」宅で危機一髪というくだりはボンデージ・ファッション+SMを絡めてありましたけど、安手のお笑いバラエティ番組以下で場内には失笑が起きていました。
だいたい、俳優の演技がわざとらしすぎるんです。私が日本人だから日本語のセリフにリアリティを感じないのかもしれませんが、この映画は現地のアメリカ人俳優もなぜか生硬な演技をしています。
また、それ以前に主要キャスト四人の人物像に全然リアリティがありません。かなりイヤミで意地悪な言い方になりますが、「ワイナリーにつとめていてアメリカのワインの資格まで持っている」という設定の鈴木京香がワイングラスを拭くシーンだけで、「ああ、これは作り物だな」とばれちゃうんですよ。ワイン好きな人に、あんな拭き方をする人はいません(断言)。そういうところにこだわるとカッコいいし、奥行きが出ると思うんですけど。ワインに関してはプロの方々がアドバイザーとして入っているはずなのに、なぜ注意してあげなかったんでしょう。
さらに菊池凛子が演じた「生まれも育ちもアメリカ」のミナ・パーカーには無理がありすぎます。どう贔屓目に見ても、第二言語である日本語の拙いアメリカ人ではなく、母語である日本語が拙い日本人にしか見えません。
総じて、なぜ日本人俳優をつかって、ナパ・ヴァレーでリメイクしなければならかったのか、ちっとも理解できない作品になってしまっています。
ラスト近くで、小日向文世演じる主人公が語るセリフはけっこう心にしみ入るのですが、それだけではいかんともしがたいです。★☆☆☆☆
それは何?
勤務先の文化祭があって、今週は学校に行けませんでした。というわけで担任の先生に今週の学習範囲を聞いておいて自習。
数字
32から100までを覚えます。
40 quarante
50 cinquante
60 soixante
……ときて、69“soixante-neuf”までは規則的ですが、70は“soixante-dix”。60+10ということですか。ここから先は60に11から19までをくっつける形で進みます。
80は“quatre-vingts”。4×20です。「4つの20」だから、“vingt”のあとに“s”がついているんでしょうか。
81は“quatre-vingt-un”。“s”が消え、21“vingt et un”にはついていた“et”がありません。確かに81は4×21じゃありませんから、理屈には合ってます。以後、“quatre-vingt”に1から19をつける形で99まですすみ、100は“cent”。
二十進法的な考え方が残っているようで、ややこしいです。が、それなりの規則性がありますから、覚えちゃえばそれほどでもなさそうです。
それは何か
Qu'est-ce que c'est? ――C'est Musée du Louvre.
Où est-ce que c'est? ――C'est en France, à Paris.
一行目の問い、「ケスクセ?」と発音するだけなのにこの綴りの多さ(^^)。
二行目は“Où”だから、「どこにある?」ですが、答えにある“en France”が新しい学習事項です。
国名
“Je suis français.”や“Je parle français.”のような「フランス人」、「フランス語」のほかに、「フランス」という国名は“la France”。“la”という女性名詞用の定冠詞がつき、大文字です。洋ナシの「ラ・フランス」ですね。
「日本」は“le Japon”で男性名詞用の定冠詞“le”がついています。ソフトバンクのCMで「ル・ジャポン、フシギ」と言ってましたな。
なぜフランスは女性で日本は男性なのか分かりませんが、どうも“-e”で終わる国名は“la”がつく女性名詞、それ以外は“la”がつく男性名詞……のようです。
アメリカは“États-Unis”ですが、これは「合衆国」なので、複数用の“les”がつきます(男女共通)。
どこにあるか
で、この定冠詞が“在”をあらわす“à”と組み合わさると……
女性単数 à+la=en
男性単数 à+le=au
男女複数 à+les=aux
……になると。だから「それはフランスの、パリにあります」の場合、“C'est à la France à Paris.”が“C'est en France à Paris.”となるわけですね。ちなみに“Paris”のような都市名、地名には定冠詞がつかないので“à”のままです。
Qu'est-ce que c'est? ――C'est l'Arc de Triomphe.
Où est-ce que c'est? ――C'est en France, à Paris.
“la”や“le”は母音字などの前では“l'”になります。“arc(アーチ、門)”は辞書によれば男性名詞ですから“le arc”が“l'arc”(ラルク・アン・シエルの「ラルク」ですね)のになったわけですけど、省略されちゃうと女性名詞だか男性名詞だかはわからなくなります。
Qu'est-ce que c'est? ――C'est le mont Fuji.
Où est-ce que c'est? ――C'est au Japon, à Shizuoka.
Qu'est-ce que c'est? ――C'est la statue de la Liberté.
Où est-ce que c'est? ――C'est aux États-Unis, à New York.
知っている?
Vous connaissez Jackie Chan? ――Non, je ne connais pas. Qui est-ce?
C'est un acteur chinois.
ジャッキー・チャンは男性だから、“un acteur”です。女性なら“une actrice”。
“connaître”は「知っている」とか「面識がある」などという意味で、“认识”ですね。これは不規則に活用する第三グループの動詞です。
私 Je connais Jackie Chan.
あなた Tu connais Jackie Chan.
彼/彼女 Il/Elle connaît Jackie Chan.
私たち Nous connaissons Jackie Chan.
あなたたち Vous connaissez Jackie Chan.
彼ら/彼女ら Ils/Elles connaissent Jackie Chan.
ところで、「彼は俳優です」というのは“Il est acteur.”で冠詞がついていませんでしたが、“C'est un acteur.”の場合には冠詞がつくんですね。なぜだろう?