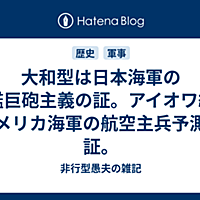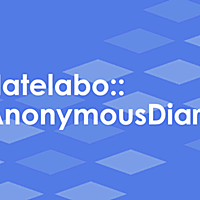アイオワ級
アメリカが建造した最後の戦艦にして、もっとも近年まで現役として稼動していた戦艦。
1938年、軍縮条約エスカレーター条項発動に伴う高速戦艦計画案が発端。
その後、条約制限いっぱいの基準排水量45,000トン、主砲16インチ3基、対16インチ砲防御、33ノットの高速戦艦としてとして計画されたものがアイオワ級である。
主砲口は日本海軍が条約明け後に建造していた新戦艦を想定して*1定められている。
しかし、アイオワ級最大の特徴でもある速度性能に関しては欧州各国の新型戦艦*2だけでなく、対日渡洋作戦にとって大きな障害となる金剛型戦艦を多分に意識していた節がある。
というのも、33ノットの発揮が可能な巡洋戦艦レキシントン級6隻はワシントン条約により完成させることが出来ず、当時の米海軍の保有する戦艦は21ノットの低速戦艦に過ぎず*3、金剛型4隻がその機動力を生かして渡洋作戦の妨害を行なった場合、それに対処できる高速戦艦を保有していなかった為である。
配置や防御能力に関しては、サウスダコタ級を踏襲しているが、高速発揮に伴う機関部の増大・主砲位置の変更は、パナマ運河通過制限のための細い艦幅と相俟って縦強度及び安定性の不足が指摘されている。又、同じ理由により、特に第一主砲塔に対する側面・水中防御力の欠如も挙げられる。アイオワ級は一般に大和型戦艦とよく比較されるが、防御面の不安に関しては大和型とまったく同様に、非バイタル・パート部分の防御力不足と予備浮力欠如が挙げられ、より以上に問題であると言える。
その外、計画時の乗員数1,900名に比べ、戦時中の乗員2,800名以上という大幅な増加により、居住スペースに不足していた。
1943年2月22日以降順次就役したアイオワ級は、高速性能を生かし、機動部隊に随伴できる戦艦として十二分に活躍、第二次大戦及び大東亜戦争を戦い抜いた。
戦後間もなくミズーリ以外の3隻が予備役に指定されたが、朝鮮戦争におけるミズーリの陸上砲撃を契機に全艦が順次現役復帰した。挑戦戦争終結に伴い今度は全艦が予備役に編入されたが、ベトナム戦争における火力支援の為にニュージャージーが現役復帰、ベトナム戦争終結後に予備役に編入された。
1980年代、レーガン大統領の米海軍600隻艦隊構想に基づき、今度は4隻全てが電子兵装近代化・SSM・SLCM搭載などの改装を施されて現役復帰、1983年のニカラグア封鎖作戦に参加したほか、同年のレバノン紛争、1991年の湾岸戦争では艦砲射撃を行なっている。
しかし、国際緊張緩和に伴う国防費策源により、1990年にアイオワが予備役に編入されたことを皮切りに、翌年にはニュージャージー・ウィスコンシンが退役、1992年にミズーリが退役した。各艦共にモスボール状態で保存されていたが、1995年1月12日、ついに除籍された。
アイオワ要目(新造時)
- 基準排水量:45,000トン
- 満載排水量:56,270トン
- 全長:270.4メートル
- 水線長:262.1メートル
- 水線幅:33.0メートル
- 最大幅:33.0メートル
- 浮心:0.593
- 軸馬力(PS):212,000馬力
- 主機:ジェネラル・エレクトリック・オール・ギヤード蒸気タービン4基*4
- 軸数:4軸
- 主罐:パブコック&ウィルコックス罐8基
- 蒸気性状:42kgf/cm²・454.4℃
- 発電機
- ターボ発電機:1,250kw8基
- ディーゼル発電機:250kw2基
- 速力:32.5ノット
- 航続距離:15,000海里/15ノット
- 燃料搭載量:8,983トン
- 乗員
- 士官:117名
- 下士官兵:1,804名
- 武装
- 主砲:55口径16インチ3連装砲塔:3基
- 副砲/高角砲:38口径5インチ連装両用砲:10基
- 機銃
- ボフォース40ミリ4連装機銃:15基(後に増加)
- エリコン20ミリ単装機銃:52基(後に増加)
- カタパルト:2基
- 飛行機:偵察機2〜3機
- 同型艦