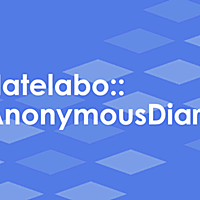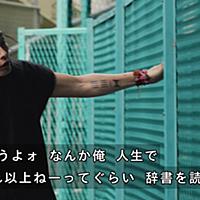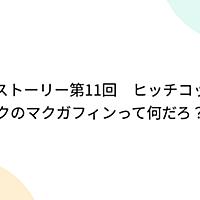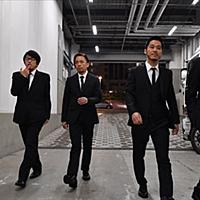マクガフィン
- 作劇において、登場人物の動機づけやストーリー展開を左右する重要な小道具でありながら、最後までその正体が不明な物のこと。
- 提唱者のアルフレッド・ヒッチコックは、あくまでも物語を動かす口実に過ぎないのだから、そこに具体的な意味をもたせる必要はない、としている。
作例
- 「バルカン超特急」の暗号
- 「汚名」のウラニウム
- 「RONIN」のトランク
- 「パルプ・フィクション」のトランク
- 「M:I:III」のラビットフット
参考
T <マクガフィン>という暗号は単にプロットのためのきっかけというか口実にすぎないのではありませんか。
H そう、たしかに<マクガフィン>はひとつの<手>だ。仕掛けだ。しかし、これにはおもしろい由来がある。きみも知ってのとおり、ラディヤード・キプリングという小説家はインドやアフガニスタンの国境で原地人とたたかうイギリスの軍人の話ばかり書いていた。この種の冒険小説では、いつもきまってスパイが砦の地図を盗むことが話のポイントになる。この砦の地図を盗むことを<マクガフィン>と言ったんだよ。つまり、冒険小説や活劇の用語で、密書とか重要書類を盗みだすことを言うんだ。それ以上の意味はない。だから、ヘンに理屈っぽいやつが<マクガフィン>の内容や真相を解明しようとしたところで、なにもありはしないんだよ。わたし自身はいつもこう考えている──砦の地図とか密書とか書類は物語の人物たちにはたしかに命と同じように貴重なものにちがいない。しかし、ストーリーの語り手としてのわたし個人にとってはなんの意味もないものだ、とね。
ところで、この<マクガフィン>という言葉そのものの由来は何なのか。たぶんスコットランド人の名前から来ているんじゃないかと思う。こんなコントがあるんだよ。ふたりの男が汽車のなかでこんな対話をかわした。「棚のうえの荷物はなんだね」とひとりがきくと、もうひとりが答えるには、「ああ、あれか、あれはマクガフィンさ」。「マクガフィンだって? そりゃ、なんだね」「高地地方でライオンをつかまえる道具だよ」「ライオンだって? 高地地方にはライオンなんていないぞ」。すると、相手は、「そうか、それじゃ、あれはマクガフィンじゃないな!」と言ったというんだよ。
この小話は<マクガフィン>というのはじつはなんでもないということを言っているわけなんだ。『ヒッチコック/トリュフォー映画術』(蓮實重彦・山田宏一訳)より引用
その他
- 本来の概念とは異なる使い方であるが、スラヴォイ・ジジェクは、イラク戦争においてアメリカ等が大量破壊兵器の存在を捏造した件を、こう呼んで揶揄している。ジジェク著『イラク』の「イラクのマクガフィン」の章を参照。