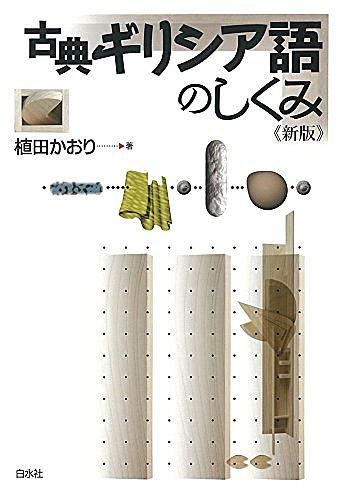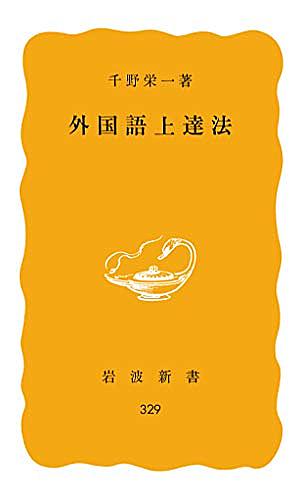古典語
一般的に言えば、「古典」を記すために使われている言語が「古典語」ということになるだろう。したがって、それは何を「古典」と位置づけるかによって変わってくる。
とりあえずは、「近代ヨーロッパの知識社会にとっての古典」を記している言語として、古典ギリシア語とラテン語を指すとするのが伝統的な使いかただろう。その「近代ヨーロッパの知識社会」から、自然科学・社会科学・哲学・文学などの現在の学問が派生していったのだから。
近代ヨーロッパの知識人の一部は、中世には圧倒的な影響を持ったキリスト教の世界観を相対化するために、キリスト教より前の古典ギリシア語・ラテン語で書かれた文章(戯曲なども含む)に着目した。また、アリストテレスの諸学やストア哲学の一部の著作のように、キリスト教の世界観を支持するための学問としてキリスト教の体系に組みこまれていたものを、独自の価値を持つものとして読み直そうとした。このようななかで、キリスト教が広まる以前の地中海世界が近代ヨーロッパの起源として位置づけられ、この時代に書かれた文章が「古典」として尊重されることになった。
そのため、近代ヨーロッパの学問にとっては古典語とは主として古典ギリシア語とラテン語を指すことになった。長らく「教会式発音」で読まれてきたラテン語を、なるべく紀元前一世紀、キケロー(キケロ)やカエサルの時代の読みかたで読もうという「古典式発音」の復活もこの時期にさかんに行われた。
ただし、新約聖書はもともと古典ギリシア語(コイネー)で書かれているし、カトリック圏では聖書はラテン語で読まれるのが標準だったのだから(20世紀の第二バチカン公会議までカトリックの典礼言語はラテン語と定められていた)、近代ヨーロッパの知識社会が尊重した言語だからといって、キリスト教のもとでは使われなかった言語というわけではない。むしろキリスト教が伝えてきた言語が「古典語」となったのである。ただ、それを、教会と教会人の手から、そうではない知識人の世界に「解き放った」ところに、「古典語」が成立したのである。
近代ヨーロッパ社会では、この「古典語」の教養に通じることが「中流以上の階級」に属することの条件とされた。そのため、近代ヨーロッパの学校教育では、これらの古典語の教育、とくにラテン語の教育には力が注がれた。19世紀にもなると「古典教育が何の役に立つのだろう?」という(日本の高校生が古文・漢文の授業で感じるような)疑問も広がっていたが、それでも階級社会を支える一つの「制度」として古典語教育は続けられたのである。
なお、ギリシア語については、ここで注目されたのはあくまで「古典のギリシア語」であるから、「同時代のギリシア語」(現代ギリシア語)にはその関心は及んでいない。
もちろん、古典ギリシア語・ラテン語だけを古典語と呼び、それ以外を古典語と呼んではならないということはないのであって(そういう立場もあるだろうが)、最初に書いたように何を「古典」と位置づけるかによって、何が「古典語」かは変わってくる。何を「古典」とするかによって、たとえば古代漢語、サンスクリット語、アヴェスタ語、古代〜中世の日本語……なども「古典語」と位置づけることができるだろう。