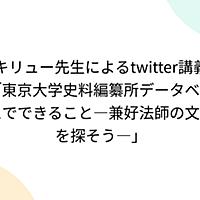史料編纂所
(一般)
【しりょうへんさんじょ】
東京大学の附置研究所の一。
史料編纂所は、「日本に関する史料及びその編纂の研究、並びに研究成果による史料集出版を行うことを目的とする」(「東大規則」第73号「東京大学史料編纂所規則」)東京大学の附置研究所です。 明治以来の史料蒐集並びに研究の蓄積を背景に、現在では日本史の研究の最大の拠点の 一つであると同時に、国内外の研究者その他に対する所蔵史料の公開、史料集の出版、 そしてデータベースの構築・公開を通じて、歴史学の発展や一般への知識の普及に大きな 役割を果たしています*1。