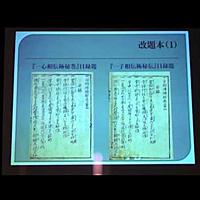川平敏文
(読書)
【かわひらとしふみ】
国文学者、九州大学准教授。1969年10月24日福岡県生まれ。1999年九州大学大学院博士後期課程修了、「近世徒然草注釈史論考」で九大文学博士。1998年柿衞賞、2000年日本古典文学会賞受賞。熊本県立大学文学部助教授、2007年准教授。2014年九州大学文学研究科准教授。専攻、日本近世文学・思想史。
著書
- 『兼好法師の虚像 偽伝の近世史』平凡社選書 2006
- 『徒然草の十七世紀 近世文芸思潮の形成』岩波書店、2015
編注
- 『近世兼好伝集成』編注 平凡社 東洋文庫 2003