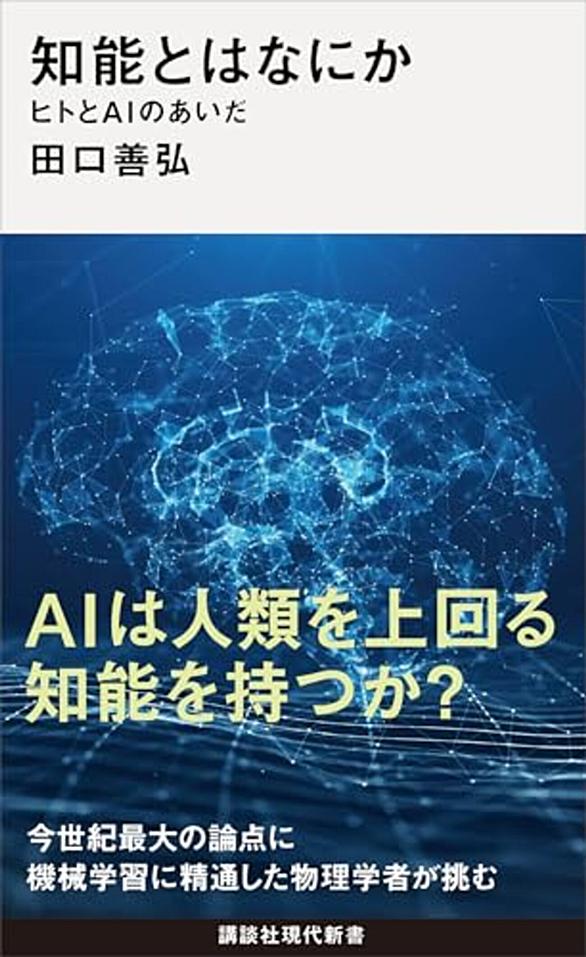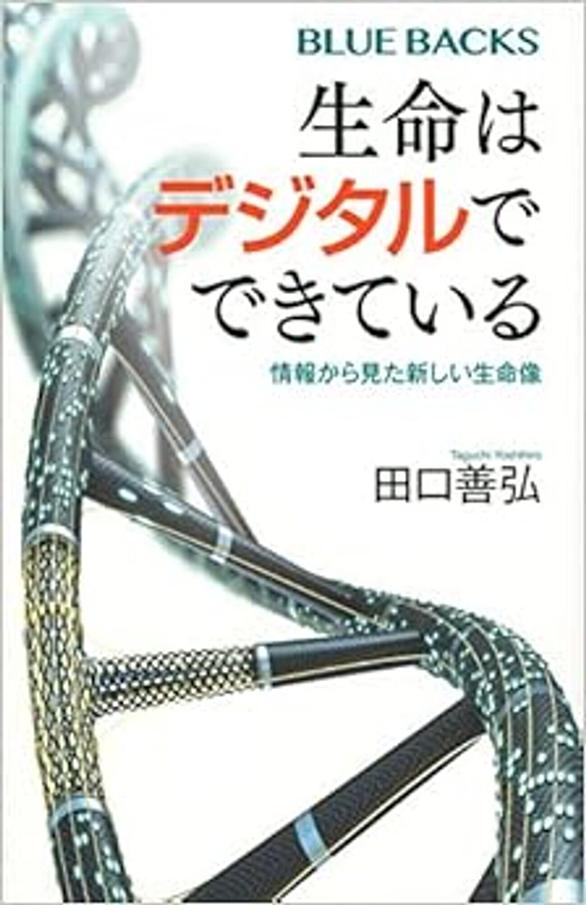田口善弘
(サイエンス)
【たぐちよしひろ】
物理学者、中央大学教授。1961年6月21日東京都生まれ。1984年東京工業大学応用物理学科卒、1988年東京工業大学大学院理工学研究科物理学専攻博士後期課程修了、「規則格子,不規則格子およびフラクタル格子上の相転移」で理学博士。同年、東京工業大学理学部物理学科助手。1997年中央大学理工学部物理学科助教授、2006年教授。96年『砂時計の七不思議』で講談社出版文化賞受賞。専門はバイオインフォマティクス。
著書
- 『砂時計の七不思議 粉粒体の動力学』1995 (中公新書)
- 『高校で教わりたかった物理』日本評論社 2009 (シリーズ大人のための科学)
共著
- 『複雑性のキーワード』三井秀樹, 高木英行共著 共立出版 2000 (インターネット時代の数学シリーズ