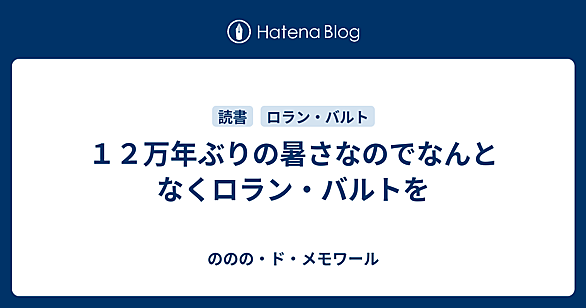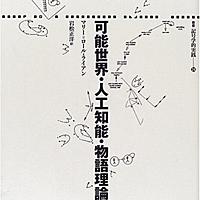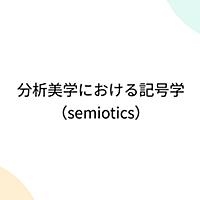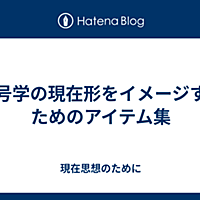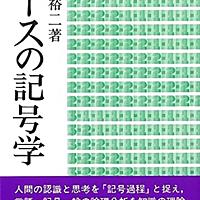記号学
試験の設問に出てくるような「イ、ロ、ハ、ニ の中から、最も適切なものを選び、記号で答えなさい」の「記号」のように一般的に使われている「記号」の意味は、記号学で言う「記号」の意味のほんの一部である。記号学は、人間をとりまくあらゆる意味のある事物としての記号を扱う。
現代の記号学/記号論の系譜には創始者とされる二人の人物がいる。一人はスイスの言語学者F.de.ソシュール(1857-1913)。ソシュールは特に言語記号の体系を研究した。もう一人はアメリカの哲学者C.S.パース(1839-1914)である。彼らは、ほぼ同時期に別々に記号学を提唱した。ソシュールが提唱したのは「記号学」と訳されることの多いSemiology、パースが提唱したのが「記号論」と訳されることの多いSemiotics/Semiotic/Semeotic。現在では「記号学」「記号論」共に、semioticsが一般的である。
-
- -
Saussure uses the term semiology as opposed to semiotics. The former word will become associated with ther European school of sign study, while ther latter will be primarily associated with American theorists. Later, "semiotics" will be used as the general designation for the anylsis of sign systems.
(Introducing Semiotics, Paul Cobley, Richard Appignanesi,2001, Natl Book Network)
-
- -
パースの三分法
http://genesis.hss.iwate-u.ac.jp/ntgoto/Cou/Doc/H13_SC/SCI_no7.html
性質記号 (qualisign)、単一記号 (sinsign)、法則記号 (legisign)
類似記号 (icon)、指標記号 (index)、象徴記号 (symbol)
名辞的記号 (rheme)、命題的記号 (dicisign or dicent sign)、論証 (argument)
ソシュールの二分法
http://genesis.hss.iwate-u.ac.jp/ntgoto/Cou/Doc/H13_SC/SCI_no6.html
シニフィエ:シニフィアン
言語の二重分節性