法政大学の佐野嘉秀先生から、池田心豪先生・松永伸太朗先生とのご共著『人的資源管理-事例とデータで学ぶ人事制度』をご恵投いただきました。ありがとうございます。
人的資源管理の総論2章、各論12章から成る本で、各章ともまず最初に「〇〇とは何か」の項がおかれ、解説に続いて副題のとおり「事例で理解する」「データで確認する」の項がおかれていて、たいへん理解の進みやすい構成になっています(おおむね佐野先生が解説、松永先生が事例、池田先生がデータという受け持ちになっています)。各章とも20ページ前後があてられているので読書会の輪読などにも使いやすそうですし、学部生や初任人事担当者のテキストとしてたいへん有効な本といえそうです。特に人事担当者にとっては、人事制度の企画立案や改定にあたって、事例を参考に、データを踏まえて仕事を進めるというスタイルを知るという面でも有意義な本といえそうです。内容的には、教育訓練の章で知的熟練論の解説に続いて、事例として梅崎修先生が提唱された「工程設計力」が紹介されているのがなんといっても目を引くところで、思わず「おっ」と声がでました。あとはいつもの慨嘆になりますが集団的労使関係への言及が少ないなあという思いは禁じえず、それでも総論部分の労使コミュニケーションに関する節で4ページほどの解説がある(データの項でも言及あり)のは、今日としてはむしろ配慮が行き届いていると受け止めるべきなのかもしれません。

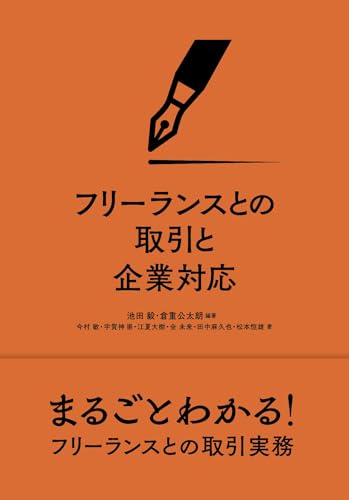
![2024年労働政策研究会議報告 2025年 01 月号 [雑誌]: 日本労働研究雑誌 増刊 2024年労働政策研究会議報告 2025年 01 月号 [雑誌]: 日本労働研究雑誌 増刊](https://m.media-amazon.com/images/I/51n4yChwEGL._SL500_.jpg)
![ビジネスガイド 2025年 03月号 [雑誌] ビジネスガイド 2025年 03月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51d9atb0RxL._SL500_.jpg)
![日本労働研究雑誌 2025年 01 月号 [雑誌] 日本労働研究雑誌 2025年 01 月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61VUkmQiVlL._SL500_.jpg)
![ビジネスガイド 2025年 02月号 [雑誌] ビジネスガイド 2025年 02月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51ybfTaS1NL._SL500_.jpg)