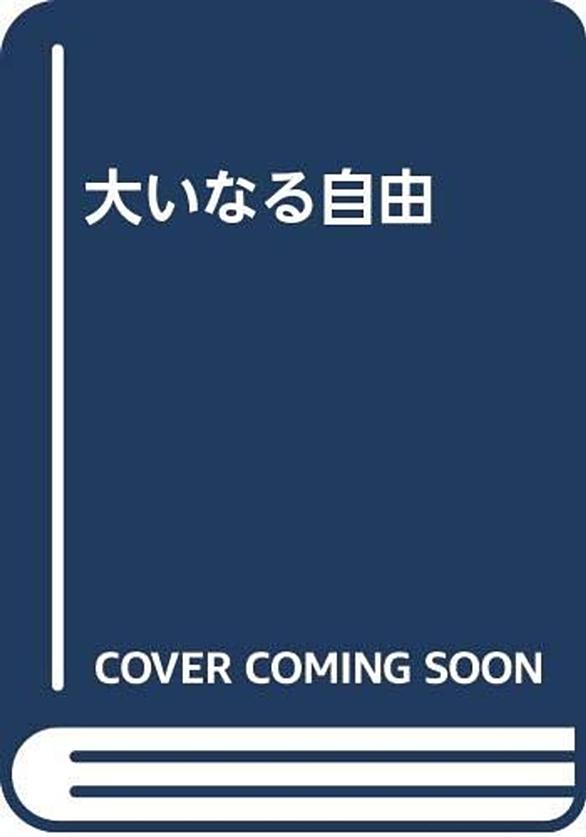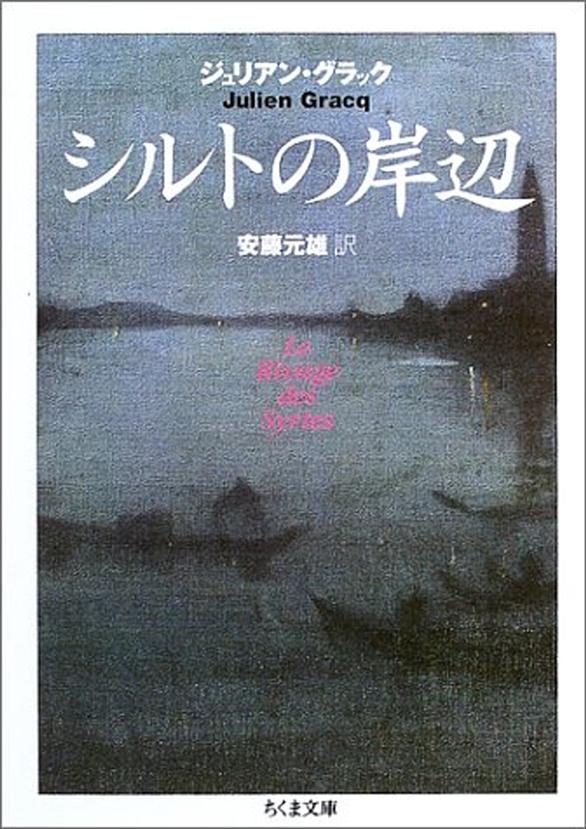ジュリアン・グラック
(読書)
【じゅりあんぐらっく】
Julien Gracq 1910-2007
フランスの小説家。本名ルイ・ポワリエ。青年期にアンドレ・ブルトンをはじめとするシュルレアリストたちと親交を結ぶ。戦後はパリの高校などで地歴の教師として勤務するかたわら創作活動を行う。
1951年『シルトの岸辺』に対しゴンクール賞を与えられるが、受賞を拒否する。以後も文壇と隔絶して過ごす。
主な作品
- 『アルゴールの城にて』1938 ISBN:4560070792 安藤元雄訳
- 『陰鬱な美青年』1945 小佐井伸二訳
- 『大いなる自由』1946 ISBN:4783728046 天沢退二郎訳
- 『漁夫王』1948
- 『アンドレ・ブルトン 作家の諸相』1948 ISBN:4409140469 永井敦子訳
- 『シルトの岸辺』1951 ISBN:4480038779 安藤元雄訳
- 『異国の女にささげる散文』1952 ISBN:4783728461 天沢退二郎訳(日仏対訳版)
- 『森のバルコニー』1958 中島昭和訳(『狭い水路』併収)
- 『偏愛の文学』1961 中島昭和訳
- 『花文字』1967
- 『半島』1970 中島昭和・中島公子訳(『街道』『コフェチュア王』併収)
- 『花文字II』1974
- 『読みながら書きながら』1980
- 『ひとつの町のかたち』1985 ISBN:4902854015 永井敦子訳
- 『七つの丘のまわりで』1988
- 『街道日誌』1992
- 『対談集』2002