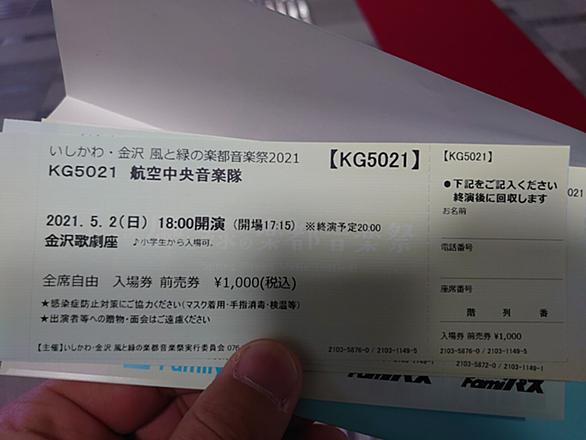岡本潤
(読書)
【おかもとじゅん】
アナキスト詩人 明治34(1901)〜昭和53(1978)
明治34年埼玉県児玉郡本庄町に生まれた。本名保太郎。大正9年京都の平安中学校を卒業後上京し、同10年東洋大学専門学部文化学科に入学したが中退した。クロポトキン、大杉栄らの著作を通じてアナキズムの思想に近づき、日本社会主義同盟の結成に参加。大正12年萩原恭次郎・壺井繁冶らと『赤と黒』を創刊、既成詩壇に反逆するアナキスト詩人としての立場を鮮明にした。
主な詩集に『夜から朝へ』(昭3)・『罰当りは生きてゐる』(昭8)などがある。