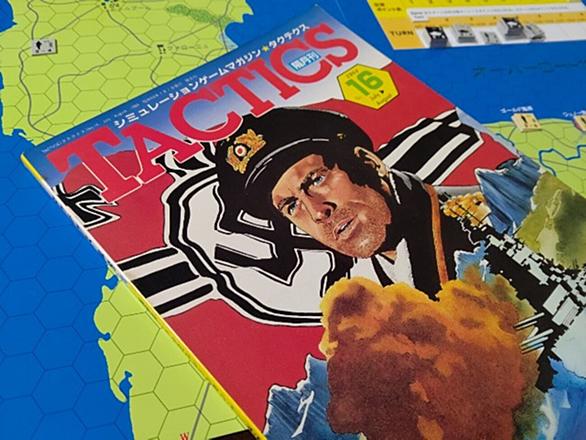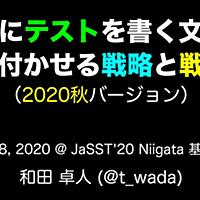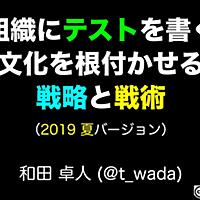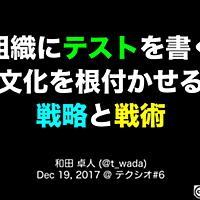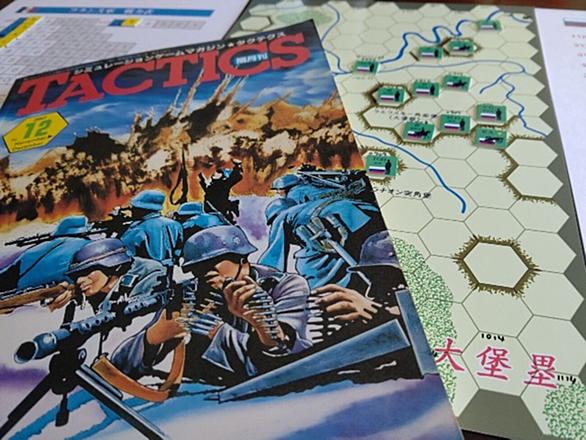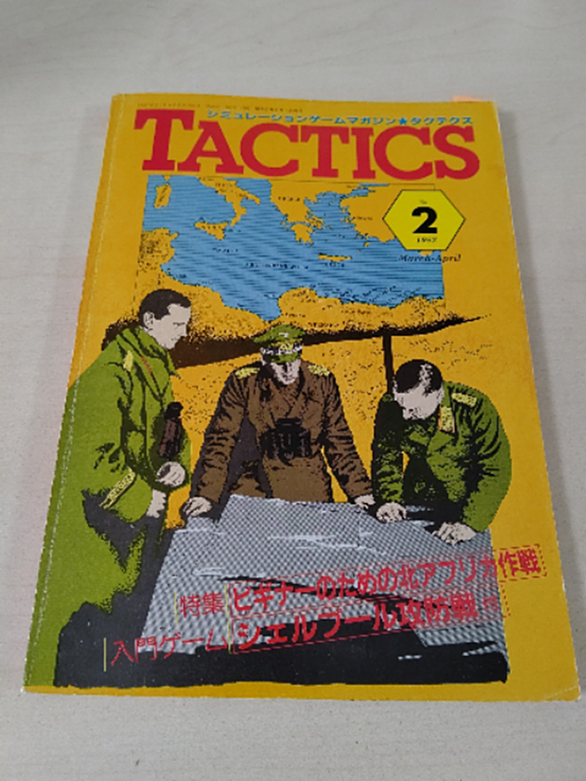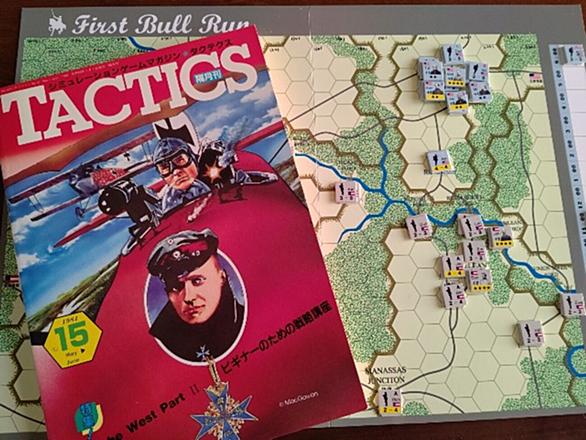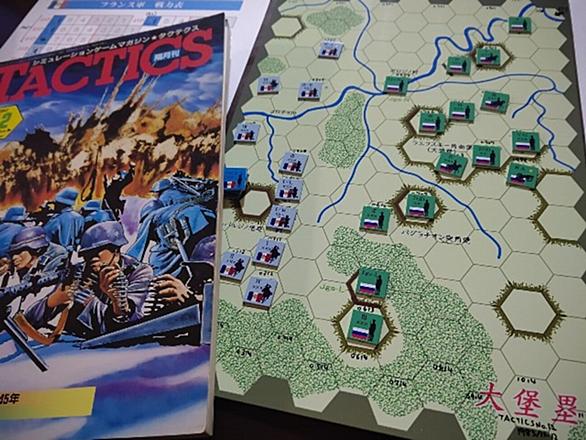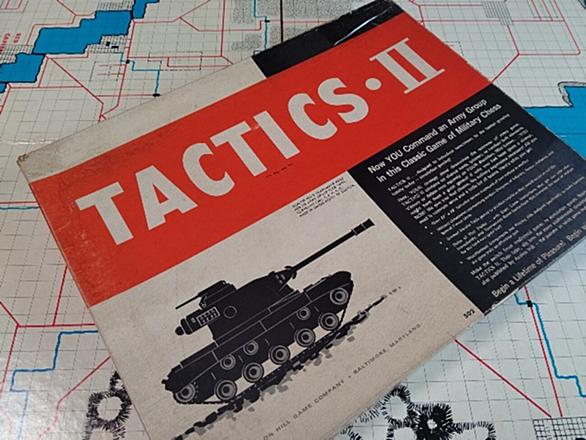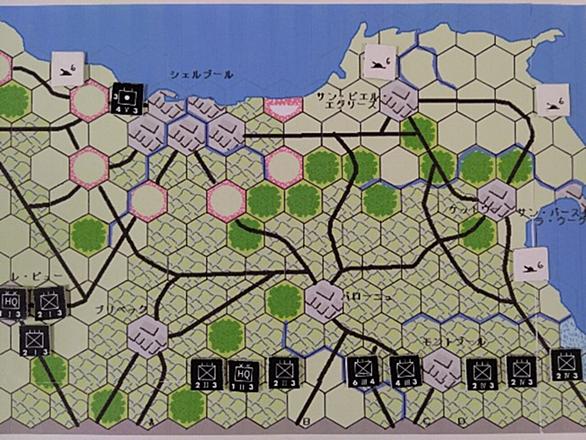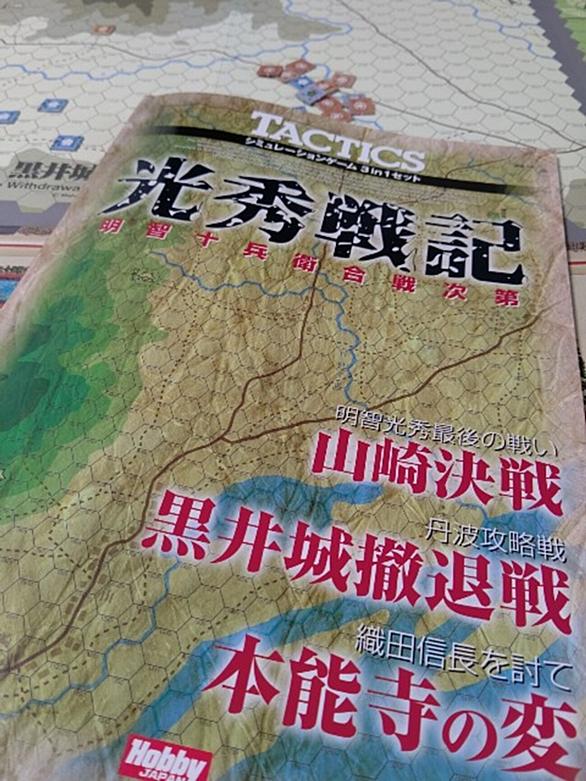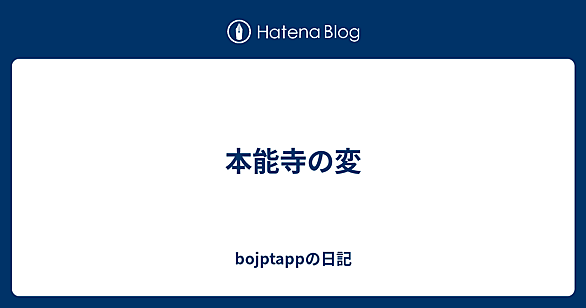tactics
(アニメ)
【たくてぃくす】
リスト::アニメ作品//タイトル/た行
リスト::アニメ作品//2004年
「コミックブレイドMASAMUNE」にて連載中の同名漫画のアニメ化。
10月5日(火) 深夜25:30〜 テレビ東京で放送開始。
スタッフに関しては、原作者の一人である木下さくらの作品をアニメ化した
「魔探偵ロキRAGNAROK」をほぼ引き継いでいる。
スタッフ
- 原作:木下さくら×東山和子
- 監督:わたなべひろし
- シリーズ構成:金巻兼一
- キャラクターデザイン:岡真里子
- 美術監督:阿久津美千代
- 色彩設計:松本真司
- 脚本:川崎ヒロユキ/久保田雅史/鈴木雅詞/高山カツヒコ
- アニメーション制作:スタジオディーン
キャスト
- 一ノ宮勘太郎:宮田幸季
- 春華:櫻井孝宏
- ヨーコ:川上とも子
- 江戸川すず*1:水樹奈々
- スギノ様:保志総一朗
- むーちゃん/レイコ:南央美
- 蓮見:飛田展男
- 源頼光:松風雅也
*1:アニメオリジナルキャラ
tactics
(ゲーム)
【たくてぃくす】