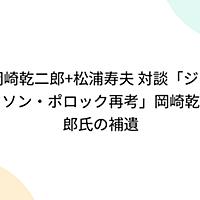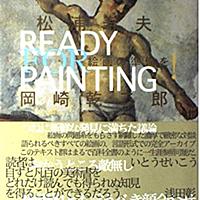岡崎乾二郎
(読書)
【おかざきけんじろう】
現代日本を代表する美術家。その活動は絵画、造形建築の広範囲にわたっている。美術批評家、社会文化批評家としても活躍している。
第12回パリ・ビエンナーレ(パリ、1982年)、ユーロパリア89現代日本美術展(ゲント)、第 9回インド・トリエンナーレ(ニューデリー、1997年)などに出品してアーチストとして世界的に知られる。
最近は近自然公園『日回り舞台』(2000年)を発表。著作に『ルネサンスー経験の条件』(筑摩書房)ISBN:4480873279 など多数。