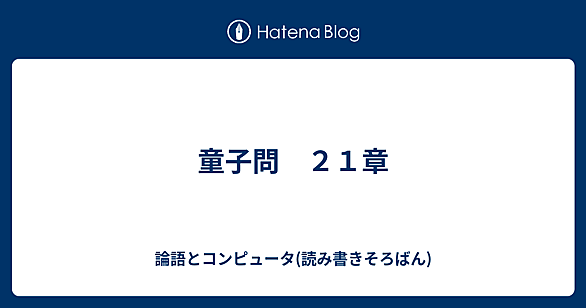朱熹
(一般)
【しゅき】
1130年〜1200年。
中国の宋代(南宋)の儒学者。字は元晦または仲晦。号は晦庵・晦翁・雲谷老人・滄洲病叟・遯翁など。また別号として考亭・紫陽がある。謚は文公。「朱子」の尊称で呼ばれている。儒教の体系化を図った儒教の中興者で朱子学の創始者である。朱子学やその後、明の時代に学問部分が国教と定められた。また、日本にも輸出されて江戸時代には幕府も朱子学を尊重した。
このタグの解説について
この解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。関連ブログ
ネットで話題
もっと見る5ブックマーク四書五経・老子・菜根譚・孫子・空海・世界三大詩歌集「詩經・万(萬)葉集・Sonnet (Shakespeare シェークスピア)」・荘子・小学・近思録・孝経 ・武士道 茶の本(大学 論語 孟子 中庸 書経 詩経 易経 春秋 礼)朱熹/朱子・王陽明・道徳/江守孝三-温故知新-Learn a lesson from the past. 日本の文化 Japanese culture ー(JAPAN AS NO.1)ー 四書五経(朱熹) & 老子・荘子 & 菜根譚 & 孫子 & 空海 & 日本史& 聖徳太子 詩經・万葉集・ Sonnet (Shakespeare)&王陽明& 般若心経 朱子学の基本となる書 儒学では、『四書』(『論語』・『孟子』・『大学』・『中庸... www.1-em.net
www.1-em.net