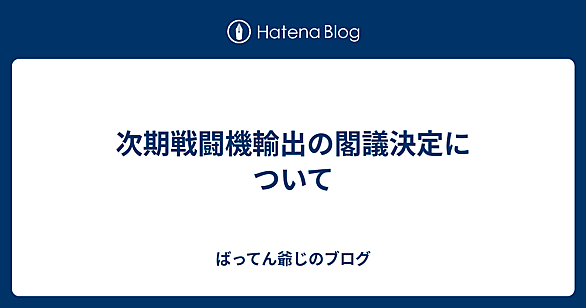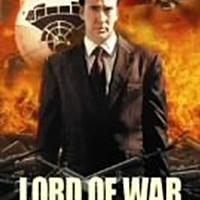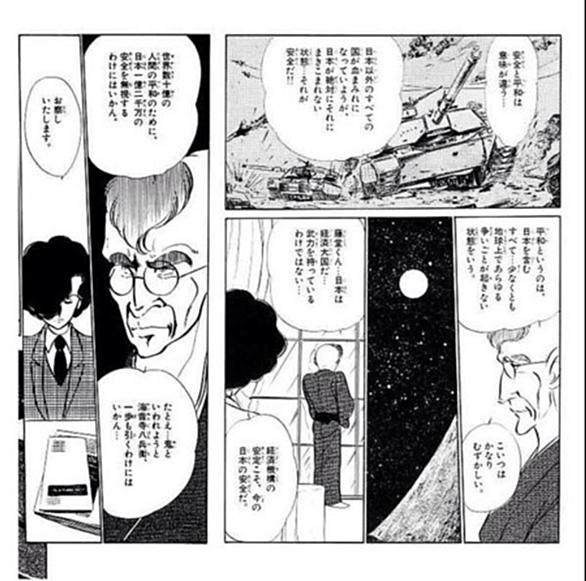武器輸出三原則
(社会)
【ぶきゆしゅつさんげんそく】
武器輸出三原則とは、武器輸出に関する日本政府の規制のことをいう。
1967年4月21日、衆院決算委員会での佐藤栄作首相(当時)の発言に端を発する。同首相は、
- 共産諸国
- 国連決議による武器禁輸対象国
- 国際紛争当事国
には武器輸出は認めないという立場を明らかにした。
さらに、1976年2月27日には、三木武夫内閣が衆議院予算員会において、
- 三原則地域への輸出を認めない
- それ以外の地域への輸出も慎む
- 武器製造関連設備の輸出も武器に準じて扱う
との方針を表明した。
ここで「武器」とは
- 軍隊が直接戦闘用に使うもの
- 人を殺傷、物を破壊する機械、器具、装置
定義しており、日本製トラック、四輪駆動車、無線機などは「武器」ではないため、多くの軍隊で実戦にも使われている。
武器輸出三原則の見直し
これまで、兵器の共同開発が世界的に主流になりつつあることなどから、日本政府は官房長官談話を出して個別に例外を認めており、たとえば2004年、政府はミサイル防衛(MD)に関する米国との共同開発・生産を三原則の例外とするなどしてきた。
しかし、世界的に国防予算が縮小する中で、性能の高度化や複雑化に伴い軍事装備品の開発・生産コストが高騰化しており、各国は同盟国や友好国との間で軍事装備品の共同開発を推進している状態で、日本としても積極的に共同開発に参加することで、装備品の調達コストが削減できるほか、自国の防衛関連産業を支援することにもなると考えられるようになった。
そうした流れを受けて、2013年12月5日、政府・与党は具体的な見直しを方針を固めた。その骨子は、
- 国際的な平和・安全の維持を妨げることが明らかな場合は輸出しない
- 輸出を認め得る場合を限定し、厳格に審査する
- 目的外使用・第三国への移転は、適正管理が確保される場合に限定する
というものである。
具体的には、
- 国連安保理決議などに違反している国には輸出を禁じる
- 国連平和維持活動(PKO)の派遣先の要請で自衛隊が装備品を置いてくるなど平和に貢献しうる場合や、武器の共同開発など日本の安全保障に有益な場合は可能とする
- 目的外使用と第三国への移転は、これまで通り相手国に日本の事前同意を義務づける
- 実際の輸出の可否は、安全保障に関わる貿易を審査する経済産業省が判断する
- 重要な案件は、新たに設置した国家安全保障会議で関係閣僚が協議する
といった内容が素案としてあげられている。
2014年4月1日、政府は「防衛装備移転三原則」として閣議決定した。