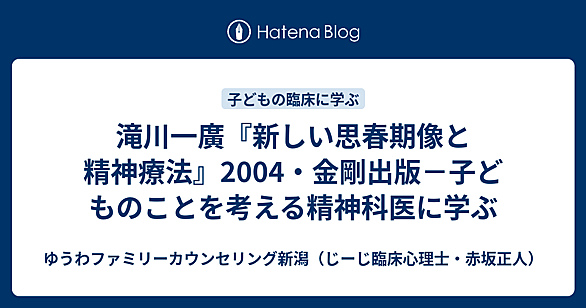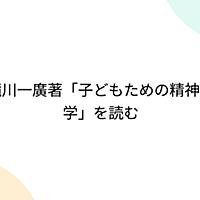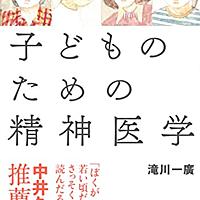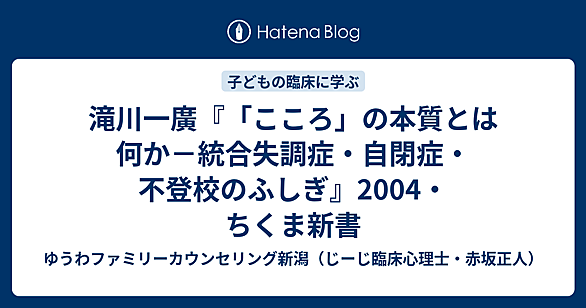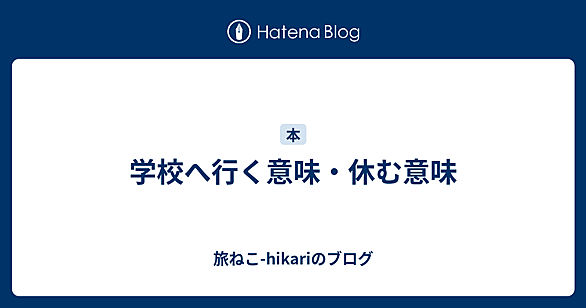滝川一廣
(読書)
【たきかわかずひろ】
臨床精神科医。
1947年生まれ。愛知県名古屋市出身。名古屋市立大学医学部卒業。
名古屋児童福祉センター、愛知教育大学の障害児教室・治療センターなどを経て、2003年4月より大正大学教授(人間科学部人間福祉学科臨床心理学専攻)。
『そだちの科学』(日本評論社)の編集人を務めている。→amazon:そだちの科学
著書
- 『新しい思春期像と精神療法』,金剛出版 ,2004年,ISBN:4772408479
- 『「こころ」の本質とは何か』,筑摩書房(ちくま新書),2004年,ISBN:4480059954
- 『「こころ」はだれが壊すのか』(聞き手・編:佐藤幹夫),洋泉社(新書y),2003年,ISBN:4896917022
- 『「こころ」はどこで壊れるか』(聞き手・編:佐藤幹夫),洋泉社(新書y),2001年,ISBN:4896915305
- 『〈こころ〉の定点観測』(共著),岩波書店(岩波新書),2001年,ISBN:400430718X
- 『いじめ―『子どもの不幸』という時代』(共著),批評社,1999年,;ISBN:4826502850
- 『不登校を解く―三人の精神科医からの提案』(共著),ミネルヴァ書房,1998年,ISBN:4623029344
- 『治療のテルモピュライ―中井久夫の仕事を考え直す』(共著),星和書店,1998年,ISBN:4791103661
- 『青年期の精神医学』(共著),金剛出版,1995年, ISBN:4772404961
- 『家庭のなかの子ども 学校のなかの子ども』,岩波書店,1994年,ISBN:400002812X