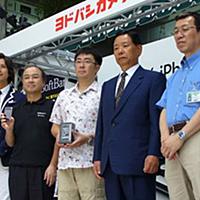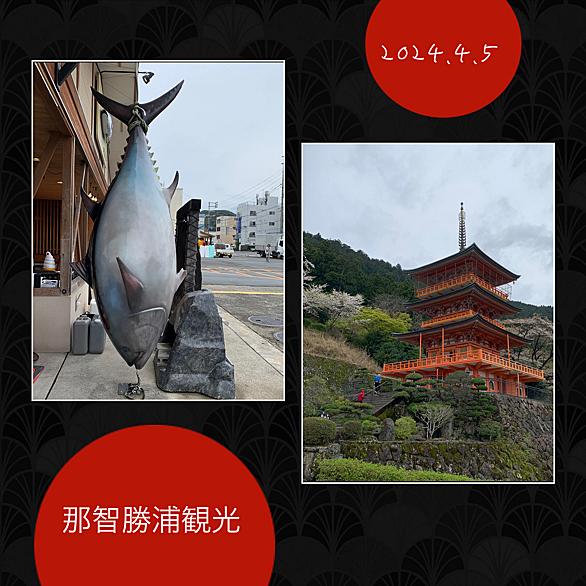不平等条約
(一般)
【ふびょうどうじょうやく】
不平等な条約。締結国の一方にのみ有利な条約のこと。
外交の基本は相互主義もしくはギブアンドテイクであり、普通の条約の中身は「オレが○○するからお前も○○しろ」か「オレは××しないからお前もするな」である。
国際社会においてはホッブズ的無政府状態が常態であり、互いが互いを制する以外の強制力が存在しなかったからである。
が、これはウェストファリア以後の主権国家の並立を前提とした考えであって、必ずしも普遍的なものでもない。例えば中華帝国と周辺冊封国との関係に見られるように、対等でない国家間関係というのは決して珍しいものではない。
近代的な意味での不平等条約とは、西欧列強が非ヨーロッパ世界の国々と結んでいた条約を指す。これらは基本的には強者の側がおくれた国々から利益を得ようと押しつけるものだった*1。
日本の場合
幕末に開国した日本が負った不平等条約的な要素は大きく以下の三つがあった。
- 片務的最恵国待遇
- 日本は相手国に最恵国待遇を与えねばならないが、相手国は日本をそう扱わずともよい。双務的最恵国待遇に改めるべく努力がなされた。
- 領事裁判権
- 俗に治外法権とも呼ばれる。日本で起きた外国人の起こした事件を、その国の領事が裁く制度。日本側に裁判などの法的諸制度が整っていなかった時代には必要悪だったとも言える。
- 協定関税制
- 通常の関税自主権を否定し、税率を話し合いで決める制度。話し合いといっても、力関係の都合上、日本側に不利な税率を飲ませることに繋がる。
いずれも幕末に結ばれた和親条約と修好通商条約によって発生したものであり、この改訂は明治日本にとっての外交的悲願となった。
*1:「保護国」という言葉に見られるように、他国の侵略を受けないようにその国を保護するといった要素が含まれる場合もあるが