脇役好きに二種あり

茺田研吾さんの『脇役本―ふるほんに読むバイプレーヤーたち』*1(右文書院)を読み終えた。
著者をはじめとした方々のご厚意で、今年2月に出された本書の原型となった私家版はおろか、本書まで懐を痛めず手に入れることができたことを、まず感謝申し上げたい。しかも私家版・右文書院版いずれにも「トリュフ」が仕込まれた得難い本であるのが、「脇役本」ごころをくすぐられる。
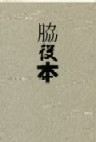 「トリュフ」というのは洲之内徹の『気まぐれ美術館』シリーズから拾い出した“(後発的な)本の挿入物”を意味するフランス語の喩えである。このことを書いた『BOOKISH』の拙文を私家版「あとがき」で言及していただいたのは身に余る光栄であった。
「トリュフ」というのは洲之内徹の『気まぐれ美術館』シリーズから拾い出した“(後発的な)本の挿入物”を意味するフランス語の喩えである。このことを書いた『BOOKISH』の拙文を私家版「あとがき」で言及していただいたのは身に余る光栄であった。
ふじたさん(id:foujita)から私家版と右文書院版はまったく違うということをお聞きし、直後晩鮭亭さん(id:vanjacketei)もこのことを指摘されているのを読み、私家版をまだ読んでいないくせにまず右文書院版を読もうと思い立った。
それにしても茺田さんという方は恐ろしい。まだ30歳をちょっと越したばかりだというのに、何という知識量だろう。本書を読むと、すでに大学生の頃から歌舞伎や文学座などの芝居を観たり、気になる役者さんが出演するテレビ番組をこつこつ録画したり、古本を買い集めたりしている。そのたゆまぬ情報収集は尊敬に値し、憧憬を持たずにはいられなくなる。
わたしも「脇役」は好きである。映画を観て主役より脇役にひかれることが多い。そんな共感を持って本書を読んでいたが、自分の脇役好きと著者の脇役好きには決定的な違いがあることに気づき、愕然とした。
わたしの場合、脇役好きは「ひねくれ者」「天の邪鬼」という性格によるところが大きい。そのうえ厄介なのは、いっぽうでメジャー志向もあることで、メジャーに受け入れられないゆえのひねくれという困った一面がある。ところが著者の場合は、脇役好きに天の邪鬼という心理的作用がまったく見られないのだ。純粋な脇役好き。つねに主役を意識している脇役好き(相対的脇役好き)と、主役など眼中にない脇役好き(絶対的脇役好き)の違いと言うべきか。
たとえば東野英治郎を論じた一節。
東野黄門さまは、平日夕方の再放送でよくやっている。ぼくとしては、柳沢吉保(山形勲)にしか興味がないし、あのカッカッカッな高笑いは、あまり好きでもない。東野英治郎といえば、やっぱり銀幕のバイプレーヤーだと思いたい。(175頁)東野英治郎という俳優のすべてが好きなのではない。「銀幕のバイプレーヤーとしての東野英治郎」でなければならない。その東野が主役である「水戸黄門」では、脇役の山形勲だけが好き。この指向性は、「ひねくれ」という身ぶりとはまったく異なるものだ。
ところでその山形勲が本書では一番最初に取り上げられている。そこでは彼について書かれた文章の少なさを嘆いている。脇役的知識に乏しいわたしにとって山形勲は、成瀬巳喜男の名作「浮雲」で高峰秀子を手ごめにし、インチキ臭い新興宗教を主導する義兄の印象であるが、それを観る前には、永井荷風がよく食事に通った麻布の高台にある「山形ホテル」の経営者の息子としてしか知らなかった。川本三郎さんの『荷風と東京』*2(都市出版)の第十章「山形ホテル」では、山形勲の談話も収録されている。これもある意味乏しい山形勲文献のひとつだろう。
山形勲とくれば伊藤雄之助。彼を取り上げた「隔離病棟の怪優」は、本書のなかでも大好きな一篇で、ここで紹介された「脇役本」の『大根役者 初代文句いうの助』はもっとも欲しいと感じた本だった。
去年茺田さんは山形と伊藤が主役として共演した映画「気違い部落」を三百人劇場に観に行かれたという。わたしも同じく観に行ったものだから(→2004/8/21条)、思わず居ずまいを正した。二人のケンカシーンは
「どちらもはげしい攻めの芝居を見せるので、さすがにクドかった」(168頁)とあるのを読んで、「たしかに」と苦笑する。
山形勲と伊藤雄之助の対比のように、本書では似た雰囲気をもつ脇役を対比する視点で語られた部分が面白い。河津清三郎と田崎潤、山村聰と佐分利信などがそのいい例だ。
取り上げられた脇役たちへのオマージュだけでなく、彼らのことを書いた人にも暖かい目を向ける。そうした本たちを手に入れた時間、空間に対する思い出もおろそかにされていない。誰もかえりみないような脇役本でも、著者の手にかかれば宝石箱のようなきらめきを見せる。
いくらさがしても手に入らない脇役本があれば、さがしてもいないのに勝手に目につく脇役本もある。これもなにかの縁なのであろう。(73頁)脇役本とは、上の一文に尽きる。けれども、それを懸命にさがす執念や、「勝手に目につく」ようなオーラを感じとるセンスがなければ、古本の山に埋もれたただの雑本として見過ごされてしまうのである。