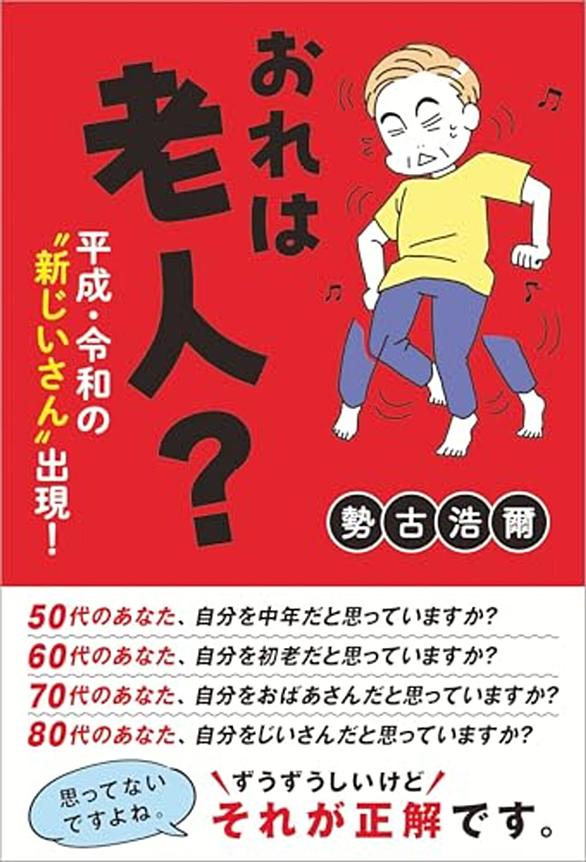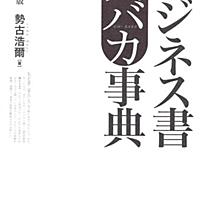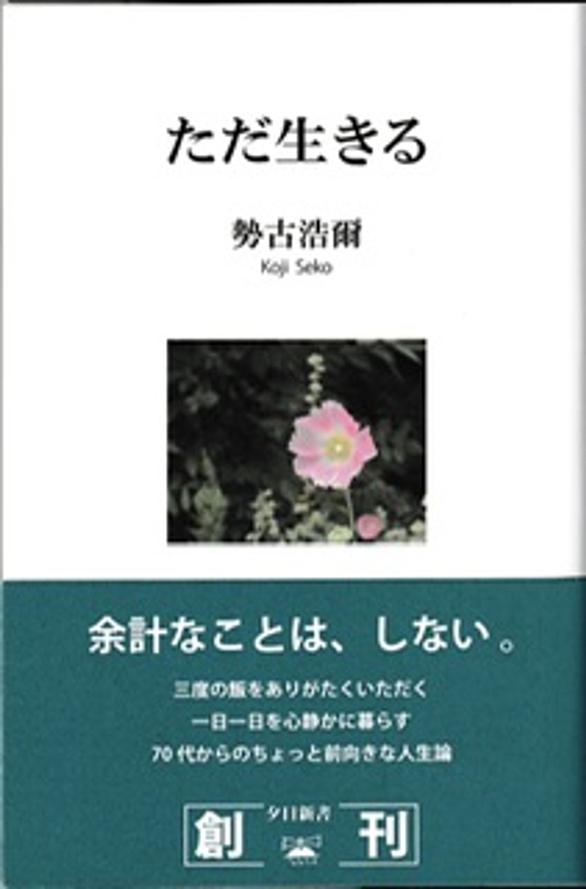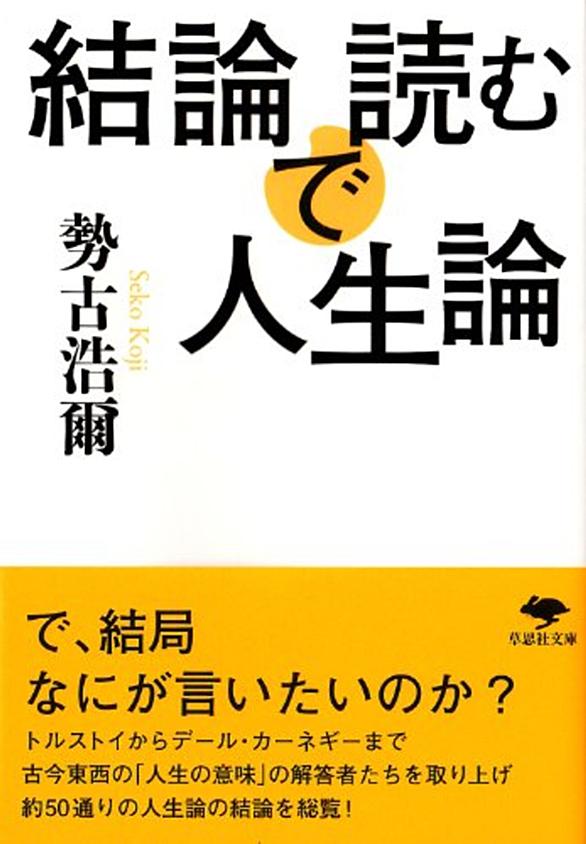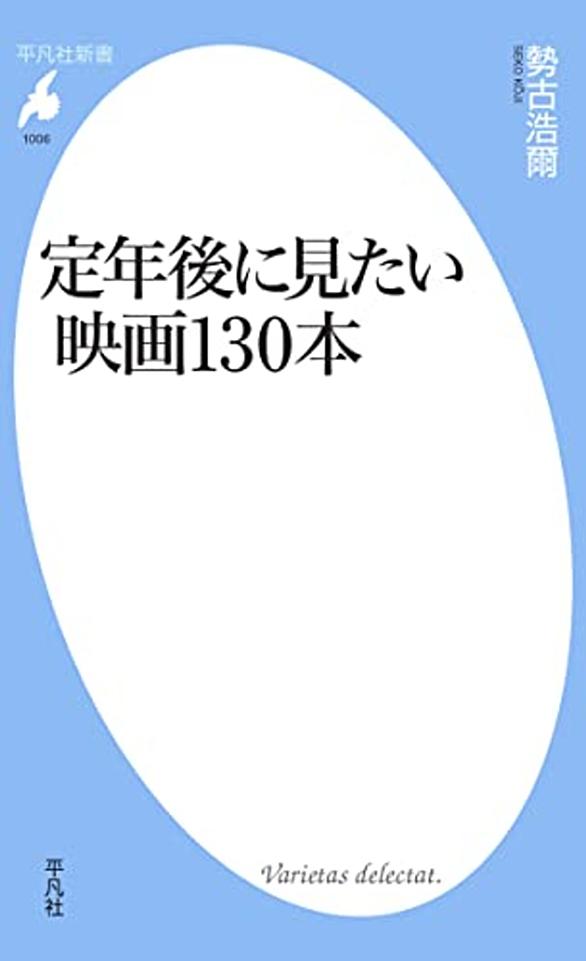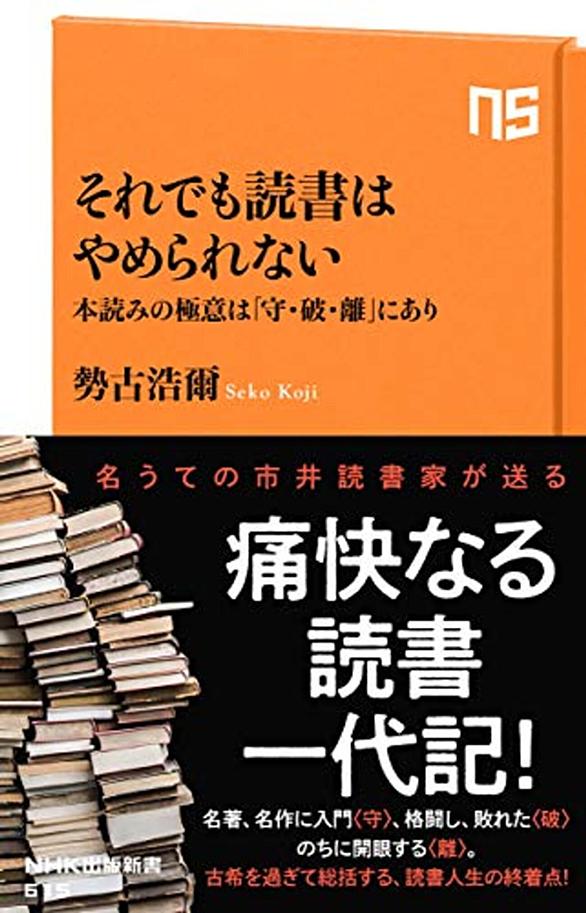勢古浩爾
(読書)
【せここうじ】
評論家(1947-)。大学時代に1年間、ヨーロッパ滞在の経験を持つ。
卒業後、洋書の販売会社に就職し、在籍時の経験を生かして評論活動に勤しんでいる。
著書「目にあまる英語バカ」で自らも英語を勉強してきた人間だったが、本質を見失った英語バカになったことを
反省しているという。英語はもう二度と話すまいと公言している。
著書
- 『中島みゆき・あらかじめ喪われた愛』
- 『自分をつくるための読書術』
- 『こういう男になりたい』
- 『まれに見るバカ』
- 『ぶざまな人生』
- 『この俗物が!』
- 『「自分の力」を信じる思想』
- 『おやじ論』
- 『自分様と馬の骨』
- 『思想なんかいらない生活』(2004年)
- 「目にあまる英語バカ」