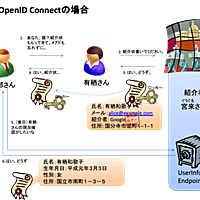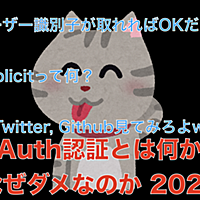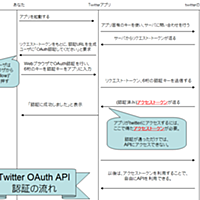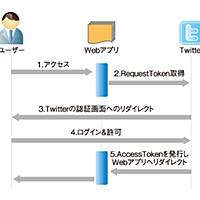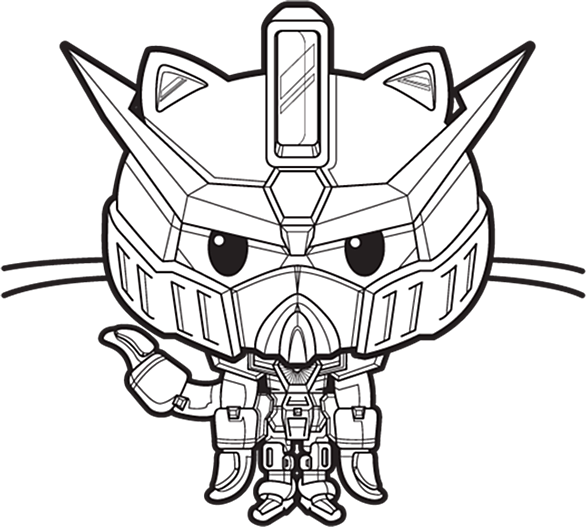OAuth認証
(ウェブ)
【おおーすにんしょう】
「Open Authorization 認証」の略記。
Web上の情報委譲形式「OAuth」を利用して、異なるサービス間での認可情報を受け渡しを行うこと。実行には、両サービスの「OAuth認証」対応が必須である。
サービス側で、委譲された情報の適用範囲や有効期限を予め設定することができるため、サービス利用に無関係な情報は受け渡しされない。ユーザーがパスワードを知らせなくても、必要な情報だけが外部サービス委譲されるため、情報漏洩のリスクを抑えられる。