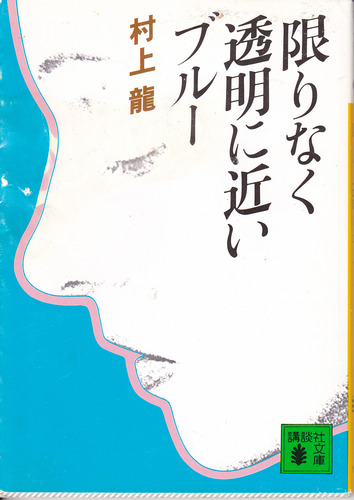これまで米軍基地やデペンデント・ハウスの「天国」的側面について、繰り返し言及してしまったけれど、占領は強制的混住であったことからすれば、そのような綺麗事ばかりのイメージですまされるはずもない。
そのことを考えると、高校生の時に読んだ小説にもかかわらず、いつまで経っても記憶に残っている一冊が浮かんでくる。それは宇能鴻一郎の『肉の壁』である。カッパノベルスの『肉の壁』単行本の巻末を確認してみると、この小説はすでに廃刊となった月刊誌『宝石』に「昭和42年8月号から43年6月号まで連載された」と注記されている。奥付には昭和43年6月初版とあるので、連載終了後、ただちに刊行されたとわかるし、私の所持するのは7月7版となっていることから、準ベストセラー的売れ方をしたのではないかと想像される。
ただ私はリアルタイムで買い求めておらず、これはかなり後になって古本屋の均一台で拾ったものである。だから最初にこの小説を読んだのは『宝石』の連載で、しかも毎月立ち読みし、最後まで読んだことになる。それは主人公の少年がほぼ同年であることに加えて、そこで描かれていく体験が、基地と進駐軍とアメリカ兵が絡んだ特異な光景のように思われたし、そのような小説は読んだことがなかったからだ。またその少し前に読んでいた、やはりカッパノベルスの松本清張の『黒地の絵』の凶々しさが想起されてもいた。そのイントロダクションは次のように始まっている。
その奇妙な趣味を、竜也は少年のころ、気まぐれな白人女によって教えこまれた。
終戦後まもなく、父親を栄養失調で死なせたあと、竜也は心臓の悪い母親と弟との三人の生活を支えるために、旧制中学を中途退学して、進駐軍キャンプ内の調達庁出張所に、ボーイとして働いていた。キャンプには母の兄である伯父が通訳として、やはり勤務しており、その手引きではいったのである。
「その奇妙な趣味」とは何か。それは占領軍のPX主任の婦人将校(ワツクス)による、十五歳の日本人給仕に対する「飼育」を通じての性の調教に他ならず、サディズムとマゾヒズムを体験させることだった。そのような場として、デペンデント・ハウスは機能していたのであり、ジェーンという婦人将校は日本で、「裸の美少年に酒をつがせたり」する「エジプトの女王になりたい」と望み、竜也にそれを命じ、さらに自分をベルトで鞭打たせる。そのような行為に対して、宇能鴻一郎は注釈を施している。
―当時、日本に進駐した占領軍兵士のなかには、男女を問わず、本国では満たされない性的な、ひそかな趣味や珍奇な思いつきを日本人を相手に満たそうと試みるものが珍しくなかった。
おそらく彼らは対等の人格を感じさせる同国人に対しては、そうした嗜好は恥ずかしくて言いだすこともできなかったにちがいない。しかし被征服国民で、みじめな、飢えた黄色人種で、さして強烈な人格も道徳律も感じさせない日本人に向かっては、彼らは気やすく大ぴらに、動物に変身することができたのだ。
占領軍のセクシュアリティがここで語られている。占領下においては男もまた犯されるのだ。後にサイードの『オリエンタリズム』(平凡社)の中でも、同じような言葉に出会うことになる。「オリエントは、我々がヨーロッパにおいてはもちえない性的体験を探し求めることができる場所なのであった。(中略)彼らがしばしば(中略)探し求めたものは、いっそう放埓で、いっそう罪の意識にさいなまれることの少ないさまざまな性的関係であった」。
かくして竜也は婦人将校に「飼育」されるばかりでなく、その後黒人兵にも犯され、「奇妙な趣味」の段階を越え、サディズムを根底に秘めた復讐の一生へと駆り立てられていくのである。これが他ならぬ『肉の壁』の主題であり、ジョン・ダワーの『敗北を抱きしめて』(岩波書店)とは異なる物語ということになる。
宇能やサイードの注釈の言葉に込められているキートーンは、村上龍の『限りなく透明に近いブルー』や山田詠美の『ベッドタイムアイズ』の性の場面にも否応なく表出していたし、ダワーの『敗北を抱きしめて』からも伝わってきたものである。さらに沼正三のマゾヒズム小説『家畜人ヤプー』(角川文庫)にしても、その他の戦後の多くのSM小説にしても、敗戦と占領をトラウマとして、すなわち強制的混住に大いなる端を発していると考えざるをえないのだ。
そのような作品として、豊川善一の「サーチライト」がある。これは一九五六年に琉球大学の学生を同人とする『琉球大学』に掲載された作品だが、アメリカ軍の圧力により発売禁止即回収という措置をこうむったために、長い間読めない一作として封印されていた。しかし二〇一二年になって、『オキュパイドジャパン』(『コレクション戦争と文学』10、集英社)に収録されるに至ったので、半世紀を経て、ようやく公開され、読むことができるようになったといっていいだろう。

「サーチライト」でも、まず基地の存在が提示される。それは沖縄の軍用道路の一号線に面している。
そして、この道と並行して、こいつもまた地面のあるかぎり、どこまでも繋がっているバラ線の一列縦隊。その向うがわに思い切りひろがっている飛行場。高射砲陣地。格納庫。弾薬倉庫。ガソリンタンク。通信隊。など、など、いわゆる基地というもの。
「サーチライト」の主人公信吉と仲間たちはその通信隊の裏側にあるチリ捨て場周辺をかせぎ場所としている。その「かせぎ」はスクラップ漁りのように語られてもいるが、何か別の気配も漂っている。そこはゲートの方角からガード交代の点呼の号令が聞こえ、定期的にサーチライトの光りが当てられ、時としてジェットの轟音が耳の鼓膜をつんざくほどだが、もはや「かせぎ」はいくらにもならない時期に入っていた。
信吉はドサ回りの芝居小屋で、座長と衣裳係の子どもとして生まれ、十二歳から舞台に立っていたが、一座は一九四四年十月十日の那覇大空襲の数日後に解散になり、彼は同じく身寄りのない娘役のシズに連れていってくれるように頼んだ。そして二人はどうしてあの激しい戦争をくぐり抜けたのかふしぎなほどだったが、生き残った。ところがその後、シズは収容所で骨と皮にやせ細り、栄養失調で死んだ。
そうしたシズの回想にひたっていた信吉は、サイレンの音によって現実に連れ戻される。MPのジープがゲート前に泊まり、白い救急車が駆けつけてきていた。事故が起き、誰かが車に轢かれたらしく、アスファルトの上は血の海となり、赤いハイヒールが転がっていた。
その光景は信吉に「不慮の災禍」のなげきを喚起させ、「異様な衝撃感」をもたらした。またそれらの血の匂いとかたまりは、自分が米軍の古い銃創で喉を突き、自殺しそこねた記憶を生々しく思い出させた。それ以来、数少ない周囲の人々も彼を避けるようになっていた。自殺へと追いやった原因は「占領直後のあの混迷と乱雑のなか」にあって、しかも「人間にとって精神形成にあたるだいじな時期」に遭遇した事件に他ならない。それは「実にくやしい屈辱の思いに身をさいなまれること」であり、「男らしい意地や張りもすべて、あの時を境いにしてみんなつぶれてしまった」のである。
それは「三年の前の夏、というと戦争がすんでまだ三年目の夏。十六才の信吉は家族部隊にいた。/ウエノヤの住宅地帯。仕事はハウスボーイ。」とあるので、場所は基地住宅(ベースハウジング)、すなわちデペンデント・ハウスをさしている。仏桑華の赤い「暗い花」がいっぱい咲く庭、チョコレート色のプリモス、真空掃除機、電気洗たく機、電気冷蔵庫、大きな電蓄、洋服だんすにぶら下がる多くの洋服と色とりどりの靴、「この規格住宅は、手にさわるもの見るもの、なんでもすべてが、まったくすばらしく、はじめて経験するばかりのそれこそ『ワンダフル』の連発だった」。
だがそのような生活は長く続かなかった。初めての給料をもらった外出の日の帰り道で、信吉は「モシモシ ボーイサン ヘエイ ストップ」と呼び止められ、「大きなクバうちわほどの黒い手と腕」による「あらあらしい暴力」に襲われ、犯されてしまったのだ。その回想の間にも「執拗にえものをあさりまわるどん欲なサーチライトの光り」が移動していく。
あの夜、信吉がこぼした涙に映って散ったキャンプの夜の権力を持ったまたたきには、性の倒錯のなかで非力に踏みにじられた〈少年〉の、相手を呪いころしたい最高最大の憤怒と感傷があった。
しかし「サーチライト」はクロージングの段になって、それが信吉の奇妙な欲望の対象と化してしまったこと、「へんちくりんなおシャレ」としかいいようのない女装をするに至っている事実が語られ、占領下における「性の倒錯」が生々しく露出する。そして三週間前の「ケネディさん」の「こっけいなくらいいきり立って馬みたいなくふれたヤツ」が言及されることで、信吉の夜の基地での「かせぎ」の実態が明らかにされ、この短編は終わっている。つまり『肉の壁』の竜也が復讐に向かったのとは逆に、「サーチライト」の信吉は占領され、同化せざるをえなかった沖縄のメタファーのような存在と考えるべきなのだろうか。
私はこの作品を新城郁夫の、『沖縄を聞く』(みすず書房)所収の「サーチライト論」である「植民地の男性セクシュアリティ」で知った。おそらく『オキュパイドジャパン』への収録も、この示唆に富んだ論考に起因しているようにも思われる。新城の「サーチライト」論は、植民地における異人種、占領被占領者、男性のそれぞれの間の重層的な性関係に表出する欲望の動きの中に、自らのセクシュアリティの問題も含め、ゲイの身体政治を探る試みとして提出されている。この論考、及び彼が「注」において示している「サーチライト」の発売禁止処分、それに続く豊川を始めとする『琉球文学』同人たちが除籍となる「第二次琉球事件」から、この短編「サーチライト」が米軍と大学当局に大きな波紋と衝撃をもたらしたことは疑いを得ない。
村上龍の『テニスボーイの憂鬱』のところで、彼の「占領された者だけが文学へ向かう。彼は掠奪されているのだ」という言葉を紹介しておいたが、それは豊川と「サーチライト」にも当てはまるのではないだろうか。

そしてこの「サーチライト」と「植民地の男性セクシュアリティ」に加えて、『肉の壁』を添えれば、占領における男のセクシュアリティのトライアングルが、いささかなりとも可視化されるようにも思える。拙文をきっかけにして、これらの三作にふれる読者を持つことができれば、とてもうれしい。
| ◆過去の「混住社会論」の記事 |
| 「混住社会論」13 城山三郎『外食王の飢え』(講談社、一九八二年) |
| 「混住社会論」12 村上龍『テニスボーイの憂鬱』(集英社、一九八五年) |
| 「混住社会論」11 小泉和子・高薮昭・内田青蔵『占領軍住宅の記録』(住まいの図書館出版局、一九九九年) |
| 「混住社会論」10 ウラジーミル・ナボコフ『ロリータ』(河出書房新社、一九五九年) |
| 「混住社会論」9 レイモンド・チャンドラー『長いお別れ』(早川書房、一九五八年) |
| 「混住社会論」8 デイヴィッド・ハルバースタム『ザ・フィフティーズ』(新潮社、一九九七年) |
| 「混住社会論」7 北井一夫『村へ』(淡交社、一九八〇年)と『フナバシストーリー』(六興出版、一九八九年) |
| 「混住社会論」6 大江健三郎『万延元年のフットボール』(講談社、一九六七年) |
| 「混住社会論」5 大江健三郎『飼育』(文藝春秋、一九五八年) |
| 「混住社会論」4 山田詠美『ベッドタイムアイズ』(河出書房新社、一九八五年) |
| 「混住社会論」3 桐野夏生『OUT』後編(講談社、一九九七年) |
| 「混住社会論」2 桐野夏生『OUT』前編(講談社、一九九七年) |
| 「混住社会論」1 序 |