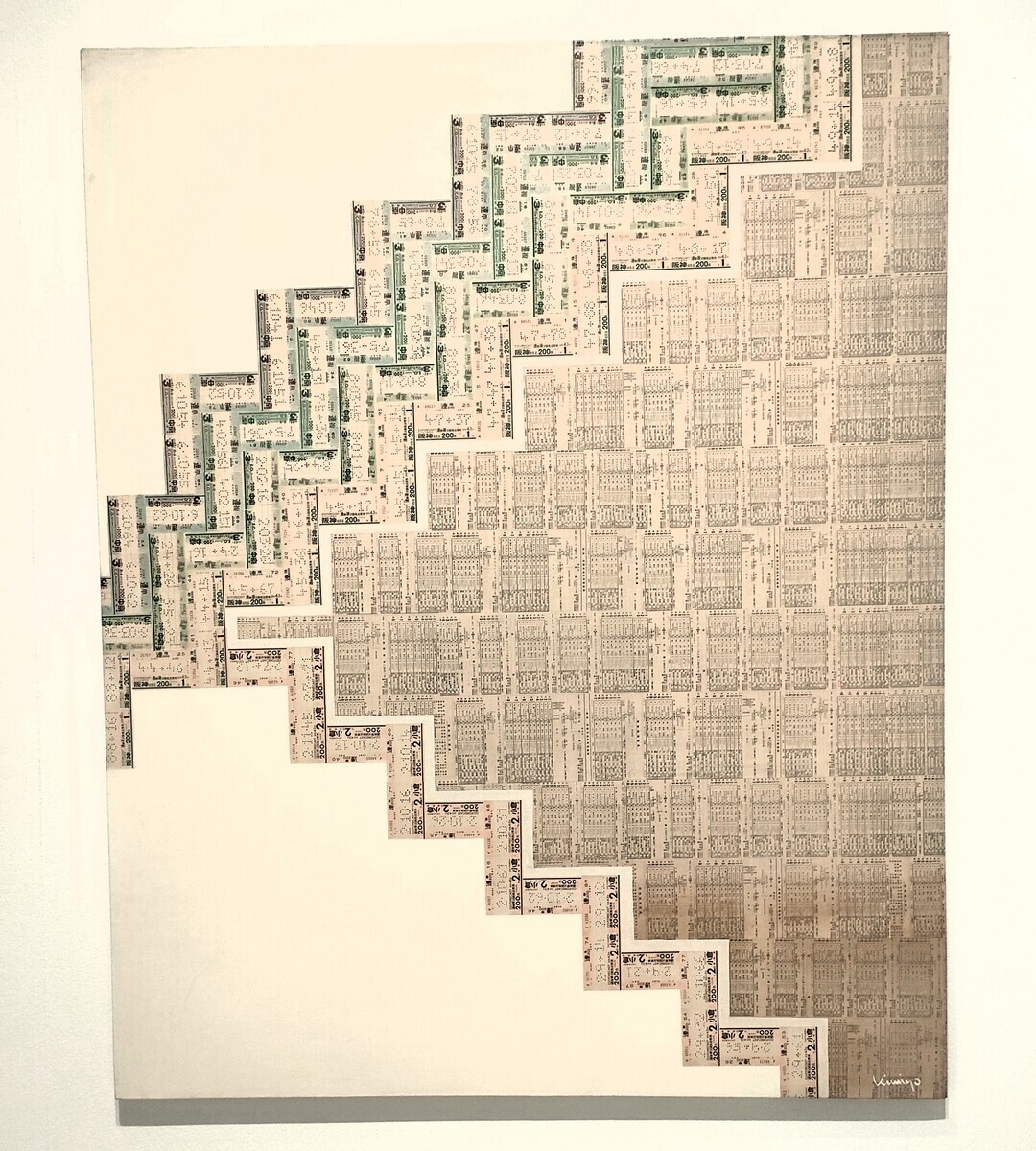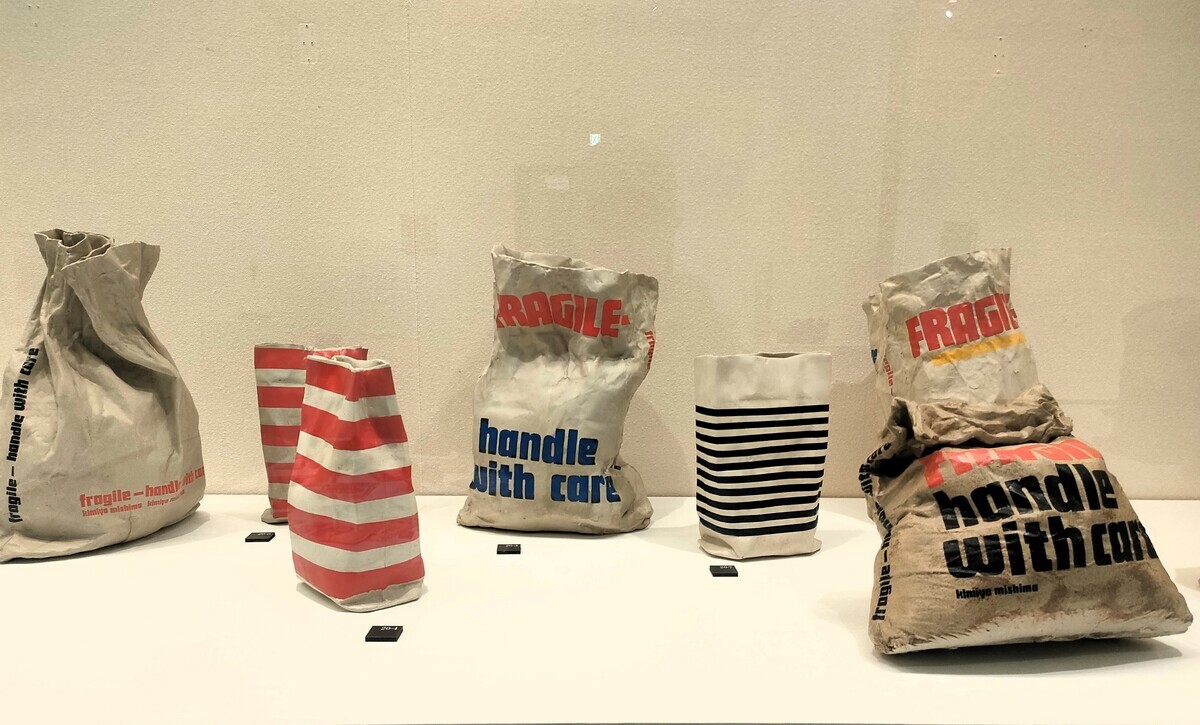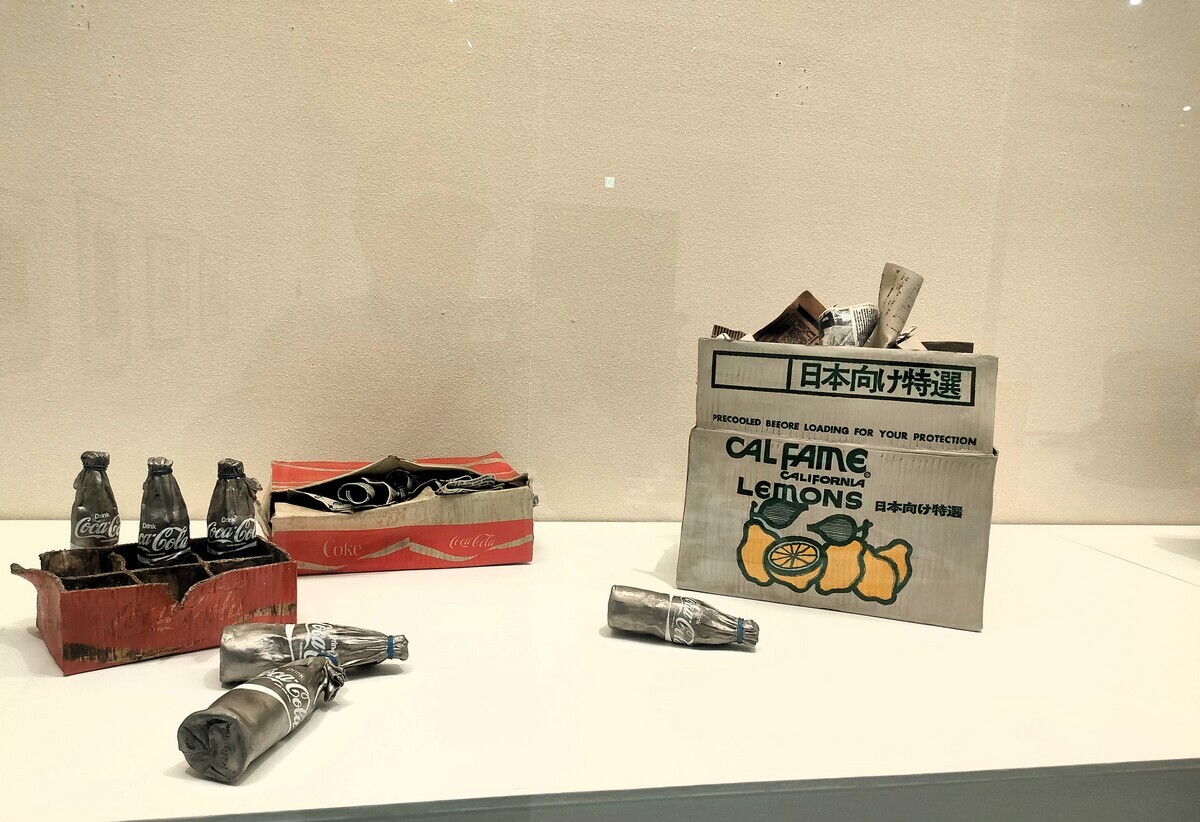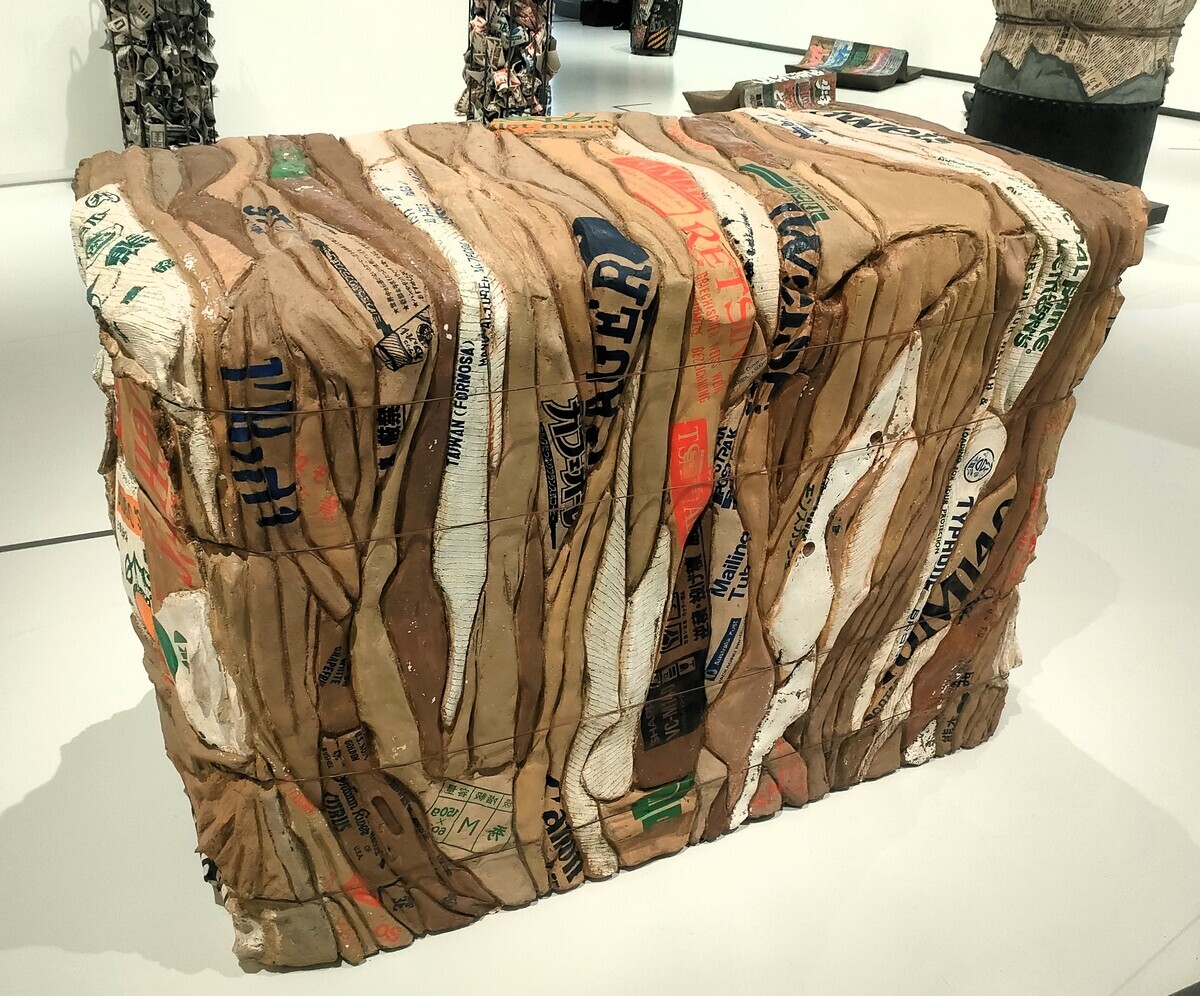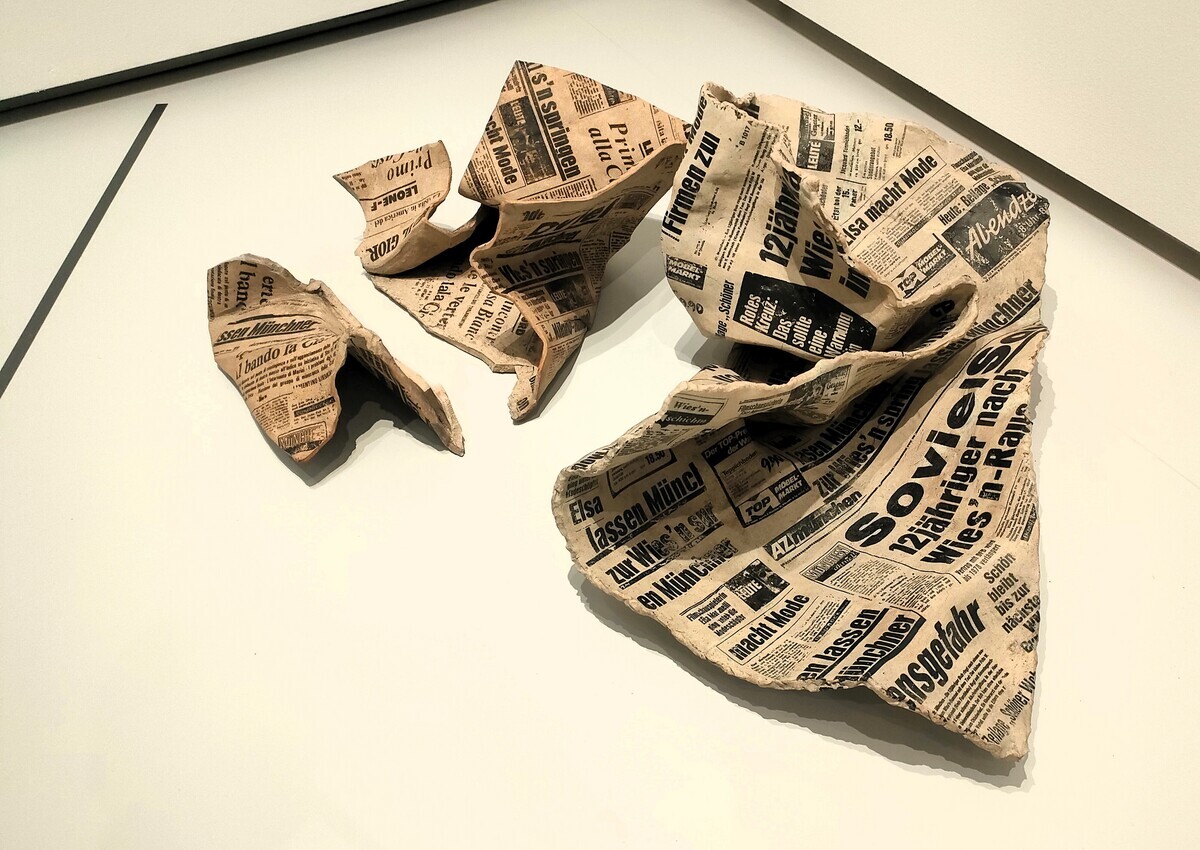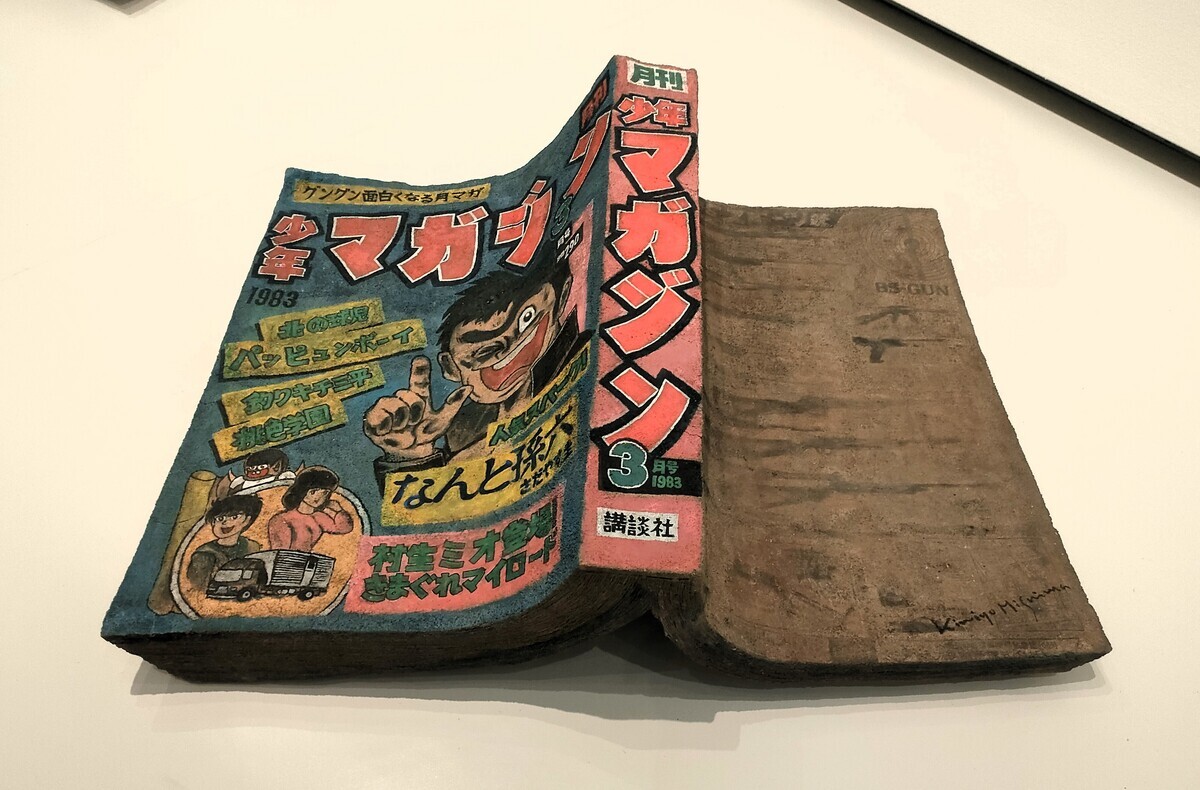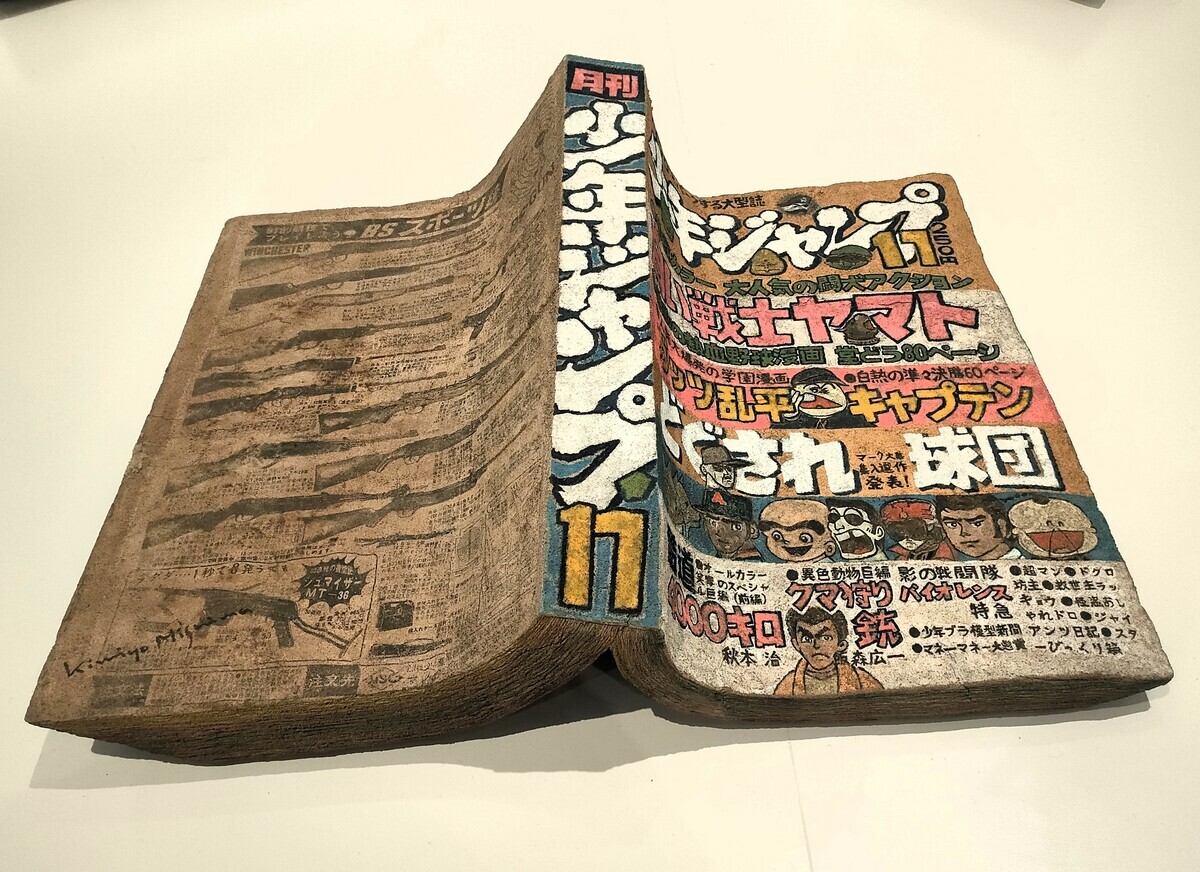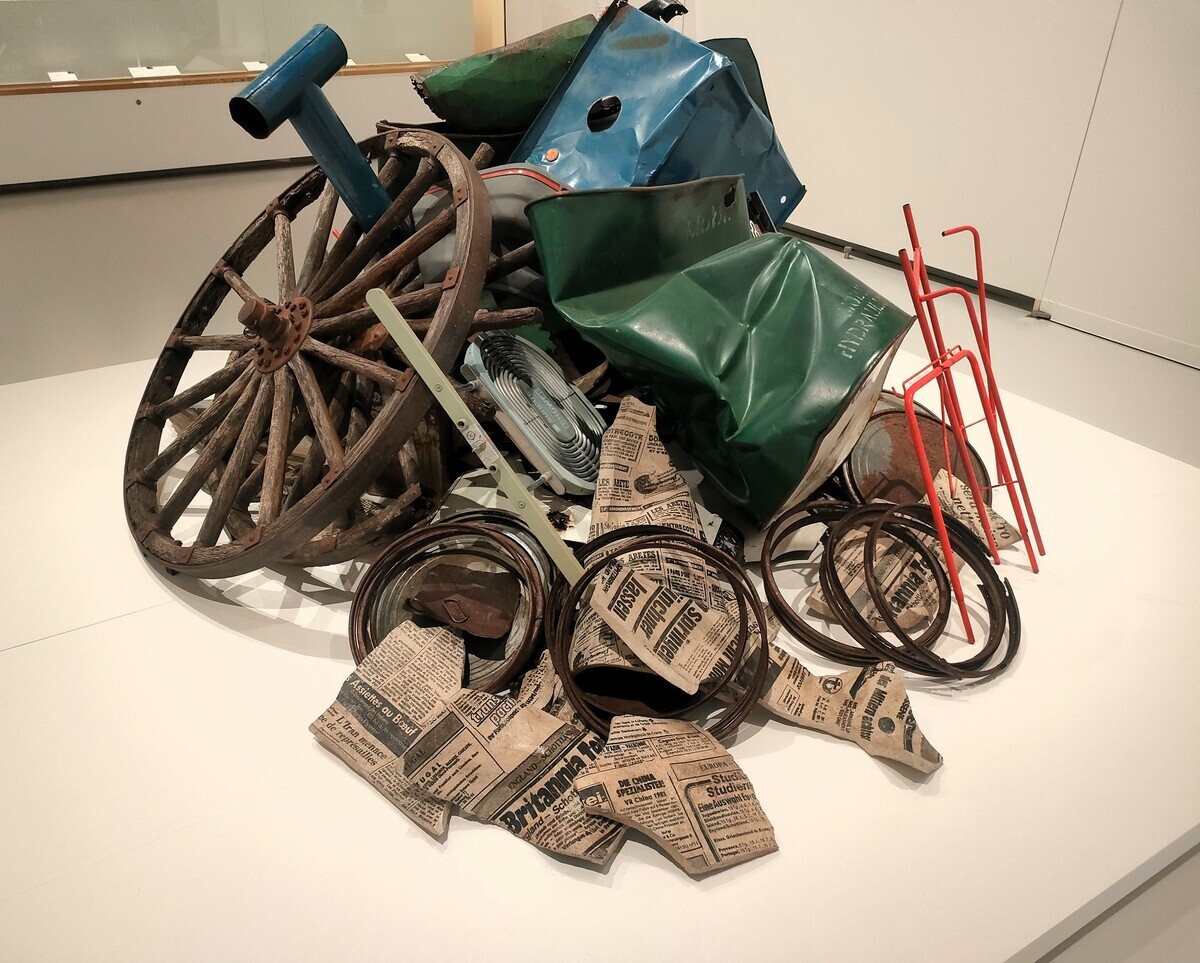豊﨑由美『ニッポンの書評』(光文社新書)を読む。豊﨑は書評家の第一人者、本書は15年前に光文社のPR誌『本が好き!』に連載したもの。15講に渡って書評に関するテクニックを詳しく語っている。私もブログで書評の真似事をしているので大変参考になった。ただ、豊﨑は小説を書評の対象としており、粗筋やネタばらしなどが話題になっている。小説を取り上げない私のブログとは多少違うかなと思った。
さて、第12講に「新聞書評を採点してみる」と興味深いテーマが紹介されている。豊﨑が朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、東京新聞、産経新聞、日本経済新聞の6紙について、2009年4月26日に掲載された署名入りの書評を5段階評価(特A~D)で採点した。
その結果、朝日:A3点、B5点、C3点、D1点。読売:特A1点、A5点、B3点。毎日:特A1点、A5点。東京:A4点、B1点。産経:B3点、C2点。日経:A1点、B4点、C1点となっている。
特Aと評されたのは、読売新聞の小野正嗣のデニス・ジョンソン『ジーザス・サン』(白水社)の書評、毎日新聞の若島正の入不二基義『足の裏に影はあるか? ないか?』(朝日新聞社)の書評の2冊、最低ランクのD評価は、朝日新聞の江上剛のタハール・ベン・ジェルーン『出てゆく』(早川書房)の1冊だった。
このD評価というのは、「取り上げた本の益になっているどころか、害をもたらす内容になってしまっている」というもの。特A評価は、「もしかすると、取り上げている本を凌駕している可能性すらある傑作書評。トヨザキが100回生まれ変わっても書くことができないレベルの、わたしにとっては悔しい書評」というもの。
さらに村上春樹『1Q84』について、さまざまな書評を読み比べ、5段階評価を示している。その結果、北海道新聞に掲載された黒古一夫の書評をC~Dとしている。
いや、大変勉強になった。実は本書を13年前に読んでいて、このブログにも紹介していた。大分耄碌が進んでいる。やれやれ・・・