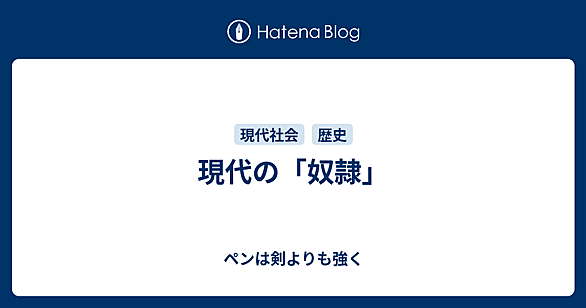竹内好
(読書)
【たけうちよしみ】
1910〜1977 中国文学者・評論家。
長野県生まれ。東大卒。魯迅の研究・翻訳のほか、アジア的視座から近代日本文化を批判。
著書に「魯迅」「現代中国論」「日本イデオロギー」等。
東京帝国大学出身、戦前は中国文学研究会を結成、機関誌「中国文学月報」を発刊。復員後、魯迅などの近代文学の翻訳をてがけるかたわら、『国民文学論』などの文学論を発表し活躍した。特に日本文化の性格について吉本隆明と影響を相互に与えた。61年安保反対闘争後、都立大教授を辞職。著作に『魯迅』『不服従の遺産』など、全集あり。