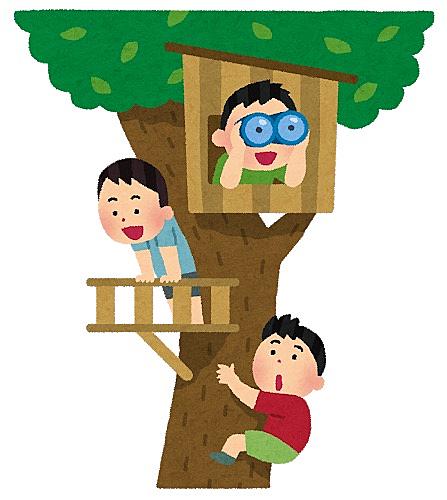福知山線
(地理)
【ふくちやません】
尼崎(兵庫県)と福知山(京都府)の間を結ぶJRの路線(幹線)。総合距離は106.5km。
近畿地方の日本海側は海水浴・温泉・スキー・カニなどを目当てとした関西からの観光客が多く、そのような客を運ぶ特急列車が多く走っている。
それだけでなく、最近は西宮北部や三田などの住宅開発が進み、大阪への通勤路線としての役割も大きくなってきている。普通・快速列車は尼崎から東海道本線大阪方面、JR東西線京橋方面との直通運転が行われている。通勤路線として使われている大阪駅〜篠山口駅間*1は「JR宝塚線」の別名がある。
近年車両の近代化も急速に進み、JR宝塚線区間では、2003年まで新製された207系に続いて2006年からは321系、2008年には223系6000番台が入り、篠山口以北でも車両運用の関係から223系5500番台が投入された。
駅(篠山口駅 以北)
| 駅名 | よみ “えき”は略 |
接続路線 |
|---|---|---|
| 篠山口駅 | ささやまぐち | |
| 丹波大山駅 | たんばおおやま | |
| 下滝駅 | しもたき | |
| 谷川駅 | たにかわ | 加古川線 |
| 柏原駅 | かいばら | |
| 石生駅 | いそう | |
| 黒井駅 | くろい | |
| 市島駅 | いちじま | |
| 丹波竹田駅 | たんばたけだ | |
| 福知山駅 | ふくちやま | 山陰本線 北近畿タンゴ鉄道宮福線 |
特急列車
- 北近畿(新大阪〜福知山・豊岡・城崎温泉)
- 文殊(新大阪〜天橋立)
- タンゴエクスプローラー(新大阪〜宮津・久美浜)
事故
2005年4月25日午前9時20分ごろ、尼崎−塚口間で脱線事故が発生した。「JR福知山線脱線事故」などと称される。
曲線での速度超過を直接の原因として上り列車が脱線し、線路沿いの建物に激突。死者107人、重軽傷者460人という、鉄道事故では戦後4番目の惨事となった。死者が100人を越えた鉄道事故は昭和38年(1963年)の鶴見事故以来。
私鉄との競合の中でスピードを重視したため余裕がなくなったダイヤや、列車が遅れた際に乗務員に過大なペナルティを課す手法が問題とされた。2006年3月のダイヤ改正ではアーバンネットワークで列車の余裕時分の延伸が行われている。
車両
- 113系(宮原)
2005年6月29日に脱線事故から復旧の際、117系に取って代わった。篠山口以北では福知山電車区の2両編成が運行されていたが、223系の投入に伴い現在は宮原のみ配置。朝と夜のみ運行。4両編成と6両編成がある。 - 207系(網干)
JR宝塚線区間のみを運行。1994年に同線進出。1編成を除き3+4両編成となっている。JR東西線直通全列車と、JR京都線直通列車の一部を担当する。脱線事故で被災したのは同系。 - 221系(網干)
福知山線では朝夕のみ運転で6両・8両編成が運行。ほとんどが快速列車に充当されている。 - 223系6000番台(宮原)
2008年6月29日より221系に代わって福知山線での運行を開始。すべて4両編成。おもに快速・丹波路快速を担当。網干配置の同番台と違ってダブルパンタグラフとなっている。 - 223系5500番台(福知山)
篠山口以北で限定運行される2両編成のワンマン対応車。福知山線では2008年7月22日より運行されている。 - 321系(網干)
207系をベースに改良した車両。宝塚線区間のみの運用。7両編成。2006年3月18日より同線で運行を開始。 - 183系(福知山)
特急「北近畿」「文殊」に充当される。もともとは1986年に同線での運行を開始した485系を直流専用化改造したもの。一部「スーパー雷鳥」用改造車から転用した車両もある。 - KTR001系(北近畿タンゴ鉄道)
「タンゴエクスプローラー」専用の車両で、福知山線では唯一の気動車。ATSの取り付け工事がされていなかった影響で2005年4月26日〜2007年3月17日まで同線では運行されていなかった。
*1:大阪駅〜尼崎駅間は東海道本線。JR神戸線と重複。