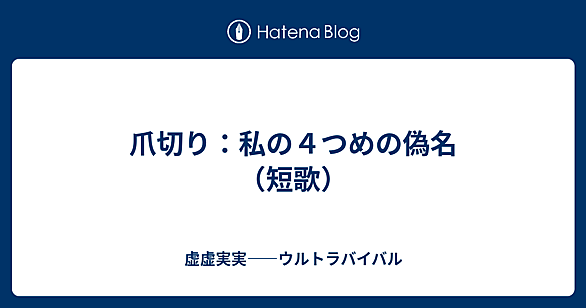フォン・ドマルスの原理
(一般)
【ふぉんどまるすのげんり】
神話や統合失調症患者の世界把握パターンを説明する、精神科医フォン・ドマルスが、豊富な症例から帰納した原理。
通常の認識では、文法的構文の基本「AがBをする」があるとき、主語のAによって、行為者を認識するが、述語のBによって行為者を認識する者がいる、という主張である。この場合、「体をあたあためる」ものを、同じことだからと、「コタツ」と「太陽」を同一なものだと認識するようなことを指す。
なお、コンピュータ言語の記述・解析にもこの原理は応用できる。