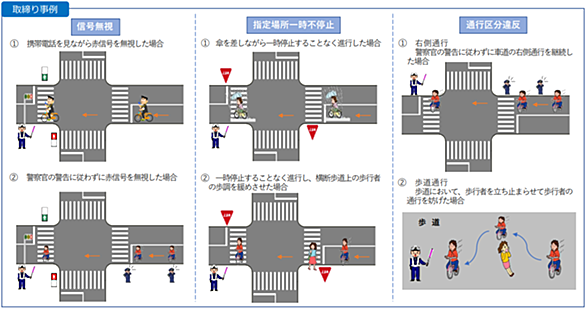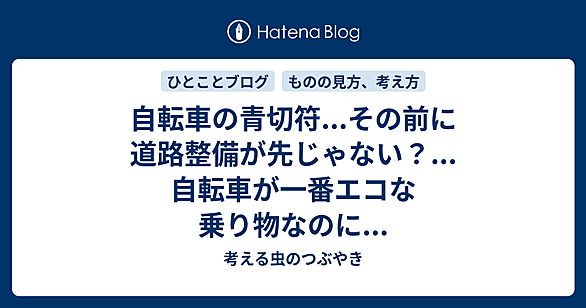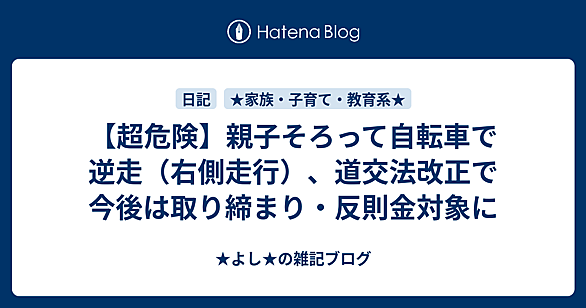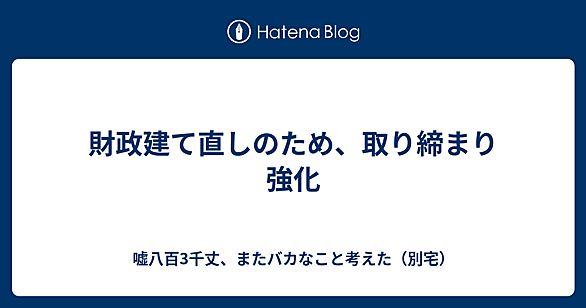反則金
主に交通取締において、刑事罰に至るほどでないと思われる軽微な違反者に対して、通常の
- 検挙(取締を受ける)→検察庁(起訴)→裁判所(裁判)→しかるべき罰則
という行程を踏まず、検挙された段階で被疑者が全面的に自分の否を認めた場合のみ、反則金を払って罪を償ったとする制度が採られている。
被疑者が自分の否を認めない場合は、反則金を納める必要は無いことが、反則キップの裏側にも小さく描かれているのだが、一般ドライバーには殆ど知られていない。
反則金未納の場合、通常の刑事事件と同じように上記の行程で進むはずなのだが、こと交通取締の場合、非常に危険性の高い違反並びに、具体的に被害者がいるような違反でなければ、検察庁で起訴されず、被疑者の不利益になる処分は行われない。
モータリゼーションによって急増する交通違反者に検察が対応出来なくなったため、反則金制度は生まれた。 取締に当たった警察以外の第三者を通さないで有罪とするシステムは反則金制度採用以前から危険視されており、警察庁次長の名において依命通達が出される程である。現在でも有効であることは平成に入ってからも警察庁の国会答弁でも認めている。 その通達内容のあらましは次のとおりである。
交通指導取締り等の適正化と合理化の推進(42・8・1通達)
交通取締り指導のあり方 交通指導取締りにあたっては、いわゆる点数主義に堕した検挙のための検挙あるいは取締りやすいものだけを取締る安易な取締りに陥ることを避けるとともに、危険性の少ない軽微な違反に対しては、警告による指導を積極的に行うこととし、ことさら身を隠して取締りを行ったり、予防または制止すべきにもかかわらず、これを黙認してのち検挙したりすることのないよう留意すること。(一部抜粋)
だが、現実は、そもそもドライバー自体「反則金は必ず払わなければならない」と思いこまされており、取締を行う警察側にも反則金収入を利権としてより強固なものにすべく、放置違反金制度や行政制裁金制度などを持ち出し、42・8・1通達など無き者とする動きがあることが、今井亮一などの交通ジャーナリストに指摘されている。