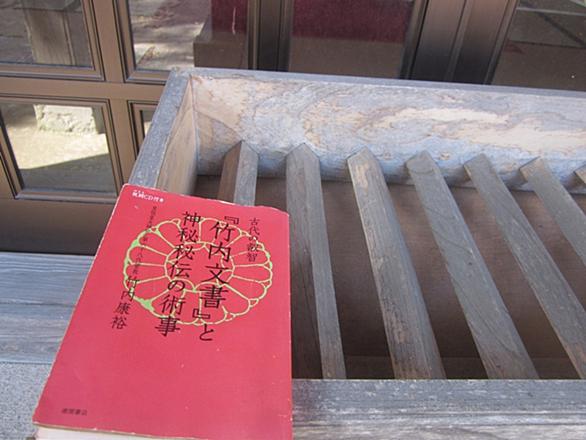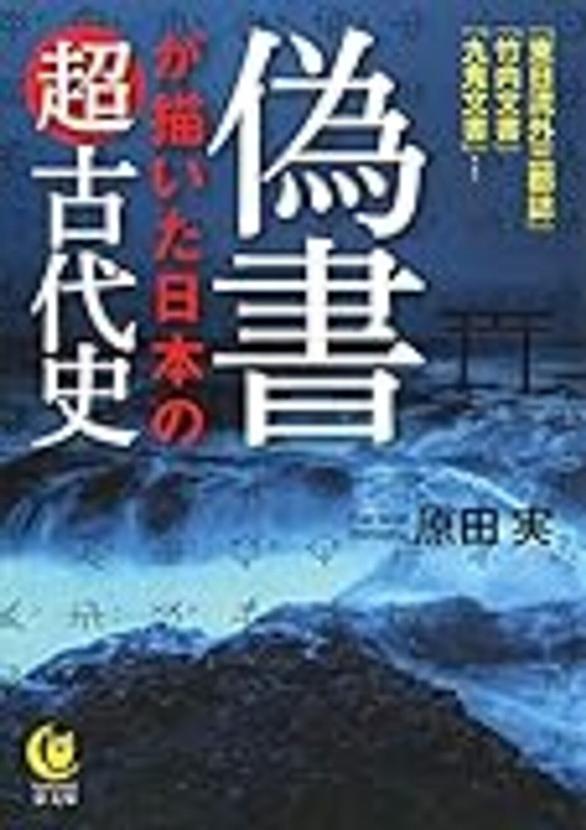古史古伝
いわゆる古事記以前の書。所謂超古代史そのもの。
また、古語拾遺には、「上古之世、未有文字。貴賤老少、口口相傳。前言往行、存而不忘。」がある。つまり、漢字が伝入以前、文字がなかったり、古事記以前も書籍がなかったということを示している。対して、古史古伝は多くその独自の文字・神代文字で書いて、漢字以前も文字が存在すると主張する。
残念ながらそのほとんどは自らが主張するよりも成立が新しい偽書だと考えられ、中には東日流外三郡誌のように1970年代以降の成立と見られるものまである。中には近年万葉集の時代においても死語となっていたと判明した言葉が含まれているなど、成立に大きな謎のあるものもあるため、内容が完全な創作とは断定できないが、そのような文献にしても、年代計算からして大きく誇張して書かれていると考えられるため、現天皇系血縁を正当化する文の多い記紀と比較しても、正確な歴史資料とはいえない。
よって、これらには正確な歴史研究の上での価値は皆無に等しいといって良いだろう。だが国学研究などの文化研究に関しては、作成者の思想やその背景を読み解くために、偽書と断定した上で一定の価値が認められる。
古史古伝
- 古史三書
- 『竹内文献』(たけうちぶんけん)
- 『九鬼文書』(くかみもんじょ)
- (『天津鞴韜秘文』(あまつたたらのひふみ)は九鬼文書群の一部)
- 『宮下文書』(みやしたもんじょ『富士文書(ふじもんじょ)』とも)
- 古伝三書
- 『上紀』(ウエツフミ)
- 『秀真伝』(ホツマツタヱ)
- 『三笠紀』(ミカサフミ)
- 古史同列
- 物部文書
- 大伴文書
- カタカムナ
- 異録四書
- 東日流外三郡誌
- 但馬故事記
- 忍日伝天孫記
- 神道原典
- その他
- 甲斐古蹟考
- 春日文書
- 先代旧事本紀大成経
- 白河本旧事紀
このタグの解説について
この解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。関連ブログ
東日流外三郡誌が面白かった件

数年前にYoutubeで古史古伝の動画を見てから、古史古伝の面白さにどっぷりとハマってしまった訳なのですが、動画を見るだけではなく自分でも古史古伝を読んでみようと思い、WEBで無料公開されている東日流外三郡誌(つがるそとさんぐんし)に目を通してみた。 大半は自分に興味の無い内容だったのですが、これはもしや?!と感じるような内容もあったので、それを紹介できればと思います。 ※当サイトはあくまでもLEDの危険性を訴えて行くことが主目的のハズなのですが、、、😅 ちなみに自分が興味を引いたのは ①津軽地方の先住民のこと ➁ヤマト国のこと ③卑弥呼のこと の3点なのですが、本題に入る前に東日流外三郡誌の…
ネットで話題
もっと見る関連ブログ
かごめ歌の真相に迫ってみた件

誰もが一度は聞いたことがある(遊んだことがある)であろう、かごめ歌… LEDの話題は一休みして、今回はかごめ歌の真相に迫って行きたいと思います ----------------------------- 「かごめかごめ」カゴメ紋をシンボルに持つ一族よ 「籠の中の鳥は」影に隠れている鳥は 「いついつ出やる」いつ正体を現すのか? 「世分けの晩に」1つにまとまっていた世が乱れ分断された晩に 「鶴と亀が統べた後ろの」鶴と亀が治めた後の 「正面だれ?」正当(な権利を持つ人)は誰? ----------------------------- 亀は出雲王朝のシンボルである そして、同王朝末期に渡来した徐福な…