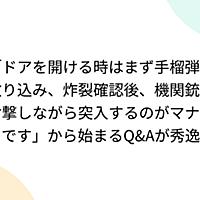機関銃
machine gun(英)
文字通り、機関(マシーン)を内蔵している銃。
この場合の「機関」とは、連射(銃弾を連続的に発射)できるようにするための「からくり」のことである。
歴史
前史
射撃武器を連射可能にするというのは男のロマンの一つであり、古くは連射可能な弩であるとか、もっと遡れば投擲の名人と投擲用の槍を運ぶ人間をセットで運用するとか、そういう時代にまで起源を持つ。
銃という「悪魔の発明」が登場すると、この扱いのやっかいな道具の発射速度を上げるために多数の発明家たちが心血を注いだ。いろいろあったが、加工精度の向上によって銃弾の後装が可能となると*1、あとは適切なからくりを導入すれば自動的に連射できる銃を実現できるはずだった。
ガトリングらによる多銃身というアプローチもあったが、今日知られているような本当の連射を行う機関銃を完成させたのはマキシムである。
マキシム機関銃
1880年代になってアメリカ人の電気技師兼発明家のハイラム・マキシム*2が、実用的な機関銃の開発に成功した*3。
連射のための自動装填機構には銃の発射の際の反動を利用(いわゆるショートリコイル)し、さらに連続射撃時に避けられない銃身の過熱問題には、銃身を水冷式とすることで対応した。これによって、「引き金を引くだけで」一分間に500発もの弾丸が発射できるようになった。
こうして「銃弾(と冷却水)さえ尽きなければ何時間でも撃ち続けられる」機関銃を完成したマキシムは、ヴィッカーズから援助を受けて製造販売に乗り出し、大成功を収める。ついでに英国籍を取得していたのでサーの称号までもらったりもした。
植民地戦争
初期の機関銃は後から考えると非常に重かったが、それでもせいぜい50kg程度に過ぎなかった。重いことは重いが、大砲とは比べるのも無意味なほど軽く、兵士2人程度でなんとかなる程度の重さでしかない。で、ありながら、その発射能力はマキシム自身の言を借りるならば「ライフル100挺分」にも達する。
列強の軍隊に売り込まれたマキシム機関銃は、まず各地の植民地戦争に投入された。辺境において、100名のよく訓練された兵士たちを、常時統制の取れた状態で配備しつづけるというのは簡単ではない。だが、マキシム機関銃とそれを扱う兵士数名を配備するだけでいいというのであれば、話は大分変わってくる。
植民地戦争において発生しがちな局面、少人数の守備隊が守る拠点を戦力集中した先住民たちが襲撃する、という場面は、その拠点に機関銃がおかれている限り集団自殺行為に近いレベルに達した*4。
では、近代軍同士の対決の場に機関銃が持ち込まれるとどうなるのか。その最初の回答は、東洋で見られることになる。