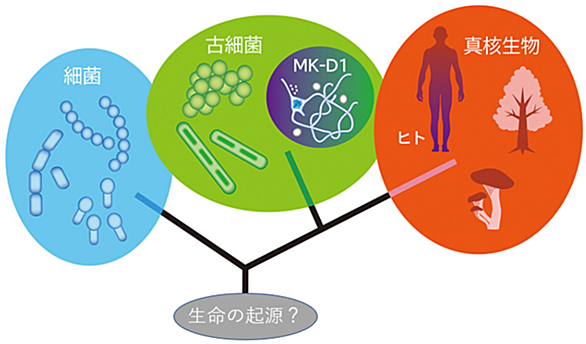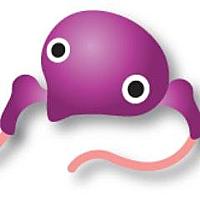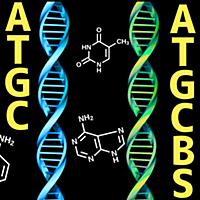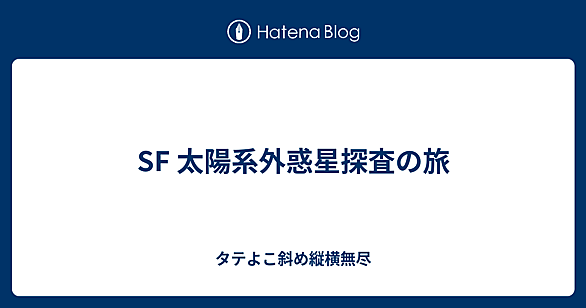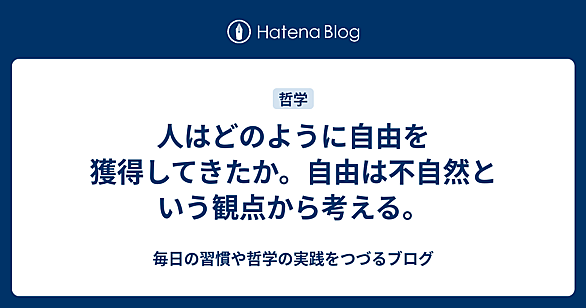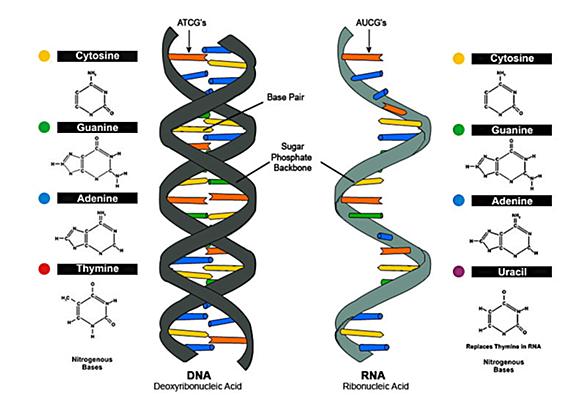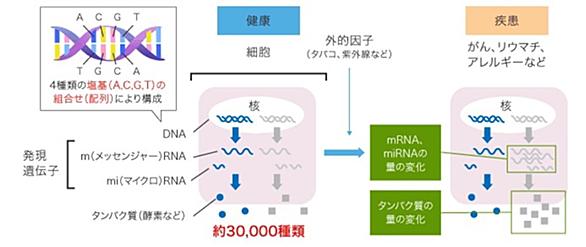セントラルドグマ
(サイエンス)
【せんとらるどぐま】
1958年クリック(DNAの二重ラセン構造を発見したワトソン・クリックのクリック)によって提唱された生命の基本原則。
「遺伝子のDNA情報は、まずRNAに、そしてタンパク質に変換される。」
ということ。
これの重要なところは、情報の流れは一方的でありタンパク質自体がRNAやDNAを合成したりできないことを示している。
しかし、1970年にある種のウイルスが生物学的情報をRNAからDNAに変換できることが発見され、このセントラルドグマは書き換えられた。