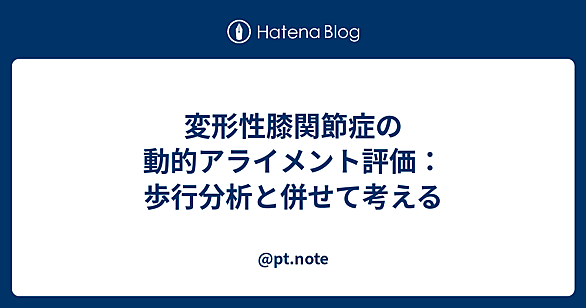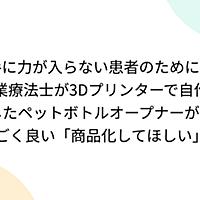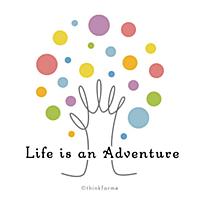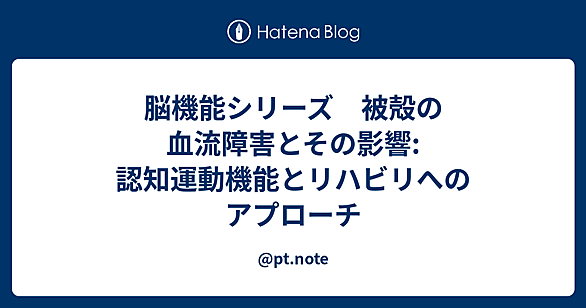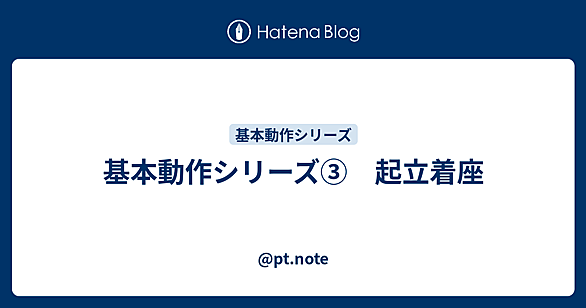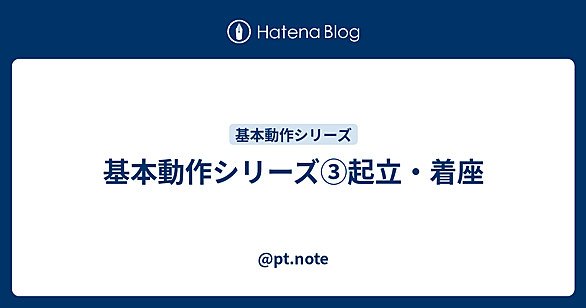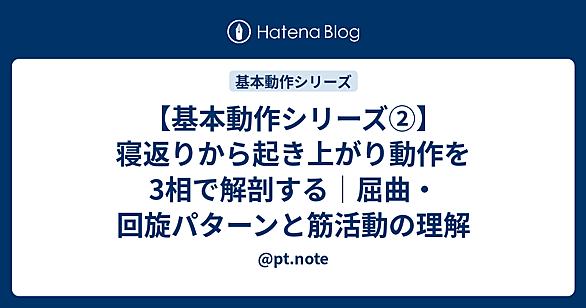作業療法士
(サイエンス)
【さぎょうりょうほうし】
OT。作業を通して、社会に適応できる能力の回復を図る。
理学療法士が物理的な機具を用いて患者のリハビリを行うのに対して、医師の指示のもとに、心身に障害がある人に対して、手芸・工作などのなどの「作業」を通じて、社会に適応できる能力の回復を図る。所定の教育課程を修めた後、国家試験に合格することが必要。
社団法人 日本作業療法士協会 http://www.jaot.or.jp/
理学療法士・作業療法士のサイト-療法士.com http://ryouhousi.com/