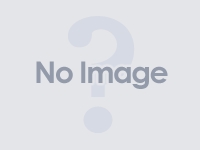日本の裏側からデータセンターを夜間監視、ITフロンティア − @IT
ブラジルで夜間監視ですか、新しい考え方だ。
確かに手順にしてツールにしてしまえばどこでも対応は取れるわけだ。
三菱商事子会社のアイ・ティ・フロンティア(ITフロンティア)は11月5日、ブラジルの大手IT企業であるPolitec S.A.(ポリテック)と協業し、日本とブラジルの12時間の時差を使った国内データセンターの夜間監視を開始すると発表した。
初めてのトラブル対応。これで直ると思ったのに! − @IT自分戦略研究所
本当に多い遅延障害のインデックスが張られていなかったのが原因・・・結構多いっすよね。
そこで、バッチ処理内のSQLを発行している個所に、開始・終了時刻を出力するログを埋め込み、調査することにしました。すると……あっという間にボトルネックを見つけてしまいました。プログラム内で「削除してからインサートする」という処理をしていたのですが、そこが異常に遅かったのです。
そのSQLを解析してみると、異常に遅かった理由も簡単に分かってしまいました。削除するときのキー情報に、インデックスが付いていなかったのです……。
すぐにその項目にインデックスを付け、プログラムを再実行しました。結果、2000件の処理が数十秒で終わりました。そして私は、この長い長いトラブル対応に、ようやく終止符を打つことができました。
Windows server Virtualization 検証してみました。(matsu 気楽なBlog)
わぁーーーWindows Server2008のVirtualizationを動かしてるー♪
まだ、英語版のみなのね。
Windows server Virtualization 検証してみました。
といっても動かしただけですが....
検証の内容ですが
①RC0日本語でVirtualizationが動かないのか?
②RC0英語版でのインストール
③RC0英語版Virtualizationで日本語ゲストOSのインストール
④RC0英語版Virtualizationで英語ゲストOSのインストール環境が構築できれば 仮想環境をVirtualSevrer2005から移行して
Exchange2007のゲストも構築したいです。
最速!富士通が解説 Exchange 2007 SP1を利用した旧バージョンから最新版への移行:Platform Solution Center セミナー情報 : 富士通
Exchange2007のセミナーです。移行検証レポートとか面白そう。
実際にExchangeの提案事例も面白そうだ。
14時 〜 15時15分
Exchange Server 2007を利用した理想のオフィス環境
Exchange Server 2007におけるエンドユーザメリットを中心にご紹介します。
マイクロソフト株式会社
- -
15時30分 〜 16時30分
Exchange Server 2007 SP1によるメールボックス移行検証レポート
Exchange Server 2007 SP1を使ったメールボックス移行の方法について、富士通にて検証した結果をご紹介します。
富士通株式会社
- -
16時30分 〜 17時
Exchange Server 2007の提案実例
富士通が提案した実例のご紹介と、実現するのに必要な構成のご説明をします。
富士通株式会社
“規模縮小”した「Internet Week 2007」の狙いとは
実際にインターネットやセキュリティをやり始めたころ、インターネットWeekの資料やチュートリアルに刺激を受け新しいものを使おうと思ったのも確か
──今回、Internet Weekの規模がずいぶんと縮小されたように見えます。
江崎氏:今回のスタイルの変更にあたっては、大きく2つの声を聞くところから始めました。「チュートリアルは本当に必要なのか」と「Internet Week本来の役割を果たせているか」です。
この部分についてのセッション多かったと思いますけど、昨今はSaaSやWeb2.0も増えてきていましたね。
もともとInternet Weekというのは、情報通信サービス全般に関して、特に実際にオペレーションをやっている方々の間で情報を共有し、方向性を議論するということをしてきたわけです。
ある意味勉強会スタイルに変えるとのこと。
江崎氏:基本的には、チュートリアルのように講義を行なって、最後に会場からちょっとだけ質問を受け付けるという形はやめたいと考えています。淡々と誰かの意見を聞くのではなく、やはり議論が欲しいですよね。
聞く側にしても、「こういう問題を抱えているんだけど、何か良い解決策はないか」とか、「これからの世の中はどういった方向に進んでいくんだろうか」といった話などを期待して来ると思うんです。予定されたストーリーだけで枠が埋まっていると、聞く側とのギャップがあった場合にそれを上手に埋めることができません。会場にいる方からの意見も出て、それによって議論が活性化するという形が1つの理想です。
インターネットWeekコミュニティってのが形成されたら面白いですね。
江崎氏:議論することに大きな意味があると思います。また、すぐには無理かと思いますが、ある問題に対して情報共有と意見形成を参加者の方々を含めて行ない、その結果を何らかのステートメント(声明書)として出せるようになるところまで持っていければ素晴らしいですね。
リテラシーのお値段:日経パソコンオンライン
園田さんのリテラシー教育に関してかかる費用についての記事です。
Windowsで動くLinuxの最新安定版「coLinux 0.7.1」がリリース | エンタープライズ | マイコミジャーナル
CoLinux0.7.1が出ているそうです。Vistaに対応しているそうです。
coLinux 0.7.1は、2006年9月に公開されたcoLinux 0.6.4に次ぐ安定版リリースという位置付け。2007年1月以来リリース候補を4度にわたり公開、動作の検証を続けてきたもの。
前バージョン以降の変更点としては、サポートされるLinuxカーネルが2.6.11から2.6.12へと更新されたほか、仮想ネットワークドライバのTAP-Win32がWindows Vistaに対応した。直接ホストマシン上の領域をcoLinuxからマウントする「cofs」も改良され、パスのベースネームは255文字まで、フルパスは最大256階層まで対応した。なお、サービス開始時に参照される設定ファイルは、記述様式が従来のXMLからプレインテキストに変更されている。
SRA OSS, 「PHP4セキュリティ保守サービス」を開始
超便利! ビジネスに役立つ無料サイト:企画やプレゼン資料の強い味方!「統計データ・ポータルサイト〜政府統計の総合窓口〜」
第2回 仮想化は耐障害性や運用管理にも効く:ITpro
仮想化で検証をしたり開発環境を作ったりするってのは便利だよねぇ。
例えば,システム開発にサーバー仮想化を応用すると,開発用のマシンを別途用意することなく開発環境を構築できる。開発中のプログラムに問題がありOSがクラッシュしても,影響があるのはその仮想マシンだけだ。システムの可能性を上げるフェイルオーバー・クラスタに仮想マシンを利用することも可能である。その場合は待機系のシステムのリソースを実際に必要になるまで減らしておけるというメリットがある。さらに,システム移行も容易になる。仮想化ソフトには,古いバージョンのOSの稼働をサポートしているものが多い。古いアプリケーションをOSごと仮想マシンに移すことで,新しいハードウエアへの移行が容易にできる。
リソース再配分はすごくいいよねぇ、物理ハードだったらメモリ増設して、再起動とか、色々面倒だけど、事前にメモリを積んでおけば(ここ重要)
あとからなら、仮想マシンへのメモリ追加でいけるし。
仮想化技術活用の究極は,負荷に応じてハードウエア・リソースを再配分する「自動化」である(図7)。システムの負荷を運用管理ツールで測定し,それと仮想化によるリソース再配分を連動させる。
インド離れを始めたアウトソーシング 今度はインド企業が業務を海外移転:ITpro
既にインドから次の場所へ。次はどこ???
インド国産IT企業はアウトソーシングのさらなる「アウトソース」に動く。06年からそれが顕著になってきた。第一の理由は利益の圧迫だ。今年に入ってからルピーが対ドルで12%高騰したほか、9月の米IDCの調査によれば、インドにいるIT技術者の平均年俸は昨年の18.3%増をやや上回る 18.7%に上昇し1万5300ドル(約180万円)となる。インド企業は、売り上げの大半をドルで受け取るがインド人スタッフの費用をルピーで支払うことが多く、ルピーや人件費の高騰は直接ハネ返る。
また、英語以外の言語を話す従業員への需要、そして世界のITバックオフイスとして成功したインドに続けと台頭めざましい新興国との競争が、従来モデルに挑戦状を突きつけている。先のインド系日本法人の幹部は、インドに大量に降り注いだアウトソーシングは将来、「世界中から出された仕事を、世界のどの地域でも処理できるようになる」と見ている。
メキシコは、おもしろいなぁ。ブラジルにも米国にも近いし。。。。
変化する勢力地図と戦い、登場した競合相手を打ち負かすために、インド企業も需要の先回りをして新興国で従業員を雇い、拠点を構え始めた。タタ・コンサルタンシー・サービシズは5月に、メキシコのグアダラハラに新オフィスの設置を発表した。同社は既にブラジルやチリ、ウルグアイでも5000人が働く。カナダ、中国、ポルトガル、ルーマニア、サウジアラビアにアウトソーシングセンターを持つウイプロは8月、米国アトランタに開発センターを開設した。加えて、米国の中でも発展が遅れている州を活用するため、アイダホやバージニアでもハブの建設を検討中だ。インフォシスも負けてはいない。メキシコ、チェコスロバキア、タイ、中国のほか、ウイプロ同様コストが低い米国の地域で拠点開発を進めている。目標は顧客に近い場所でアウトソーシングに応える企業になることだ。
第3回 最新CPUの性能(後編) デュアルCPU vs. デュアルコア:ITpro
デュアルコアとデュアルCPUの違いらしいです。
へぇー、デュアルコアとデュアルCPUってSQLとかの実行では処理数変わらないんだ。てかシングルで動いてたりしてw
単位時間当たりのSQL文の処理件数を実測したところ,Xeonデュアルコア(Paxville DP)は約2783.7件,XeonデュアルCPUは約2858.3件で,デュアルコアは約2.6%(約74.6件)しか劣らなかった。この場合, Xeonデュアルコアのクロック周波数が0.2GHz低かったことなどを考慮すると,処理性能はほぼ互角と言ってよいだろう。
あんまり差がないのね。以外。64ビットOSの方がメモリ空間の動きが単純で少し早いくらいみたい。
結果から言うと,32ビット・システムと64ビット・システムでは,処理性能に大きな違いは見られなかった。平均CPU余剰率の差はわずか1ポイント程度。具体的には,Xeon(ハイパー・スレッディング無効)の場合,32ビット・システムは約 38.8%,64ビット・システムは約37.1%。Xeon(同有効)の場合,32ビット・システムは約46.5%,64ビット・システムは約47.4%となった。Opteronの場合,32ビット・システムは約38.1%,64ビット・システムは約37.9%だった。
SQL文の処理件数では,ハイパー・スレッディングを有効にしたXeonで約2.3%(約64.4件),Opteronで約6.3%(約172.7件)とわずかながら,64ビット・システムが32ビット・システムを上回った(図A)。64ビット・システムの広いメモリー空間が有効に働いたと見るのが妥当だろう。
これからシステム開発する人は、ここに注意が必要ですよね
このあたりを簡単に作れるようにならないと、マルチCPUはユーザに利用されないですね。
マルチCPUやマルチコアCPUを生かすには,OSやアプリケーションがマルチスレッドで動作するように設計されている必要があり,スレッド処理機構の実装次第でベンチマーク結果に大きな違いが出る。今回はWindows Server 2003やSQL Server 2005で検証したが,単純な処理でもマルチコアCPUのメリットが数字に表れた点は興味深い。この結果から,サーバー・アプリケーションの開発者は今後,マルチコア環境を前提としてマルチスレッド・プログラミングを意識しなければならないと痛感した。
第2回 TCP/IP高速化:大量データをまとめて送信:ITpro
意外と知られていないTCP/IPのオーバーヘッド。100Mbps全部使えるという誤認・・・
高速化技術を理解するには,基本となるもともとのTCP/IP技術を押さえておく必要がある。TCP/IPのスループットは理論上,「1パケットで受信できるデータ量(RWIN)÷1パケットの受信が完了するまでの遅延時間(RTT)」で求められる。LinuxやWindows 2000 SP3以降の主要なOSは,TCP仕様の最大値64Kバイト(512kビット)をRWINとして設定する。RTTが20ミリ秒だとすると,スループットは最大約25Mビット/秒となる。
この環境で100Mビット/秒の帯域を占有できるとすれば,約25Mビット/秒では遅い。つまり,もともとのTCP/IPでは力不足というわけだ。その最大の理由は,TCP通信の「フロー制御」と「輻輳制御」の仕組みにある。
IIJさんが利用しているネットリ社さんとかは、おそらくトンネルを張ってその中のWindowサイズを大きく、複数パケットをACK関係なく送付したりすることで距離遅延を受けないようにしているんでしょうね。
「大容量初期ウインドウ」(RFC3390)や「ウインドウ・スケーリング・オプション」(RFC1323)である。大容量初期ウインドウは,最初に送るセグメント数を増やす(図1右上)。もともとのTCPは1460バイトで,それを4380バイトに拡大する。さらにウインドウ・スケーリング・オプションは,RWINの最大値を従来の64Kバイトから1Gバイトに拡張する(図1右下)。より多くのデータをまとめ送りできるので,スループット向上を期待できる。
大容量初期ウインドウやウインドウ・スケーリング・オプションはすでに標準化されており,主要なOSやルーター装置が対応済みである。ただし,帯域が狭い場合やネットワークの信頼性が低い(エラー率や損失率が高いなど)場合にウインドウ・スケーリング・オプションを使うと,大容量データが頻繁に再送されてしまい,逆効果になりかねないので注意したい。
シスコがスイッチの仮想化で冗長化プロトコル廃止、障害時の即時切り替え可能に:ITpro
ついにCiscoがHSRP廃止?!?!、仮想化技術で2台のスイッチを1台に見せることが出来るそうです。
シスコは11月6日、スイッチ/ルーターの最上位機「Cisco Catalyst 6500」シリーズにおいて、仮想化機能が搭載できるようになったと発表した。ここでいう仮想化とは冗長化のための2台のスイッチ/ルーターをあたかも1 台のように扱えること。これによって、冗長化のためのプロトコルを運用する必要がなくなった。シスコによると、「世界初の取り組み。米国に先駆けて日本で発表した」
HSRPやVRRPなんかが入らなくなるし、スパニングツリーもいらなくなるらしい・・・
切り替え時間もゼロらしい・・・まぁ、他社との連携もあるのでVRRPやSTPは残るでしょうけど・・・
具体的には、「Virtual Switching System(VSS)」という技術で、2台のCatalyst 6500と2つの回線をあたかも「1台と1回線」として運用できるようにした。2台のCatalyst 6500は同期して稼働する。これによって、機器監視のためのプロトコル「HSRP」や「VRRP」、冗長化プロトコルの「STP」が不要となった。後者はいわゆるスパニング・ツリーである。万が一、一方のCatalyst 6500で障害が発生した際、「従来は切り替えに1.5〜3秒かかっていたが、これをゼロにできる」(佐々木プロダクトマネージャー)。
仮想サーバは仮想パッチで保護 − @IT
IPSをハイパーバイザで搭載しちゃってExploitを防止しましょうって内容ですね。
VirtualShieldは、米ブルーレーン・ソフトウェアが開発したセキュリティ製品だ。VMware ESX Serverで構築された仮想サーバとハイパーバイザーの間でトラフィックを監視し、ソフトウェアベンダが提供するパッチの動きをエミュレートする。つまり、仮想サーバ本体に直接手を加えなくとも、パッチを適用したのと同レベルの保護を実現する。
ブルーレーンはこれまで、物理的なサーバを対象に同じように「パッチの外出し」を実現するアプライアンス製品「PatchPoint」を提供してきた。
色々なアプリにも対応って事で、IPSのハードを入れるか、ソフトでIPSするかは事前に考えておいた方がよい内容ですね。
なお、仮想パッチの実現方法はPatchPointと同じだ。WindowsやSolaris、Red Hat Enterprise Linux、SuSEといったOSのほか、ApacheやSendmail、IISやSQL Serverといったアプリケーション向けにベンダが提供する公式のパッチをブルーレーン側で解析し、「InlinePatch」という独自のパッチとして実装する。ただし、PatchPointではOracleデータベースも対象に含まれているのに対し、VMware上で動作する VirtualShieldはサポート外となっている。