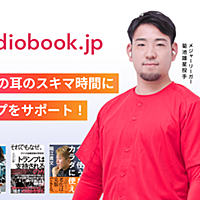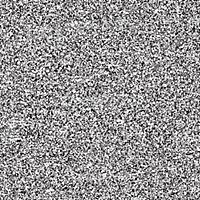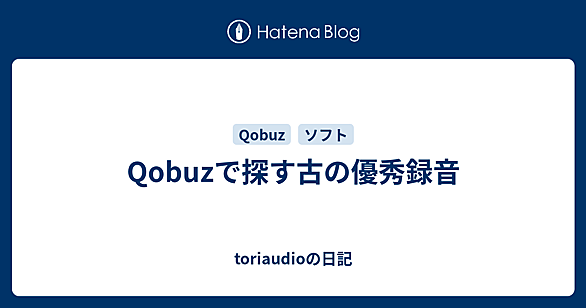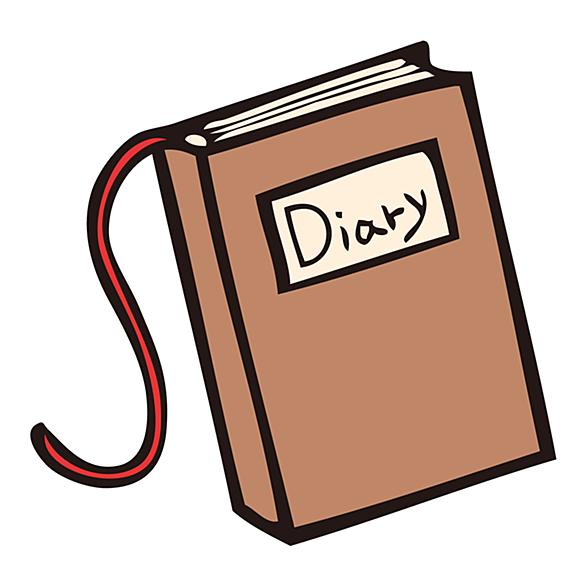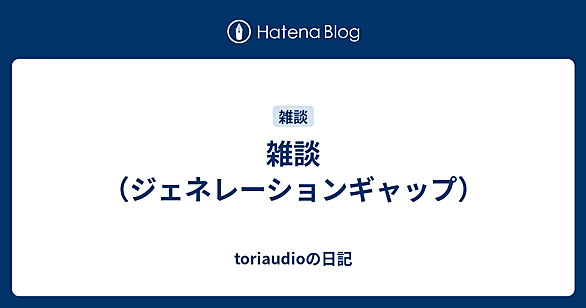オーディオ
(音楽)
【おーでぃお】
音楽やその他の音を再生したり録音したりする装置のこと。
また、その装置を使って音の再生や録音を楽しむこと。
原語は英語で「音声の」を意味する“audio”。その語源はラテン語の「聞く」を意味する“audire”。
主に「人間に聞こえる」音を表す。
人間に聞こえない域の表現は「サウンド」が好ましい
このタグの解説について
この解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。関連ブログ
ネットで話題
もっと見る695ブックマークAudacity: フリーのオーディオエディタ・レコーダーAudacity is a free, easy-to-use, multi-track audio editor and recorder for Windows, Mac OS X, GNU/Linux and other operating systems. Audacity is free software, developed by a group of volunteers and distributed under the GNU General Public License (GPL). Programs like Audacity are also called ope... sourceforge.net
sourceforge.net