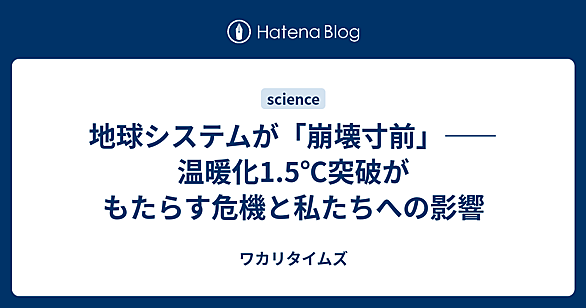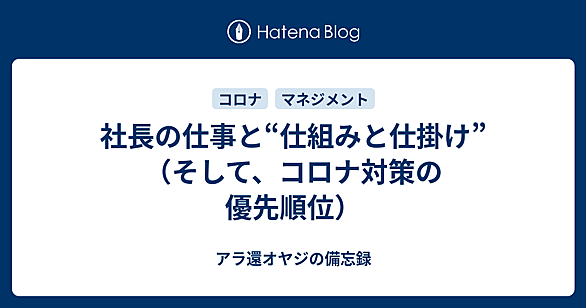ティッピングポイント
(ウェブ)
【てぃっぴんぐぽいんと】
物事の流行のプロセスを見ると、ある一定の閾値を越すと一気に全体にいきわたる状態になることがある。この閾値をティッピングポントという。
流行の状況をグラフに書くと「S」の字を横に倒したような形になる。この突然あがっていく地点がティッピングポイントである。
複雑ネットワーク理論関係の用語で言えば、パーコレーションの一種と考えられるだろう。
同名の本が有名。

ティッピング・ポイント―いかにして「小さな変化」が「大きな変化」を生み出すか
- 作者: マルコムグラッドウェル,Malcolm Gladwell,高橋啓
- 出版社/メーカー: 飛鳥新社
- 発売日: 2000/02
- メディア: 単行本
- 購入: 29人 クリック: 711回
- この商品を含むブログ (63件) を見る