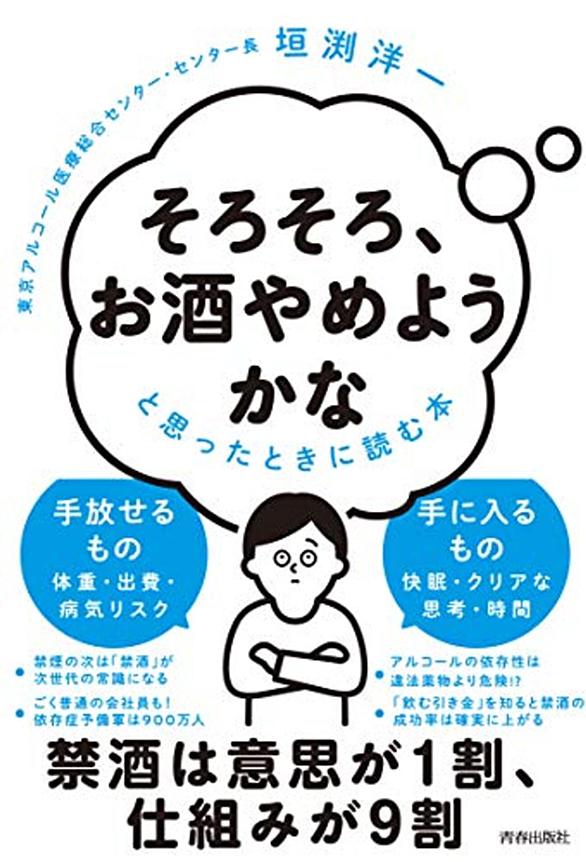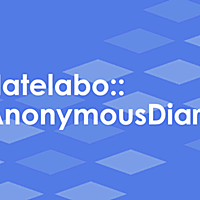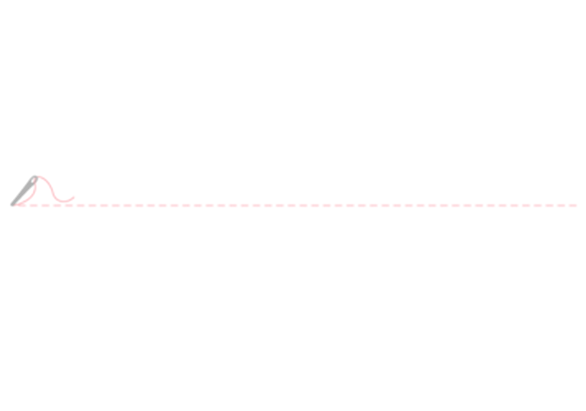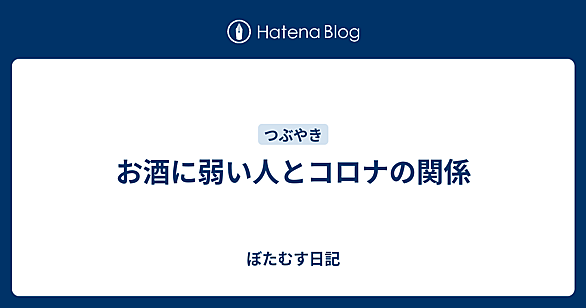下戸
(食)
【げこ】
酒が飲めない人、酒が嫌いな人を言い表す俗語。
対義語は、上戸(じょうご)。
由来
「下戸」は、日本の律令制時代の階級「大戸/上戸/中戸/下戸」の最下級。課税階級としても使用されていた。
祝儀席での酒の量が、「大戸は八瓶」「下戸は二瓶」と定められていたため、「酒を少ししか飲めない人」を「下戸」と呼ぶようになった。
下戸の有名人
- 江夏豊
- 高倉健
- 渡哲也
- 北島三郎
- 浜田幸一
- 宇崎竜童
- 関根勤
- 舘ひろし
- 泉谷しげる
- 岡村隆史(ナインティナイン)
- 田中光(爆笑問題)
- 的場浩司