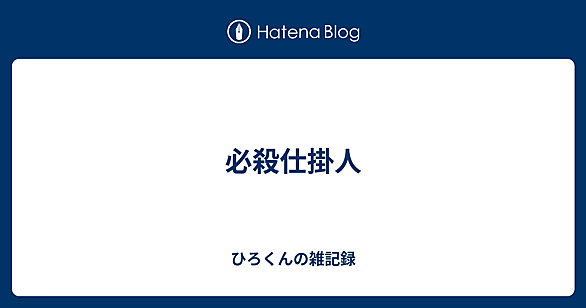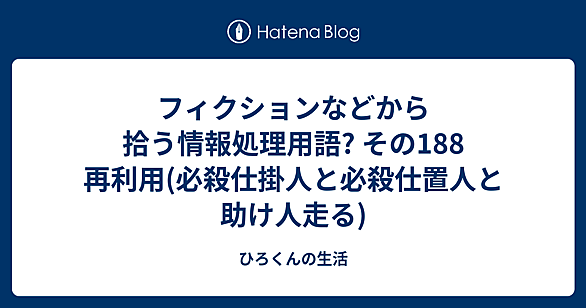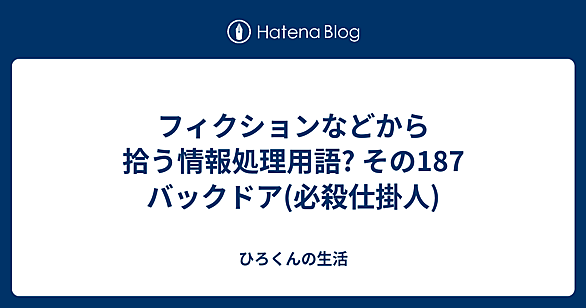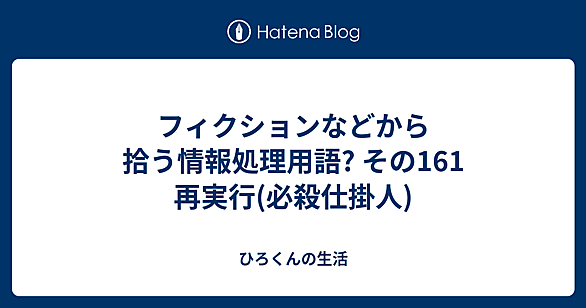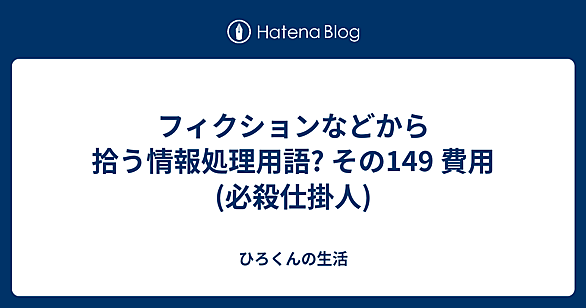必殺仕掛人
必殺仕掛人
人気時代劇「必殺シリーズ」第1弾。延べ30作続いた必殺シリーズの記念すべき第一作である。
1972年(昭和47年)9月2日より1973年(昭和48年)4月14日まで全33話にわたって放送された。
原作は池波正太郎『仕掛人・藤枝梅安』シリーズ。
プロダクションノート、あらすじ、スタッフ、キャスト、登場人物紹介、各話タイトル、DVD情報
プロダクションノート
当時、朝日放送のドラマプロデューサーであった山内久司は、裏番組として絶大な人気を誇っていた人気時代劇『木枯し紋次郎』に対抗するため、今までにない形の時代劇を模索していた。
そこで白羽の矢が立ったのが、池波正太郎が描く殺し屋を主役に据えた時代小説『仕掛人・藤枝梅安』であった。当時の風潮として、時代劇とは勧善懲悪であり、金を貰って人を殺す殺し屋稼業(つまりは悪人)を主役にすることは、山内にとって大きな賭けであった。そこで、単にダーティな部分だけを突出させて非情に描くのではなく、ところどころに人間臭さを出させたり、一般大衆と同じく、欲望に正直な部分を織り交ぜ、視聴者からの共感を得ることを盛り込んだ。
また、梅安の「針による殺し」についても、演出に拘りを加味。特に第6話「消す顔消される顔」での、完全防護を施した文殊屋多左衛門(三國連太郎)殺しにおける梅安の拘りなど、殺しの得物を通して殺し屋としてのプライドを加えた秀逸なものに仕上がっている。
当時としては異質であったコンセプトだけに、キャスティングにも難航。藤枝梅安役には天知茂、もう一人の主役である西村左内役には竹脇無我といった、当時の人気時代劇俳優にオファーを行うも断られ(天知茂は第12話「秋風二人旅」でゲスト出演)、結局梅安役は当時新国劇の緒形拳が、西村左内役は林与一に落ち着いた。
異質である上に、ライバルが市川崑率いる『木枯し紋次郎』であることから、スタッフ面でもテコ入れを開始。まず、市川崑に対抗できる監督として、東映から深作欣二、大映からは三隅研次を、そして、松竹からは松野宏軌、長谷和夫を起用。脚本においても、『十三人の刺客』の池上金男、橋本忍の愛弟子である國弘威雄、池波正太郎から師事を受けた安倍徹郎、『天下御免』などで知られる早坂暁などが参加。一流の映画人が集結した。
当時のキー局であったTBSからの猛反対を押し切り作られた本作は、制作側の熱意と現場の高い能力によって作り出され、更には、池波正太郎独特の江戸情緒や心の機微を逃さず描きあげた結果、視聴者に好評を得ることができ、シリーズ化も決定。今現在視聴しても、まったく遜色の無い作品として、現在もファンが多い。
内容
藤枝梅安(緒形拳)は、表向きは老若男女を問わず親しまれる腕の確かな針医者だが、その裏では生かしておいても世のため人のためにならない人間を人知れず始末する殺し屋・仕掛人であった。
ある日、口入屋を営みながらも、裏では仕掛人の元締として梅安と懇意の間柄である音羽屋半右衛門(山村聡)のもとに依頼が舞い込んだ。依頼人は材木商の伊勢屋勝五郎(浜田寅彦)。仕掛ける相手は、同じ材木商の辰巳屋(富田仲次郎)と、作事奉行の伴野河内守(室田日出男)である。
早速、梅安は行動を開始。辰巳屋が一人になる頃を狙い、夜道で仕掛けようとするも、辻斬りを趣味とする凄腕の浪人・西村左内(林与一)に邪魔をされ失敗する。
その結果により辰巳屋は警戒心を強め、ヤクザ大岩組の大岩(高品格)を雇い入れ、仕掛けがより一層難しくなってしまう。そこで音羽屋は、梅安が出会った浪人・左内を仕掛人にスカウトすることを発案する。仕掛人のプライドが高い梅安は頑なに拒否するが、やがて承諾。左内も仕掛人としての道を歩むこととなった。
いよいよ仕掛が始まった。まず、辰巳屋が妾であるおぎん(野川由美子)の家を訪れた際に、脳卒中に見せかけて辰巳屋の殺害に成功。続いて、万吉(太田博之)の扇動によって反乱を起こした長屋の住人と、大岩組の抗争の中で、伴野河内守を左内が斬り伏せる。仕掛けは見事成功したのだ。
そして、音羽屋は雨の中、大岩を仕掛ける。依頼人である伊勢屋勝五郎に仕掛けの成功を報告をするが、そこで伊勢屋勝五郎は、大岩と住人立ち退き後の長屋をどうするか、今後の算段を行っていたという。つまりは辰巳屋に取って代わろうとしているのだ。
そこで音羽屋は、この世の中に生きていても仕方のない、生かしておいても世のため人のためにならない大岩を刺し殺したことを報告。伊勢屋に釘を刺し、その場を離れるのであった。
スタッフ
- 原作
- 池波正太郎
- 音楽
- 平尾昌晃
- 主題歌「荒野の果てに」作詞:山口あかり/作曲:平尾昌晃/歌:山下雄三 ミノルフォンレコード
- 平尾昌晃
- ナレーション
- 睦五郎
- 題字
- 撮影
- 石原興
- 中村富哉
- 小辻昭三
- 照明
- 中島利男
- 染川広義
- 鎌田(釜田)幸一
- 編集
登場キャラクター
- 藤枝梅安(緒形拳)
- 表稼業は腕の良い針医者として、老若男女を問わず親しまれている名医。針の腕前は一級品で、無料で治療を行うときには沢山の人間が押しかけるほど(針で記憶すらも奪ってしまう)。しかし裏では、生きていても仕方が無い人間を抹殺する殺し屋「仕掛人」である。慎ましく、人柄も良いが、反面欲望に忠実な部分もあり、良い女を抱くのが好きだし、美味いものを食べるためには金を惜しまない。今作では音羽屋半右衛門を直属の元締とし、依頼があれば行動を開始する。仕掛人としてのプライドが非常に高く、自分と互角の腕前である西村左内を仕掛人にスカウトすることを知ったときには、当初反対した。また、自分の得物である「針」で仕留められない相手であっても、他の武器を使わず、針で仕留めるために工夫・研究を行い、必ず息の根を止める。「医師として人を生かしながらも、人の命を奪う」という、殺し屋としての「業」を背負っており、それにより実の妹さえも仕掛の対象となり、自らその命を奪った。得物は針。相手の急所を突いて仕留める。また、風車を固定している木の、尖った部分で仕掛を行ったこともあった。
- 西村左内(林与一)
- 梅安が仕掛けようとしたときに偶然出会った浪人。妻子持ち。凄腕の剣客ながら辻斬りが止められないという、一種病的な人間であったのだが、音羽屋半右衛門から仕掛人にスカウトされたことにより、自分の居場所と理想を見出し、殺し屋としての道を歩むこととなった。ちなみに、殺しの際には高額の報酬を受け取るわけだが、その理由を「道場の師範代をしている」と妻子に報告している。武士道を重んじている部分もあり、仕掛るときには必ずと言って良いほど「仕掛人・西村左内」と名乗る。当初は仕掛人という裏稼業に疑問を抱いていたこともあったが、梅安との息も合うようになり、抜群のチームワークを見せるようになる。得物は刀。ちなみに、「西村左内」という人物は、池波正太郎原作の時代小説の中に度々登場する武士の名前であり、その名前を受け取り、本作に登場させた。
- 千蔵(津坂匡章(※現・秋野太作))
- 音羽屋半右衛門の配下で梅安の密偵。よく梅安とつるみ、料亭や水茶屋で遊んでいる。
- 万吉(太田博之)
- 密偵の一人。
- お美代(松本留美)
- 左内の妻。夫を立て、息子を愛する、まさに良妻賢母である。左内が急に巨額のお金を家に持ってくるようになり、不振に思うのだが、左内の「道場の師範代をしている(嘘)」という言葉を信じ、夫のために家族を支えている。最終回において「人殺し」であった左内の正体を知るのだが、別れよりも家族の絆を選んだ。
- 彦次郎(岡本健)
- 左内の息子。左内を尊敬している。ちなみに「彦次郎」の名前は、原作『仕掛人・藤枝梅安』における梅安の相棒の殺し屋の名前である。
- おぎん(野川由美子)
- 第1話において、偶然梅安と出会った女。美しさと色気を持つ女性で、元々は標的の妾であったのだが、梅安もすぐに虜になった。その後、梅安とおぎんは大人の関係となるのだが、好奇心旺盛な性格であるため、何かと首を突っ込んだり、挙げ句の果てには「仕掛人になる」とまで言い出す始末。梅安も、そのお転婆ぶりには手を焼いていたようだ。
- おくら(中村玉緒)
- 音羽屋半右衛門の妻。勿論、裏の稼業のことも承知している。普段はおしとやかなのだが、興奮すると関西弁でまくし立ててしまう。曰く付きの過去を持ち、当時関わりがあり、しかも初めて「女」にしてもらった相手の同心が再び目の前に現れ、強請られたときには、夫である半右衛門をはじめ、誰にも相談できず苦悩する反面、女としての情熱が湧き上がり、つい、着替え中の左内の体に身を凭れかけてしまったこともあった。とはいえ、半右衛門とおくらの夫婦の信頼は厚く、お互いを信頼し、愛し合っていることは間違いがない。
- 音羽屋半右衛門(山村聰)
- 表稼業は口入屋を営む温厚なナイスミドルだが、裏では「生かしておいても、世のため人のためにならない」人間の始末一切を請け負う「仕掛人」の元締の一人である。分別もあり博識、更には懐も深い人物であるが、悪に対して容赦はなく、仕掛人を利用しようとする卑劣な依頼人には容赦なく罵声を浴びせ、掟に従い始末する。元締という立場柄、様々な人物に命を狙われるのだが、梅安や左内、最愛の妻おくら達の力を借り、抜群のチームワークで危機を脱する。過去には捕まり、遠島の刑を受けたこともあるが、その時に捕まえられた同心の恨みを晴らすなども行った。得物は匕首や紐など特定のものを使用しないが、その腕前は確かなものである。
各話タイトル(全33話)
- 仕掛けて仕損じなし 脚本:池上金男 監督:深作欣二 ゲスト:浜田寅彦 室田日出男
- 暗闇仕掛人殺し 脚本:國弘威雄 監督:深作欣二 ゲスト:美川陽一郎 遠藤辰雄 白木万理
- 仕掛られた仕掛人 脚本:安倍徹郎 監督:三隅研次 ゲスト:小池朝雄 弓恵子
- 殺しの掟 脚本:池上金男 監督:三隅研次 ゲスト:亀石征一郎 大友柳太郎 金田龍之介
- 女の恨みはらします 脚本:池上金男 監督:大熊邦也 ゲスト:草薙幸次郎
- 消す顔消される顔 脚本:山田隆之 監督:松本明 ゲスト:三國連太郎 西沢利明
- ひとでなし消します 脚本:山田隆之 監督:松本明 ゲスト:中尾彬 マイク真木
- 過去に追われる仕掛人 脚本:安倍徹郎 監督:大熊邦也 ゲスト:戸浦六宏
- 地獄極楽紙ひとえ 脚本:山田隆之 監督:三隅研次 ゲスト:神田隆
- 命売りますもらいます 脚本:國弘威雄 監督:松野宏軌 ゲスト:園井啓介
- 大奥女中殺し 脚本:國弘威雄 監督:松野宏軌 ゲスト:磯村みどり
- 秋風二人旅 脚本:安倍徹郎 監督:三隅研次 ゲスト:天知茂 小林昭二
- 汚れた二人の顔役 脚本:山田隆之 監督:松野宏軌 ゲスト:内田朝雄 安倍徹
- 掟を破った仕掛人 脚本:石堂淑朗 監督:大熊邦也 ゲスト:下条正巳 伊藤孝雄 小坂一也
- 人殺し人助け 脚本:山田隆之 監督:松本明 ゲスト:津川雅彦 赤座美代子
- 命かけて訴えます 脚本:早坂暁 監督:大熊邦也 ゲスト:松橋登
- 花の吉原地獄の手形 脚本:松田司 監督:松野宏軌 ゲスト:加藤嘉 住吉正博 八木孝子
- 夢を買います恨みも買います 脚本:國弘威雄 監督:長谷和夫 ゲスト:近藤正臣 玉生司郎
- 理想に仕掛けろ 脚本:山田隆之 監督:松本明 ゲスト:佐藤慶 球めぐみ
- ゆすりたかり殺される 脚本:山崎かず子・安倍徹郎 監督:松野宏軌 ゲスト:松山省二
- 地獄花 脚本:安倍徹郎 監督:三隅研次 ゲスト:田村高廣 外山高士
- 大荷物小荷物仕掛の手伝い 脚本:本田英郎 監督:長谷和夫 ゲスト:藤原釜足 浜田晃
- おんな殺し 脚本:山田隆之 監督:松本明 ゲスト:加賀まりこ 天田俊明
- 士農工商大仕掛け 脚本:池田雄一 監督:深作欣二 ゲスト:雪代敬子 堺左千夫 梅津栄
- 仇討ちます討たせます 脚本:國弘威雄・鈴木安 監督:松野宏軌 ゲスト:御木本伸介
- 沙汰なしに沙汰あり 脚本:本田英郎 監督:長谷和夫 ゲスト:柳沢真一 平井昌一
- 横をむいた仕掛人 脚本:石堂淑朗 監督:大熊邦也 ゲスト:大月ウルフ 穂積隆信 河原崎長一郎
- 地獄へ送れ狂った血 脚本:安倍徹郎 監督:松野宏軌 ゲスト:林隆三 島田順司 城所英夫
- 罠に仕掛ける 脚本:津田幸夫 監督:長谷和夫 ゲスト:榊原るみ 田口計
- 仕掛けに来た死んだ男 脚本:早坂暁 監督:大熊邦也 ゲスト:田村高廣 米倉斉加年 石堂淑朗
- 嘘の仕掛けに仕掛けの誠 脚本:國弘威雄・鈴木安 監督:長谷和夫 ゲスト:井上孝雄 小島三児
- 正義にからまれた仕掛人 脚本:山田隆之 監督:松本明 ゲスト:伊藤雄之助
- 仕掛人掟に挑戦! 脚本:國弘威雄 監督:三隅研次 ゲスト:三津田健 新田昌玄 浜田寅彦
DVD
BOX
![必殺仕掛人 上巻 [DVD] 必殺仕掛人 上巻 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51Z3QSNK8EL._SL160_.jpg)
|
![必殺仕掛人 中巻 [DVD] 必殺仕掛人 中巻 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/211GMSAD9FL._SL160_.jpg)
|
![必殺仕掛人 下巻 [DVD] 必殺仕掛人 下巻 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/218QWHH349L._SL160_.jpg)
|

|
単品
![必殺仕掛人 VOL.1 [DVD] 必殺仕掛人 VOL.1 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51dZiZrbGfL._SL160_.jpg)
|
![必殺仕掛人 VOL.2 [DVD] 必殺仕掛人 VOL.2 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/518%2Bn80Z1uL._SL160_.jpg)
|
![必殺仕掛人 VOL.3 [DVD] 必殺仕掛人 VOL.3 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/515b0%2BhAQwL._SL160_.jpg)
|
![必殺仕掛人 VOL.4 [DVD] 必殺仕掛人 VOL.4 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/21M6FDEDE4L._SL160_.jpg)
|
![必殺仕掛人 VOL.5 [DVD] 必殺仕掛人 VOL.5 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/21EG8KD2EQL._SL160_.jpg)
|
![必殺仕掛人 VOL.6 [DVD] 必殺仕掛人 VOL.6 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/21VY7YH0QRL._SL160_.jpg)
|
![必殺仕掛人 VOL.7 [DVD] 必殺仕掛人 VOL.7 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/21VRYZ43QFL._SL160_.jpg)
|
![必殺仕掛人 VOL.8 [DVD] 必殺仕掛人 VOL.8 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/21B589Q2QNL._SL160_.jpg)
|
![必殺仕掛人 VOL.9 [DVD] 必殺仕掛人 VOL.9 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/21WKJXWQ4XL._SL160_.jpg)
|