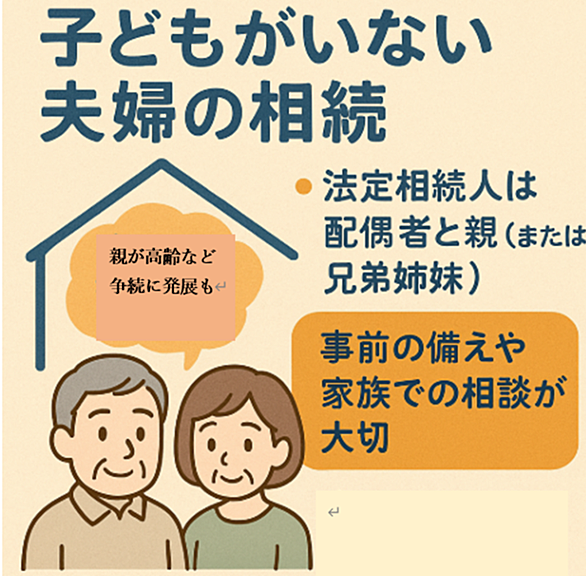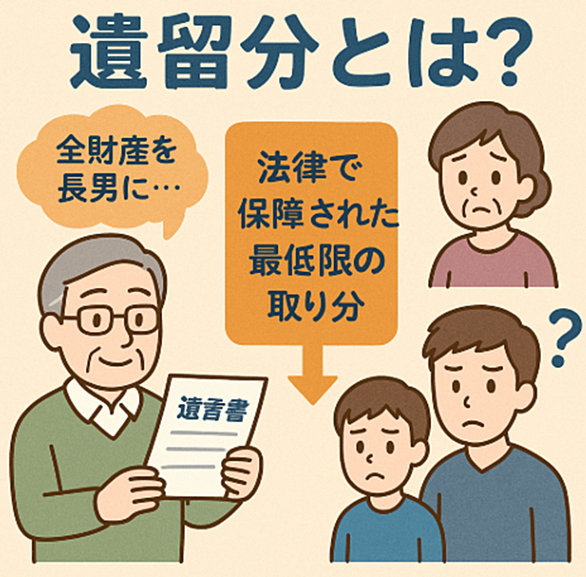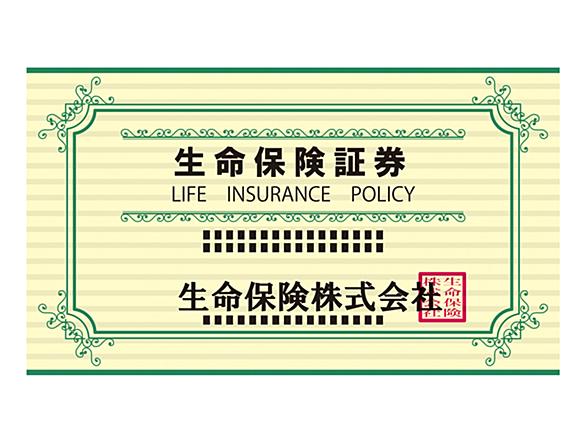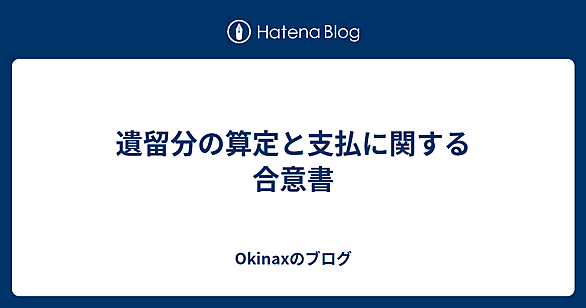相続
(一般)
【そうぞく】
相続
亡くなった人の財産上の地位を相続人が継承すること.
亡くなった人を「被相続人(ひそうぞくにん)」.財産を受け継ぐ人を「相続人」という.
法令(民法)
民法882条(相続開始原因)
- 相続は、死亡によって開始する。
民法30条(失踪宣告)
- 1:不在者の生死が7年間わからないときは、家庭裁判所は利害関係人の請求により、失踪の宣告を為すことができる。
- 2:戦地に行った者、沈没した船にいた者、生命の危険を伴う災難に遭った者の生死が戦争終了後、沈没後、災難が去った後、1年間不明なときは、前項と同様の措置をとることができる。
民法31条(失踪宣告の効力)
- 前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は、失踪から7年目に死亡したものとみなし、前条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者は、危難が去ったときに死亡したものとみなす。
民法883条(相続開始の場所)
- 相続は、被相続人の住所において開始する。