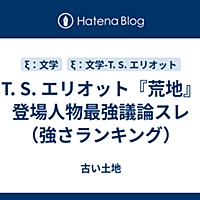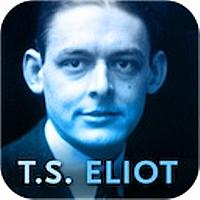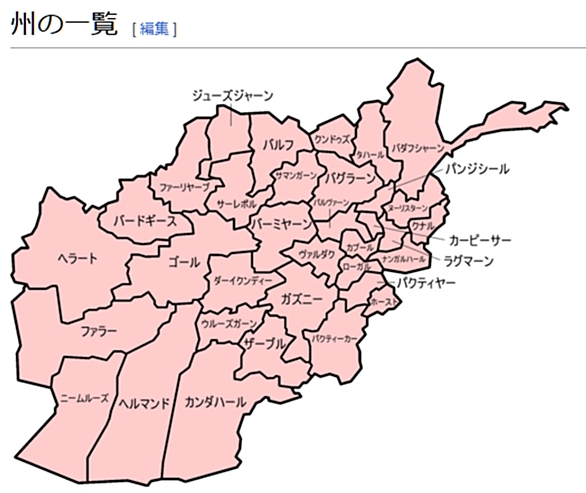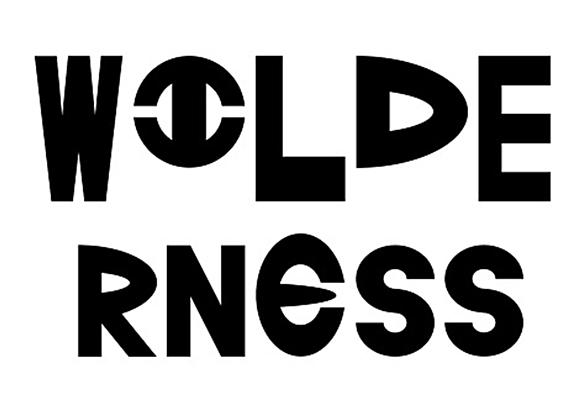荒地
1947年〜1948年にかけて刊行された、現代詩の同人誌。これに属した詩人は「荒地派」と呼ばれた。「荒地」という詩誌の名は、第一次世界大戦後、T・S・エリオットが著したThe Waste Land(1922)にインスパイアされて名づけられた。
鮎川ら中核となるメンバーは、戦前からの友人関係を持つ。鮎川らは太平洋戦争戦時中に、詩誌LE BALを立ち上げる。 彼らの幾人かは従軍し、戦後に「荒地」を創刊し、その後各人は多彩な活動を始めた。つまり荒地とは太平洋戦争後の状況の中で立ち上げられた一つの芸術運動であるが、個々人は固有のテーマを持つ。相互に影響関係にありながら、それぞれは独自の創作活動を展開した。
鮎川の友人森川義信の戦死を通じて、鮎川信夫は戦争の死者の問題を詩を通じて内在的に問うた。田村も初期の代表作「四千の日と夜」を書くことで、戦争によって究極的な荒廃を呈した世界と自己の内面を、高度な詩的手法を通じて表し戦後詩の傑作のひとつとされる。
彼らは戦前のモダニズム詩やシュルレアリスム詩に影響を受けながらも、戦争での文明的変容の中で批判的に詩法を問い直し、独自のスタイルを確立する。エリオットやヴァレリーらの西洋の大戦間詩人にも通暁している。鮎川・田村・北村にはそれゆえ英米文芸作品の翻訳家としての側面もある。これに対し同時期に影響力を持った詩誌「列島」は、戦前からのプロレタリア詩、アヴァンギャルド芸術の流れを汲みながらも、その可能性をなおも追求する点で「荒地」とは異なる詩的実践を行なった。
基本的に鮎川、田村、北村らは現実の社会に対し一歩引いた姿勢をとり続けた。それに対し吉本隆明は詩的活動を中断し政治活動にコミットし旺盛な批評や提言を行なう。黒田三郎のようにより庶民的なあり方に親和性を持つ者もいる。各人の戦後社会での生き方は非常に個別性が大きいものの、戦争の復興により暗い影が日本社会の表面上からその痕跡が消えていく状況に対し各人が様々な対応の変化を迫られた事実は否めない。
近年、ねじめ正一が北村太郎と田村の複雑な関係を描いた「荒地の恋」が出版された。また加島祥造はもともとフォークナーなどの翻訳で知られる著名な英米文学者でもあった。現在は隠棲しタオイズムに傾倒する。近年「生き方」について平易な語彙を用いた詩集『求めない』等を発表している。
鮎川信夫、北村太郎、中桐雅夫、加島祥造、三好豊一郎、黒田三郎、高野喜久雄、田村隆一、野田理一、吉本隆明らの詩人を輩出した。