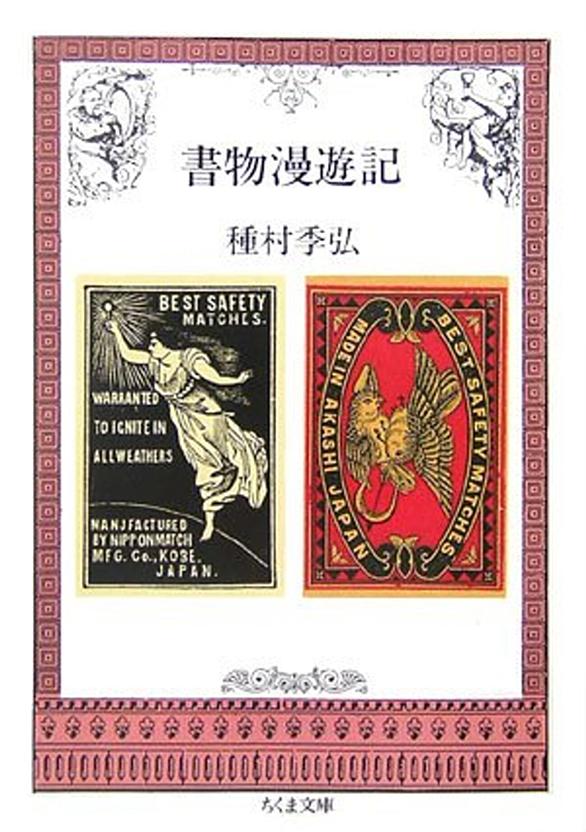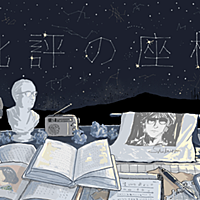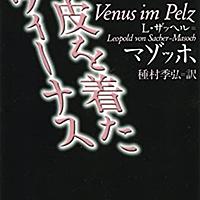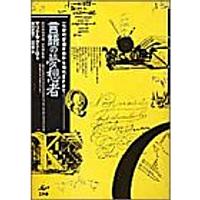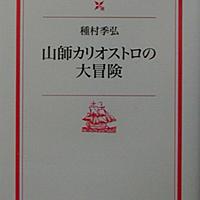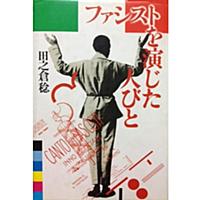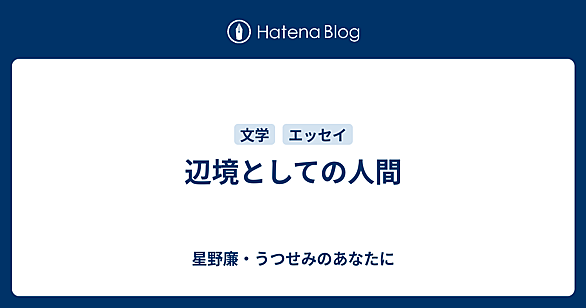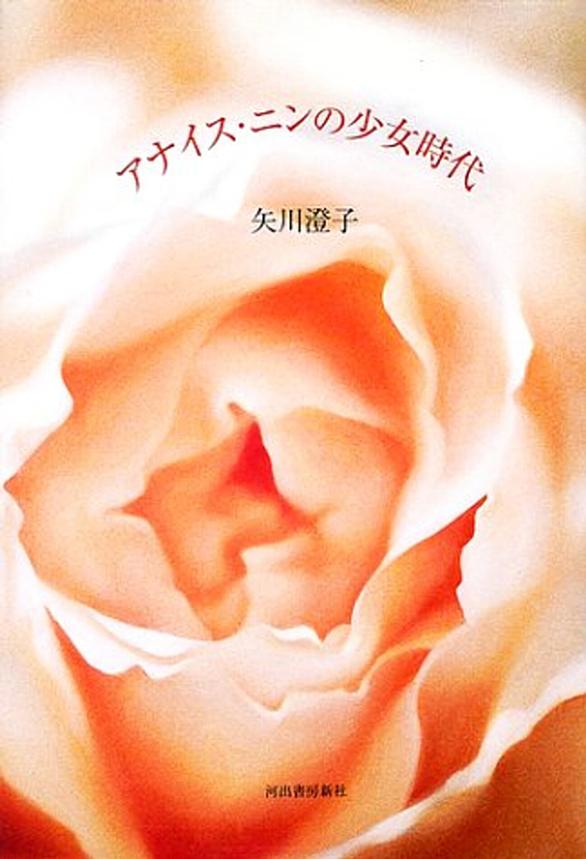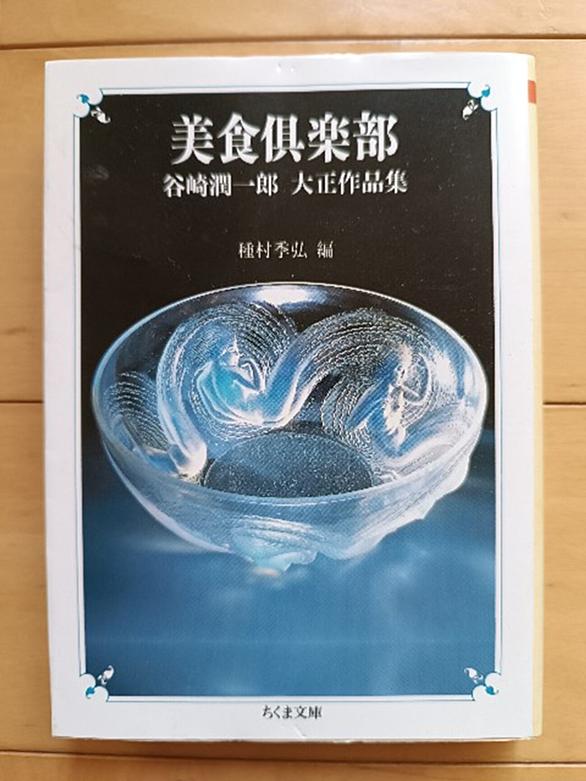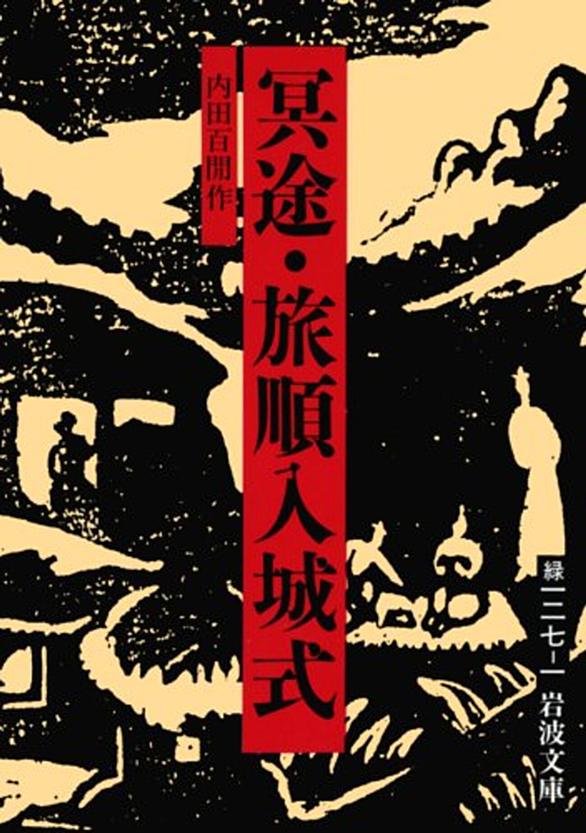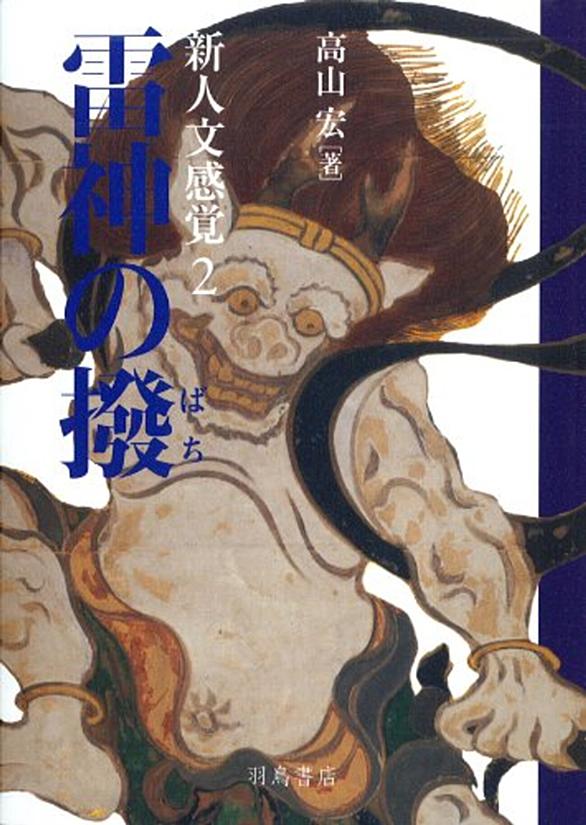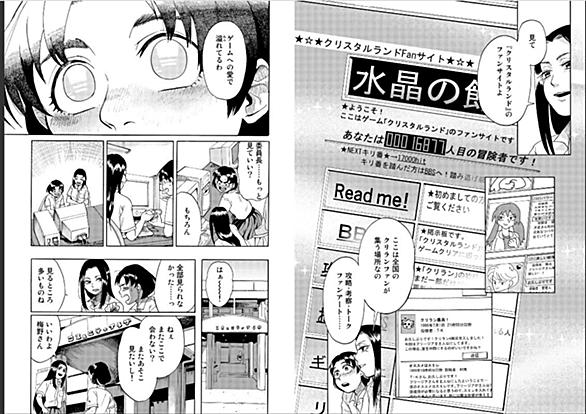種村季弘
(読書)
【たねむらすえひろ】
(1933〜2004) エッセイスト、翻訳家、ドイツ文学者
東京生まれ。東大卒。国学院大学教授。ドイツ文学者。ホッケ、マゾッホなどの著作を訳出紹介するかたわら、マゾッホ、パラケルスス、カリオストロなどの評伝、怪物、ペテン師、錬金術師などをめぐる多彩なエッセイを発表している。「種村李弘のラビリントス」全10巻 他著書多数。2004年8月29日、死去。
文庫本で読める種村季弘(抄)
エッセイ・評論
- 『悪魔礼拝』
- 『吸血鬼幻想』
- 『ぺてん師列伝』
- 『怪物の解剖学』
- 『詐欺師の楽園』
- 『影法師の誘惑』
- 『毛皮を着たヴィーナス』マゾッホの訳
以上河出文庫
- 『贋物漫遊記』
- 『書物漫遊記』
- 『好物漫遊記』
- 『迷信博覧会』
- 『ブランビラ王女』E.T.A.ホフマンの訳
以上ちくま文庫
- 『ナンセンス詩人の肖像』(ちくま学芸文庫)
- 『山師カリオストロの大冒険』(中公文庫)
編集もの
- 『日本怪談集(上下)』
- 『ドイツ怪談集』
以上河出文庫
- 『東京百話-天の巻・地の巻・人の巻-』
- 『温泉百話-東の旅・西の旅-』
- 『美食倶楽部-谷崎潤一郎・大正作品集-』
- 『泉鏡花集成』全14巻
以上ちくま文庫