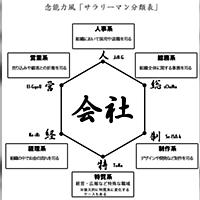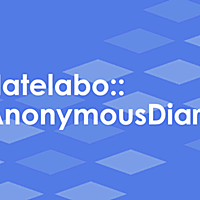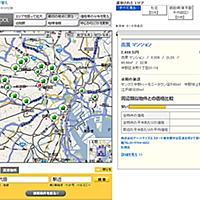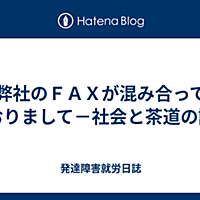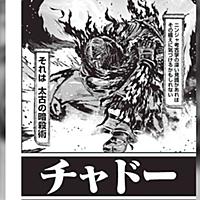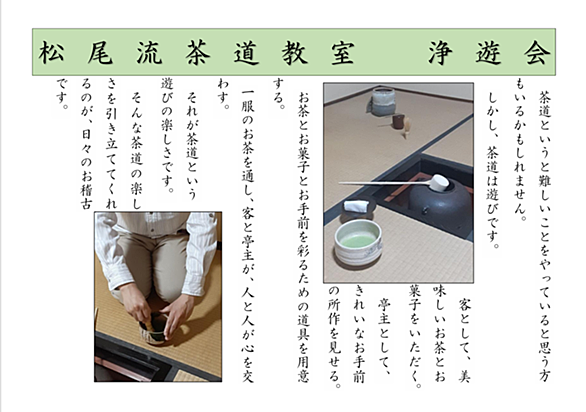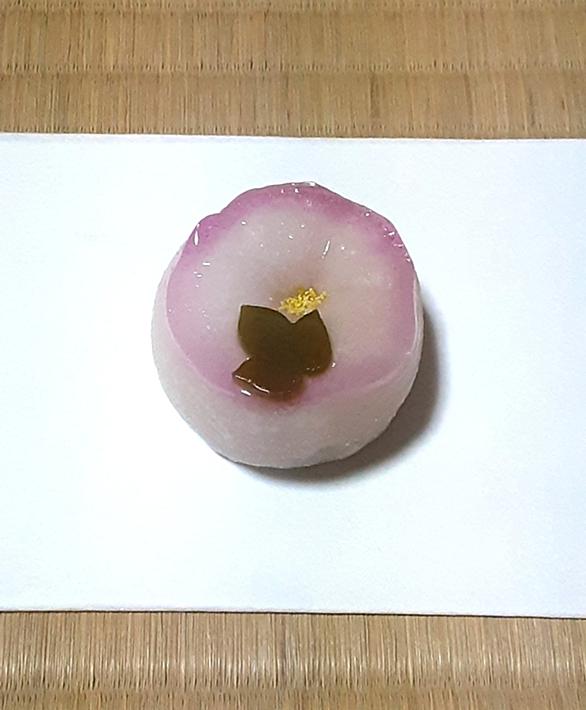このタグの解説について
この解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。関連ブログ
ネットで話題
もっと見る194ブックマーク【動画】 韓国の茶道に「ステンレス水筒」が登場してネット住民驚愕 - 痛いニュース(ノ∀`) : ライブドアブログ1 名前: ニールキック(北海道):2013/08/13(火) 23:37:22.30 ID:87CnKChq0 韓国のオリジナル茶道クッソワロタwwwwww 【吹いたら負け】 これが韓国の茶道だ! http://www.nicovideo.jp/watch/sm21555732 http://youtu.be/PMKpO3uQ3_0 開始1秒で左下に不穏な物が映ってるんですが……w http://i.imgur.com/L81toWm.j... blog.livedoor.jp
blog.livedoor.jp