イッツ・オール・ライト
昨晩右耳に激痛が走り、こりゃ中耳炎かな、と危惧していたが、一晩寝たらころっと治った。良かった。そういえばジャズ・トゥナイト聴き逃してしまったよ。このところ目醒めるのが余りに早くて、夜は早く寝てしまうんだ。10時とか11時とか。
それはそうと、さっき起きてウィントン・ケリー・トリオのヴァーヴへの一枚、『イッツ・オール・ライト』を聴いている。最近こういう「ジャズらしいジャズ」を多く聴いてるんだが、どれも非常に素晴らしくて感動する。昨日だったらガレスピーとかね。
図書館にも行くつもりだが、余り性急に借りたり返したり繰り返したいと思ってるわけではなく、既に借りているものもそれなりに丁寧に読もうとしているが、どれも面白いんだけれど、例えば文藝春秋編『アベノミクス大論争』(文春新書)。山脇直司『公共哲学からの応答 3.11の衝撃の後で』(筑摩選書)。大友良英・金子勝・児玉龍彦・坂本龍一『フクシマから始める日本の未来』(アスペクト)。ま、いつも申し上げてるように僕の意見になどなんの重みもないわけだが、それでも古典だけじゃなくて時論、時事評論とか時局関連のあれこれも読むのが好きだってことだね。3.11、脱原発、放射線(放射能被曝)、復興とかアベノミクスとかね。憲法、改憲問題とか。そうはいっても時事的なテーマだけ読んでも致し方がない。哲学でも文学でももっと古典を読まなければ。そして、自分の本来の関心に沿ったものを、とも思うんだ。だけど自分の本来の関心とかいうものももはやよく分からないが、例えば昨晩テネシー・ウィリアムズを読んだが余りピンとこなかったとか。
昨日は一日素晴らしいことがあった。Ustreamを放送しなかったんだ。一日休んだ。酷暑で自室から出る気がしなかっただけだが、毎日長時間放送したところで、みんな仕事や活動、趣味などに多忙なので、視聴する人もいないし、録画を保存しても誰も再生しないので無駄っぽいと感じていた。だから放送せずのんびりしているのはいいことだ。それに、毎日6時間も7時間もそれ以上も放送するのを休止したら、そのぶん音楽を聴けるしね。昔の名盤の数々を。
それにしても昨晩右耳が痛かったのはCDウォークマンでヒノテルを聴いたからだったんだろうか? そうかもしれないが、ただそれだけのことでああなってしまうのは困るな。そんなに大音量だった覚えもないんだが。
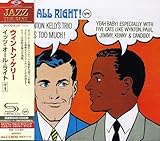
- アーティスト: ウィントン・ケリー,ポール・チェンバース,ジミー・コブ,ケニー・バレル,キャンディド
- 出版社/メーカー: ユニバーサル ミュージック クラシック
- 発売日: 2011/07/20
- メディア: CD
- この商品を含むブログを見る
連日いろんな人のいろんな意見に文句をつけてるが、ちょっとまとめて総合的に申し上げてみよう。「この世には不確かなことが多い」というだけだったらみんなそう思うわけだ。科学を疑ったり否定する神秘主義者、オカルティストも科学主義者も全員そう思う。だって普通、科学で現在すべてが完全に解明されてるなんて誰も思わないからだ。それは勿論そうなんだが、とりわけ最近の混乱状況ってのはそういう一般論とは違うということでしょう。ただ単にまだわかっていないことも多いとか、専門家の間でさえ複数の見解や複数の基準がある(例えば、低線量被曝に関して)とかいうことだけではなく、そういうはっきりしない状況のなかで或る特定の意見を確信的に主張しなければならない。それが脱原発の倫理であり政治である。そうすることを躊躇う、またはできないヤツは……という下らないことになっている。
僕はそんなのには与することはできない。僕は物理学そのものには限りなく素人なんで、直接それというよりは周辺領域、哲学(『放射能問題に立ち向かう哲学』、『公共哲学からの応答』)、経済学(『原発事故の経済学』)などのものから読むことが多いが、もし今判明していることの範囲が上記のようなことだったら、つまり、専門家と一般市民(=非専門家)の間にギャップがあるし、専門家の間でも何の専門家なのかによって違いがあるし、国際機関の主張する基準も違うということであるならば、そういうことがあるということを踏まえて、「まだ確かではないが予防原則で広域の避難をしたり、食品の規制をしましょうか」という話になるか、または、「そうはいっても、福島の復興や移動コストもあるし、事業者・生産者の経営や生活もありますよね」という話になるかのいずれかのはずなのだ。
というふうにしか思わないということだし、最近エコロジストの皆さんからの「挨拶」が減って、ほとんどなくなってものすごく喜んでるんだ。ようやく諦めてくれたかと……。僕は誰の味方もしませんので。
ホームカミング!
朝食はまたしてもラーメン、但し今度はカップラーメンの坦々麺である。そんなことはともかく、冷水シャワーを浴びて図書館に行ってこようと思ったが、何となく気乗りがせずやめた。右耳の痛み、中耳炎(?)は一晩寝て治ったかと思いきや、今手で触れて確かめてみるとやはりひどく痛い。そんなことはともかく(あっ二回目)、エルモ・ホープ『ホームカミング!』を聴いている。
Twitterで相原たくや氏の「反・反原発」批判を読んだ。瓦礫焼却反対運動を批判するのが被災地に同情するふりをした欺瞞であり、反・反原発だから悪であり反動だというのだ。そしてさらに、「大日本帝国臣民」の心情がどうのこうのというが、僕は思わず吹き出してしまった。この人は何を云っているのか。ラディカル左派には瓦礫問題の異論も「放射脳」批判も何もかも全部「大日本帝国臣民」とかいうアナクロニズムなものに見えてしまうわけですか?
それにFacebookで詳しい批判を加えたのだが、その議論の全部を再録はしないが、要するに倫理過剰の純粋主義なんだ。美しい魂っていうか心が綺麗、綺麗過ぎるんだよ。玉置浩次の「ワインレッドの心」でも聴いてみていただきたいというところだが、上記のことにしても、瓦礫について脱原発の中にさえ賛否両論あるなんてことは相原さんも当然承知してるんだ。だとすると、相手を「カルト」とか「****」(伏字)とか「放射脳」と「汚い言葉」で罵倒するのがよろしくないという倫理(?)と美学であるということになる。
だがしかし、そんな下らない反差別の道義的心情が一体何か? 悪いが、**は**であり****は****だろう。そう申し上げて何が悪いのか? 事実でしょう。そしてさらに「放射脳」という揶揄のどこがいけないのか? それは脱原発の否認ですらないだろう。脱原発/反被曝の一部に、いや多数に頭がどうかしたおかしい連中が巣食っていて、それが全体を腐らせダメにしてるなんてことは周知の事実ではないのか? カマトトぶるな、いい子ぶってもしょうがないだろうと思うが。
それに根本的なことを申し上げれば、そんな綺麗事を並べる相原さんが、これまで小沢派や孫崎享・岩上安身・佐藤優周辺などなどの連中を「革マルと同じカルト」、「陰謀論者」と声高に非難されてきたこととはどう両立し整合しているのか? ご自分が小沢派をカルトとか革マル・オウムと同じと云うのはいいが、運動の多数派に距離を取る人々が脱原発運動の一部や瓦礫焼却反対派の一部をカルトと呼ぶのは「汚い言葉」だから許されない、嫌悪感がどうのこうのというダブルスタンダードはどこからくるのか? わけがわからないとしか申し上げようがないし、僕自身は「花より団子」、華を捨てて実を取るリアリストである。
参考までに。哲学が様々な「比較考量」を始めたのは一ノ瀬正樹『放射能問題に立ち向かう哲学』やその背景になっている20世紀の英米系の分析哲学・科学哲学からではないのだ。遥か昔からそういうことは思考されていたのだということを申し上げておきたい。
金子武蔵『ヘーゲルの精神現象学』(ちくま学芸文庫)28ー29ページ
たしかに、この定言命法には間違いはありません。しかし、カント倫理学には一つの大きな欠陥があります。それは道徳的生活の悲劇的な面が看過されていることです。もう少しわかりやすくいえば、義務と義務との間に衝突が起こるということをほとんど考えていないことです。先にのべたように、自分だけは特別にしてもらいたいというのは、わがまま勝手というものです。カントの倫理学の用語でいえば、これは理性に反抗する傾向 Neigungというものです。理性に反抗するこの傾向が働くところに悪が生まれてくるというわけです。しかし、それだけでは片づきません。道徳的生活ということをよく考えてみると、そこでは葛藤や衝突が生ずることが非常に多いのです。たとえば、偽りの約束をして金を借りるというような場合にも、こういうことがしばしば起こります。親が病気で困っている、なんとかして手当てをしてやりたい。たとえ助からないにしても、一週間でも十日でも生かして上げたいが、金がない、そこで、払える見込みがないのに、やはり約束をして金を借りようという気持ちを起こす。こういうときに義務と義務との間に衝突が起こっているわけです。他人をあざむく、他人を手段としてのみ取り扱う、偽りの約束をする、ということは悪いことにちがいないが、といって、親が病気で苦しんでいるのになんの手当てもしないのも悪いことです。だからこういうときに義務と義務との間に衝突が起こってきます。しかもこの葛藤は、その人が道徳的であればあるほど、それだけ深刻になってくるのです。
このように、定言命法にそむくのは、必ずしも傾向だけがそうさせるのではなく、義務と義務とが衝突して葛藤にまき込まれたことによる場合のあるのを認めないわけにはゆきません。ところがカントは、それをほとんど認めていないのです。つまり、カントはそれぞれの義務を各個ばらばらに考えているだけで、義務を真に全体として考えてゆくことをほとんどしません。
ラスト・トリオ・セッション
ウィントン・ケリーの『ラスト・トリオ・セッション』を聴く。『情況』にかつて載った小泉義之・王寺賢太・長崎浩による湯浅誠・宮本太郎・芹沢一也、それからおまけに濱口桂一郎への批判がひどいらしい。僕は民主党の議員で現在選挙戦を戦っている松浦大悟のTwitter及び濱口桂一郎のブログで読んだ。実物を読んだほうがいいだろうが、こんな下らないもののために1円も払う気はない。図書館にも所蔵されていない。
どう申し上げればいいのか、統治論というかファシズム(!)というか、社会政策に定位してというか、具体的な国家なり政府なり政党なり……そういうものとは異なる左翼的(?)な批判的ポジションを確保したいのだろうが、そんなものは空想の世界にしかないのではないのか。マルクス自身は違ったのかもしれないが、ヘーゲルの全体論的な立場、国家や社会総体という視点で考える立場を批判する左翼の多くは、個人倫理ではないとしても、カント的な主体的/主観的倫理に退行したのではないのか。対抗運動ではなく退行運動。定言命法ではなく提言迷法だ。政治とか社会に提言しているつもりで、そのじつ完璧に無意味だからね。世迷言。戯言。愚劣極まりない……いや、この辺でやめておこう。あなたはディドロ研究だけおやりになればそれがみんなにとって一番よろしい。適当に左翼的趣味で無意味な介入をするのは金輪際二度とやめなさい。それだけだ。

- アーティスト: WYNTON KELLY
- 出版社/メーカー: DELMARK
- 発売日: 2002/08/11
- メディア: CD
- クリック: 3回
- この商品を含むブログ (6件) を見る